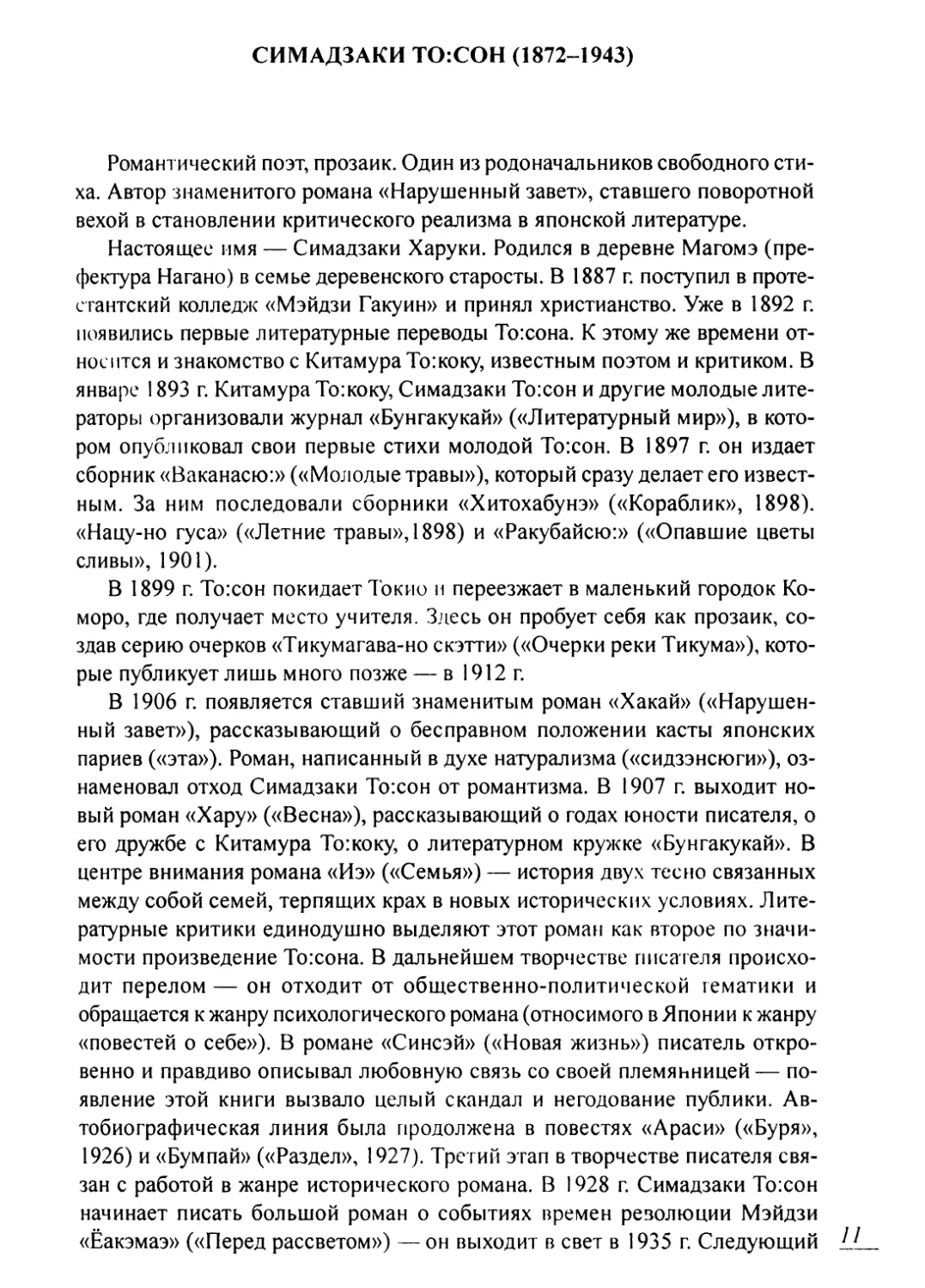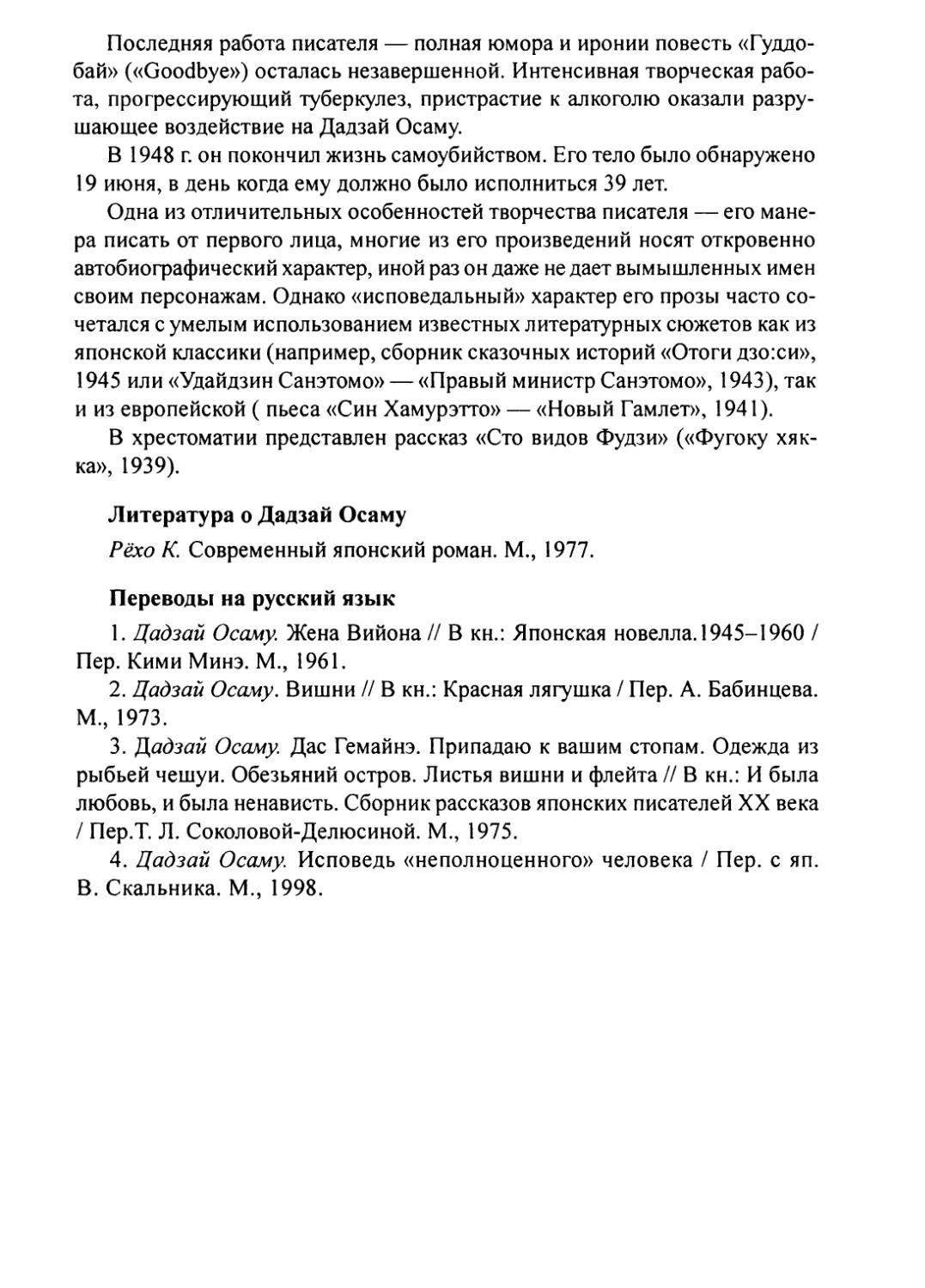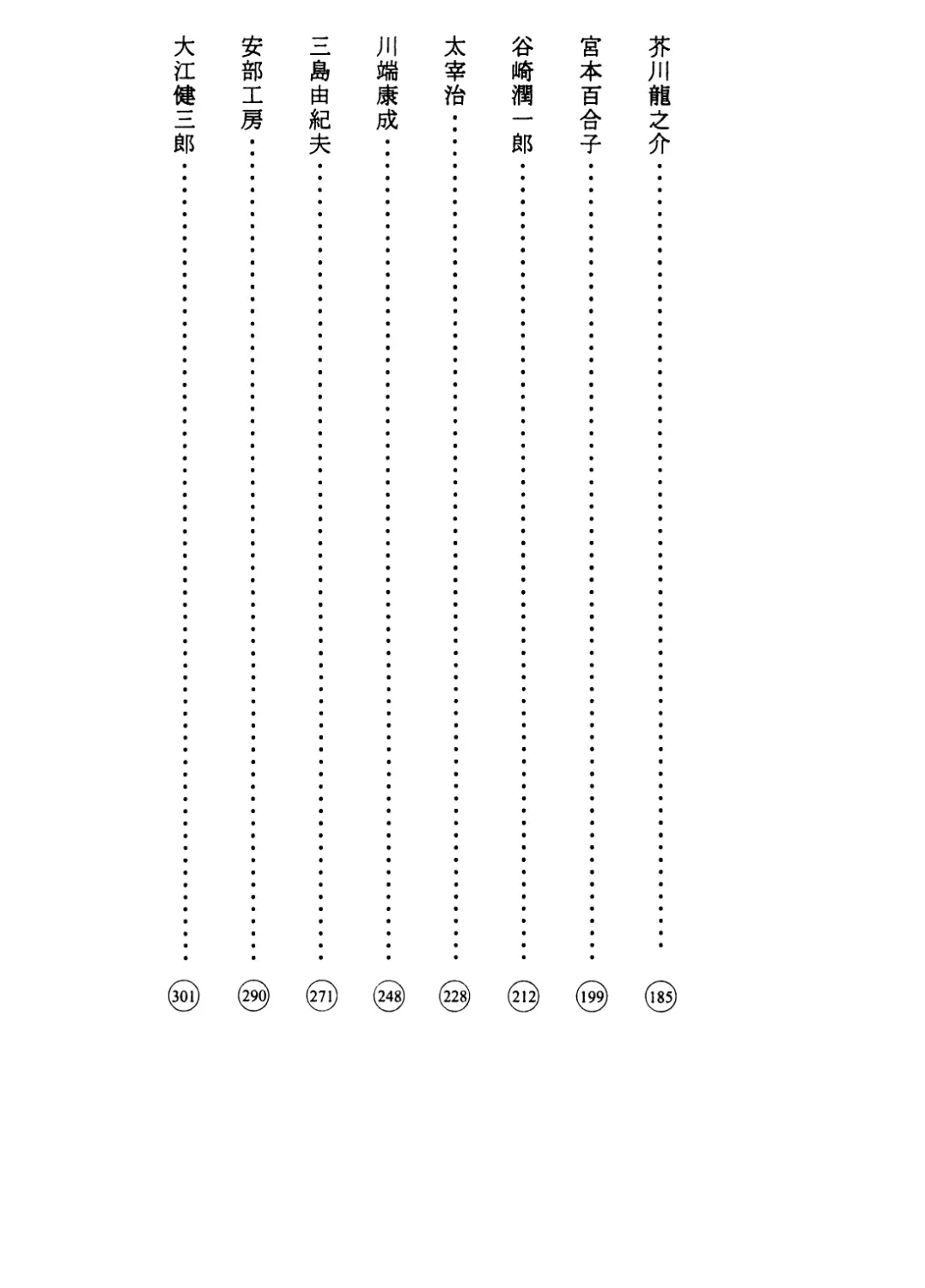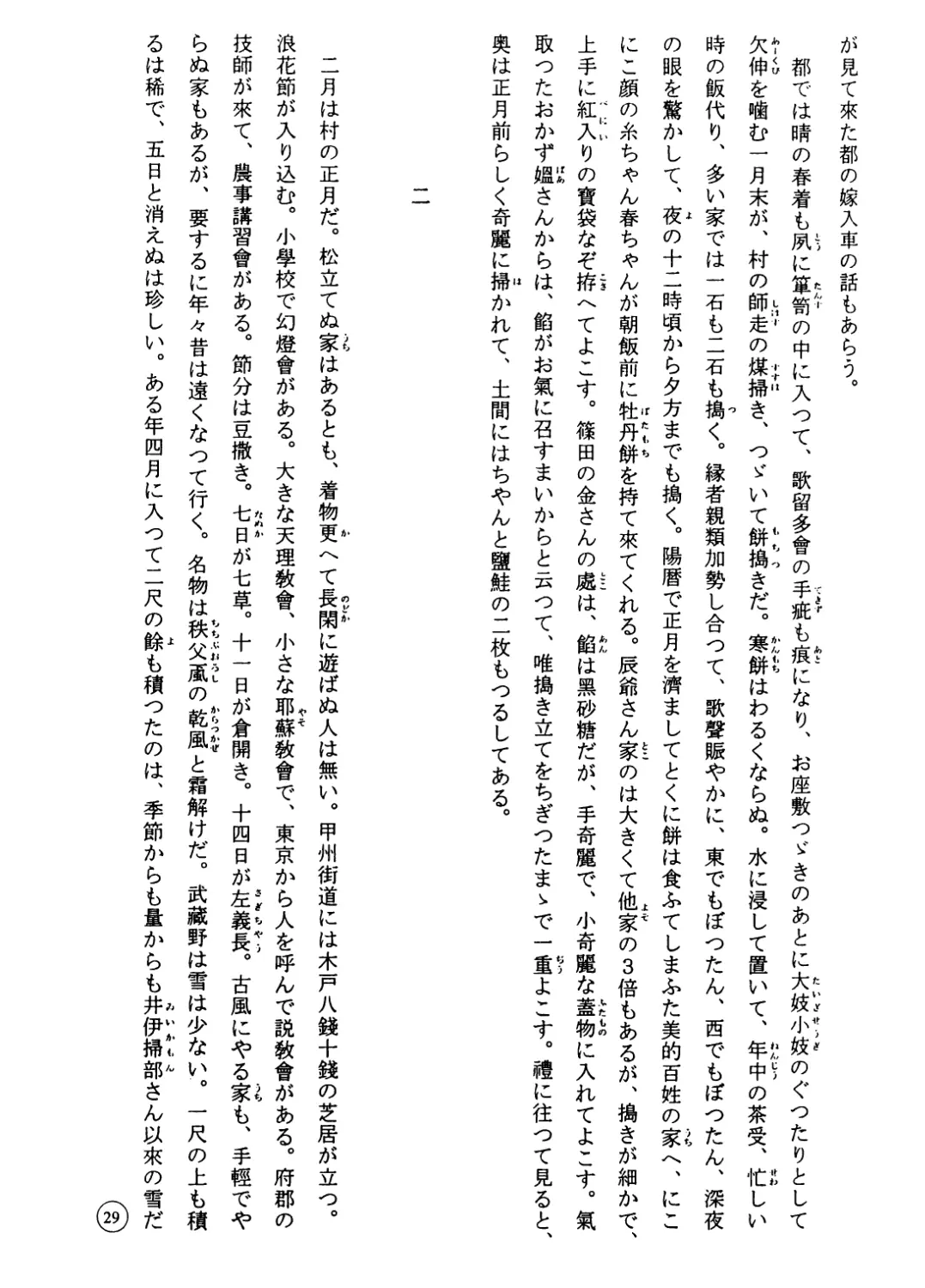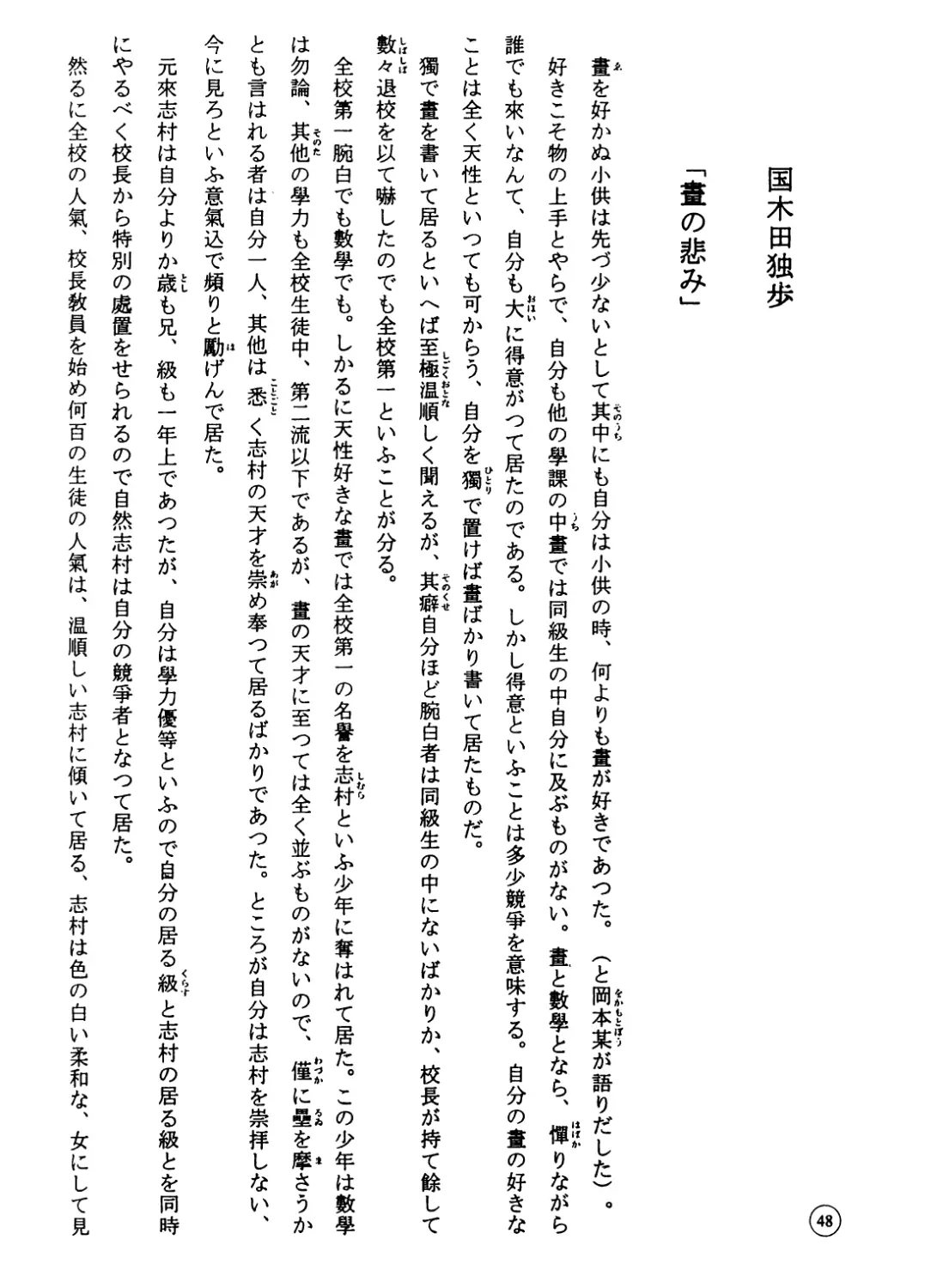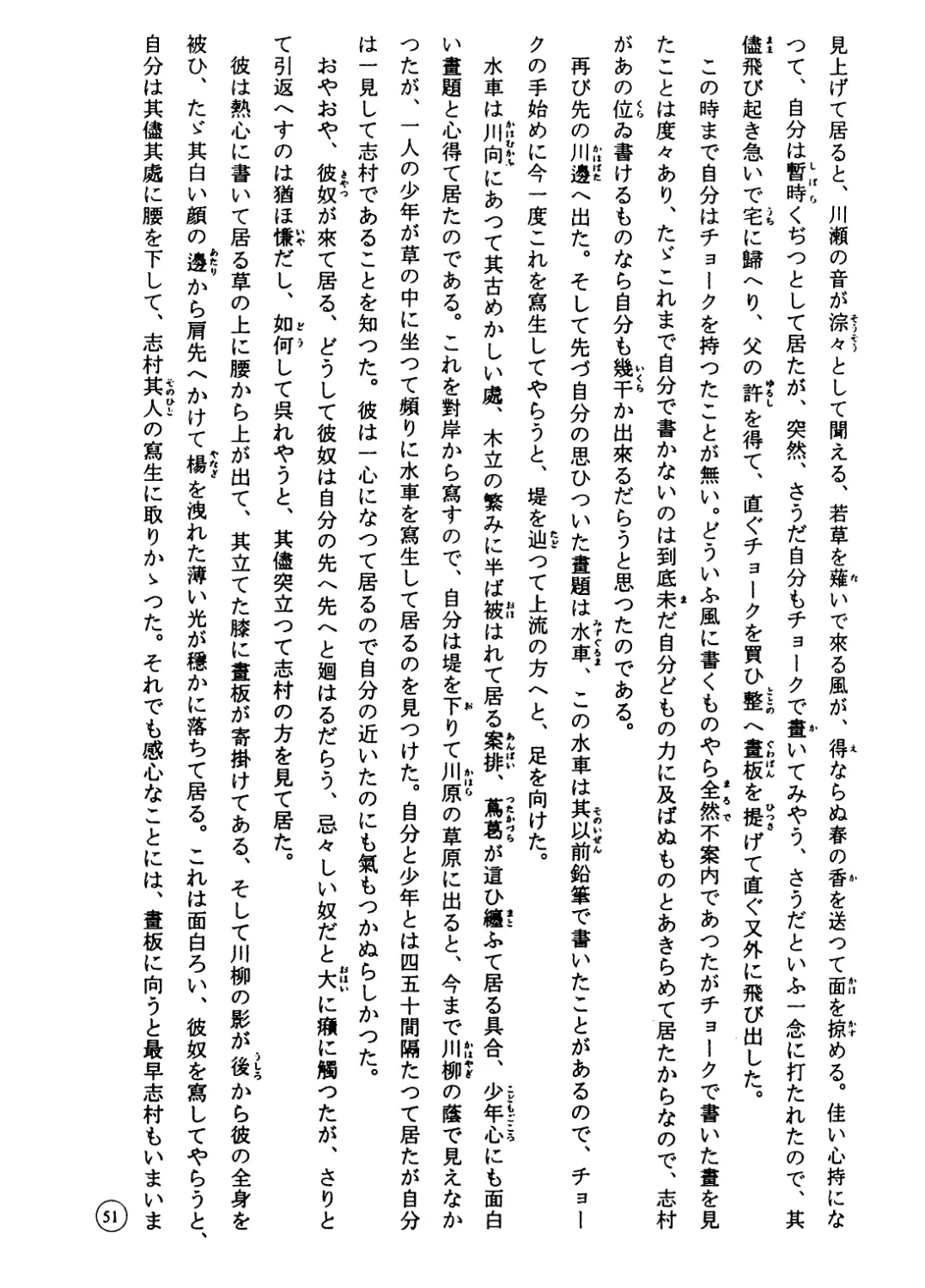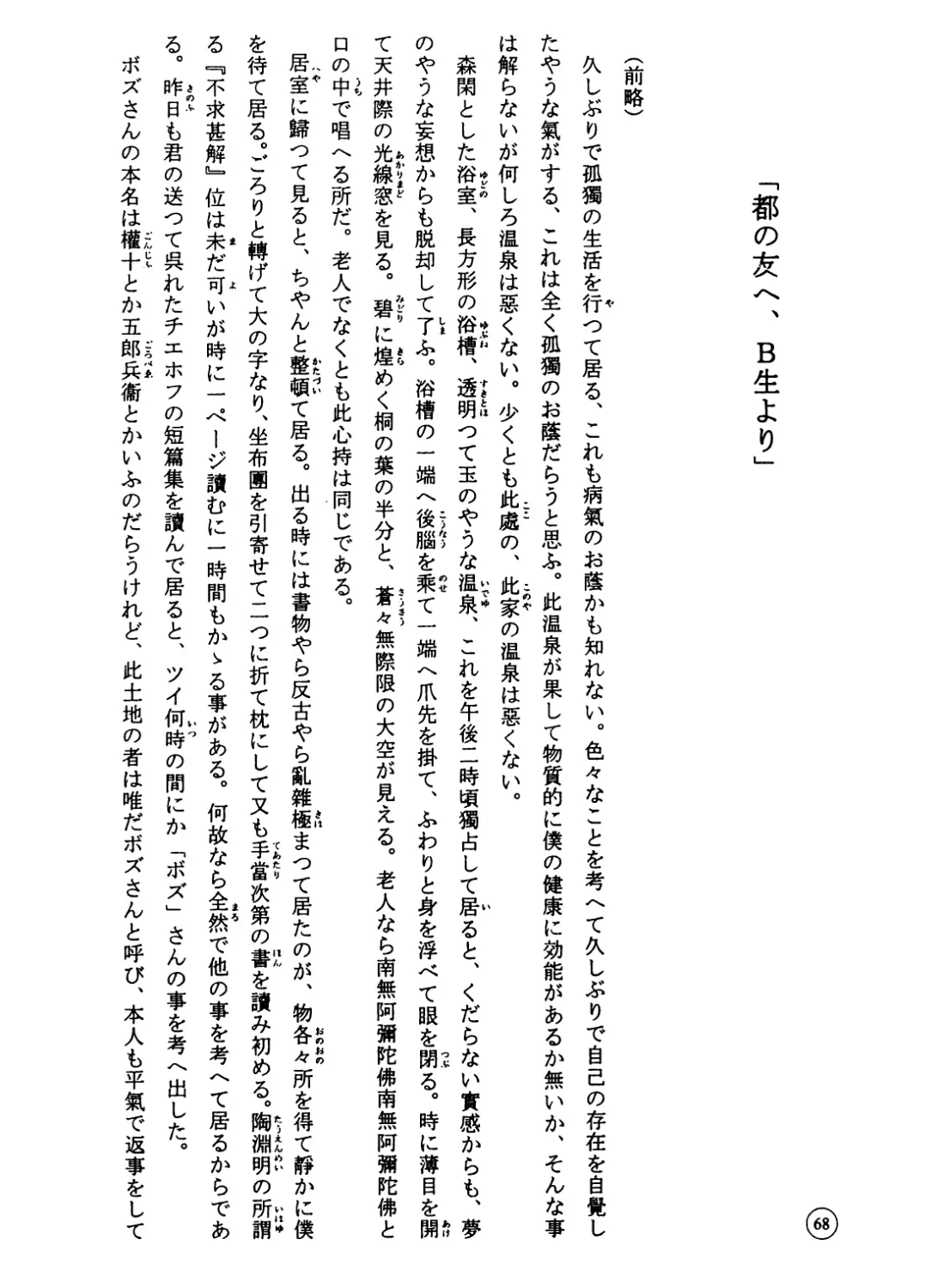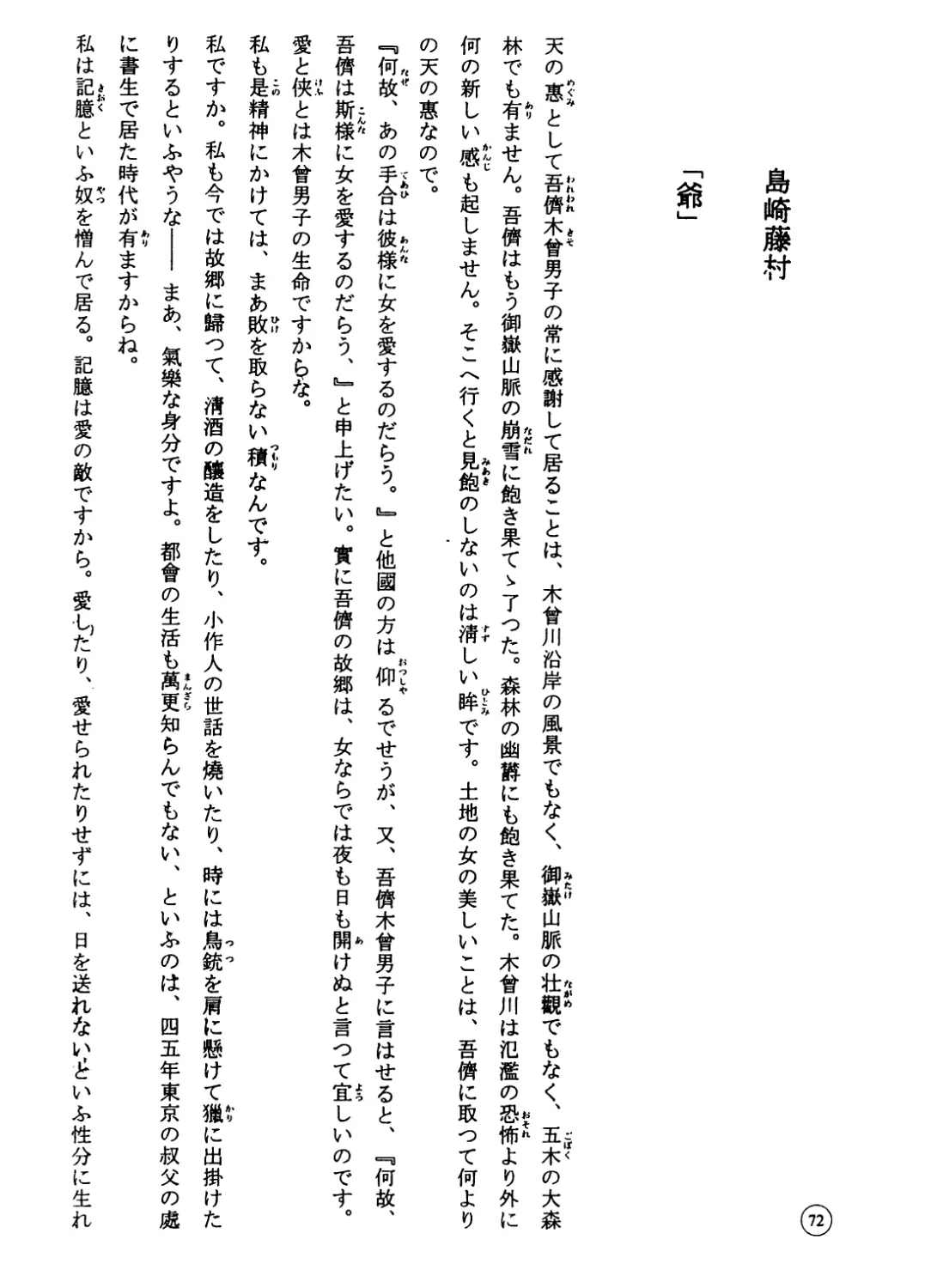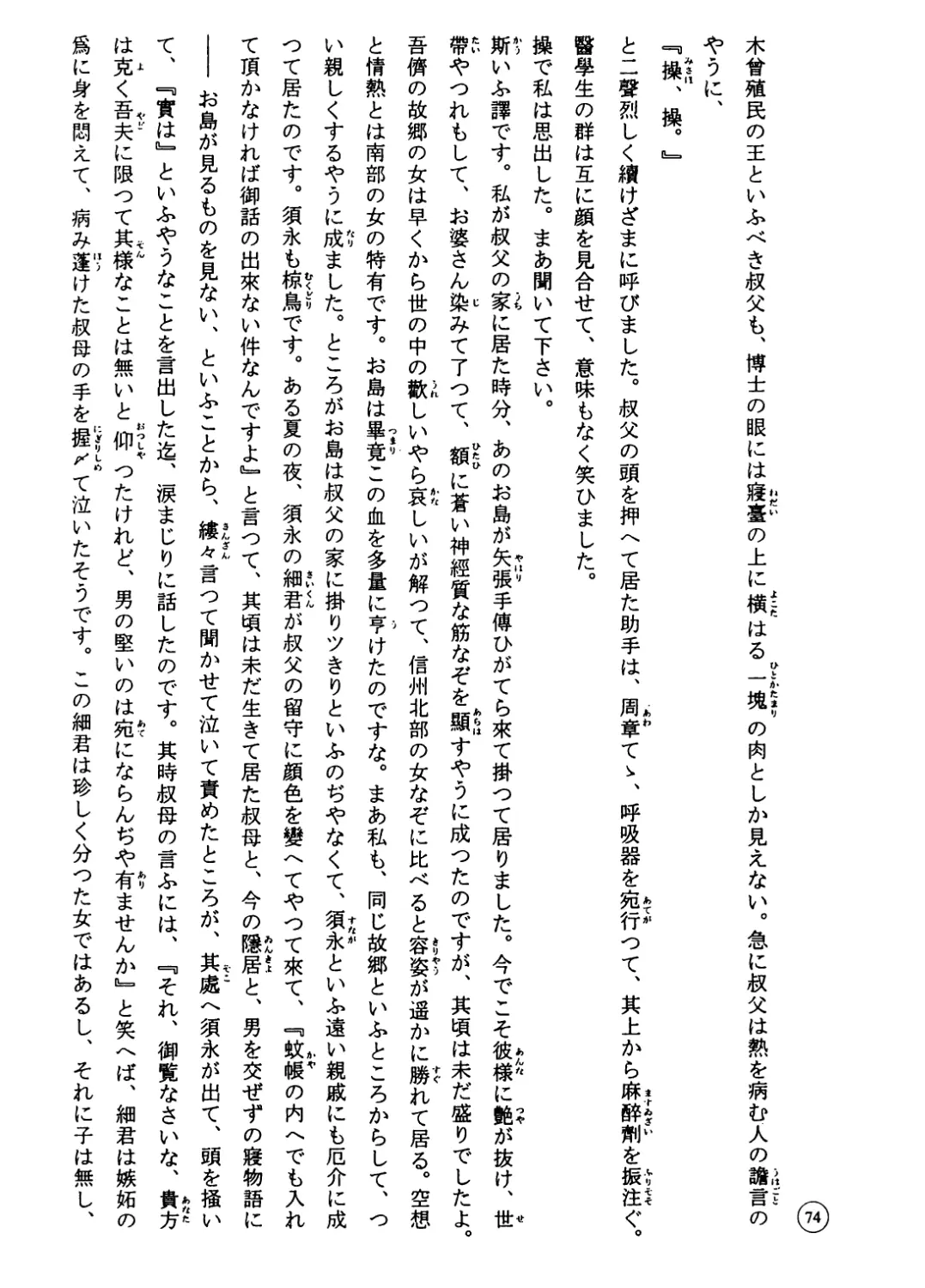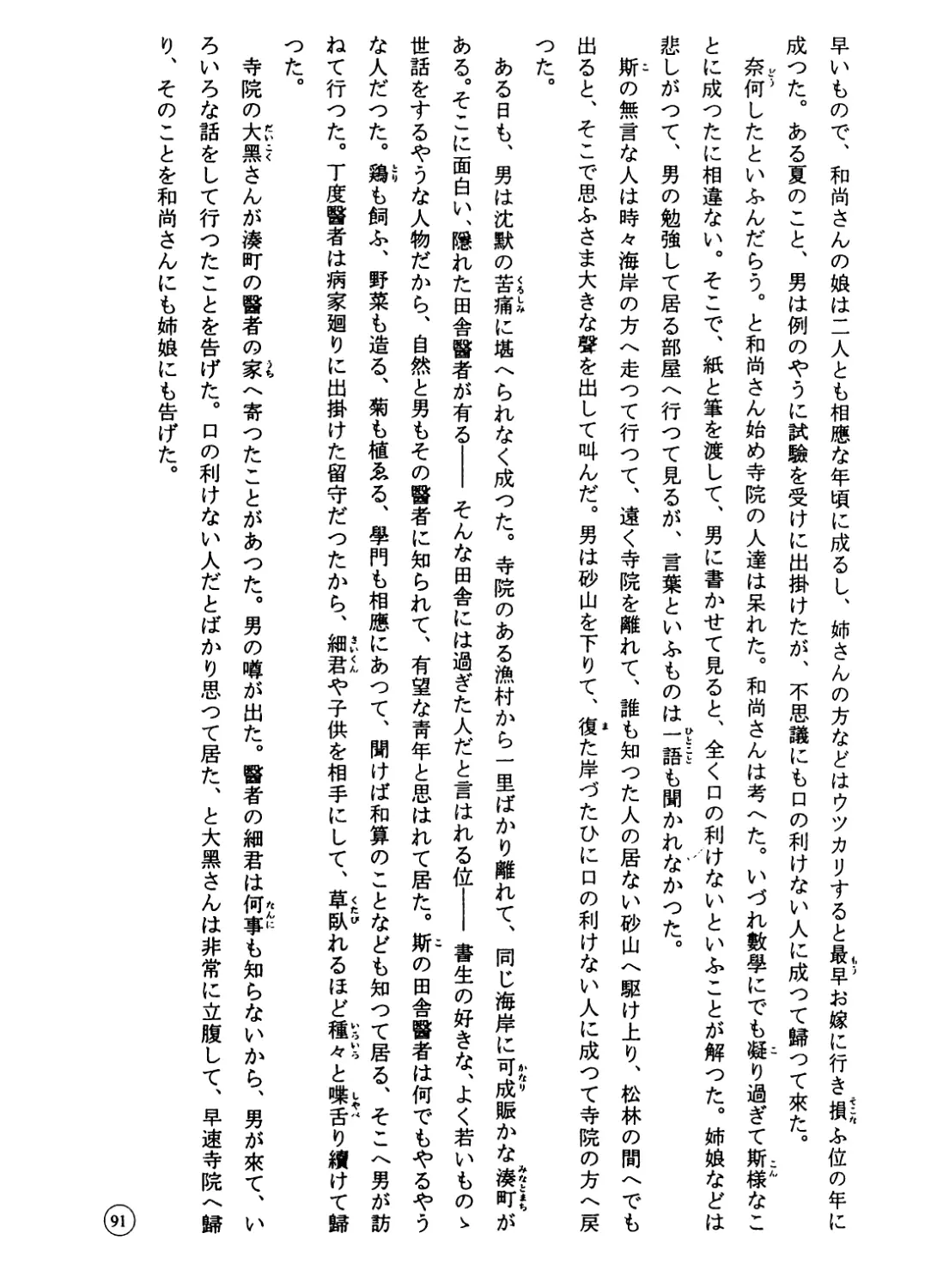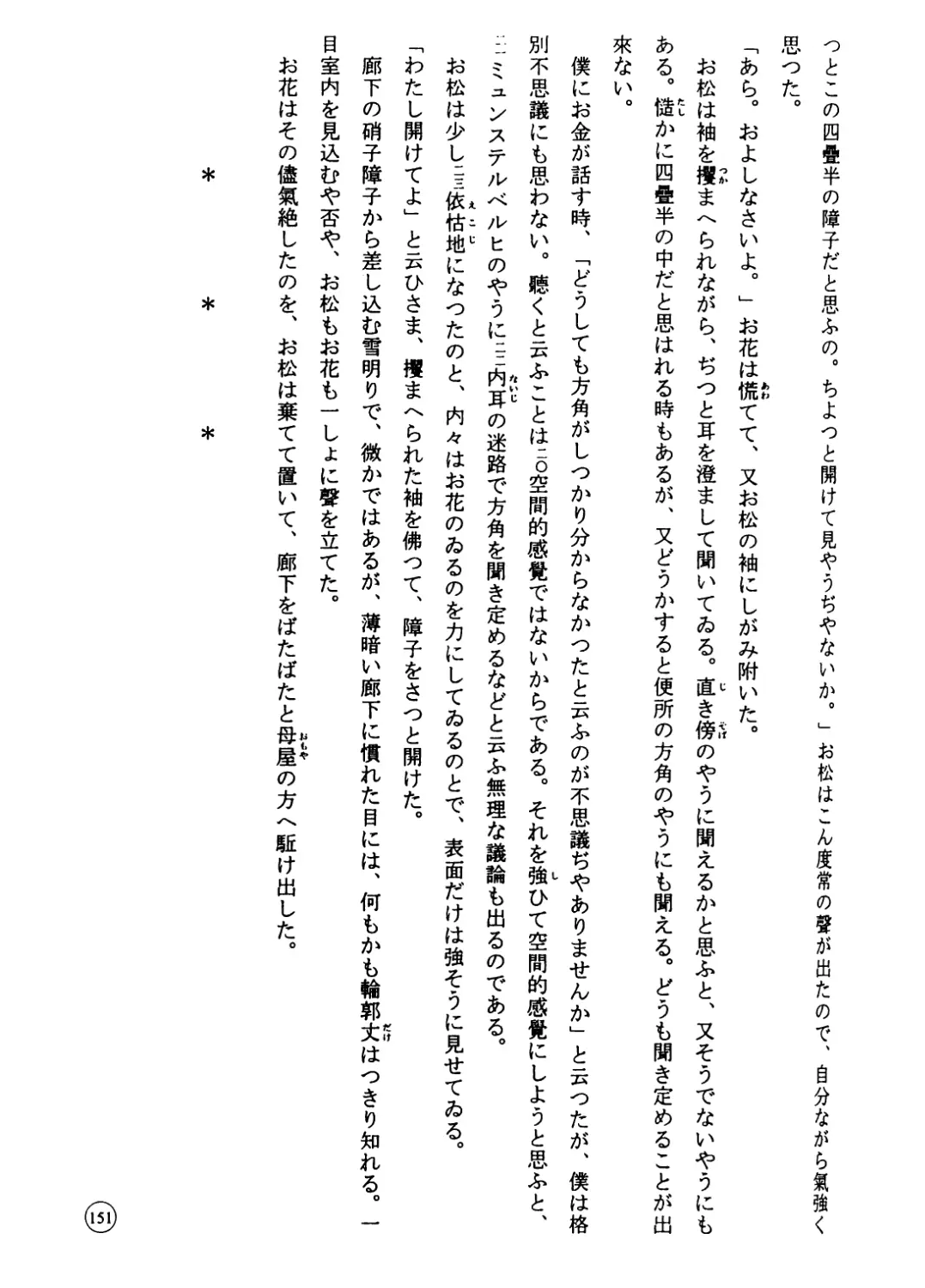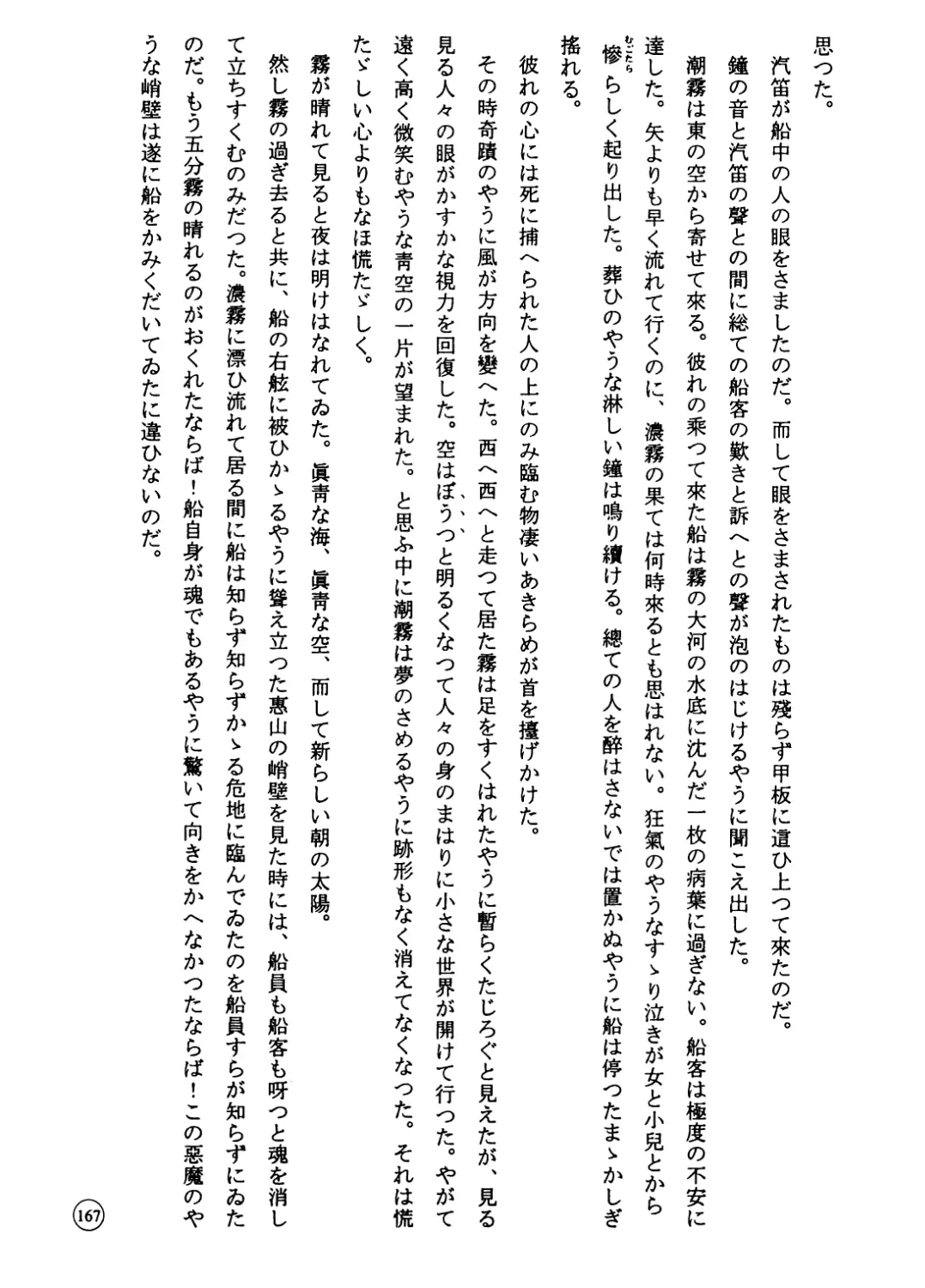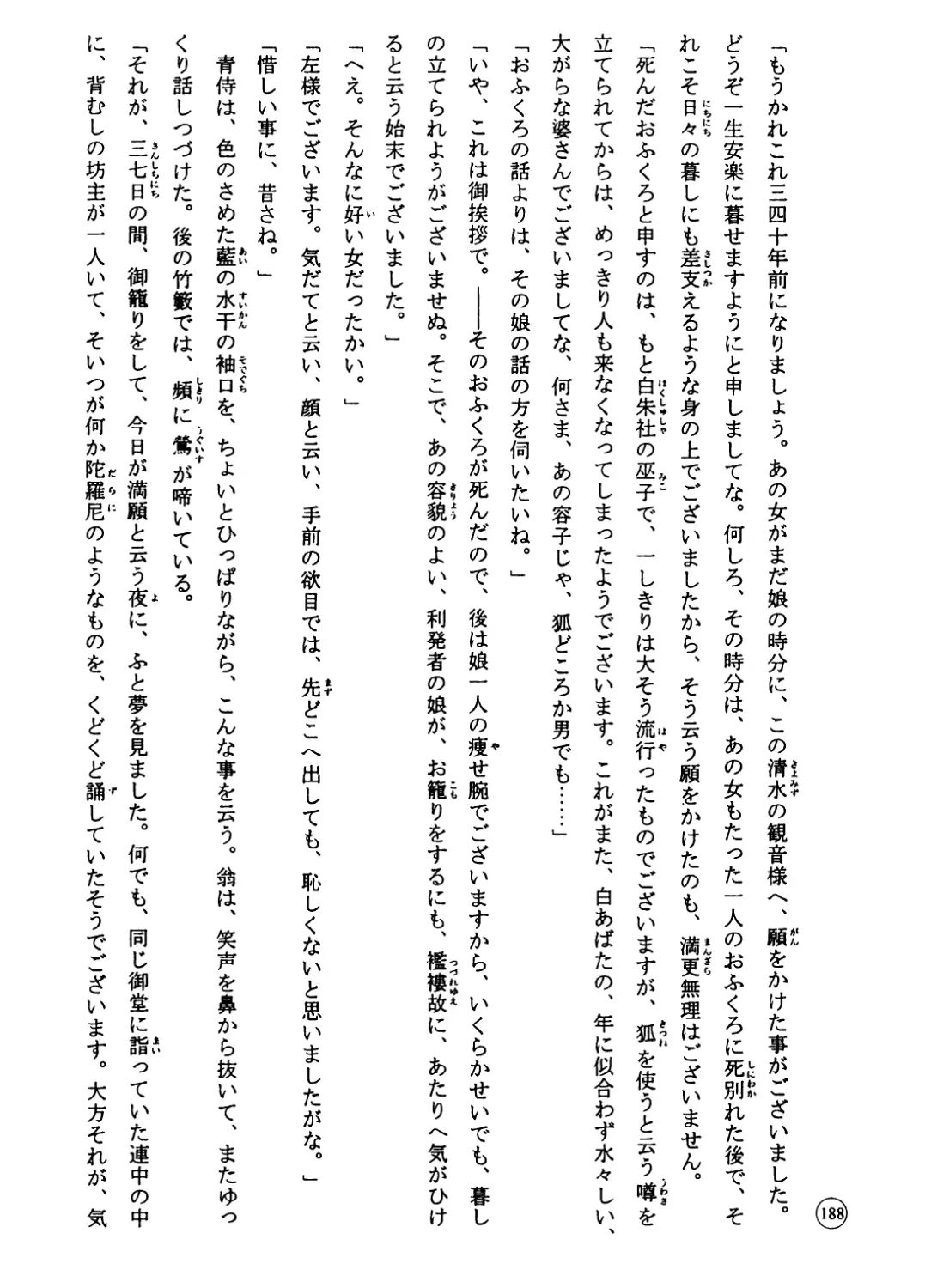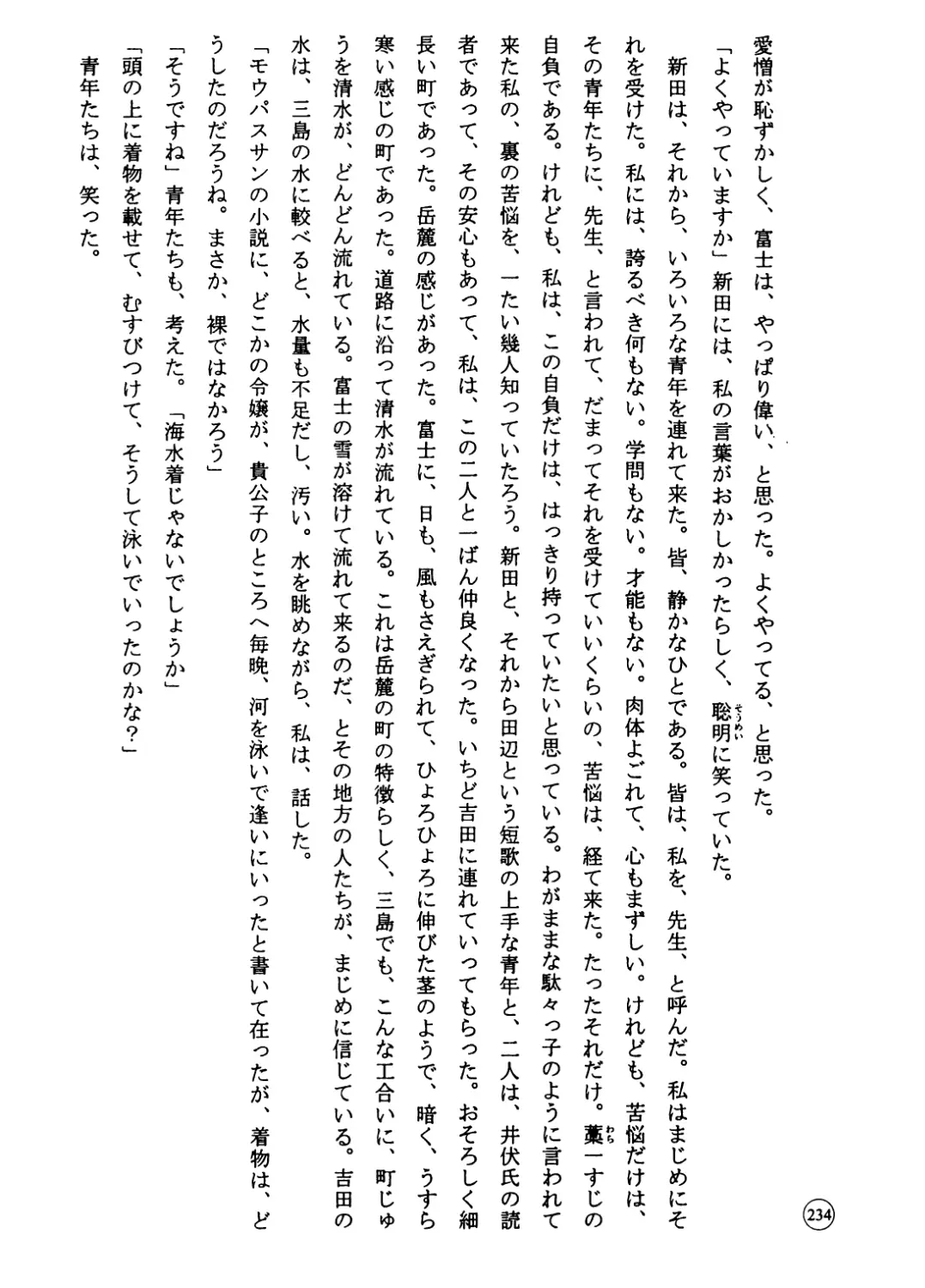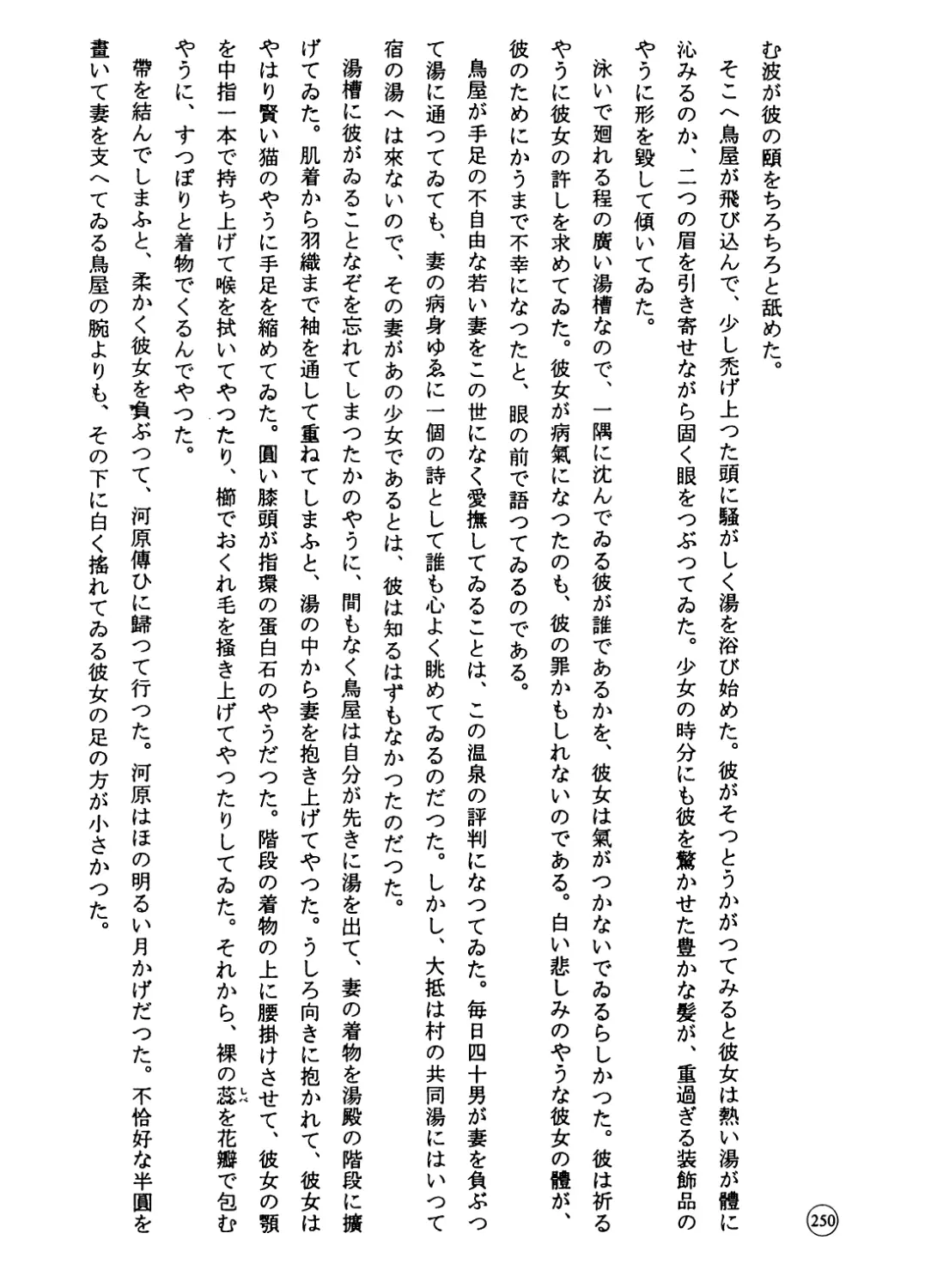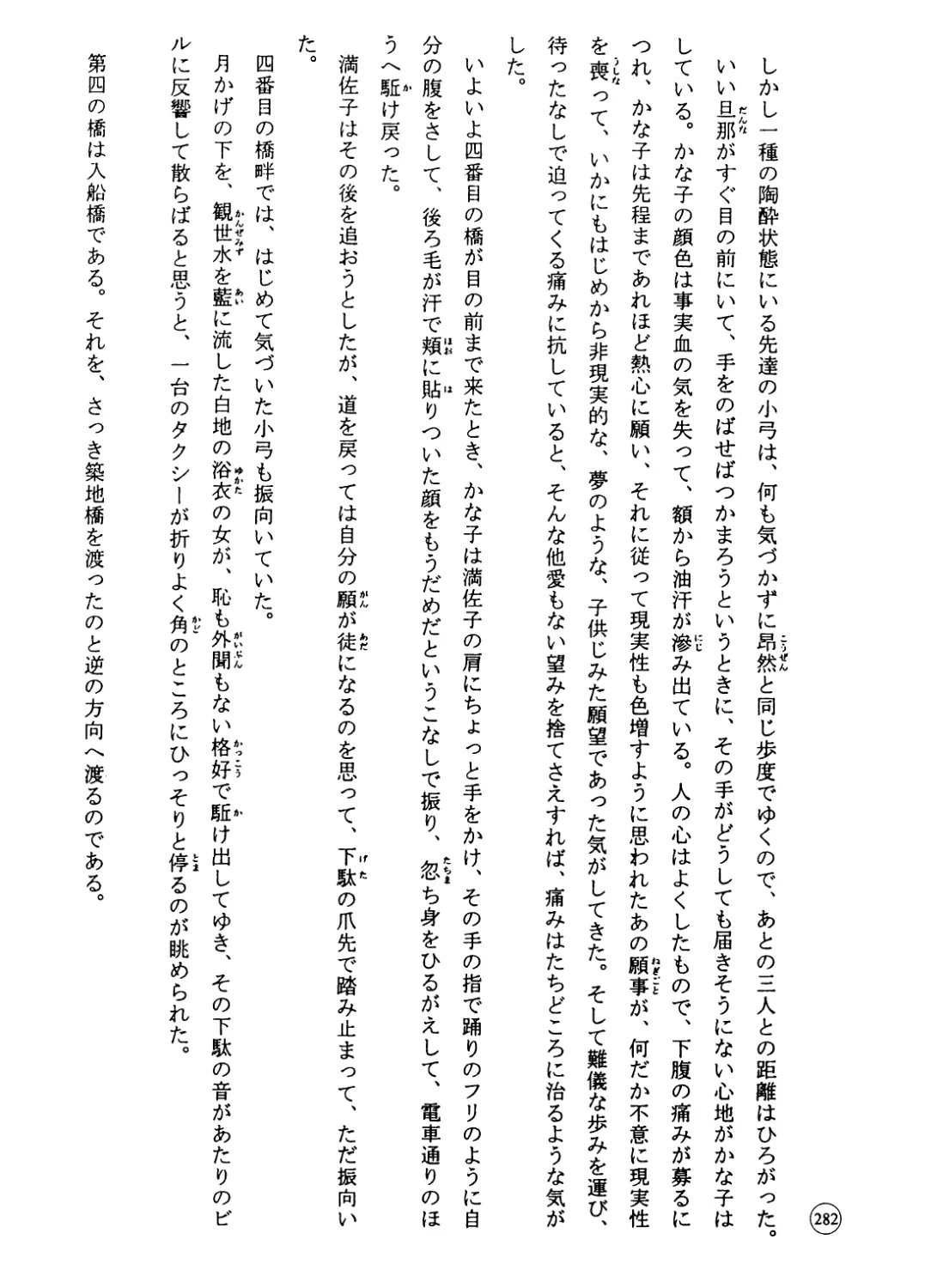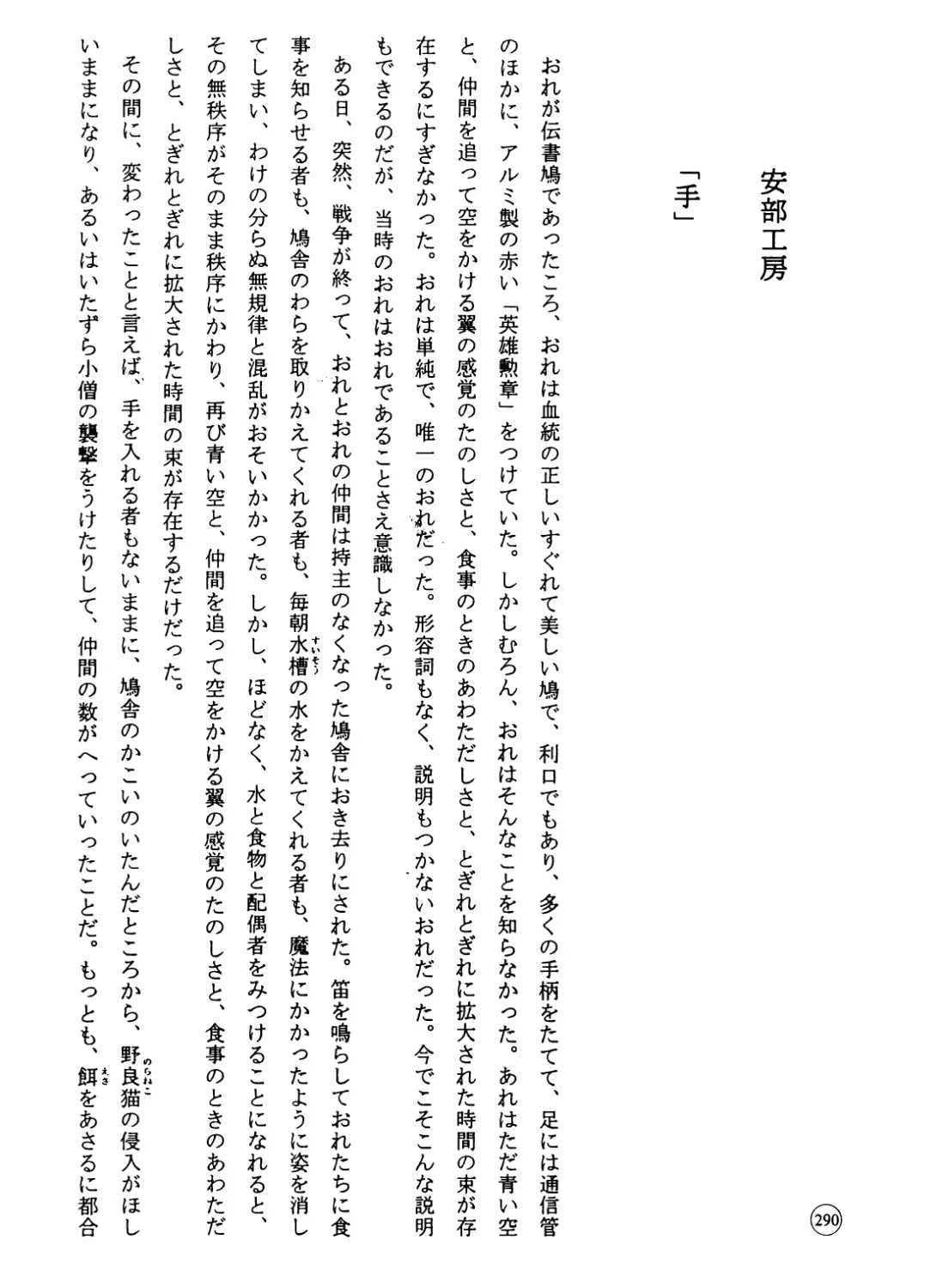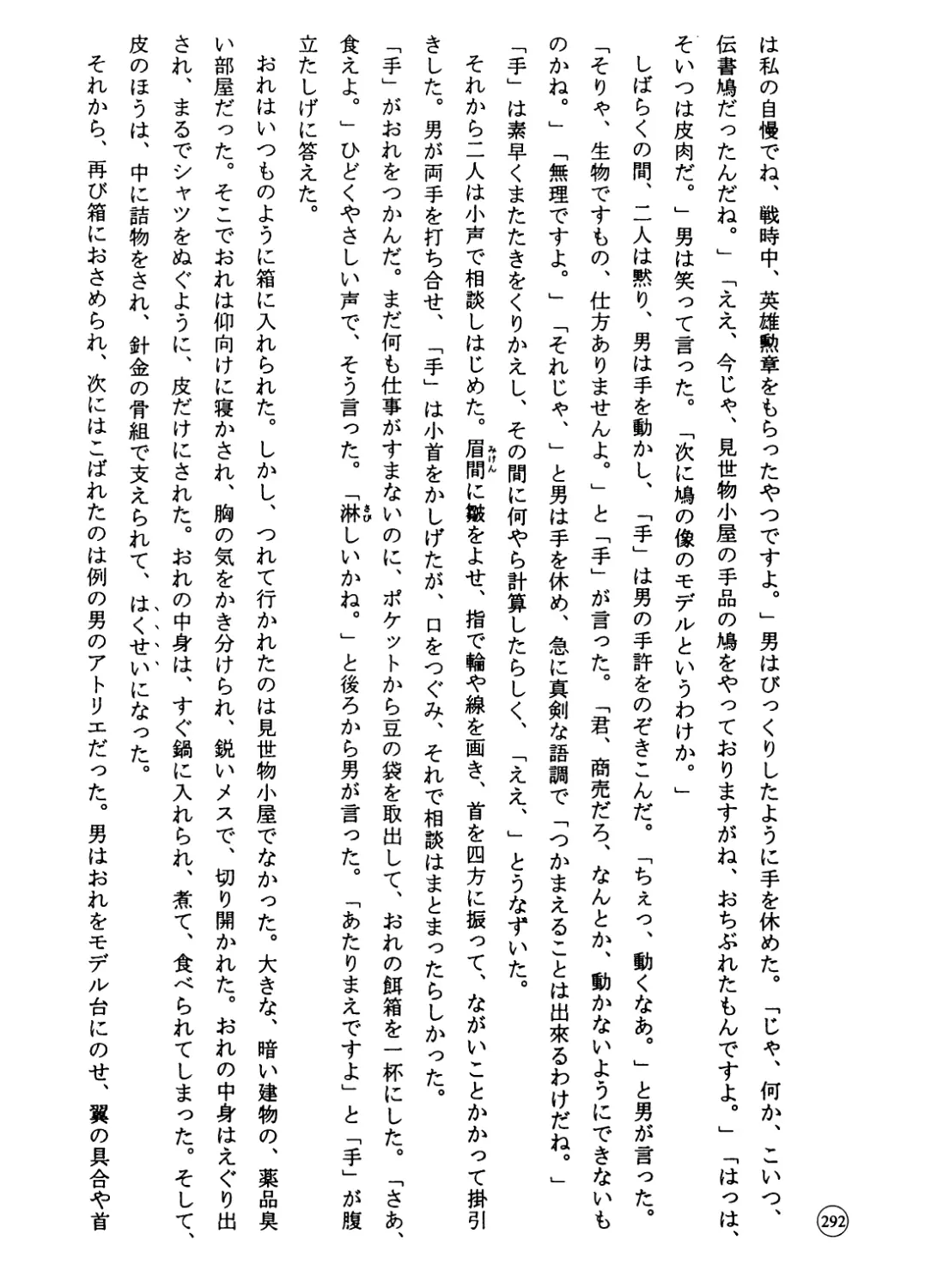Author: Торопыгина М.В. Маранджян К.Г.
Tags: художественная литература японская литература
ISBN: 5-89332-041-7
Year: 2001
Text
ХРЕСТОМАТИЯ по ИСТОРИИ
ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТ УРЫ
том II
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА
СЕРЕДИНЫ XIX-XX ВВ.
Составитель
К. г. МАРАНДЖЯН
Санкт-Петерб ург
«Гиперион»
2001
ББК84 (5ЯПО)я7-3
X79I
Издательство «Гиперион» вмражает благодарность Японскому Фонду за
финансовую помощь в издании этой книги
Рublication of this book was generously supported by a grant
from The Japan Foundation
Данное издание выпущено при поддержке
Института «Открытое общество» (Фонд Сор оса)
Х791 Хрестоматия по истории японской литературы: В 2 т. / Составл.
М. В. Торопыгиной и К. Г. Маранджян. // Т. 2. Художественная
проза середины XIX-XX вв. СПб.: Гиперион, 2001.一 268 с.
Настоящее пособие является вторым томом «Хрестоматии по истории
японской лите ратуры» для студентов-японистов. Оно охватывает пер иод с
сер едины XIX в. вплоть до наших дней. 2-й том «Хр естоматии» включает в
себя произведения семнадцати наиболее значительных японских писателей
сер едины XIX-XX вв.
ББК84 (5ЯПО)я7-3
ISBN 5-89332-041-7
ISBN 5-89332-042-5
© Фтабатэй Симэй, наследники, 2001
© Токутоми Рока, наследники, 2001
© Куникида Доппо, наследники, 2001
© Симадзаки Тосон, наследники, 2001
© Нацумэ Сосэки, наследники, 2001
© Нагаи Кафу, наследники, 2001
© Мори О гай, наследники, 2001
© Арисима Такэо, наследники, 2001
© Сига Наоя, наследники, 2001
© Акутагава Рюноскэ, наследники, 2001
© Миямото Юрико, наследники, 2001
© Танидзаки Дзюнъитиро, наследники, 2001
© Дадзай Осаму, наследники, 2001
© Кавабата Ясунари, наследники, 2001
© Мисима Юкио, наследники, 2001
© Абэ Кобо, наследники, 2001
© Оэ Кэндзабуро, 2001
© К. Г. Маранджян, составление,
комментарии, 2001
© В. В. Неклюдов, о(|)ормление, 2001
© Издательство «Гиперион», 2001
ПРЕДИСЛОВИЕ
Хрестоматия по истории японской литературм середины Х1Х-ХХ вв.
задумана как учебное пособие для студентов-японистов. Идея создания по¬
добной хрестоматии возникла в процессе преподавания японского художе¬
ственного текста студентам Восточного Института (Санкт-Петербург). Не¬
обходимость составления подобной книги вызвана рядом соображений.
Во-первых, отсутствием современных отечественных изданий такого рода.
Во-вторых, нынешние студенты, изучающие японский язык, имеют воз¬
можность ознакомиться с многочисленными пер сводами японской литера-
туры на русский язык. Однако, нам кажется, что в процессе обучения сту¬
денты должны получить представления не только 〇 произвольно отобранных
текстах, а 〇 всем корпусе японской литературы в его эволюции и многооб¬
разии. Существует определенный набор текстов, который в данной литера・
туре может быть определен как «классика». Студенты-гуманитарии долж¬
ны прочитать эти тексты на языке ор игинала, а не только в пер сводах. Именно
эту задачу и призвана решить данная хрестоматия, позволяющая студентам
в р амках занятий по пер своду художественного текста ознакомиться со сти¬
листическим многообразием японской литературы.
Хрестоматия включает в себя произведения семнадцати наиболее зна¬
чительных японских писателей сер едины XIX-XX вв.
Принцип построения хрестоматии следующий: сначала дается краткая справ¬
ка 〇 писателе, затем подробная библиография, включающая в себя переводы
произведений данного писателя на русский язык и исследования его творчест-
ва (на русском языке). Далее следует японский текст ——без перевода, так как
мы сознательно отбирали для хрестоматии произведения, ранее не переводив¬
шиеся на русский язык. Нам кажется правильным включать в хрестоматию
законченные произведения, в основном новеллы или рассказы. Такой подход
позволяет читателю получить целостное представление 〇 тексте, 〇 его стилис¬
тических особенностях и, кроме того, делает процесс чтения более увлекатель¬
ным. Чтение отрывка текста, взятого вне контекста, лишь усложняет его пони¬
мание и более напоминает чтение учебных текстов, необходимых студентам
для отработки тех или иных грамматических конструкций, но никак не позво¬
ляющих оценить своебразие и прелесть художественного текста.
Необходимо сразу оговорить, что в хрестоматии представлена только
叩〇за. Бесспорно, что хрестоматия по истории литературы должна вклю¬
чать в себя произведения японских поэтов, и думается, что в будущем сле¬
дует составить отдельный том по японской поэзии.
В кратких справках 〇 писателях и в обоих указателях пр оставлен^】 дол¬
готы гласных во всех японских названиях и именах, однако в библиографии
написания имен даны в том виде, как они представлены на титульном листе
печатных изданий, другими словами, без обозначения долгот. 1
Тексты произвепений взяты из следующих изданий:
1. Фтабатэй Симэй дзэнсю: [Собрание сочинений Фтабатэя Симэй]. То¬
кио, 1964. Т. 4.
2. Токутоми Рока сю: [Сочинения Токутоми Рока]. Токио: Тикума сёбо:.
1977. Т. 42.
3. Куникида Доппо сю: [Сочинения Куникида Доппо]. Токио: Тикума
сёбо:. 1977. Т. 66.
4. Симадзаки То:сон сю: [Сочинения Симадзаки Тосон]. Токио: Тикума
сёбо:. 1977. Т. 69.
5. Нацумэ Со:сэки сю: [Сочинения Нацумэ Сосэки]. Токио: Тикума сёбо:.
1977. Т. 55.
6. Нагаи Кафу: сю: [Сочинения Нагаи Кафу]. Токио: Тикума сёбо:. 1977.
Т. 73.
7. Мори 〇:гай дзэнсю: [Соб рание сочинений Мори О гай]. Токио: Тику¬
ма сёбо:. 1974. Т. 2,3.
8. Арисима Такэо дзэнсю: [Собрание сочинений Арисима Такзо]. Го-
кио, 1924. Т. 2.
9. Сига Наоя сю: [Сочинения Сига Наоя]. Токио, 1962. Т. 25.
! 〇. Акутагава Рю:носкэ сю: [Сочинения Акутагава Рюноскэ]. Токио, 1926,
Т.1.
11. Миямото Юрнко сю: [Сочинения Миямото Юрико]. Токио, 1954. Т. 35.
12. Танидзаки Дзюнъитиро: дзэнсю: [Собрание сочинений Танидзаки
Дзюнъитиро]. Токио, 1977. Т. 8.
13. Цадзай Осаму. Хасирэ Мэросу. Токио, 1978.
14. Кавабата Ясунари дзэнсю: [Собрание сочинений Кавабата Ясунари].
Токио, 1973. Т.З.
15. Мисима Юкио сю: [Сочинения Мисима Юкио]. Токио, 1987. Т.15.
16. Лбэ Ко:бо:. Суйтю:тоси. Дзндорокакария. Токио, 1996.
17. 〇:э Кэндзабуро:. Сися-но сгори. Сиику. Токио, 1996.
ФТАБАТЭЙ СИМЭЙ (1864-1909)
Писатель и переводчик, основоположник японского критического реа・
лизма, реформатор литературного языка, знаток русской культуры, автор
работ по теории перевода.
Фтабатэй Симэй (настоящее имя — Хасэгава Тацуноскэ) родился в Эдо
(Токио), в 1864 г. в самурайской семье. Мечтая 〇 дипломатической карьере, в
1881 г. поступил на русское отделение Токийского Института Иностранных
языков. Знакомство с творчеством Гоголя, Тургенева, Гончарова, Достоев¬
ского, со статьями Белинского и Добролюбоваопределило профессиональный
выбор Фтабатэя — он решил посвятить себя литературной деятельности. В
эти же годы он сблизился с известным переводчиком и писателем Цубоути
Сё:ё: (1859-1935), дружеское покровитепьство которого помогло начинаю¬
щему авт ору опубликовать в 1887 г. первую часть романа «Укигумо» («Плы¬
вущее облако»). Публикация романа завершилась в 1889 г. и поначалу не
принесла успеха. Небольшое по объему произведение носило новаторский
характер — созданное в традициях критического реализма оно рассказыва-
ло исторню провинциального юноши, приехавшего в столицу и столкнув¬
шегося с двуличием и цинизмом окружающих его людей. Новизна романа
про явилась и в его языке 一 живом, близком к разгор ному. Именно Фтаба¬
тэй, как считают японские литературоведы, ввел в тирокий обиход стиль
«гэмбун итти» (единство разговорной и письменной речи) и стал создате¬
лем нового литературного языка.
Настоящее rip изнание и успех Фтабатэю пр инесли его пер своды. В 1888 г.
вышел в свет перевод рассказа Тургенева «Свидание» (из «Записок охотни¬
ка»), который был не только пер вым пер сводом (в противоположность пред¬
шествующей пр актике адаптаций), но и пер вым художественным пер сводом
литературного произведения на японский язык. Последующие переводы про¬
изведений Тургенева («Ася», «Рудин» и др.), Гоголя, Л. Толстого, Л. Андрее¬
ва, русской критики и публицистики стали неотъемлемой частью японской
лите ратуры.
Литературная деятельность не приносила денег; поэтому Фтабатэй уст-
роился на работу в Управление по делам печати при кабинете министров,
где он ггроспужил 9 лет. Затем некоторое время преподавал русский язык,
работал в Харбине и Пекине, потом стал корреспондентом газеты «Осака
Асахи Симбун». Все эти годы он не прекр ащал заниматься пер сводом. 1904-
1909 гг. были очень плодотворной порой в жизни писателя. В 1906 г. был
опубликован новый роман «Соно омокагэ» («Его образ»), а в 1907 г. вышел
полуавтобиографический роман «Хэибон» («Обыкновенный человек»).
К этому пер иоду относится увлечение Фтабатэя языком эспе ранто, кр еп-
нут его связи с Россией, он сотрудничает с русскоязычным еженедельником
«Восток», издающимся в Иокогама. В 1908 г. в качестве корреспондента -—
газеты «Асахи» он отп равняется в Пете рбург, но веко ре заболевает туберку¬
лезом и решает вернуться в Японию.
Он скончался 10 мая 1909 г. на борту судна «Камомару» в Бенгальском
заливе по пути на родину.
В хрестоматию включен(j)pагмент (9-21 главы) из романа «Обыкновен¬
ный человек» («Хэйбон»,1907).
Литература 〇 Фтабатэй Симэй
1. Карлина Р. Г. Творческие связи Хасэгава Фтабатэя с русской литера・
турой / В КН.: Японская лите ратура. Исследования и мате риалы. М.,1959.
2. Цоктоева Т. Н. Фтабатэй Симэй — переводчик русской литературы.
(Переводм произведений И. С. Тургенева на японский язык) / Автореф. дисс.
на соискание ученой степени канд. филол. наук. Л., 1983.
3. Цоктоева Т. Н. Первый из японских русистов / В кн.:100 лет русской
культурн в Японии / Под реп. Л. Л. Громковской. М.,1989.
Переводы на русский язык
1.Фтабатэй Симэй. Мои принципы художественного пер свода / В кн.:
Восточный альманах. Вып.1./ Пер. Р. Карлиной. М.,1957.
ТОКУТОМИ РОКА (1868-1927)
Классик новой японской литературы, автор популярных «семейных» и
«социальных» романов, очерков, эссе и дневников путешествий.
Настоящее имя ——Токутоми Кэндзиро:, псевдоним Рока ——«Цветок тро・
стника»). Родился в префектуре Кумамото в семье мелкого землевладельца.
Вместе со своим братом Токутоми Иитиро: (псевдоним Сохо:, впоследст¬
вии известный публицист и историк) учился в христианском колледже
«До:сися» (Киото), нз которого вышло немало крумных политических дея¬
телей и журналистов. В 17 лет принял христианство. В конце 80-х годов
сотрудничал с издательством «Минью:ся» («Общество друзей народа»),
р аботал в редакции либе рального жур нала «Кокумин-но том о» («Друг на¬
ро да»). В 1898 г. печатает в газете «семейный» роман «Хототогису» («Ку¬
кушка» 一 в русском переводе «Лучше не жить»), которой рассказывает
историю тратической любви молодых супругов, разлученных по воле стар・
ших родственников. Роман имел огромный успех и был издан отдельной
книгой в 1900 г. В 1900 г. вышел в свет сборник «С и дзэн то дзинсэй» («При-
рода и человек»), на следующий год роман «Омоидэ-но ки» («Летопись вос¬
поминаний», 1901),а спустя два года был опубликован ро ман «Ку рос ио»,
критиковавший политический строй японского общества тех лет. В 1906 г.
Токутоми Рока соверожл путешествие в Палестину, а затем в Росеню — он
посетил Ясную Поляну, где провёп пять дней вместе со своим давним куми-
ром и учителем Львом Толстым. Вернувшись в Японию, он решил последо¬
вать примеРУ Толстого, т. е. перебраться в деревню и посвятить себя крес¬
тьянскому труду. Писатель поселился в небольшом поселке Касу я, недалеко
от Токио (отсюда его новый литературный псевдоним «отшельник из Ка-
суя»). Впечатления тех лет легли в основу сбор ника «Мимидзу-но тавагото»
(«Бормотанье земляного червячка»,1913), который, по словам П. И. Конра・
да, был одним из лучших по своим художественным достоинствам произ・
ведений мэйдзийской литературы. Рсальная «жизнь на земле» оказалась не
столь идиллической и романтичной как рисовалось вначале——Токутоми
Рока вернулся в Токио, лишь время от врсмени заезжая в Касуя. С этого
врсмени в его творчестве начинают преобладать автобиографические мо¬
тивы. Роман «Курой мэ то тяироно мэ» («Черные глаза и карие глаза»,1914)
рассказывают 〇 его юношеской любви, романы «Си-но кагэ-ни» («Под се¬
нью сме рти»,1917) и «Синсюн» («Новая весна»,1918) про должают тенден¬
цию «самообнажения» художника. Сам писатель называл «Новую весну»
«золотым ключом к своей жизни» 一 в ней нашли отражение многие размы¬
шления, впечатления и воспоминания 1'окутоми Рока. В 1919 г. он отправля・
ется в кругосветное путешествие, которое длится больше года ——в результа-
те появляется книга «Нихон-кара Нихон-э» («Из Японии в Японию»), в которой
рассказывается 〇 сокровенном смысле путешествия, которое, по мнению Z_.
Токутоми Рока, было предписано ему Богом. В последние годы жизни он
начинает работу над большим автобиограбическим романом «Фудзи» (1925-
1927), но успевает издать только две части ——после смерти роман заканчи¬
вает его жена. Токутроми Рока умер в 1927 г. Он похоронен в своей усадьбе
в Касу я.
В хрестоматию включен отрьibok из книги «Бормотанье земляного чер-
вячка» («Мимидзу-но тавагото»,1913), раздел «Пшеничные и рисовые ко¬
лосья», глава «Год в деревне» («Мура-но итинэн»).
Литература 〇 Токутоми Рока
1. Конрад И. И. Токутоми Рока» / В кн.: Конрад Н. И. Японская литера¬
тура. М.,1974.
2. Громковская Л. Л. Токутоми Р ока. Отшельник из Касу я. М.,1983.
Hepеводы на русский язык
1. Току томи Рока. Куросиво / Пер. И. Львовой. М.,1957.
2. Токутоми Рока. Пр ирода и человек.(① р агменты) / В кн.: Восточный
альманах. Вып.1./ Пер. Е. Пинус. М., 1958.
3. Токутоми Рока. Избранное / Пер. Е. Пинус. Л., 1978.
4. Токутоми Кэндзиро. Лучше не жить. СПб., год не указан.
5. Токутоми Рока. Воспоминания. Японский паломник / В кн.: Литера・
турное наследство. Т. 75, кн. 2. М.,1965.
КУНИКИДА ДОППО (1871-1908)
Поэт и новеллист. Настоящее имя Куникида Тэцуо. Доппо ——литератур¬
ный псевдоним («Одинокий стр ан и и к»). Традиционно считается одним из
основателей реалистического направнения в литературе, однако многие кри¬
тики относят его произведения (особенно ранние) к романтическому на-
пр авлению.
Родился в префектуре Тиба. Учился на английском отделении Токе Сэм-
мон Гакко: (нынешний университет Васэда), в 1890 г. из-за конфликта с на¬
чальством был вынужден уйти из университета и вернулся в префектуру
Ямагути, где начал преподавать английский язык. В 1892 г. возвращается в
Токио и сотрудничает в газете «Дзию: симбун» («Свобода»). С началом япо¬
но-китайской войны поступает в штат газеты «Кокумин симбун» («Народ・
ная газета») и в качестве военного журналиста отправляется в Китай. В 1895
г. он женится на Сасаки Нобуко, чей образ послужил прототипом『ероини
знаменитого ро мана Арисима Г акэо «Ару он на» («Женщина»), но брак про¬
длился недолго. Покинутый женой Доппо тяжело переживал разрыв ——свое
смятение и мучения он описал в «Адзамукадзару・но ки» (1893-1897) («От-
кровенные записки»). Вскоре он организовал небольшое издательство, ко¬
торое просутествовало несколько лет. Находясь под влиянием Вордсворта
и Карлейля, Доппо начинает как поэт-ро мантик, выпустив сбор ник стихов
«Доп по ГИИ» («Песни Доппо», 1897-1899). В 1897 г. он написал свой пер¬
вый рассказ «Гэн одзи» («Дядя Гэи»), который снискал себе славу самого
〈〈романтического» рассказа писателя. В 1901 г. выходит книга очерков «Му-
саси но» («Равнина Мусаси»), которая, по словам Н. И. Конрада, была «од¬
ним из лучших произведений этого жанра во всей мэйдзийской литерату・
ре». Она была посвящена поэтическому описанию осени в знаменитой
долине Мусаси и во многом была иавеяна творчеством Тургенева, которого
Куникида Доппо хорошо знал и любил. Он даже вставил в свой очерк це¬
лый 巾рагмент из «Свидания» Тургенева.
В следующие годы (1901-1904) в творчестве писателя начинают зву¬
чать реалистические мотивы, его новой темой становится проблема соот¬
ношения «действительности» и «идеала». Наиболее известные рассказы той
поры — «Гю:нику то барэйсё» («Мясо и картофель»,1901),«Уммэй ронся»
(«①аталист,1903), «Хару-но тори» («Весенняя птица»,1904). Последний
пер иод (1904-1908) считается чисто р еалистическим этапом его твор чест¬
на, когда в произведениях Доппо начинают звучать социальные темы. Они
раскрываются в таких рассказах как «Кюхи» («Жалкая смерть»,1907), «Такэ-
но кидо» («Бамбуковая калитка»,1908).
Доппо не написал ни одного крупного по размерам произведения, в кон¬
це жизни он начал работу над романом «Ураган», но не успел его завер¬
шить. Он умер от туберкулеза в 1908 г. в возрасте тридцати восьми лет. £
Акутагава Р ю:носукэ писал: «У Доп по был ост рый ум, и потому он не
мог не видеть землю. У него было нежное сердце, и потому он не мог не
видеть неба.... К несчастью, эти черты не гармонировали, и жизнь его была
трагической». [(3]
В хрестоматии представлены четы ре рассказа: «Тоска по р исованию»
(«Э-но канасими»,1902), «Полицейский» («Дзюнса»,1902), «Шляпа»
(«Бо:си»,1906) и «Столичному другу от господина В.» («Мияко-но томо-э,
В-сэй ёри»,1907).
Литература 〇 Куникида Доппо
1. Конрад Н. И. Лекции по японской литерату ре пер иода Мэйдзи / В кн.:
Очерки японской литературь1.М.,1973.
2. Григорьева Т. П. Одинокий странник. 〇 японском писателе Куникида
Доппо. М.,1967.
3. Григорьева Т. П. Японская литература XX века. М.,1983.
Repеводы на русскни язык
1.КуникидаДоппо. «Избранные рассказы» / Пер. и послесловие Т. Гопе-
хи. М.,1958.
СИМАДЗАКИ ТО:СОН (1872-1943)
Романтический поэт, про заик. Один из родон ач аль ни ков свободного сти¬
ха. Автор знаменитого романа «Нарушенный завет», ставшего поворотной
вехой в становлении критического реализма в японской литературе.
Настоящее имя ——Симадзаки Харуки. Родился в деревне Магомэ (пре・
фектура Нагано) в семье деревенского старосты. В 1887 г. поступил в проте¬
стантский колледж «Мэйдзи Гаку ин» и пр инял хр истианство. Уже в 1892 г.
появились первые литерату рные пер своды Тохона. К этому же времени от¬
носится и знакомство с Китам ура То:коку, известным поэтом и кр итиком. В
январс 1893 г. Китамура То:коку, Симадзаки То:сон и другие молодые лите-
раторы организовали журнал «Бунгакукай» («Литературный мир»), в кото-
ром опубликовал свои первые стихи молодой То:сон. В 1897 г. он издает
сборник «Ваканасю:» («Молодые травы»), который сразу делает его извест¬
ным. За ним последовали сбор ники «Хитохабунэ» («Кораблик»,1898).
«Нацу-но гуса» («Летние травы»,1898) и «Ракубайсю:» («Опавшие цветы
сливы»,1901).
В 1899 г. То:сон покидает Токио м переезжает в маленький「ородок Ко-
моро, где получает место учителя. Здесь он пробует себя как про заик, со¬
здав серию очерков «Тикумагава-но скэтти» («Очерки реки Тикума»), кото-
рые публикует лишь много позже 一 в 1912г.
В 1906 г. появляется ставший знаменитым роман «Хакай» («Нарушен¬
ный завет»), рассказывающий 〇 бесправном положении касты японских
париев («эта»). Роман, написанный в духе натурализма («сидзэнсюги»), оз¬
наменовал отход Симадзаки Тохон от романтизма. В 1907 г. выходит но¬
вый роман «Хару» («Весна»), рассказывающий 〇 годах юности писателя, 〇
его дружбе с Китам ура То: коку, 〇 лите ратурном кружке «Бунгакукай». В
центре внимания романа «Иэ» («Семья»)——история двух тесно связанных
между собой семей, терпящих крах в новых историчсскнх условиях. Лите-
ратурные критики единодушно выделяют этот роман как второе по значи¬
мости произведение Тохона. В дальнейшем творчестве писагеля происхо¬
дит перелом ——он отходит от общественно-политической гематики и
обращается к жанру психологического романа (относимого в Японии к жанру
«повестей 〇 себе»). В романе «Синсэй» («Новая жизнь») писатель откро・
венно и правдиво описывал любовную связь со своей племянницей——по¬
явление этой книги вызвало целый скандал и негодование публики. Ав-
тобиограбическая линия была продолжена в повестях «Араси» («Буря»,
1926) и «Бумпай» («Раздел»,1927). Третий этап в творчестве писателя свя¬
зан с работой в жанре исторического рОмана. В 1928 г. Симадзаки То:сон
начинает писать большой роман 〇 событиях времен резолюции Мэйдзи
«Ёакэмаэ» («Перед рассветом»)——он выходит в свет в 1935 г. Следующий Li_
роман «То:хо:-но мон» («Врата на Восток»), замысленный как продолже-
ние «Ёакэмаэ», так и не был завершен — Симадзаки То:сон умер в 1943 г.
Одной из отличительных особенностей творческой манеры писателя был
живой разговорный язык его произведений. И хотя То:сон не был новато-
ром в языке ——но в отличие, например, от Фтабатэя Симэй он показал, что
раз го в ор ным я зыком могут быть написаны не только диалоги, но и всё про¬
изведение целиком. По меткому определению Н.①ельдман, То:сон пишет
как бы тонкой прозрачной аква релью, часто только намечая оче ртани я, поз¬
воляя читателю дор исовать целую кар тину по одной-двум деталям.
В хрестоматию вошли два рассказа: «Старик» («Оядзи»,1903) и «Мол¬
чун» («Мугон-но хито»,1912)
Литература 〇 Симадзаки Тосон
1. Гривиин В. С. Симадзаки Тосон. Био-библиограбический указатель.
М.,1957.
2. Маркова В, Н. Симадзаки Тосон / В кн.: Восточный альманах. Вып. 2.
М.,1958.
3. Конрад Н. И, 〇 некоторых писателях пери ода Мэйдзи. Симадзаки
Тосон / В КН.: Конрад И. И. «Японская литература». М.,1974.
4. Шефтелевич Н. С. Новая японская поэзия. Симадзаки Тосон. М.,1982.
5. Долин Л. Л. Японский романтизм и становление новой поэзии. М.,
1978.
Пер своды на ру сский язык
1. Симадзаки Тосон. Нарушенный завет / В кн.: Мори Огай. Дикий гусь.
Танцовщица. Симадзаки Тосон, Нарушенный завет / Нер. Н. Фельдман. М.,
199〇.
2. Симадзаки Тосон. Семья / Пер. Б. Поспелов, А. Рябкина. М.,1966.
3. Симадзаки Тосон. Ранняя весна / В кн.: Шефтелевич Н. С. Новая япон¬
ская поэзия. Симадзаки Тосон. М.,1982
НАЦУМЭ СО:СЭКИ (1867-1916)
Крумный писатель, автор шестнадцати романов, повестей и рассказов,
поэт, литературовед, переводчик, знаток китайского языка и культуры. Его
влияние на японскую литературу было столь велико, что целое десятиле¬
тие 一!905-1916 一 получило название «Годов Сохэки».
Настоящее имя Нацумэ Кинноскэ (Сохэки ——псевдоним). В раннем воз-
расте был отдан на усыновление, однако в приемной семье дела шли неваж¬
но и мальчика вернули настоящим родителям. Несчастливые детские годы
стали причиной частых неврозов и непростых отношений с близкими.
В 1893 г. закончил (непопулярное тогда!) английское отделение Гокий-
ского Университета и начал преподавать, сначала в Токио, азатем в провин・
ции, на 〇, Сикоку. В 1900 г. Министе рство пр освещения посылает его на
учебу в Англию, где Нацумэ занимается изучением английской литературы.
По возвращении домой (1903 г.) он приступает к чтению курса лекций по
литературе в Гокийском Университете. Преподавательская деятельность
(как, впрочем, и нелюбимая английская словесность) тяготили Нацумэ, и
когда редактор журнала «Хототогису» предложил ему написать художест¬
венный очерк, он с радостью согласился. Именно так и появился на свет
знаменитый ро ман «Вагахай-ва нэко дэ ару» («Ваш по ко рный слуга кот»,
1905) , одна из глав которого первоначально была представлена в журнале
как самостоятельное произведение. Написанный от лица кота роман — одно
из пер вых сати рических пр оизведений в новой японской лоте ратуре ——имел
оглушительный успех. За ним последовала повесть «Боттян» («Мальчуган»,
1906) , ро ман «Кусамаку ра» («В дор оге»,1906), повесть «Нихякутожа» («210-
й день»,1906) и роман «Новаки» («Пронизывающий осенний ветер»,1907),
который ознаменовал отход от 叩ежних сатирических и романтических ус¬
тановок и переход на позиции реализма. Критикуя натуралистов («сидзэн-
сюги») за их неспособность отрешиться от изображаемо「〇 мира, писатель
выдвигал идею «хининдзё:» («бесстрастности»), под которои понимал «уме¬
нье наблюдать все явления жизни с сох ранением душевной независимос¬
ти» (Н. И. Конрад). Принцип «ёю:» (дословно «духовная свобода») выра¬
жал творческую позицию писателей школы Нацумэ («ёю:ха»).
В 1907 г. писатель переходит на постоянную работу в газету «Асахи»,
полностью посвятив себя литературному труду. Он пишет роман «Губинд-
зинсо» («Полевой мак»,1907). Затем под ряд выходят три романа, составля¬
ющие своебразную трилогию 一 «Санейро:» (1908), «Сорэкара» («Затем»,
1909), «Мон» («Врата»,1910), в которой, описывая «увядание чувств в че¬
ловеке», писатель показывает царившую в душах его современников ду¬
шевную растерянность и нерешительность. Тема человеческого эгоизма по¬
следовательно разрабатывается и в других произведениях писателя, таких
как «Хиган судэ мадэ» («Пока не кончилея Хиган»,1912), «Ко:дзин» («Пу- 22
тешественник»,1913), «Кокоро» («Сердие»,1914), «Митигуса» (автобио¬
графический роман «Придорожная трава»,1915) и последний роман «Мэй-
ан» («Свет и тьма»), в котором мечущийся герой Нацумэ пытаете я выйти за
пределы «эгоистического» начала в человеке.
Нацумэ Сохэки, написавший свой первый роман в тридцать восемь лет,
скончался в 1916г. Через пять дней после его кончины газета «Асахи» напе¬
чатала последнюю порцию романа «Мэйан», который так и остался недо-
писанным до конца.
В хрестоматию включен рассказ «Десять снов» («Юмэ дзю:я»,1918)
Литература 〇 Нацумэ Со:сэки
1. Конрад И. И, 〇 некоторых писателях пер иода Мэйдзи. Нацумэ Сосэ-
ки/В КН.: Конрад И. И. Японская литература. От «Кодзики» до Токутоми».
М.,1974.
2. Гривнин В. Нацумэ Сосэки / В кн.: Нацулгэ Сосэки. Сансиро. Затем.
Врата.. М.,1973.
3. Григорьева Т. Японская литература XX века. М.,1983.
4. Краткая история литературы Японии. Курс лекций / Под ред. Е. М. Пи-
нус. Л., 1975.
Нереводы на русский язык
1. Нацумэ Сосэки. Мальчуган / Пер. Р. Карлиной. М.,1956.
2. Нацумэ Сосэки. Сердце / Пер. Н. Конрада. Л., 1935.
3. Нацумз Сосэки. Ваш покорный слуга кот/ Пер. Л. Коршикова и А. Стру¬
гацкого. М.,196〇.
4. Нацумэ Сосэки. Сансиро. Затем. Врата / Пер. А. Рябкина. М.,1973.
5. Нацумэ Сосэки. Тауэр / В кн.: Весенние дожди. Зарубежный Восток.
Литературная панорама. Вып.17. / Пер. И. Львовой. М.,1989.
НАГАИ КАФУ: (1879-1959)
Писатель и эссеист. Считается одним из лидеров неоромантизма. Насто¬
ящее имя Нагаи Со:кити. Р одился в Токио в семье кр упного го суда рствен・
но го чиновника. Поступил на китайское отделение Токийской Школы ино-
странных языков, но вскоре забросил занятия, отдав предпочтение миру
традиционного японского искусства 一 миру Кабуки, веселых кварталов.
Он стал брать уроки игры на сямисэне и флейте сякухати. Начав писать, он
показал свой рассказ популярному тогда писателю Хироцу Рю:ро:(1861—
1928) и был пр инят к нему учеником. В пер вых книгах Нагаи Кафу: «Ясин»
(«Честолюбие»,1902) и «Дзигоку но хана» («Цветы ада»,1902) было замет¬
но влияние фр анцузских натур ал истов и, в особенности. Золя. Однако вско-
ре кум и ром молодого писателя стал Г. Мопассан, любовь к которому он
про нес через всю жизнь. В 1903 г. по настоянию отца он отправился учить¬
ся за границу, в Америку, где немедленно начал брать уроки французского
языка. Впечатления от пребывания в Америке, от встреч с японскими им-
миг рантами легли в основу сбор ника «Амэрика моногатари» («Рассказы об
Америке»), опубликованного в Японии в 1908 г.. В 1907 г. он переехал во
Францию, 〇 которой давно мечтал ——там были написаны «Фурансу моно-
гатари» («Рассказы 〇 ①ранции»,1909), которые по цензурным соображена
ям были запрещены к печати. Вскоре после возвращения в Японию (1908)
он получил место профессора лите ратуры в Кэйо Гидзюку Дай гаку, где на¬
чал издавать литературный журнал «Митабунгаку». 10-е годы были необы¬
чайно плодотворными ——в 1909 г. по рекомендации Нацумэ Со:сэки писа¬
тель начинает печатать в газете Асахи свою повесть «Рэйсё:» («Холодная
улыбка»), выходит из печати повесть «Сумидагава», считающаяся одним из
лучших творений Нагаи Кафу:. В 1917 г. появляется повесть «Удэкурабэ»
(«Соперничество»), в 1920 г. «Окамэдзаса» («Карликовый бамбук»). Эти
повести рассказывают 〇 жизни полусвета, где главные герои— гейши и
актеры, писатели и художники. В повести «Амэ сё:сё:» («Уныние дождя»,
1921)Нагаи Кафу: воссоздает атмосферу современной ему эпохи. Кроме
того, он выпускает сборник переводов из французской поэзии «Сангосю:»
(«Коралловая антология»,1913), пишет множество коротких рассказов и
эссе. Затем, в двадцатые годы, наступает пауза, и писатель вновь публикует
повесть только в 1931 г.——«Цую но атосаки» («До и после дождей»),『ероиня
которой по собственной воле выбирает для себя судьбу продажной женщи¬
ны. Сюжет повести «Бокуто: кидан» («Уцивительная история с западного бе-
рera реки»,1937) строится вокруг случайного знакомства коллекционера,
любителя старины (alter ego Нагаи Кафу:) с проституткой. Действие ripоисхо・
ДИТ в квартале Таманои, в котором все еще царит дух старого Эдо, столь
милого сердцу писателя. В 1937-1945 гг. Нагаи Кафу:, отрицающий ценно¬
сти сов ременного ему общества, испытывает трудности с публикацией сво¬
их р абот. Молчание было пр ервано лишь после войны, когда нар яду с рас¬
сказами писатель опубликовал свои дневники, которые он вел, начиная с
1917 г.
Нагаи Кафу:, известный своей экс цент ричностью и нестандартностью
поведения, последние годы вел жизнь затворника и умер в одиночестве в
1959 г. Он снискал себе славу знатока старого Эдо, красоту и своеобразие
которого воспел в своем творчестве.
В хрестоматии представлены два рассказа «Двенадцать часов за кулиса¬
ми» («Гакуя дзю:нидзи»,1901)и «Нездоровье» («Кадзз гокоти»,1912)
Литература 〇 Нагаи Кафу:
1.Краткая история литерату ры Японии/Под ред. Е. М. Пинус. Л., 1975.
Переводы на русский язык
1.Нагаи Кафу. Рисовые шарики / В кн.: Японская новелла. 1945-1960 /
Пер. Н. Чегодарь. М.,1961.
МОРИ 〇:ГАЙ (1862-1922)
Один из крупнеиших писателей новой японской литератури, драматурт;
поэт, переводчик и критик. Традиционно считается одним из основополож¬
ников японского романтизма.
Настоящее имя — Мори Ринтаро:. Родился в семье потомственных ме¬
диков в г. Цувано (соврем, префектура Симанэ). После нескольких лет уче¬
ничества у известного ученого-просветителя Ниси Аманэ (1829-1897), по¬
ступил на медицинский факультет токийского университета. В год окончания
учебы он напечатал свою первую статью в газете «Ёмиури симбун» и ре・
шил посвятить себя журналистике. Однако семья воспротивилась ——стар・
ший сын в семье традиционно должен был наследовать отцовскую ripoфес-
сию. До конца своих дней Мори 〇:гай совмещал занятия литературой с
медициной, избрав для себя область санитарии и добившись высоких чи¬
нов в военной иерархии (долгое время он возглавлял санитарную службу
японской армии).
В 1884 г. он был командирован на стажировку в Германию (Мори 〇:гай
владел немецким и голландским языками), где смог ближе познакомиться с
немецкой лите ратурой, философией и эстетикой. Веко ре после возв pame・
НИЯ в Японию (1888) он издал свои переводы из немецкой и английской
поэзии (сборник «Омокагэ» 一 «Образы 叩〇шлого»,1889) и основал лите-
ратурный журнал «Сигарами сохи» («Запруда»), на страницах которого на¬
шла отражение его дискуссия с известным критиком Цубоути Сё:ё: 〇 сущ¬
ности литературы.
В 1890 г. он опубликовал свою первую повесть «Маихимэ» («Танцовщи¬
ца»), в основу которой легла драматическая история молодого человека,
отказавшегося от своей любви. Вслед за ней появились «Утаката-но ки»
(«Пузыри на воде»,1890) и «①умидзукаи» («Курьер»,1891).
После некоторой паузы писатель вновь заявил 〇 себе как драматург (пьеса
«Тамакусигэ футари Урасима» 一 «Драгоценная шкатулка и два Урасима»,
1902). В пер своде Мори 〇:гай выходят пьесы Ибсена, в 1913 г. его пер свод
«Фауста» Гёте, который во многом способствовал рождению новой япон¬
ской поэзии. В 1909 г. была напечатана большая повесть «Vita sexualis» —
своеобразный отклик на произведения писателей-натуралистов.
В 1911 г. писатель издает повесть «Сэйнэн» («Юноша»), в которой рас¬
сказывается 〇 молодом провинцнале, мечтающем сделать литературную ка-
рьеру в Токио. Затем появляются повести «Ган» («Дикий гусь», 1911-1913)
и «Каидзин» («Пепел», 1911-1912).
Большой рассказ «Окицу Ягоэмон-но исё» («Посмертное письмо Окицу
Ягоэмона»,1912) открывает целый цикл исторических ripоизведений, в ко-
торых описываются быт и нравы самурайства. («Абэ итидзоку» ——«Семья
Абэ», 1913; «Сакаи дзикэн» — «Случай в Сакаи», 1914; «〇:сио Хэйхати- IZ.
ро:», 1914, и др.). Последние годы жизни Мори 〇:гай посвятил написанию
исторических биографий, к числу которых относятся такие книги как «Сибуэ
Тю:сай» (1916), «Исава Ранкэн» (1916), «Хо:дзё: Катэй» (1917). Подробные
биогра(()ии Эдосских медиков — знатоков китайской медицины ——сам писа¬
тель считал самым главным достижением в своем творчестве, несмотря на
то, что отношение критики к этим длинным и изобилующим незначительны¬
ми деталями сочинениям и по сей день остается весьма неоднозначным.
Мори 〇:гай скончался в 1922 г.
Большая часть сюжетов его исторических произведений взята из япон¬
ской истории, но иногда писатель обращался к событиям китайской стари¬
ны. Сочинения Мори 〇:гай написаны архаическим языком в стиле старой
орнаментальной прозы.
В хрестоматию вошли два рассказа «Самоубийство по сговору» («Синд・
ЗЮ:»,1911)и «Трамвайное окно» («Дэнся-но мадо»,1910)
Литература 〇 Мори 〇:гай
1.Иванова Г. Д. Мори Огай. М.,1982.
Repеводы на русский язык
1. Мори Огай. Дикий гусь. Танцовщица. Рассказы // В кн.: Мори Огай.
Дикий гусь. Танцовщица; Симадзаки Тосон, Нарушенный завет. М.,199〇.
2. Мори Огай. Однажды в лодке // В кн.: «Восточный альманах». Вып. 4.
/ Пер. В. Костеревой. М.,1961.
18
АРИСИМА ТАКЭО (1887-1923)
Писатель, автор коротких рассказов, критик, публицист. Традиционно
относится к писателям группы «Сиракаба». Несмотря на скромное по объ¬
ему литературное наследие, занимает особое место в японской литературе
как автор знаменитого романа «Ару онна» («Женщина»).
Родился в 1878 г. в Токио в семье чиновника Министерства финансов,
который старался дать своим детям хорошее европейское образование.
После окончания миссионерекой школы, где преподавание велось на
английском языке, поступил в школу Пэров. С детства мечтал 〇 карьере
морского офицера, но затем передумал и в 1986 г поступил в сельскохозяйст¬
венный институт в Саппоро. Под влиянием сильных христианских настрое・
НИЙ, господствовавших среди студентов и преподавателей школы, в 1900 г.
обратился в христианство. В 1903 г. в соавторстве со своим другом Мори・
мото Кокити (1878-1950) опубликовал биогра(|)ик)миссионера Д. Ливинг¬
стона. Для продолжения образования Арисима уезжает в Америку, где изу¬
чает историю и экономику. Находясь в США, он знакомится с идеями
социалистов, позднее в Евр one встречается с Кропоткиным. В эти годы
Арисима серьезно занимается европейской и русской литературой, и место
действия его первого литературного опыта ——рассказа «Канкан муси» («Глу¬
хари», 1906)разворачивается на берегу Днемра. В 1907 г. он возвратаетеяв
Японию и веко ре начинает пр еподавание английского языка в сельскохо¬
зяйственном университете в Саппоро. С 1910 г. Арисима сотрудничает с
журналом «Сиракаба» («Еереза»), поставляя для него критические статьи и
рассказы. В 1911 г. он приступает к изданию первой части романа «Женщи¬
на», но веко ре прекр ащает публикацию, недовольный собой. Ар исима за¬
вершает р аботу над книгой только через несколько лет (1919). В цент ре
ро мана судьба женщины, которая не может жить по нор мам современного
ей общества и в одиночку борется за свое право на счастье. Новаторство
ро мана определялось тем, что Сацуки Йоко ——имевшая реальный про то-
тип ——принадлежала к новому для японской литературы типу【ероинь. (Ско・
рее она напоминала толстовскую Анну Каренину.)
В 1917 г. Арисима публикует небольшую повесть «Каин-но мацуэй» («По¬
томок Каина»). Главный герой ——крестьянин Нинъэмон — в своем стрем-
лении вырваться из нищеты утрачивает все человеческие чувства, превра-
тившись в машину для выживания.
По единодушному признанию критиков именно эти два произведения
являются лучшими работами Арисима Такэо. Однако список его литера・
турных трудов намного шире, в него входят новеллы, пьесы, эссе, роман
«Сэйдза» («Созвездие»,1921).
В конце своей жизни Арисима Такэо пожертвовал свое наследственное
поместье на Хоккайдо в совместное владение гтроживающим на земле кре・
стьянам. Приветствуя становление про лета рекой литерату ры и подде ржав
первый ripолетарский журнал «Танэмаку хито» («Сеятель»), писатель тем
не менее не мог примкнуть к пролетарскому направлению, четко осознавая
свою принадлежность к иному классу.
В 1923 г. он ушел из жизни, совершив двойное самоубийство со своей
возлюбленной в Каруидзава.
В хрестоматии приводится рассказ «Густой туман» («Гасу»,1916).
Литература об Арисима Такэо
1. Гривнин В. Послесловие // В кн.: Арисима Такэо. Женщина. Потомок
Каина. М.,1967.
2. Краткая история литературы Японии. Курс лекций. Л., 1975.
Переводы на русский язык
1.Арисима Такэо. Женщина. Потомок Каина / Пер. А. Рябкина. М.,1967.
СИГА НАОЯ (1883-1971)
Известный японский писатель, маетер короткой прозы, автор повестей
и романов, написанных в жанре эгобеллетристики {ватакусп сё:сэцу).
Родился в г. Исиномаки префектуры Мияги в семье банковского слу¬
жащего.
Веко ре семья пер еехала в Токио и мальчик поступил в пр ивилегирован-
ную школу «Гакусю:ин», где впервые попробовал себя на литературном
поприще. В это время Наоя знакомится с философом и теологом Утимура
Кандзо: (1861-1930), христианские взгляды которого оказали значительное
влияние на творчество писателя. В 1906 г. Наоя поступает в Токийский им-
ператорский университет на отделение английской литературм, затем пере、
ходит на отделение японской лите ратуры, но веко ре оставляет студенчес¬
кую скамью, так и не доучившись. В годы учебы начинается его дружба с
Арисима Такэо, а в 1908 г. вместе с литераторами Мусяноко:дзи Санэацу
(1885-1976), Сатоми Тон (1888-1983) и др. Сига Наоя начинает выпускать
журнал «Сиракаба» («Береза»), выходящий под знаменем идей гуманизма и
сыгравший большую роль в становлении японской литературы.
Из-за разногласий с отцом Сига Наоя уходит из дома ив 1912 г. публику¬
ет автобиографический роман «Оцу Дзюнкити», сделавший известным его
имя. Веко ре выходит пер вый сборник новелл писателя, куда входят такие
знаменитые произведения как «Камисори» («Вритва»), «Хаха-но си то ата-
расии хаха» («Смерть матери и новая мать»), «Хан-но хандзай» («Нреступ-
ление Хана») и др.
В 1917 г. появляется повесть «Вакай» («Примирение»), в которой Сига
Наоя про должает тему сложных отношений в семье.
В 1921 г. начинается публикация романа «Путь в ночном мраке» («Анъя
ко:ро»). Главный герой романа Токито Кэнсаку стремится к свободной ис¬
полненной смысла жизни, но не встретив понимания близких, замыкается в
себе, погрузившись в одиночество и избрав для себя путь самосовершенст-
вования. Работа над произведением оказалась столь мучительной для писа¬
теля, что он несколько раз оставлял её, закончив роман только в 1937 г.
В 1928 г. в предисловии к тому собственных произведений Сига Наоя
объявляет об отказе от литературной деятельности. После пяти лет молча¬
ния выходит в свет новелла «Фарфор Ванрэки» («Банрэки акаэ»), написанная
под впечатлением поездки в Маньчжурию в 1929-1930 гг. На годы войны
писатель вновь прекращает писательскую деятельность и только в 1945 г.
публикует новеллу «Луна пепельного цвета» («Хай иро но цуки»). Хотя по¬
следние годы своей жизни Сига Наоя не занимается литературным творче¬
ством, в глазах читателей и критики он продолжает оставаться одним из
наиболее почитаемых авторов, которого журналисты и литературоведы еще
при жизни окрестили «Богом литературы» (бунгаку-но камисама). Он счи- 27
тается непревзойденным стилистом, для его манеры свойственны эскизность
изображения, недосказанность, внимание к деталям, больший акцент не на
фабуле rip оизведения, а на в нут ренних пер еживаниях и ощущениях героев.
Как отмечают многие критики, язык Сига Наоя прост — вы не найдете в его
текстах архаичных и редко-употребляемых иероглифов, число используе¬
мых им идеограмм ограничено, но кажущаяся «простота» его прозы ——ре・
зультат долгой и кропотливой работы писателя над каждой фразой ——при¬
дает его стилю удивительную отточенность и изящество.
Акутагава Рю:носкэ, относившийся к Сига Наоя с почтительным благо¬
говением, называл его «чистым» писателем, отмечая «атмосферу высокой
морали, царившей в его произведениях». Oripеделяя его метод как «свобод¬
ный от фантазий реализм», Акутагава подчеркивал, что именно Сига Наоя
«влил в него поэтический дух, базирующийся на восточной традиции... что
придает неповторимую красочность его 叩оизведениям». (Цит. по: Рюнос-
кэ Акутагава. Слова пигмея. Рассказы. Воспоминания. Эссе. Письма//Сост.
В. С. Гривнин. М.,1992).
В хрестоматию вошел рассказ «Хорошие супруги» («Ко:дзимбуцу-но
фу:фу»,1917).
Литература 〇 Сига Наоя
1. Сига Наоя. Библиографический указатель // Сост. В. П. Алексеев. М.:
ВГБИ 几198〇.
2. Краткая история литературы Японии// Под ред. Е. М. Пинус. Л.,1975.
С. 82-83
3. Григорьева Т., Логунова В. Японская литература. М.,1964. С. 193-
194.
ГТереводы на русский язык
1. Преступление Фаня// В кн.: Восточный альманах. Вып. 5. / Пер. В. Скрып-
ника. М.,1962.
2. Серая луна // В кн.: Восточная новелла / Пер. Г. Ивановой. М.,1963.
3. Бог мальчугана. В полдень третьего ноября. Преступление Хана // В кн.:
И была любовь, и была ненависть / Пер. Т. Григорьевой. М.,1975.
4. На водах в Киносаки / Пер. В. Скальника. Там же.
5. Божество мальчугана // В кн.: Похвала тени. Рассказы японских писа¬
телей в переводах М. П. Григорьева / Пер. М. Григорьева. СПб., 1996.
АКУТАГАВА РЮ:НОСКЭ (1892-1927)
Один из наиболее ор игинальных и яр ких маете ров малой фор мы. Авто р
свыше полусотни новелл, миниатюр, стихов, сценариев, эссе и критичес¬
ких статей.
Родился 1 марта 1892 г. в Токио. Вскоре из-за душевного расстройства
матери был отдан на воспитание родственникам по материнской линии.
Мальчик с детства интересовался литературой, круг его чтения ——японская
и китайская классика, Нацумэ Сохэки, Мори 〇:гай. Стриндберц Бодлер,
Ибсен, Франс, Стендаль, Толстой, Достоевский, Гоголь ——был необыкно¬
венно тир ок. В 1913 г. он поступил на английское отделение Токийского
университета, а еще через год опубликовал в журнале «Синейте:» («Новые
течения») первый рассказ «Ро:нэн» («Старость»). За ним последовали но¬
веллы «Расё:мон» (1915) и «Хана» («Нос»,1916), получивший хвалебную
оценку Нацумэ Со:сэки. Среди ранних работ Акутагава преобладают «ква-
зиисторические» новеллы, сюжеты которых были позаимствованы из раз・
личных литературных памятников (например, из «Кондзяку моногатари»,
«Уазисю:и моногатари» и др.). Как объяснял сам писатель в «Тё:ко:до: дзак-
ки» («Заметки Тёкодо»,1925), «чтобы с максимальной художественной си¬
лой р аск рыть тему, необходимо какое-то необычное событие. ... Я пер сно¬
шу действие в давние времена, чтобы избежать их неестественности».
Поэтому действие его новелл происходит то в эпоху Хэйан («Имогаю» 一
«Бататовая каша»,1916), то в эпоху Эдо (цикл новелл из истории христиан-
ства в Японии ——«0-Гин»,1922), то в первые десятилетия после револю-
ции Мэйдзи («Ханкэти» ——«Носовой платок»,1916). Художника интересу-
ет прежде всего внутренний мир героев, их психология ——ведь именно в
нестандартных ситуациях начинает про являться истинная природа личнос¬
ти («Кумо-но ИТО» 一 «Паутинка»,1918). Еще одна важная тема 一 искусст¬
во и жизнь, мастерски решаемая в таких новеллах как «Дзигокухэн» («Муки
ада»,1918) или «Гэсаку дзаммэй» («Одержиммй творчеством»,1917).
После окончания университета Акутагава некоторое время ripеподавал
английский язык в Морском училище в Камакура, но в 1919 г. переехал в
Токио, полностью посвятив себя литературе. К этому врсмени Акутагава
(успевший издать уже несколько сбор ников р ассказов) становится одним
из признаных мэтров группы «сингико:ха» («неомастерства»), которая ра¬
товала за реалистическое воплощение действительности, увиденной в
каком-либо ярком, необычном факте.
Человек и общество, добро и зло, несовершенство социальной жизни
стали предметом размышлений Акутагава в двадцатые годы («Сё:гун», 1922
или сатирическая утопия «Каппа»,1927). В последние годы жизни писа¬
тель обращается к жанру полуавтобиограбической прозы——таков цикл «Ясу-
КИТИ-НО тэте: кара» («Из записных книжек Ясукити»,1923) или лирико-фи¬
лософские эссе «Сюдзю-но котоба» («Слова пигмея», 1923-1925). Напи¬
санные в последние месяцы и изданные посмертно новеллы «Хагурума»
(«Зубчатые колеса») и «Ару ахо:-но иссё:» («Жизнь идиота») описывают
тот страшный «ад одиночества», в котором находился Акутагава. Болезни,
душевный надлом, страх перед возможным безумием (тогда считалось, что
психические расстр ойства пер сдаются по наследству) измучили его. В июне
1927 г. Акутагава принял смертельную дозу веронала.
Ранний Акутагава стилистически тяготел к Мори 〇:гай, книги которого
он высоко чтил. Его даже обвиняли в явном подражательстве. Выделяя осо¬
бенности автор ского письма более позднего пер иода, В. С. Гривнин, пр из-
нанный знаток творчества Акутагава, отмечал «ясность, краткость, отто¬
ченность фразь1, полный отказ от внешней “крacивocти^^, лаконичность, даже
скупость в обрисовке персонажей, не просто рассказ 〇 том, что произошло,
а само действие». (Цит. по: Гривнин В. С. Акутагава Рюноскэ. Жизнь・『вор・
честно. Идеи. М.,198〇. С. 15.)
В книгу вошли два рассказа: «Ун» («Удача»,1917) и «Мандарины» («Ми-
кан»,1919)
Литература 〇 Акутагава Рю:носкэ
1. Гривнин В. С. Акутагава Рюноскэ. Био-библиографический указатель.
М.,1961.
2. Гривнин В. С. Акутагава Рюноскэ. Жизнь. Творчество. Идеи. М.,198〇.
3. Конрад Н. И. Акутакава Рюноскэ // В кн.: Хрестоматия японского языка.
Вып. З.М., 1949.
4. Ермакова Л, М. Некоторые методы пост роения новелл Акутагава Рю・
носкэ // В КН.: Литература Востока. М.,1969.
5. Стругацкий Л. Три открнтия Рюноскэ Акутагавы // В кн.: Акутагава.
Новеллы. М.,1989.
Repеводы на русский язык
1. Расёмон / Пер. Н. Фельдман. Л., 1936.
2. В стране водяных / Пер. А. Стругацкого. М.,1962.
3. Избранное. В 2-х тт. // Сост. В. Гривнина и А. Стругацкого. М.,1971.
4. Паутинка. Новеллы // Сост. В. С. Санович. М.,1987.
5. Новеллы. Эссе. Миниатюры // Вступ. ст. А. Стругацкого. М.,1985.
6. Слова пигмея. Рассказы. Воспоминания. Эссе. Письма//Сост. В. С. Грив¬
нин. М.,1992.
7. Избранное // Вступ. ст. А. М. Кабанова. СПб., 1995.
МИЯМОТО ЮРИКО (1899-1951)
Писательница и общественная деятельница. Вместе с Кобаяси Такидзи
(1908-1933) и Токунага Сунао (1899-1958) относится к числу наиболее яр¬
ких представителей «пролетарской литературь】》, ставшей заметным явле¬
нием культуры в 20-е годы.
Миямото ЮрИКО (девичья фамилия Тю:дзё:) родилась в семье известно¬
го архитектора и получила хорошее образование. Она начала рано писать, и
уже первые литературние опыты 一 повесть «Мадзусики хитобито-но мурз»
(«Бедные люди»,1916) и рассказ «Нэги-сама Мия да» («Блаженный Ми я・
да»,1917) рассказывали 〇 тяжелой доле японских крестьян. В 1919 г. она
вместе с отцом отпр авилась в Нью-Й орк и веко ре вышла замуж за Сигэ ру
Ар аки, специалиста по древним языкам. Семейная жизнь оказалась неудач¬
ной, и в 1924 г. последовал развод. События личной жизни писательницы —
поездка в Америку, разрыв с семьей, уход от мужа 一 стали материалом для
первого большого автобиографического романа «Нобуко», опубликованно¬
го в 1924-1926 гг. на страницах журнала «Кайдзо:». По мнению японских
литературоведов, это произведение было создано в лучших традициях жан-
ра «ватакуси сёсэцу» (эгобеллетристики). Сблизившись с Юаса Ёсико, пе-
реводчицей с русского языка, Миямото Юрико в 1927 г. предприн刃ла поезд¬
ку в Россию, 〇 которой давно мечтала. Именно в России произошел
окончательный переход писательницы к коммунистическому мировоззре¬
нию. Вернув山ись в Японию, она вступила в коммунистическую партию
Японии, была изб рана в Цент ральнын комитет Японской феде рации проле-
тарской культуры, возглавила журнал «Хатараку фудзин» («Работающая
женщина»). В 1932 г. Миямото НЭрико стала женой Миямото Кэндзи, тогда
одного из деятелей пролетарского движения, впоследствии генерального
секретаря Японской Компартии. В жизни писательницы наступили тяже¬
лые времена, начались гонения. Миямото Кэндзи был брошен в тюрьму
(его освободили только в 1945 г.), произведения Миямото Юрико запpema・
ют печатать, её саму неоднократно арестовывают и выпускают на свободу
лишь из-за резкого ухудшения здоровья (в тюрьме с ней случился тепловой
удар). Несмотря на превратности судьбы, Миямото Юрико продолжает пи¬
сать. В 1936 г. она издает повесть «Тибуса» («Грудь»), пишет эссе, ведет
тюремные дневники. В послевоенный период появились две автобиогра¬
фические повести «Банею: хэйя» («Равнина Банею») и «Фу:тиео:» (так на-
зываетея живучая придорожная трава), рассказывающие 〇 жизни в после-
военний Японии. В 1947-1950 гг. писательница выпустила два роман
«Футацу-но нива» («Два дома») и «До:хё:» («Вехи»), составившие вместе с
ранним романом «Нобуко» автобиографическую трилогию. «Два дома» ripo・
должает сюжетную линию «Нобуко», описывая жизнь「ероини после разво¬
да и до поездки в Россию. Роман «Вехи» посвящен трехлетнему пребыва- 25
НИЮ в России. По словам самой Миямото Qpи ко, два последних романа
трилогии написаны в духе «социалистического реализма», за распростра・
нение которого она столь горячо ратовала в своих статьях. Миямото Юрико
скончалась в 1951 г. В её архивах были найдены мате риалы для последней
(так и незавершенной) части автобиографической эпопеи ——романа «Две¬
надцать лет», в котором она хотела рассказать 〇 жизни Нобуко в 30-40 гг.
В хрестоматию включен рассказ «Воспоминания» («Омокагэ»), напи¬
санный в 1940 г.
Литература 〇 Миямото Юрико
1. Логунова Б. Б. Жизнь и творчество Юрико Миямото. М.,1957.
2. Рёхо К. Современный японский роман. М.,1977.
3. Краткая история литературы Японии // Под ред. Е. М. Пинус. Л., 1975.
Переводы на русскии язык
1.Миямото Юрико. Повести // Сост. В. Логунова. М.,195&
ТАНИДЗАКИ ДЗЮНЬИТИРО: (1886-1965)
Один из крупнейших японских писателей XX в. Новеллист, романист,
драматург; публицист. Представитель течения «неоромантизма», стоявшего
на противоположных натурализму («сидзэнсюги») позициях.
Родился в Токио, в семье купца. С детства увлекался литературой и хотел
стать писателем. Первые публикации прошли незамеченными критикой. На¬
стоящий успех принесли рассказы «Сисэй» («Татуировка»,1910) и «Кирин»
(«Цзилинь»,1910), напечатанные в литературном журнале «Синейте:» («Но¬
вые течения»), созданного студентами Имперского Университета. Молодой
студент литературного факультета сразу стал знаменитостью, удостоившись
хвалебного отзыва Нагаи Кафу:. В ранних произведениях Танидзаки, подни¬
мавших проблемы соотношения красоты и зла, искусства и жизни, прослежи¬
вается влияние таких европейских мастеров как Э. По, Ш. Бодпер, 〇. Уайльд.
Зротические мотивы, эстетизм, столь характерные для раннего Танидзаки, зву¬
чат и в более поздних его произведениях. В 1925 г. он издает роман «Тидзин-но
аи» («Любовь глупца») 〇 губительной страсти героя к прекр асной и пор очной
женщине, обладающей колоссальной властью над мужчиной. К этому врсмени
писатель успел разочароваться в своем пристрастии к Западу, и этот роман оз¬
наменовал конец определенного этапа в его творчестве. После разрушительно-
го землетрясения 1923 г Танидзаки, поселившийся в районе Кансай, обратил¬
ся к истокам классической японской культуры. В 1929 г. он публикует роман
«Тадэ куу муси» («〇 вкусах не спорят»), герой которого в минуты душевного
разлада обращается к прекрасному миру традиционного искусства. В начале
30-х гг Танидзаки создает серию произведений, принесших ему еще большую
славу и любовь читателей. Это рассказы «Ёсино кудзу» («Лианы Ёсино»,1931),
«Асикари» (1932), «Сюнкин сё:» («История Сюнкин»,1933), эссе «Инъэй р ай-
сан» («Похвала тени»,1934) и др. В 1935 г он берется за перевод на современ・
ный язык классического романа Мурасаки Сикибу «Гэндзи моногатари», ра6о・
та над которым длится несколько лет. В 1943 г в самый разгар войны Танидзаки
приступает к созданию своего лучшего ripоизведення — рОмана «Сасамэюки»
(«Мелкий снег», 1943-1948), написанного в жанре семейной хроники дома
Макиока. Центральное место в повествовании (как и во многих других произ・
ведениях писателя) занимают женские образы 一 одна из сестер, Юкико, во¬
площает собой лирический идеал японской женщины. Если в романе «Мелкий
снег» писатель обращается к тематике повседневной жизни, то в последних
работах его интересуют прежде всего два аспекта 一 плотская любовь и смерть.
Роман «Каги» («Ключ»,1956) построен на чередовании дневниковых записей
супружеский четы, стремящейся к утонченным эротическим наслаждениям.
«Тэнфу ро:дзнн НИККИ» («Дневник сумасшедшего старика»,1962) рассказыва¬
ет 〇 переживаниях семидесятисемилетнего старика, не лишенного чувствен¬
ных фантазий и желаний. 近
Уже при жизни писателя в 1930-е гг. было издано его пер вое «Соб рание
сочинений», в 1949 г. ему была присуждена Императорская премия залите-
р атурные достижения, а в 1973 г. (посмертно) он, нар яду с Ясунари Каваба¬
та, был выдвинут на Нобелевскую премию. Танидзаки по праву считается
классиком японской литературы XX в., ярким и самобытным писателем,
про должающим лучшие тр адиции японской словесности.
Художественный язык прозы Танидзаки точен и изыскан, недаром писа¬
тель считается одним из лучших японских стилистов 一он великолепно знает
иероглифику и его произведения необыкновенно лексически богаты, писа¬
тель умело пользуется тем иероглифическим многообразием, которым рас-
полагает японский язык. Акутагава Рю:носкэ, отмечавший недюжинный
талант и блестящее красноречие Танидзаки, писал, что он «умел выиски¬
вать и шлифовать японские и китайские слова, превращать их в блестки
чувственной красоты (или уродства) и словно перламутром инкрустировать
ими свои произведения... Его рассказы... от начала до конца пронизаны яс¬
ным ритмом... В этом отношении Танидзаки был и остается непревзойден-
ным маете ром».
В хрестоматию включен рассказ «Голубой цветок» («Аои хана»,1922).
Литература 〇 Танидзаки Дзюньитиро:
1. Львова И. Предисловие. // В кн.: Танидзаки Дзюнъитиро. Избранные
произведения. Т.1.М.,1986.
2. Рёхо К. Современный японский роман. М.,1977.
3. Катасонова Е. Л. Проблемы художественного маетерства Танидзаки
Дзюнъитиро / Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд.
филол. наук). М.,1982.
Repеводы на русский язык
1. Танидзаки Дзюнъ итиро. Изб ранные пр оизведения. В 2-х тт. // Сост.
И. Львова. М.,1986.
(Т.1.—Рассказы. Любовь глупца. Похвала тени. Т. 2. — Мелкий снег).
2. Танидзаки Дзюнъитиро. Мать Сигэмото. М.,1984.
3. ТанидзакиДзюнъитиро. Луна и комедианты. // В кн.: Японские новел¬
лы. М.,1962.
4. Танидзаки Дзюнъитиро. Татуировка. История Сюнкин. Шут // В кн.:
И была любовь, и была ненависть (Сборник рассказов японских писателей
XX века) / Пер. А. Долина, Е. Александровой. М.,1975.
5. Танидзаки Дзюнъитиро. Похвала тени // В кн.: Похвала тени. Расска¬
зы японских писателей в пер сводах М. П. Григо рь ева / Пе р. М. П. Григорь¬
ева. СПб., 1996.
ДАДЗАЙ ОСАМУ (1909-1948)
Про заик, пр изнанный мастер жан ра малых форм, авт ор многочислен¬
ных сборников рассказов, эссеист, создатель двух больших повестей, один
из наиболее знаменитых писателей в послевоенной Японии.
Насто ящее имя — Цусима Сю:дзи. Родился в префекту ре Аомори в се¬
мье богатого землевладельца, члена Верхней палаты Парламента. Детство
мальчика, шестого сына в семье, где было 11 детей, про шло в окру жении
слуг и кормилицы. С шестнадцати лет он мечтал стать писателем и начал
издавать вместе с однокашниками литературний журнал. Позднее увлекся
идеями коммунизма и, (по одной из версий японских биографов Дадзай
Осаму) стыдясь своего социального происхождения, попытался в 1929 г.
покончить жизнь самоубийством.
В 1930 г. поступил на французское отделение Токийского Император・
с ко го университета, продолжая подде рживать контакты с нелегальным дви¬
жением. В 1932 г. он порвал с левым движением и начал писать, взяв себе
псевдоним Дадзай Осаму. Его литературный дебют состоялся в 1935 г.,
когда в журнале «Бунгэй» был опубликован рассказ «Гякко:» («Против те¬
чения»). Начинающий писатель сразу привлек к себе внимание критики и
был включен в число претендентов на получение вновь учрежденной пре¬
мии Акутагава. В 1936 г. вышел в свет его пер вый сбор ник «Баннэн»
(«Поздние годы»). Несмотря на быстрый литературный успех, жизнь Дад¬
зай Осаму в эти годы была мучительной и напряженной. Он 6росип уни-
верситет, практически так и не выучив французский язык. Совертил еще
одну попытку самоубийства, пристрастился к наркотикам. В 1935 г. по-
тер пев неудачу при попытке уст роиться на работу в газету, он еще раз
попытался уйти из жизни.
В 1939 г. в жизни Дадзай Осаму наступил перелом — он женился, стал
вести размеренный образ жизни, занимаясь литературным трудом.
В годы войны он перебралея к себе на родину. В 1944 г. он написал не¬
большую повесть «Цугару» 〇 своем путешествии по родным местам, за ней
последовала повесть в письмах «Пандора・но хако» («Ящик пандоры»), опи-
сывающаю жизнь молодого человека в туберкулезном санатории. В 1945 г.
вышла повесть «Сэкибэцу» («Грустное расставание»). Дадзай Осаму вер・
нулся в Токио в 1946 г. К тому врсмени он уже был знаменитостью.
В последние годы жизни появились на свет два крупных (и самых чита¬
емых) произведения писателя — повести «Сяё:» («Заходящее солнце»,1947)
и «Нингэн сиккаку» («Утрата человечности» 一 в русском переводе «Испо¬
ведь ''неполноценного чeлoвeкa^^»,1948). Первая рассказывала 〇 жизни обед¬
невшей аристократиリеской семьи в послевоенные годы, вторая во многом
носила автобиографический характер, повествуя 〇 рсальных событиях из
жизни писателя. 空
Последняя работа писателя ——полная юмора и иронии повесть «Гуддо-
бай» («Goodbye») осталась незавершенной. Интенсивная творческая рабо-
та, прогр ессирующий тубе ркулез, пр ист растие к алкоголю оказали разру¬
шающее воздействие на Дадзай Осаму.
В 1948 г. он покончил жизнь самоубийством. Его тело было обнаружено
19 июня, в день когда ему должно было исполниться 39 лет.
Одна из отличительных особенностей творчества писателя ——его мане¬
ра писать от первого лица, многие из его произведений носят откровенно
автобиографический характер, иной раз он даже не дает вымышленных имен
своим персонажам. Однако «исповедальный» характер его прозы часто со¬
четался с умелым использованием известных литературных сюжетов как из
японской классики (наприме р, сбор ник сказочных историй «Отоги дзо:си»,
1945 или «Уаайдзин Санэтомо» — «Правый министр Санэтомо»,1943), так
и из европейской ( пьеса «Син Хамурэтто» ——«Новый Гамлет»,1941).
В хрестоматии представлен рассказ «Сто видов Фудзи» («Фугоку хяк-
ка»,1939).
Литература 〇 Дадзай Осаму
Рёхо К. Современный японский роман. М.,1977.
Переводы на русский язык
1. Цадзай Осаму. Жена Вийона // В кн.: Японская новелла. 1945-1960 /
Пер. Кими Минэ. М.,1961.
2. Цадзай Осаму. Вишни // В кн.: Красная лягушка / Пер. А. Бабинцева.
М.,1973.
3. J\ad3au Осаму Дас Гемайнэ. Нр и падаю к вашим стопам. Одежда из
рыбьей чешуи. Обезьяний остров. Листья вишни и флейта // В кн.: И была
любовь, и была ненависть. Сборник рассказов японских писателей XX века
/ Нер.Т. Л. Соколовой-Делюсиной. М.,1975.
4. Цадзай Осаму Исповедь «неполноценного» человека / Нер. с яп.
В. Скальника. М.,1998.
КАВАБАТА ЯСУНАРИ (1899-1972)
Один из крупнейших писателей XX в., лауреат Нобелевской премии,
присужденной в 1968 г. за «писательское мастерство, с которым Кавабата
выражает сущность японского восприятия жизни и образа мышления».
Родился в Осака в семье врача, рано потерял родителей и воспитывался
дедом. В 1920 г. поступает на английское отделение Токийского универси¬
тета, веко ре переходит на отде ление японской литерату ры. В 1924 г. вместе
с литераторами Ёкомицу Риити (1898-1947), ставшим близким другом Ка¬
вабата на всю жизнь, Кон То:ко: (1989-1977) и др. основывает журнал «Вун・
ГЭЙ дзидай», объединивший писателей-неосенсуалистов («синканкакуха»).
Кавабата рано начал печататься (с 1915 г.), и его ранние новеллы были на¬
писаны под явным влиянием теорий Фрейда и прозы Джойса. Увлечение
модернизмом пр ослеживается в коро тких р асе казах, создававшихся с 1921
по 1972 гг. и названных писателем «танагокоро-но сё:сэцу» («рассказы ве¬
личиной с ладонь»).
Первым значительным произведением Кавабата стала небольшая повесть
«Идзу-но опорико» («Танцовщица из Идзу»,1925), история юношеской люб¬
ви к бродячей артистке. Затем появился роман «Асакуса курэнайдан» («Бро¬
дяги из Асакуса», 1929-1930), положивший начало серии произведений из
жизни этого квартала. Пирическая повесть «Юкигуни» («Снежная страна»,
1937), рассказывающая 〇 встрече приехавшего в северную провинцию ге-
роя с прекрасной гейшей, многими критиками считается шедевром Каваба¬
та. В послевоенные годы писатель один за другим публикует повесть «Ма-
ихимэ» («Танцовщица»,1950), роман «Сэмбадзуру» («Тысячекрылнй
журавль», 1952 — он был удостоен 叩емии Японской Академии Искусств),
роман «Мэйдзин» («Мастер»,1954), повесть «Мидзууми» («Озеро»,1954),
роман «Яма-но ото» («Стон горы»,1954). Все эти произведения, про должая
традиции японской классической литературы, пронизанм утонченным чув¬
ством прекрасного и культом чистоты. После публикации романа «Стон
горы», вызвавшего восторженную реакцию публики и прессы, Кавабата был
объявлен «человеком-сокровиицем» («нингэн-кокухо:» 一 почетное звание
присуждаемое правительством для поощрения развития национальных тра・
диций в искусстве). Наряду с «чистой литературой», как именуют критики
лучшие р аботы писателя, Кавабата пр одолжал печатать в популя рных газе¬
тах и журналах произведения, рассчитанные на массовую аудитерию. К та¬
ким сочинениям относятся, например, самая большая по объему работа
писателя «То:кё:-но хито» («Токийцы»,1955) или повесть «Оннадэ ару кото»
(«Быть женщиной»,1956).
В 1961 г. выходит в свет повесть «Нэмурэру бидзё» («Спящие красави-
цы»), а затем роман «Кото» («Старая столица»), который был восторженно
принят читателями. В 1968 г. на церемонии вручения Нобелевской премии ——
Кавабата произнес евою знаменитую речь «Уцукусии Нихон-но ватакуси»
(«Красотой Японии рожденный»).
Последним незаконченным романом Кавабата стал роман «Тампопо»
(«Одуванчики», 1964-1972).
16 апреля 1972 г. в местечке Дзуси, где находился рабочий кабинет писа¬
теля, Кавабата Ясунари ушел из жизни, совер山ив самоубийство.
Писатель известен как один из наиболее велоколепных стилистов.
Рассказы величиной с ладонь («та на го к оро・но сё:сэцу»)
Жанр короткого рассказа был чрезвычайно популярен в японских лите-
ратурных кругах в 20-е гг. Первоначально короткие рассказы именовались
на французский манер eonte, позднее за ними закрепилось сугубо японское
название — «Рассказы величиной с ладонь» (так был озаглавлен короткий
рассказ одного малоизвестного автора).
Мода на короткие р ассказы про шла довольно быстро, однако Кавабата
Ясунари остался верен жанру и писал «Рассказы величиной с ладонь» на
протяжении 40 лет своей литературной деятельности.
Пер вый сбор ник «Р ассказов величиной с ладонь» появился в 1926 г., он
назывался «Наряд чувств» и включал в себя 36 рассказов. Затем рассказы,
выходившие в разное время, были объединены писателем в 6-м томе собра・
НИЯ сочинений Кавабата, как «Сто рассказов величиной с ладонь».
Рассказы очень разнообразни и по тематике и по стилю 一 одни рассказы
носят автобиографический характер, другие тяготеют к жанру мистических
историй, третьи близки к фольклору, четвертые напоминают исторические
новеллы, пятые как-бы бессюжетные зарисовки, вызывающие особое нас-
троение и чувство у читателя.
Писатель считается непревзойденным мастером малых форм. Как отмеча¬
ет японский критик Сэко Каку, «в рассказах Кавабата нет обыденности, прозы
жизни, присутствующая в них таинственность придает им изящество... Поэто¬
му его рассказы лишены ripoзаической сухости и изящны как стихи».
Литература 〇 Кавабата Ясунари
КавабатаЯсунари. Библиографический указатель // Сост. В. П. Алексе¬
ев. М.,1973.
Герасимова М. П. Бытие красоты. Градиции и современность в творче¬
стве Кавабата Ясунари. М.,199〇.
Григорьева Т. П. Читая Кавабата Ясунари // В жур.: Иностранная лите¬
ратура. М.,1971.№ &
Переводы на русский язык
Кавабата Ясунари. М.,1971.
Кавабата Ясунари. Изб ранные произведения. М.,1986.
МИСИМА ЮКИО (1925-1970)
Крупнейший японский писатель XX в. Автор 40 романов,18 пьес, рас¬
сказов, эссе. Трижды выдвигался на соискание Нобелевской премии.
Настоящее имя — Кимитакэ Хираока. Родился в семье государственно・
го чиновника. Учился в привилегированной школе для аристократических
семей Гакусюин и закончил её с блестящими результатами, за что был удо¬
стоен чести получить серебряные часы из рук самого императора.
Первую повесть «Ханадзакари・но мори» («Цветуший лес»,1941)напе¬
чатал в 16 лет под псевдонимом Мисима Юкио. После окончания юридиче-
ского факультета Гокийского университета был принят на службу в Минис-
терство финансов, из которого вскоре ушел, предпочтя карьере занятия
литературой. В 1946 г. Мисима показал свои рассказы Кавабата Ясунари,
который оценил маетерство начинающего писателя и порекомендовал к
печати его рассказ «Табако» («Сигареты»). Веко ре появилась пер вая боль¬
шая повесть «То:дзоку» («ВорьI»,1946-1948), а еще через год вышла «Ис¬
поведь маски» («Камэн-но кокухаку»,1949). Полуавтобиографический ро・
ман 〇 становлении под ростка, осознавшего свою гомосексуальность, был
восторженно принят критиками и публикой. За этим романом следует «Ай¬
но каваки» («Жажда любви»,1950), затем «Киндзики» («Запретные радос-
ти»,1951).После опубликования этих романов Мисима совер山ил путеше¬
ствие по Евр one и Амер ике. Одно из наиболее сильных впечатлений писатель
получил в Греции, 〇 которой мечтал с детских лет ——сюжетная канва рома¬
на «Сиосай» («Шум волн»,1954) была построена на истории Дафниса и
Хлои. В 1956 г. вышел в свет «Кинкакудзи» («Золотой храм»), единодушно
пр изнаваемый кр итиками вер шиной твор чества писателя. Исто рия поджо¬
га знаменитого храма (основанная на рсальных событиях) становится по¬
водом для размь 1шлений над вечными проблемами 〇 сущности красоты и
смерти. Все эти годы наряду с серьезными философскими произведениями
Мисима писал и совсем иную прозу 一 развлекательные романы, имевшие
большой успех, составили отдельный том в его собрании сочинений.
В 1959 г. вышел роман «Кё:ко-но иэ» («Дом Киоко»,1959), в котором
фигури ровало четы ре главных героя (как-бы четыре ипостаси самого ав¬
тора), а в 1960 г. роман «Итагэ-но ато» («После банкета»), которь1Й амери・
канский литературовед Дональд Кин, большой знаток творчества Миси¬
ма, считает «одной из самых больших удач писателя». Повесть «Ю:коку»
(«Патриотизм»,1961),повествующая об офицерекой среде 30-х гг., от-
крь 1вает новую большую тему «самурайского духа», воплощению кото-
рой (как в искусстве, так и в жизни) Мисима отдавал много сил. Его перу
принадлежит и множество пьес, к числу которых относятся «современ・
ные пьесы для театра Но», пьеса «Вага том о Хиттора:» («Мой друг Гит¬
лер», 1968) и др. ゼ
Последней крупной работой писателя стала тетралогия «Хо:гё-но уми»
(«Море изобилия»), включающая «Хару・но юки» («Весенний снег»,1969),
«Хомба» («Мчащиеся кони»,1969), «Акацуки-но тэра» («Храм на рас-
свете»,1970) и «Тэннин го суй» («Падение ангела»,1970).
В основе тетралогии лежит буддийская идея реинкарнации —— repoями
книг оказываются разные перерождения одного из главных персонажей
«Весеннего снега».
25 ноября 1970 г. Мисима Юкио ушел из жизни, совершив ритуальное
самоубийство вспарыванием живота.
В хрестоматии 叩иведен рассказ «Хождение через мост» («Хаси зуку-
си»,1956).
Литература 〇 Мисима Юкио
1. Гривиии В. С. Путь самурая // Иност ранная лите ратура. М.,1971.№ 3.
2. Чхартишвили Г. 11I. Жизнь и смерть Юкио Мисима или Как уничто¬
жить храм // В КН.: Юкио Мисима. Золотой храм. СПб., 1993.
ITepеводы на русский язык
1. Юкио Мисима. Золотой храм. Роман. Новеллы. Пьесы/Пер. Г. Ш. Чхар¬
тишвили. СПб., 1993.
2. Юкио Мисима. Исповедь маски (роман), новеллы, пьесы, эссе. / Пер.
Г. Ш. Чхартишвили. СПб., 1994.
3. Юкио Мисима. Хагакурз нюмон Самурайская этика в современной
Японии // В КН.: Ямамото Цунэтомо. Хагакурэ. Юкио Мисима. Хагакурз
нюмон / Пер. А. Мищенко. СПб., 1996.
4. Мисима Юкио. Жажда любви / Пер. А. Вялых. СПб.: Гиперион, 200〇.
АБЭ КО:БО: (1924-1993)
Писатель, драматург публицист. Один из наиболее оригинальных пи¬
сателей послевоенного поколения, получивший тирокое международное
叩 изнание.
Настояще имя Абэ Кимифуса. Родился в Токио в семье врача. Детство про¬
вел в Маньчжурии, в Мукдене, где работал отец. В 1941 г. вернулся в Гокио,
веко ре по настоянию семьи поступил на медицинский факультет Токийского
университета. В 1948 г закончил учебу, но ни одного дня своей жизни не за¬
нимался врамебной практикой. Решив еще в студенческие годы посвятить
себя литературе, пишет свои первые рассказы в 40-50-е годы. Первым про-
изведением, отмеченным критикой, стала повесть «Кабэ» («Стена. Преступ-
ление С. Кармы»,1951),за которую он получил премию Акутагава. В этой
работе были намечены основные темы 一 одиночества и отчужденности чело¬
века в урбанизированном мире, потери собственной личности, утраты само¬
идентификации 一 которые нашли свое воплощение в следующих книгах Абэ
Ко:бо:. В 1954 г вышла повесть «Кига до:мэй» («Союз голодающих»), затем
повесть «Кэмонотати-ва кокё;-о мэдзасу» («Звери стремятся домой»,1957), в
1959 г. повесть «Дайси кампё:-ки» («Четвертый ледниковый пер иод»). Наиболь¬
шую известность принесли писателю романы «Суна-но онна» («Женщина в
песках»,1962), «Танин-но као» («Чужое лицо»,1964), «Моэцукита тидзу» («Со¬
жженная кар та»,1967) и «Хако отоко» («Человек-ящик»,1973). Сюжетно эти
романы не связаны друг с другом, однако их объединяет единый мотив утраты
человеком собственной сущности, бесконечного одиночества человека средн
себе подобных, иллюзорность многих навязанных обществом ценностей, без¬
душия самого общества, живущего по законам инерини.
Наряду с про ЗОЙ Абэ Ко:бо: много и плодотворно работал для теат ра.
К числу его наиболее известных пьес относятся «Бони натта отоко»
(«Человек, превратившийся в палку»,1969), «Томодати» («Друзья»,1967),
«Мидорииро-но сутокингу» («Зеленые чулки»,1974) и др. В 1973 г. писа¬
тель организовал собственную труппу «Студию Абэ», в который успешно
выступал не только как драматург; но и как режиссер.
В 1977 г. выходит новая повесть «Миккай» («Тайное свидание»), свое-
образная сатира на бюрократическое общество. В романе «Хакобунэ саку-
ра-мару» («Вошедшие в ковчег»,1984) ставится проблема выживаемости
человека в современном мире. В 1986 г. писатель выпускает новый роман
«Си-ни исогу кудзиратати» («Киты спешат наветречу смерти»), а в 1991 г.
печатает роман «Кангару но:то» («Записки кенгуру»). Последней незавер¬
шенной работой стала повесть «Тобу отоко» («Летающий человек»).
Абэ Ко:бо: скончался в 1993 г.
Многие критики отмечают влияние Кафки на творчестве писателя, но
по собственному признанию Абэ Ко:6о:, ему ближе манера Гоголя. Абсурд 臣.
и рсальность, вымысел и достоверность, трагедия и гротеск 一 казалось бы
противоположные понятия ——легко уживаются на страницах его книг.
В хрестоматии представлены два ранних рассказа писателя «Рука» («Тэ»,
1951)и «Ловушка Плутона» («Пуру:то:-но вана»,1952).
Литература 〇 Абэ Ко:бо:
1. Гривиии В. С. Трилогия Кобо Абэ / Иност ранная лите ратура. М.,1969.
№ 10.
2. Гривиии В. С. Кобо Абэ 一 писатель и драматург // В кн.: Кобо Абэ.
Пьесы. М.,1975.
3. Григорьева Т. П. Японская литература XX века. Размышления 〇 тра¬
диции и современности. М.,1983.
4. Злобии Г. Дорога к другим — дорога к себе // В кн.: Кобо Абэ. Женщи¬
на в песках. Чужое лицо. М.,1988.
5. Рёхо К. Соврсменный японский роман. М.,1977.
6. Чегодарь Н. И. Человек и общество в послевоенной литературе Япо¬
нии. М.,1985.
Переводы на русский язык
1. Абэ Кобо, Оэ Кэндзабуро. Время «малых жанров»? Диалог // Иност-
ранная литература / Пер. И. Львовой и В. С. Гривнина. М,1965. № 8.
2. Абэ Кобо. Женщина в песках. Чужое лицо / Пер. В. С. Гривнина. М.,
1988.
3. Абэ Кобо. Четвертый ледниковый период / Пер. С. Бережкова. М,1965.
4. Абэ Кобо. Изб ранное: Чужое лицо. Сожженная кар та. Человек-ящик
/ Пер. В. Гривнина. М.,1988.
5. Абэ Кобо. Женщина в песках. Повести. Рассказы. Сцены / Пер. В. С.
Гривнина. М.,1987.
6. Абэ Кобо. Пьесы: Призраки среди нас. Крепость. Охота на рабов. М.,
1975.
〇:Э КЭНДЗАБУРО:
Прозаик, публицист. Один из крупнейших современных японских писа¬
телей. Лауреат Нобелевской премии 1994 г.
Родился в маленькой деревушке на острове Сикоку в 1935 г. В 1959 г.
закончил французское отделение Токийского универснтета, его дипломная
работа была посвящена творчеству Сартра, оказавшего серьезное влияние
на молодого литератора・ 〇:э Кэндзабуро: начал печататься еще в студенче¬
ские годы, его ранняя повесть «Сиику» («Содержание скотины»,1958) была
удостоена престижной премии Акутагава. Признанный лидер нового поко¬
ления писателей 〇:э не боялся ставить острые политические и социальные
вопросы. Его первые работы были посвящены жизни молодежи ——повесть
«Варэра-но дзидай» («Наш век»,1959), рассказ «Себунтин» («Семнадцати¬
летний», 1961)ид р.
«Обманутое» поколение, истоки зарождения левого экстремизма стали
темой романа «Окурэтэ кита сэйнэн» («Опоздавшая молодежь»,1962).
Вынержавший множество изданий и отмеченный премией Танидзаки ро・
ман «Манъэн Ганнэн-но футтобору» («Футбол 1860 года»,1967) заострял
внимание на отношении «толпа-лидер», а следующая книга «Ко:дзуй-ва вага
тамасии-ни оеби» («Объяли меня воды до души моей»,1973) исследовала
причины молодежной философии бегства от общества. Сатирой на левый
экстремизм называют критики «Записки пинчраннера» («Пинтиранна тёхё»,
1976), рисующие человечество перед лицом угрозы атомного истребления.
«До:дзидай гэ:му» («Игры современников»,1979), вскрывающий природу
тирании, предупреждал об опасности политики силы. Начиная с 70-х гг., пи¬
сатель все чаще и чаще возвращается к теме ядер ной катастрофы, р исуя уто¬
пические модели спасения человечества. «Варэра・но кё:и-о икинобиру мити-
〇 осиэё» («Научи нас изжить наше безумие»,1969) предлагает человечеству
спрятаться от всех проблем нашего врсмени в лесной чаще. Символический
образ леса вновь становится одним из гер оев романов «Икани ки-о кор осу»
(«Как убить дерево?»,1984) и «М/Т то мори-но фусиги-но моногатари» («По¬
весть 〇 [коэффициенте] М/Т и чудесном лесе»,1986).
Еще один сквозной мотив многих произведений 〇:э Кэндзабуро: 一 вза¬
имоотношения между отцом и его умственно неполноценным сыном. К се-
рии таких книг относятся романы «Кодзинтэки-на тайкэн» («Индивидуаль¬
ный опыт»,1964), «Сакэби гоэ» («Кр ики»,1962), «Атарасии хито ё мэдзамэё»
(«Пробуждайся, новое поколение!»,1983), сборники эссе «Юруякана кид-
зуна» («Слабые узы»,1995) и «Кайфуку-суру кадзоку» («Выздоравливаю¬
щая семья»,1995).
〇:э Кэндзабуро: много и плодотворно работает в жанре публицистики.
В многочисленных сборниках статей он часто обращается к таким темам
как атомные удары по Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой вой- 巴—
ны, угроза ядерного уничтожения человечества, американское присутствие
на о.Окинава, возрождение японского национализма и др.
К числу художественных произведений конца 80-начала 90-х гг., практи-
чески неизвестных в России, относятся романы «Нацукасии тоси-э-но тэга¬
ми» («Письма милым сердцу годам»,1987), «Дзинсэй но синсэки» («Родст-
венники человека»,1989), «Сидзукана сэйкацу» («Спокойная жизнь»,1990).
В хрестоматию включен один из лучших ранних рассказов «Чужие ноги»
(«Танин-но аси»), впервме опубликованный в 1957 г.
Литература 〇 〇:э Кэндзабуро:
1. Гривнин В. С. Миф и реальность // В кн.: Оэ Кэндзабуро. Игры совре・
менников. М.,1987.
2. Гривнин В. С. Творческий путь Кэндзабуро Оэ // В кн.: Оз Кэндзабуро.
Футбол 1860 года. М.,1983.
3. Гривнин В. С. Молодой герой Кэндзабуро Оэ // В кн.: Оэ Кэндзабуро.
Опоздавшая молодежь. М.,199〇.
4. Чегодарь Н. И. Человек и общество в послевоенной литературе Япо¬
нии. М.,1985.
5. Григорьева Т. П. Японская литература XX века. Размышления 〇 тра・
диции и современности. М.,1983.
6. Старосельская Н. Д. Один из самых необходимых писателей. Ф. М. До¬
стоевский и Оэ Кэндзабуро // В кн.:100 лет русской культуры в Японии / Под
ред.几几 Громко вс кой. М.,1989.
7. Карякин Ю. Ф. Взорвать воображенье третьих лиц... (О романе Оэ
Кэндзабуро «Записки пинчраннера») // В кн.:100 лет русской культуры в
Японии / Под рад. Л. Л. Громковской. М.,1989.
Переводы на русский язык
1. Кэндзабуро Оэ. Опоздавшая молодежь. Футбол 1860 года / Пер. В.
С. Гривнина. М.,199〇.
2. Кэндзабуро Оэ. Футбол 1860 года. Роман и рассказы / Нер. В. С. Грив¬
нина. М.,1983.
3. Кэндзабуро Оэ. Объяли меня воды до души моей: Роман. Рассказы.
М.,1978.
4. Кэндзабуро Оэ. Записки пинчраннера / Пер. В. С. Гривнина. М.1983.
5. Кэндзабуро Оэ. Игры совремснников / Пер. В. С. Гривнина. М.,1987.
6. Кэндзабуро Оэ. Обращаюсь к современникам: художественная публи¬
цистика. Хиросимские записки. Послевоенное поколение и конституция.
Письма к молодежи // Сост. В. С. Гривнин. М.,1987.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН
Абэ Ко:бо: (Кимифуса)安部 公房 35,36
Акутагава Рю:носукэ 芥川竜之介10, 22, 23, 24, 28
Арисима Такэ〇 有島武 郎 9,19, 21
Дадзай Осаму (Цусима Сю:дзи)大宰 治(津島修治)29, 30
Ёкомицу Рннтм 横光利一 31
КавабатаЯсунари 川端 康成28,31,32,33
Китамура То:коку 北村透谷!1
Кобаяси Такидзи 小林多喜二 25
Кон То:ко:今東光 31
Куникида Доппо (Тэцуо)国木田独歩(哲夫)9,10
Мисима Юкио (Хираока Кимитакэ)三島由紀夫(平岡公威)33,34
Миямото Юрико (Тю:дзё: Юрико)宮本百合子(中条百合子)25, 26
Мори 〇:гай (Ринтаро:)森鷗外(林太郎
Моримото Кокити森本厚吉19
Мурасаки-сикибу 紫式部 27
Мусяноко:дзи Санэацу武者の小路実篤
)17,18,23,24
21
Нагаи Кафу: (Со:кити)永井荷風(壮吉
Нацумэ Со:сэки (Кинносукэ)夏目漱(金之助)13-15,23
Ниси Аманэ 西周!7
)15,16, 27
〇:э Кэндзабуро:大江健三郎 37, 38
Сатоми Тон里見とん21
Сига Наоя 志賀直哉 21,22
Симадзаки То:сон (Харуки)島崎藤村(春樹)11,12
Танидзаки Дзюнъитиро:谷崎潤一朗 27, 28
ТокунагаСунао 徳永直 25
39
Токутоми Рока (Кэндзиро:)徳富蘆花(健次郎)7, 8
Токутоми Сохо: (Иитиро:)徳富蘇峰(猪一郎)7
Утимура Кандзо:内村鑑三 21
Футабатэй Симэй (Хасэгава Тацуносукэ)二葉停四迷(長谷川辰之
助)5,6,12
Хироцу Рю:ро:広津柳浪15
Цубоути Сё:е:坪内逍遙 5,17
Юаса Ёсико湯浅芳子25
УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИИ ПРОИЗВЕДЕНИИ
И ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕРМИНОВ
Абэ итидзоку 阿部一族!7
Адзамукадзару-но ки 欺かざるの記 9
Аи-но каваки愛の渴き 33
Акацуки-но тэра 暁の 寺 34
Амэрика моногатари あめ り か物語 15
Амэсёхё:雨しようしよう15
Анъя ко:ро暗夜行路21
Араси 嵐11
Ару ахо:-но иссё:ある阿呆の一生24
Ару онна ある女 9,19
Асакуса курэнайдан 浅草紅団 3 1
Асикари 蘆刈 27
Атарасии хито ё мэдзамэё新しい 人 よめ ざめ よ37
Баннэн 晚年 29
Банрэки акаэ 万暦赤絵 21
Банею: ХЭЙЯ播州平野25
Бокуто: кидан 墨東綺譚15
Бо:-ни натта ото ко棒になった男35
Боттян坊)ちゃん13
Бумпай 分配11
Бунгакукай 文学界1]
бунгаку-но камисама 文学の神様 21
Бунгэй 文芸 29
Бунгэй дзидай 文芸時代 31
Вага томо Хиттора:わが友ヒ、ソト ラー 33
Вагахай-ва нэко дэ ару 吾輩は Ж である13
Вакай 和解 21
Ваканасю:若菜集 !1
Варэра-но дзидайわれらの時代37
Варэра-но кё:ки-о икинобиру мити-о осиэё われらの狂気を生き延び
る道を教えよ37 _
ватакуси сёхэцу 私小説 21,25
Vita sexualisヰタ・セクスアリス17
Ган 雁17
Губиндзинсо:虞美人草
Гуддобайグッド•バ
гэмбун итти 言文一致
□孔
イ5
Гэндзи моногатари 源氏物語 27
Гэн одзи源おぢ9
Гэсаку дзаммэй戯作三味 味23
Гю:нику то барэйсё牛肉と 馬鈴薯 9
「якко:逆行 29 »
Дайси кампёжи第師間氷期 35
Дзигокухэн 地獄変 23
Дзинсэй-но синсэки 人生の親戚
Дзигоку-но хана 地獄の花 15
До:дзидай гэ:му同時代ゲーム
Доппогин獨歩吟9
До:хё:道標 25
Дзию симбун自由新聞9
Ёакэмаэ夜明け前11
Ёмиури симбун 読壳新聞 17
ЁСИНО кудзу吉野葛 27
ею:余裕!3
ёю:ха余裕派13
Идзу-но одорико伊豆の踊り子
Икани КИ-0 коросу如何に木を殺す 37
Имогаю芋粥 23
Инъэй райсан 陰影礼讃 27
Исава Ранкэн 伊沢蘭軒 18
Итагэ-но ато 宴のあと 33
出家!1
Кабз 壁 35
Кам 鍵 27
Кайдзин 灰燼17
Каин-но мацуэйカインの末裔 19
Кайдзо:改造 25
Камисори 剃刀 21
Камэн-но кокухаку仮面の告白 33
Кангару: но:то カンガルー ノート 35
19
38
37
31
Канкан мусиかん々 虫
Каппа}可童 23
Кё:ко-но из鏡子の家
Кига до:мэй飢餓同盟
Киндзики 禁色 33
Кинкакудзи 金閣寺 33
Киринきりん27
§2 Ко:дзин 行ソ/ヽ13
33
35
Кодзинтэки-на тайкэн 個人的体験 37
Ко:дзуй-ва вага тамасии-ни оёби 洪水はわが魂に及び 37
Кокоро 心14
Кокумин симбун国民新聞 9
Кокумин-но томо 国民の友 7
Кондзяку моногатари 今昔物語 23
Кото古都 31
Кумо-но ИТО蜘蛛の糸23
Курой мэ то тяиро-но М3黒い目と茶色の目 ?
Куросио 黒潮 ?
Кусамакура 草枕 13
Кэмонотати-ва кокё:-о мэдзасуけものたちは故郷をめざす
Кю:сн窮死9
Маихимэ 舞姫17
Мадзусики хитобито-но мурэ 貧しき人々の群 25
Манъэн Ганнэн-но футтоб ору 万延兀年のフ、ソ トボーノレ
М идзуум нみづうみ31
Мидорииро-но сутокннгу緑色のストンキング 35
Миккай密会 35
Мимидзу-но таваготоみみずのたはこと7, 8
Минъюхя民友社7
Мита бунгаку 三田文学 !5
Митигуса 道草14
Мон 門13
Моэцукита тидзу燃えつきた地図35
Мусаси но武蔵野9
М/Т то мори-но фусиги-но моногатари М/Тと森のフシギ物語
Мэйан 明暗14
Нацукасии тоси-э-но тэгами懐かしい年への手紙38
Нацу -но гуса 夏草 И
нингэн кокухо:人間国宝 31
Нингэн сиккаку 人間失格 29
Нихон-кара Нихон-э日本から日本へ 7
Нихякуто:ка 二百十日13
Нобуко 伸子 25
Новаки 野分13
Нэги-сама Мияда禰宜様宮田 25
Нэмурэру бидзё眠れる美人31
0-Гин ぎん 23
Окамэдзасаおかめ笹15
Окицу Ягоэмон-но исё興津弥五右衛門の遺書!7
35
37
37
43
Окурэтэ кита сэйнэн遅れてきた青年37
Омоидэ-но КН思い出の記7
Омокагэ於母影17
Онна дэ ару кото女であること31
〇:сио Хэйхатиро:大塩平八郎17
Отоги дзо:си 4伽草紙 30
Оцу Дзюнкити 大津順吉 21
Пандора-но хакоパンドラの匣29
Пинтиранна тё:сёピンチランナーの調書37
Ракубайсю:落梅集11
Расё:мон羅生門 23
Ро:нэн 老年 23
Рэйсё:冷笑!5
Сакаи ДЗИКЭН 堺事件17
Сакэби гоэ 叫び声 37
Сангосю:珊瑚集15
Сансиро:三四郎13
Сасамэюки コ拈-27
Себунтинセブンチン37
Се:гун)|爭軍 23
Сибуэ Тю:сай 渋江抽斎18
Сигарами со:сиしがらみ草紙 17
Сидзукана сэйкацу 静かな生活 38
СИДЗЭНСЮГИ 自然主義11,13, 27
Сидзэ
но онна砂の女35
Сэйнэн 青年17
Сэйдза 星座19
Сэкибэцу 惜別 29
Сэмбадзуру 千羽鶴 31
Сюдзю-но котоба 珠儒の言葉 24
Сюнкин сё:春琴抄 27
Сяё:斜陽29
Табако 煙草 33
Тадэ куу муси蓼食う虫 27
Такэ-но кндо竹の木戸9
ТамакусигэфутариУрасимаたまくしげふたりうらしま17
Тампопо蒲公英32
Танагокоро-но сё:сэцу 掌の小説 31
Танин-но као 他人の顔 35
44 Танэмаку хито 種蒔 く 人 20
Тё:ко:до: дзакки 澄江堂雑記 23
Тибуса 乳房 25
Тидзин-но ан 痴人の愛 27
Тикумагава но сукэтти千曲川の スケ、ソチ11
Тобу ото ко 飛ぶ男 35
То:дзоку 盗賊 33
Томодати 友達 35
То:хо:-но МОН 東方の門12
Тэннин госуй天人五Й 34
Тэнфу ро:дзин НИККИ瘋癩の老人日記27
Удайдзин Санэтомо 右大臣実朝 30
Удэкурабэ 腕 く らべ15
Удзисю:и моногатари 宇治拾遺物語 23
Укигумо 浮雲 5
Уммэй ронся運命論者9
Утакато-но киうたかたの記17
Уцукусии Нихон-но ватакуси 美しい日本の私 32
Фудзн 富士 8
Фумидзукаи文 づかい17
Фурансу моногатариふらんす物語15
Футацу-но нива つの庭 25
Фу:тисо風知草25
Хагурума 歯車 24
Хаиро-но цуки 灰色の月 21
Хакобунэ сакура-мару 方舟さ くら丸 35
Хакан 破戒11
Хако ОТОКО 箱男 35
Хана 鼻 23
Ханадзакари-но морн 花ざかりの森 33
Ханкэтиハンケチ23
Хан-но хандзай 范の犯罪 21
Хару 春11
Хару-но торн 春の鳥 9
Хару-но ЮКИ 春の雪 34
Хатараку фудзин 働く 婦人 25
Хаха-но си то атарасии хаха母の死 と 新しし、母 21
Хиган судэ мадз 彼岸過迄13
хининдзё:非人情13
Хитохабунэ —葉舟11
Хо:гё-но ум и 豊饒の 海 34
Хо:дзё: Катэй 北条霞亭18
45
Хомба 奔馬 34
Хототогису 不如帰 ?
Хэйбон 平凡 5, 6
Цугару 津軽 29
Цую-но атосакиつゆのあとさき15
Юкигуни 雪国 31
Ю:коку 憂国 33
Юруякана кидзуна 緩やかな絆 38
Яма-но ото 山の音 31
Ясин野心!5
Ясукити-но тэте: кара保吉の手帳から23
СОДЕРЖАНИЕ
ХРЕСТОМАТИЯ ПО ИСТОРИИ ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ФТАБАТЭЙ СИМЭЙ
ТОКУТОМИ РОКА
КУНИКИДА ДОППО
СИМАДЗАКИ ТО:СОН
НАЦУМЭ со:сэки
НАГАИ КАФУ:
МОРИ 〇:ГАЙ
АРИСИМА ТАКЭО
СИГА НАОЯ
АКУТАГАВА РЮ:НОСКЭ
МИЯМОТО ЮРИКО
ТАНИДЗАКИ ДЗЮНЬИТИРО:
ДАДЗАЙ ОСАМУ
КАВАБАТА ЯСУНАРИ
МИСИМА ЮКИО
АБЭ КО:БО:
〇:Э КЭНДЗАБУРО:
УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН
УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
И ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕРМИНОВ
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
М. В. Торопыгина
К. Г. Маранджян
ХРЕСТОМАТИЯ ПО ИСТОРИИ
ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТОМ 11
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА СЕРЕДИНЫ Х1Х-ХХ ВВ.
Составитель
К. Г. МАРАНДЖЯН
Ответственный редактор
С. В. Смоляков
Художник
В. В. Неклюдов
Корректор
〇. Ю. Гауршева
Компьютерный набор
Р. Охира
Сдано в набор 7. 05. 200〇. Подписано в печать 9.10. 200〇.
Формат 60x88 1/32. Бумага офсетная №1.
Гарнитура «Times». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 23. Тираж 5000 (1-й завод 1000).
Заказ 245
Лицензия ИД 03369 от 28 ноября 2000 г.
Издательство «Гиперион»
19917& Санкт-Петербург; В. 〇., Большой пр., 55.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии ВНИГРИ
192102, Санкт-Петербург; ул. Салова, 28
ン
ヤ
ゾ
ン
ラ
マ
匕
日本文学史読本二巻
ヒペリオン出版社
サンクト・ペテロブールク、'
2001
目次
二葉亭四迷
徳富蘆花
国木田独歩
島崎藤村
夏目漱石
永井荷風
森鸥外
有島武郎
志賀直哉
©
芥川龍之介
宮本百合子
谷崎潤一郎
太宰治
川端康成
三島由紀夫
安部工房
大江健三郎
二葉亭四迷
「平凡」
十
ポチは言ふ迄もなく犬だ。
來年は四十だといふ、もう鬢に大分白髪も見える、汚い髭の親仁の私が、親に繼いでは犬の事を憶ひ出すなんぞと、餘り
馬鹿氣ていてお話にならぬ——と、被仰る方が有るかも知れんが、私に取っては、ポチは犬だが……犬以上だ。犬以上で、ー
寸まあ、弟……でもない、弟以上だ。何と言ったものか9 さうだ\命だ、第二の命だ。恥を言はねば理が聞けぬとい
ふから、私は理を聞かせる爲に敢て恥を言ふが、ポチは全く私の第二の命であった。其癖初めを言へば、欲しくて貰った犬で
はない、止むことを得ず……いや、矢張あれが天から授かったと云ふのかも知れぬ。
忘れもせぬ、祖母の亡なった翌々年の春雨のしとしとと降る薄ら寒い或夜の事であった。宵惑の私は例の通り宵の口から
寢て了って、いつ兩親は寢に就いた事やら、一向知らなかったが、ふと目を覺すと、有明が枕元を朦朧と照して、四邊は微暗
く寂然としてゐる中で、耳元近くに妙な音がする。ゴウといふかとすれば、スウと、或は高く或は低く、單調ながら、拍子を
取って、宛然大鋸 で大丸太を挽割るやうな音だ。何だらうと思って耳を澄ましてゐると、時々其音が自分と自分の單調に厭
©
もく
©
いたように、忽ちガアと慣れた調子を破り、凄じい、障子の紙の共鳴りのする程の音を立て、、勢込んで何處へか行きさ
うにして' 忽ち物に行當ったやうに、礪と止む。と、しばらくM寂となる。——その側から、直ぐ又穩やかにスウスウといふ
音が遠方に聞え出して、其が次第に近くなり、荒くなり、又耳元で根氣よくゴウ、スウ、ゴウ、スウと鳴る。
私は夜中に滅多に目を覺した事が無いから、初は甚く吃驚したが、能く研究して見ると、なに、父の鼾なので、漸と安心
して、其儘再び眠らうとしたが、壮なゴウゴウスウスウが耳に付いて中々眠付れない。仕方がないから、聞こえる儘に其音
に聽入ってゐると、思做しで種々に聞える。或は遠雷のやうに聞え、或は浪の音のやうでもあり、又は火吹達磨が火を吹い
てるやうにも思はれ、ば、ゴロタ道を荷馬車が通る音のやうにも思はれる。と、ふと畫間見た繪本の天狗が酒宴を開いてゐる
所を憶出して、阿爺さんが天狗になってお囉子を行ってるのぢゃないかと思ふと、急に何だか薄氣味惡くなって來て、私は頭
からスポッと夜着を冠って小さくなった。けれども、天狗のお囉子は夜着の襟から潜り込んで來て、耳元に纏り付いて離れな
い。私は擬然と固くなって其に耳を澄ましてゐると、何時からとなくお囉子の手が複雑で來て、合の手に遠くで幽かにキャン
キャンといふやうな音が聞える。ゴウといふ凄じい音の時には、それに消壓されて聞えぬが、スウといふ溜息のやうな音にな
ると、其が判然と手に取るやうに聞える。不思議に思って、益耳を澄ましてゐると、合の手のキャンキャンが次第に大きく、
高くなって、遂には軒の中を脱け出し、其とは離ればなれに、確かに門前に聞える。
かうなって見ると、疑もなく小狗の啼き聲だ。時々咽喉でも締られるやうに、消魂しくきゃんきゃんと啼き立てる其の聲尻
が、廳てかぼそく悲し氣になって、滅入るやうに遠い遠い處へ消えて行くIかとすれば、忽ち又近くで堪へ切れぬやうに
啼き出して、クンクンと鼻を鳴らすやうな時もあり、ギャオと欠びをするやうな時もある。
十一
私は元來動物好きで、就中犬は大好だから、近所の犬は大抵馴染だ。けれども、此樣繊弱い可愛げな聲で啼くのは一疋も
無い筈だから、不思議に思って、竊と、夜着の中から首を出すと、
「如何したの?寢られないのかえ?」
と、母が寢反りを打って此方を向いた。私は此返答は差措いて、
「あれは白ぢゃないねえ、阿母さん?最と小さい狗の聲だねえ?如何したんだらう?」
「棄狗さ。」
「棄狗ツて何?」
「棄狗ツて誰かヾ棄てツたのさ。」
私はしばらく考えて、
「誰が棄てツたんだらう?」
「大方何處かの……何處かの人さ。」
何處かの人が狗を棄てツたと、私は二三度反覆して見たが、分らない。
「如何して棄てツたンだらう?」
蒼Йよ、などといふ母ではない。何處迄も相手になって、其意味を説明して呉れて、もう晚いから默ってお寢と優しく言
って、又彼方向いて了った。
©
©
私も亦夜着を被った。狗は門前を去ったのか、啼聲が程遠くなるに隨れて、父の軒が又蒼Sг耳にに附く。寢られぬ儘に、私
は夜着の中で今聽いた母の説明を反覆,・猿し味って見た。まづ何處かの飼犬が椽の下で兒を生んだとする。小ぽけなむくむ
くしたのが重なり合って、首を擡げて、ミイミイと乳房を探してゐる所へ、親犬が餘處から歸って來て、其側へドサリと横
になり、片端から抱へ込んでペロペロと舐ると、小さいから舌の先で他愛もなくコロコロと轉がされる。轉がされては大騒ぎ
して起返り、又ヨチヨチと這ひ寄って、ポッチリと黑い鼻面でお腹を探り廻り、漸く思ふ柔かな乳首を探り當て、狼狽てチウ
と吸付いて、小さな兩手で、揉み立て揉み立て吸出すと、甘い温かな乳汁がどくどくと出て來て、咽喉へ流れ込み、胸を下
って、何とも言へずお甘しい。と、腋の下からまだ乳首に有附かぬ兄弟が鼻面で割込むで來る。奪られまいとして、産毛の生
えた腕を突張り大騒ぎ行ってみるが、到頭奪られて了ひ、又其處らを尋ねて、他の乳首に吸付く。其中にお腹も滿くなり、親
の肌で身體も温まって、溶けさうな好い心持ちになり、不覺昏々となると、含むだ乳首が脱けさうになる。夢心地にも狼狽
て又吸付いて、一しきり吸立てるが' 直に又他愛なく昏々となって、乳首が遂に口を脱ける。脱けても知らずに口を開いて小
さな口を出したなりで、一向正體がない……其時忽ち暗黑から、もじゃもじゃと毛の生えた、節くれ立った大きな腕がヌツ
と出て、正體なく寢入ってゐる所を無手と引掴み、宙に釣す。驚いて目をポッチリ明き、いたいげな聲で悲鳴を揚げながら、
四足を張って藻搔く中に、頭から何かで包まれたやうで、眞暗になる。窮屈で息氣が塞りさうだから、出やうとするが、出ら
れない。久らく藻搔いて居る中に、ふと足搔が自由になる。と、領元を撮まれて、高い高い處からドサリと落された。うろう
ろとして其處らを視廻すけれど、何だか變な淋しい眞暗な處で、誰も居ない。茫然としてゐると、雨に打れて見る間に濡しよ
ぼたれ、怕ろしく寒くなる。身慄ひ一つして、クンクンと親を呼んで見るが、何處からも出て來ない。途方に暮れて、ヨチョ
チと這出し、雨の夜中を唯一人、温かな親の乳房を慕って悲し氣に啼廻る聲が、先刻一度門前へ來て、又何處へか彷徨って行
ったやうだったが、其が何時か又戻って來て、何處を如何潜り込んだのか、今は啼聲が正しく玄関先に聞える。
十二
「阿母さん阿母さん、門の中へ入って來たやうだよ。」
と、私が何だか居堪らないやうな氣になって又母に言掛けると、母は氣の無さ、うな聲で、
「さうだね。」
「出て見やう力!」
「出て見ないでも好いよ。寒いぢゃないかね。」
「だってえ……あら' 彼様に啼てる……」
と、折柄絶入るやうに啼入る狗の聲に、私は我知らず勃然起上がったが、何だか一人では可怕いやうな氣がして、
「よう、阿母さん、行って見やうよう!」
「本當に仕様がない兒だねえ。」
と、口小言を言ひ言ひ'母も»々起きて、雪洞を點けて起上ったから、私も其後に隨いて、玄關——と云ってもツイ次の
間だが、玄關へ出た。
母が覆脱へ降りて格子戸の掛金を外し、ガラリと雨戸を繰ると、颯と夜風が吹込んで、雪洞の火がチラチラと靡く其時〃
©
さな鞠のやうな物が衝と軒下を飛退いたやうだったが、鬆て雪洞の火先が立直って、一道の光がサッと戸外の暗黑を破り、雨水
の處々に溜った地面を一筋細長く照出した所を見ると、ツィ其處に生後まだ一ケ月も經たぬ、むくむくと肥った、赤ちゃけた
狗兒が小指程の尻尾を千切れさうに掉立って此方を瞻上げてゐる。形體は私が寢ていて想像したよりも大きかったが、果して
全身雨に濡れしよぼたれて、泥だらけになり、だらりと垂れた割合に大きい耳から零を滴し、ぽっちりと兩つの眼を靑貝のや
うに列べて光らせてゐる。
「おやおや、まあ、可愛らしい!……」と母も不覺言って了った。
況や私は犬好だ。凝として視ては居られない。母の袖の下から首を出して、チョッチョッと呼んで見た。
と、左程畏れた様子もなく、チョコチョコと側へ來て流石に少し平べったくなりながら、頭を撫でゝやる私の手を、下力
らグイグイ推上げるやうにして、ペロペロと舐廻し、手を呉れる積なのか、頻に圓い前足を擧げて、バタバタやってゐたが、
果は、和りと痛まぬ程に小指を咬む。
私は可愛くて可愛くて堪まらない。母の面を瞻上げながら、少し鼻聲を出し掛けて、
「阿母さん、何か遣って。」
「遣るも好いけど、居附いて了ふと、仕方がないねえ。」
と、口では拒むやうな事を言ひながら、それでも臺所へ行って、缺茶碗に冷缺を盛って、何かの汁を掛けて來て呉れた。
早速覆脱へ引入れて之を當がふと、小狗は一寸香を嗅いで、直ぐ甘さうに先ずピチャピチヤと舐出したが、汁が鼻孔に入る
と見えて、時々クシンクシンと小さな嚏をする。忽ち汁を舐盡して、今度は飯に掛かった。他に争う兄弟も無いのに、切
に小言を言ひながら、ガツガツと喫べ出したが、飯は未だ食慣れぬかして、兎角上顎に引附く。首を掉って見るが、其様な事
では中々取れない。果は前足で口の端を引搔くやうな眞似をして' 大藻搔きに藻搔く。
此隙に私は母と談判を始めて、今晩一晩泊めて遣ってと、雪洞を持った手に振垂る。母は一寸®ったが、もう斯うなっては
仕方がない。阿爺さんに叱られるけれど、と言ひながら、詰り棧俵法師を捜して來て、覆脱の隅に敷いて遣った——は好かっ
たが、其晚一晚啼通されて、私は些とも知らなんだが、お蔭で母は父に小言を言はれたさうな。
十三
犬嫌の父は泊めた其夜を啼明されると、うんざりして了って、翌日は是非逐出すと言出したから、私は小狗を抱いて逃廻
って、如何しても放さなかった。父は困った顔をしてゐたが、併し其も一時の事で、其中に小狗も獨寢に慣れて、夜も啼かな
くなる。と、逐出す筈の者に、いっしかポチといふ名まで附いて、姿が見えぬと父までが一緒に捜すやうになって了った。
父が斯うなったのも、無論ポチを愛したからではない。唯私に覊されたのだ。私とてもポチを手放し得なかったのは、強
ちポチを愛したからではない。愛する愛さんはЙ置いて、私は唯可哀さうだったのだ。親の乳房に縮ってゐる所を、無理に無
慈悲な人間の手に引離されて、暗い浮世へ突放された犬の子の運命が、子供心にも如何にも果敢なく情けないやうに思はれて、
手放すに忍びなかったのだ。
此忍びぬ心と、その忍びぬ心を破るに忍びぬ心と、二つの忍びぬ心が搦み合った處に、ポチは旨く引掛って、辛くも棒石
塊の危ない浮世に彷徨ふ憂目を免れた。で、どうせ、それは、蜘蛛の巣だらけでは有ったらうけれど、兎も角も雨露を凌ぐに
足る椽の下の菰の上で、甘くはなくとも朝夕ニ度の汁掛け飯に事缺かず、まづ無事に暢びりと育った。
育つに隨れて、丸々と肥って可愛らしかったのだが、身長に幅を取られて、ヒョ□長くなり、面も甚く卜ギスになって、ー
寸狐のやうな犬になって了った。前足を突張って、尻をもったてゝ、弓のやうに反って伸をしながら、大きな口をアングリ開
いて欠びをする所なぞは、誰が眼にも餘まり見とも好くもなかったから、父は始終厭な犬だ犬だと言って私を厭がらせたが、
私はそんな犬振りで情を二三にするやうな、そんな輕薄な心は聊かも無い。固より玩弄物にする氣で飼ったのでないから、
厭な犬だと言はれる程、尚可愛ゆい。
「ねえ、阿母さん此様な犬は何處へ行ったって可愛がられやしないやねえ。だから家で可愛がって遣るんだねえ。」
と、いつも苦笑する母を無理に味方にして、調戯ふ父と爭った。
犬好きは犬が知る。私の此心はポチにも自然と感通してゐたらしい。其證據には犬嫌ひの父が呼んでも、ほんの一寸お愛想
に尻尾を掉るばかりで、振向きもせんで行って了ふ事がある。母が呼ぶと、不斷食事の世話になる人だから、又何か貰えるか
と思って眼を輝かして飛んで來る、而して母の手中に其らしいものがあれば、兎のやうに跳ねて喜ぶ。が、しかし、唯其丈の
事で、其時のポチは矢張犬に違ひない。
その矢張犬に違ひないポチが私に對ふと……犬でなくなる。それとも私が人間でなくなるのかワ……何方だか其は分らん
が、兎に角互の熱情熱愛に、人畜の差別を撥無して、渾然として一如となる。
一如となる。だから、今でも時々私は犬と一緒になって此様な事を思ふ、あゝ、儘になるなら、人間の面の見えぬ處へ行っ
て、飯を食って生きていたいと。
犬も屹度然う思ふに違いないと思ふ。
十四
私は生來の朝寢坊だから、毎朝二度三度覺されても中々起きない。優しくしていては際限がないので、母が最終には夜着を
剥ぐ。これで流石の朝寢坊も不承々々に床を離れるが、しかし大不平だ。額で母を睨めて、津蟹が泡を吐くやうに、沸々言
ってゐる。ポチは朝起だから、もう其時分には疾くに朝飯も濟むで、一切遊んだ所だが、私の聲を聽き付けると、何處に居て
も一目散に飛んで來る。
これで私の機嫌も直る。急に現金に莞爾々々となって、急いで庭へ降りる所を、ポチが透さず泥足で飛付く。細い人參程の
赤ちゃけた尻尾を懸命に掉り立って、嬉しさうに面を瞻上る。視下す。目と目と直たりと合ふ。堪まらなくなって私が横抱に
引ン抱く。ポチは抱かれながら、身を藻搔いて大暴れに暴れ、私の手を舐め、胸を舐め、顋を舐め、頰を舐め、舐めても舐め
ても舐め足らないで、惡くすると、口まで舐める。父が面を颦めて汚い汚いと曰ふ。成程、考えて見れば、汚いやうではある
けれども……しかし、私は嬉しい、止められない。如何して是が止められるもんか!私が何も好い物を持ってゐるぢゃなし、
ポチも其は承知で爲る事だ。利害の念を離れて居るのだ、唯懐かしいといふ刹那の心になって居るのだ。毎朝これでは着物が
堪らないと、母は其を零すけれど、着物なんぞの汚れを厭って、ポチの此 志を無にする事が出来た話だか、話でないか、
其處を一つ考へて貰ひたい。
理屈は»置いて、この面舐めの一儀が濟むと、ポチも漸と是で氣が濟むだといふ形で、また庭先をうろうろし出して、椽の
下なぞ覗いて見る。と、其處に草鞋蟲の一杯依附った古草履の片足か何ぞが有る。好い物を看附けたと言ひさうな面をして、
其を哇へ出して來て、首を一つ掉ると、草履は横飛にポンと飛ぶ。透さず追兎けて行って、又唾へてポンと抛る。其様な他愛
もない事をして、活浣に元氣よく遊ぶ。
其隙に私は面を洗ふ、飯を食ふ。それが濟むと、今度は學校へ行く段取になるのだが、此時が一日中で一番私の苦痛の時だ。
ポチが跟を追ふ。うツかり出やうものなら、何處迄も何處迄も隨いて來て、逐ったって如何したって歸らない。こッそり出や
うとしても、出掛ける時刻をチャンと知って居て、其時分になると、何時の間にか玄關先へ廻って待ってゐる。仕方がないか
ら、最終には取捉まへて否應なしに格子戸の内に入れて置いては出るやうにしてゐたが、然うすると、前足で格子戸を引搔い
て、悲しい悲しい血を吐きさうな啼聲を立てゝ後を慕ひ、姿が見えなくなっても啼止まない。私もそれは同じ想だ。泣出し
さうな面をして、バタバタと駆出し、聲の聞えない處まで來て、漸くホッとして、普通の歩調になる。而して常も心の中で反
覆し反覆し此様な事を思ふ、
「僕が居ないと淋しいもんだから、それで彼様に跟を追ふンだ。可哀さうだなあ……僕あ學校なんぞへ行きたか無いンだけ
ど……行かないと、阿父さんがポチを棄てツ了ふッて言ふもんだから、それでショウがないから行くンだけども:::」
十五
ジャンジャンと放課の鐘が鳴る。今迄靜かだった校舎内が俄かに騒がしくなって、彼方此方の教室の戸が前後して慌だし
くパツパツと開く。と、その狭い口から、物の眞黑な塊りがドッと廊下へ吐出され、崩れてばらばらの子供になり、我勝に
玄關脇の昇降口を目菟けて駆出しながら、口々に何だか喚く。只もう校舎を撼ってワーッといふ聲の中に、無數の圓い顔が默
って大きな口を開いて躍ってゐるやうで、何を喚いてゐるのか分らない。で、それが一旦昇降口へ吸込まれて、此處で又粉々
と入亂れ重なり合って、腋の下から才槌頭が偶然と出たり、外齒へ肱が打着かったり、靴の踵が生懵と霜燒の足を踏むだり
して、上を下へと捏返した揚句に、ワッと門外へ押出して、東西へ散々になる。
仲善二人肩へ手を掛合って行く前に、辨當箱をポンと抛り上げてはチョイと受けて行く頑童がある。其隣りは往來の石塊を
蹴飛ばし蹴飛ばし行く。誰だか、後刻で遊びに行くよ、と喚く。蝗を取りに行かないか、といふ聲もする。君々と呼ぶ背後
で、馬鹿野郎と誰かヾ誰かを罵る。あ、痛たツ、何でい、わ一い、といふ聲が諜然と入違って、友達は皆道草を喰ってゐる中
を、私一人は駆脱けるやうにして側視もせずに切々と歸って來る。
家の横町の角迄來て 操 たいやうな心持ちになって、竊と其方角を觀る。果してポチが門前へ迎へに出てゐる。私を看附る
や、逸散に飛んで來て、飛付く、舐める。何だか「兄さん!」と言ったやうな氣がする。若し本包に、辨當箱に、草履袋で
兩手が塞がってゐなかったら、私は此時ポチを捉まへて何を行ったか分らないが、其が有るばかりで、如何する事も出來な
い。據どころなくほたほたしながら頭を撫でゝ遣るだけで不承して、又歩き出す。と、ポチも忽ち身を曲らせて、横飛にヒョ
イと飛んで馳出すかと思ふと、立止って、私の面を看て滑稽た眼色をする。追付くと、又逃げて又其眼色をする。かうして
巫山戯ながら一緒に歸る。
玄關から大きな聲で、「只今!」といひながら、内へ翫込んで、卒然本包みを其處へ抛り出し、慌てゝ辨當箱を開けて、今
日のお菜の殘り——と稱して、實は喫べたかったのを我慢して、半分殘して來た其物をポチに遣る。其でも足らないで、お
ハッにお煎を三枚貰ったのを、責って五枚にして貰って、二枚は喫べて、三枚は又ポチに遣る。
夫から庭で一しきりポチと遊ぶと、母が屹度お温習をお爲といふ。このお温習程私の嫌ひな事はなかったが、之をしない
と、直ポチを棄ると言はれるのが辛いので、傩々内へ 入って、形の如く本を取出し、少し許おんによごよごと行る。それで
©
終だ。餘り早いねと母がいふのを、空耳潰して、衝と外に出て、ポチ來い、ポチ來いと呼びながら、近くの原へ一緒に遊び
に行く。
これが私の日課で、ポチでなければ夜も日も明けなかった。
十六
ポチは日增しにメキメキと大きくなる。大きくはなるけれど、まだ一向に孩兒で、垣の根方に大きな穴を掘って見たり、下
駄を片足門外へ啣へ出したり、其様惡戯ばかりして喜んでゐる。
それに非常に人懐こくて、門前を通掛りの、私のやうな犬好きが、氣粉れにチョッチョッと呼んでも、直ともう尾を掉っ
て飛んで行く。況して家へ來た人だと、誰彼の見界はない、皆に喜んで飛付く。初ての人は驚いて' 子供なんぞは泣出すの
もある。すると、ポチは吃驚して其面を視てゐる。
人でさへ是だから同類は尚戀しがる。犬が外を通りさへすれば吃度飛んでくる。喧嘩するのかと、私がハラハラすれば、喧
嘩はしない。唯壯に尻尾を掉って鼻を嗅合ふ。大抵の犬は相手は子供だといふ面をして、其儘さっさと行かうとする どっ
こいとポチが追菟けて巫山戯かゝる。蒼Йいと言はぬばかりに、先の犬は齒を剥いて叱る。すると、ポチは驚いて耳を伏せて
逃げて來る。
ポチは此様な無邪氣な犬であったから、友達は直出來た。
友達といふのは黑と白とのーー匹で、いづれもポチより三ツ四ツも年上であった。歴とした家の飼ひ犬でありながら、品性の
甚だ下劣な奴等で、毎日々々朝から晚まで近所の掃溜をあさり歩き' 二度の食事の外の間食ばかり貪ってゐる。以前から私
の家の掃溜めへも能く立廻って來て、馴染の犬共ではあるけれど、ポチを飼ふやうになってからは、尚ほ頻繁に立廻って來る。
ポチの喫剩しを食ひに來るので。
ポチは大様だから、餘處の犬が自分の食器へ首を突込んだとて、怒らない。默って快く食はせて置く。が、他の食ふのを見
て自分も食氣附く時がある。其様な時には例の無邪氣で、うツかり側へ行って一緒に首を突込まうとする。無論先の犬は、馳
走になってゐる身分を忘れて、大に怒って叱付ける。すると、ポチは驚いて飛退いて、不思議さうに小首を傾げて、其ガッガ
ッと食ふのを默って見てゐる。
父は馬鹿だと言ふけれど、馬鹿氣て見える程無邪氣なのが私は可愛ゆい。尤も後には惡友の惡感化を受けて、友達と一緒
に近所の掃溜めへ首を突込み、鮭の頭を舐ったり、通掛りの知らん犬と喧嘩したり、屑拾ひの風體を怪しむで押収圍んで吠
え付いたりした事も無いではないが、是れは皆友達を見やう見眞似に其の尻馬に騎って、譯も分らずに唯騒ぐので、ポチに些
っとも惡意はない。であるから、獨りの時には、矢張元の無邪氣な人懐こい犬で、滑稽た面をして他愛のない事ばかりして遊
んでゐる。惟ふに、私等親子の愛しみを受けて、曾て痛い目に遭った事なく、暢氣に安泰に育ったから、それで此様に無邪
氣であったのだらうが、あゝ想出しても無念でならぬ。何故私はポチを«けて、人を見たら皆惡魔と思ひ、一生世間を睨め付
けては居させなかったらう?愁じ可愛がって育てた爲に、ポチは此様に無邪氣な犬になり、無邪氣な犬であった爲に、遂に殘
忍な刻薄な人間の手に掛って、彼様な非業の死を遂げたのだ。
十七
或日の事。卑しい事を言ふやうだが、其日の辨當の菜は母の手製の鰹節でんぶで、私も好きだが、ポチの大好きなものだっ
たから、我慢して半分以上殘したのが、チャンと辨當箱に入ってゐる。早く歸ってこれが喫させたかったので、待憧れた放課
の鐘が鳴るや、大急ぎで學校の門を出て、友達は例の通り皆道草を喰ってゐる中を、私一人は切々と歸って來ると、俄かに行
手がワツと騒がしくなって、先へ行く兒が皆雪崩れて、ドッと道端の杉垣へ片寄ったから、驚いてヒョイと向ふを見ると、ツ
イ四五間先を荷車が來る。瞥と見たばかりでは何の車とも分らなかった。何でも可なり大きな箱車で、上から菰を被せてあっ
たやうだったが、其を若い土方風の草鞋穿の男が、餘り重さうにもなく、さっさと引いて來る。車に引添うてまだ一人、四十
許りの、四角な面の、茸々と鬚の生えた、人相の惡い、矢張草履穿の土方風の男が、古ぼけて茶だか鼠だか分らなくなっ
た、塵埃だらけの鉢巻もない帽子を阿彌陀に冠って、手ぶらで何だか饒舌りながら來る。
あみた かぷ
道端の子供等は皆好奇の目を圓くして此怪し氣な車を見迎へ見送って、何を言ふのか、
忽ち一段際立って甲高な、「犬殺しだい犬殺しだい!」といふ叫聲が其處此處から起る。
身の血の通ひが急に一時に止ったやうな氣がして、襟元から冷りとする、足が窘蹙む……
鼓動し出す。「ポチはワ……」といふ疑問が曇ったやうな頭の中で、ちらりと電光のやうに閃いて又暗中に没する時、ガタガ
口々に諜然と喚いてゐる中から、
と聞くより、私はハッとした。全
と、忽ち心臓が破裂せむばかりに
タと車が前を通る。
後で聞けば、菰の下から犬の尻尾とか足とかヾ見えてゐたといふけれど、私が其時佶と目を据ゑて視たのは、唯車が躍っ
て菰がゆさゆさと揺るのが見えたばかりで、他には何も見えなかった。或は最う目も霞むでゐたのかも知れぬ。
「おツそろしい餓鬼だなあ!まだ彼様に出て來やがら……」
と太い煤けたやうな野良聲で、——確に年上の奴に違ひないが、然う言ふのが聞えた。
ガタンと一つ小石に躍って、車は行過ぎて了ふ。
跡は兩側の子供が又續々と動き出し、四邊が大黑帽に飛石の衣服で粉々となる中で、私一人は佇立ったまゝ、茫然として轅棒
の先で子供の波を押分けて行くやうに見える車の影を見送ってゐた。
と、誰だか私の側へ來て、何か言ふ。顔は見覺えのある家の近所の何とかいふ兒だが、言ってる事が分らない。私は默って
其面を視たばかりで、又竊と車の行った方角を振向いて見ると、最う車は先の横町を曲ったと見えて、此方を向いて來る澤山
の子供の顔が見えるばかりだ。
「ねえ、君、君ン所のポチも殺されたかも知れないぜ。」
という聲が此時ふと耳に入って、私はハッと我に反ると、
「腔だい!殺されるもんか!札が附いてるもの……」
と狼狽て打消てから、始めて木村の賢ちゃんといふ児と話をしてゐる事が分った。
「やあ……札が附いてたって、殺されますから。へえ。僕ン所の阿爺さんが……」
と賢ちゃんが言掛けると、仲善の友の言ふ事だが、私は何だか口惜しくなって、赫と急込んで、
「何でい!大丈夫だい》……」
と怒鳴り付けた。賢ちゃんが吃驚して目を圓くした時、私は卒然バタバタと騷出し、前へ行く兒にトンと衝當る。何しゃがる
ンだいと、其児に突飛されて、又誰だかに衝當る。二三度彼方此方で小突かれて、蹌踉として、危うかったのを辛と踏耐へる
びツくり
や、後をも見ずに逸散に宙を飛で家へ歸った。
十八
門は明放し、草履は飛び飛びに脱棄て、、片足が裏返しなったのも知らず、「阿母さん阿母さん!」と卒然内に喚き込んだ
が、母の姿は見えないで、臺所で返事がする。
誰だか來て居るやうで、話聲がしてゐるけれど、其様な殊に頓着しては居られない。學校道具を座敷の中央へ抛り出して置
いて臺所へ飛んで行くなり、
「阿母さん》……ポチは?:
と喘ぎ喘ぎまづ聞いてみた。
母は默って此方を向いた。常は滅入ったやうな蒼い面をしてゐる人だったが、其時此方を向いた顔を見ると、微と紅くなっ
て、眼に潤みを持ち、どうも尋常の顔色ではない。私は何か物に行當ったやうにうろうろして、
「殺されたかいワ 」
と疑と母の面を視た時には、氣息が塞りさうだった。
母は一寸躊躇ったやうだったが、思切って投出すやうに、
「殺されたとさ:::」
逸散に騷て來て、ドカッと深い穴に落ちたら、彼様な氣がするだらうと思ふ。私は然う聞くと、ハッと内へ氣息を引いた。
と、張詰めて破裂れさうになってゐた氣がサッと退いて、何だか奥深い穴のやうな處へ滅入って行くやうで' 四邊が濛と暗く
なると' 母の顔が見えなくなった……
「炭屋さんが見て來なすッたンだッさ。」
といふ聲がふと耳に入ると、クワッとまた其處らが明るくなって眼の前に丸髻が見える。母は又彼方向いて了ったのだ。
「ぢや、木村さん處の前で殺されたんですね?」と母の声がいふ。
「へえ」、といふ者がある。機械的に其方へ面を向けると、腰障子の蔭に、ふるい馴染の炭屋の爺やの、小鼻の脇に大きな
黑子のある、皺だらけの面が見えて、前齒の二本脱けた間から、チョコチョコ舌を出して饒舌ってゐる聲が聞える。「丁度あ
の木村さんの前ン處なんで。手前は初めは何だと思ひました。棒を背後に匿してましたから、遠くで見たんぢや、ほら、分り
ませんや。一寸見ると何だか土方のやうな奴で、其奴がかう手を背後に廻しましてな、お宅の犬の寢てゐる側へ寄ってくから、
はてな、何をするンだらう、と思って見てゐますと、彼様な人懐こい犬だから、其奴の面を見て、何も知らずに尻尾を掉って
ましたよ。可哀さうに!普通の者なら、何ぼ何でも其様なにされちゃ' 手を下せた譯合のもんぢゃございません、——ね、今
日人情としましても。それを貴女……いや、どうも、あ、いふ手合に逢っちゃ敵ひませんて、卒然匿してた棒を取直して、
おやッと思ふ間に、ポンと一つ鼻面を打ちました。さうするとな、お宅のは勃然と起きましてな、キリキリと二三遍廻って、
バタリと倒れると' 仰向きになってかう四足を突張りましてな、尻尾でバタバタ地面を叩いたのは、あれは大方苦がったん
でせうが、傍で見てゐりや何だか喜んで尻尾を掉ったやうで、妙な鹽梅しきでしたがな、其處を、貴女、またポカポカと三つ
四つ咽喉ン處を打ちますとな、もう、其切りで、ギヤツともスウとも聲を立て得ないで、貴女……」
私はもう後は聽いてゐなかった。誰を憚る必要もないのに、窃と目立たぬやうに後方へ退って、狐鼠々々と奥へ引込んだ。
は-еづら
こそこそ
ペタリと机の前に坐つた。キリキリと二三遍廻ったといふ今聞いた話が胸に浮ぶと、そのキリキリと廻ったポチの姿が、顯然
と目に見えるやうな氣がする。熱い涙がほろほろ零れる、手の甲で擦っても擦っても、止度なくほろほろ零れる。
十九
ポチが殺されて、私は氣脱けしたやうになって、翌日は學校も休むだ。何も自分が罪を犯したでもないのに、何となく友達
に顔を見られるのが辛くツて:::
午過にポチが殺されたといふ木村といふ家の前へ行って見た。其處か此處かと尋ねて見たけれど、もう其らしい痕もない。
私は道端にたゝずむで、茫然としてゐた。
炭屋の老爺やの話だと、うッかり寢轉んでゐる所を殺されたのだと云ふ。大方昨日も私の歸りを待ちかねて、此處らまで迎
えに出てゐたのであらう。待草臥れて、ドタリと横になって、角のポストの蔭から私の姿がヒョッコリ出て來はせぬかと、其
方ばかりを餘念なく眺めてゐる所へ犬殺しが來たのだ。人間は皆私達親子のやうに自分を可愛がって呉れるものと思ってゐる
ポチの事だから、犬殺しとは氣が附かない。何心なく其面を瞻上げて尾を掉る所を、思ひも寄らぬ太い棍棒がブンと風をきっ
て來て……と思ふと、又胸が一杯になる。
ヒウと悲しい音を立て、、空風が吹いて通る。跡からカラカラに乾いた往來の中央を、砂烟が濛と力のない渦を巻いて、
振れてひょろひょろと行く。
私は其行方を眺めて茫然としてゐた。何処でかキャンキャンと二聲三聲犬の啼聲がする:::佶と耳を引立って見たが、も
う其切で聞えない。隣町あたりで凍けたやうな物賣の聲がする。
何だか今の啼聲が氣になる。ポチは殺されたのだから、もう此處らで啼いてる筈はない。餘所の犬だ犬だ' と思ひながら、
何だか其儘聞流して了ふのが殘惜しくて、思はずバタバタと監出したが、餘所の犬ぢや詰らないと思返して、又頹然となると、
足の運びも自然と遅くなり、そろりそろりと草履を引摺ながら、目的もなく小迷って行く。
小迷って行きながら、又ポチの事を考えてゐると、ふッと氣が變って、何だか昨日からの事が皆嘘らしく思はれてならぬ。
私が餘りポチばかり可愛がって勉強をしなかったから、父が萬ーしたら懲しめのため、ポチを何處かへ匿したのぢゃないかと
思ふ。さうすると、今の啼聲は矢張ポチだったかも知れぬと、うろうろとする目の前を、土耳其帽を冠った十德姿の何處か
のお祖父さんが通る。何だか深切さうな好いお祖父さんらしいので、此人に聞いたら、偶然とポチの居處を知っていて、敎へ
て呉れるかも知れぬと思つて、凝然と其面を視ると、先も振向いて私の面を視て、莞爾して行って了った。
向ふから順禮の親子が來る。笈摺も古ぼけて、旅窶れのした風で、白の脚絆も埃に塗れて狐色になってゐる。母の話で聞
くと、順禮といふ者は行方知れずになった親兄弟や何かを尋ねて、國々を經巡って歩くものだと云ふ。此人達も其様な事で斯
うして歩いてゐるのかも知れぬ、と思ふと、私も何だか此仲間へ入って一緒にポチを探して歩きたいやうな氣がして、立止っ
て其の後姿を見送ってゐると、忽ち背後でガラガラと雷の落懸るやうな音がしたから、驚いて振向かうとする途端に、トンと
突飛ばされて、私はコロコロと轉がった。
「危ねい!往來の眞ン中を彷徨してやがって:::」
と、せいせい息を逸ませながら立止って怒鳴り付けたのは、目の怕い車夫であった。
車には黑い高い帽子を冠って、温かさうな黄ろい襟の附いた外套を被た立派な人が乘ってゐたが、私が面を颦めて起上る
のを尻目に掛けて、鬚の中でニヤリと笑って
「鎌藏、構はずに行れ。」
「へい……本當に冷りとさせやがった。氣を付けろ、涕垂らしめ・
と、車夫は又トットッと曳出した。
紳士は犬殺しではない。が' ポチを殺した犬殺しと此人と何だか同じゃうに思はれて、クラクラと目が眩むと、私はもう無
茶苦茶になった。卒然道端の小石を拾って打着けてやらうとしたら、車は先の横町へ曲ったと見えて、もう見えなかった。
バタリと小石を手から落した。と、何だか急に悲しくなって來て耐らなくなって、往來の眞中で私は到頭シクシク泣出した。
二十
ポチの殺された當座は、私は食が細って痩せた程だった。が、其程の悲しみも子供の育つ勢には敵はない。間もなく私
は又毎日學校へ通って、友達を相手にキャツキヤツとふざけて元氣よく遊ぶやうになった
今日は如何したのか頭が重くて薩張り書けん。徒書でもしゃう。
愛は總ての存在を一にす。
愛は味ふべくして知るべからず。
愛は住すれば人生に意義あり、愛を離るれば、人生は無意義なり。
人生の外に出て' 人生を望み見て、人生を思議する時、人生は遂に不可得なり。
人生に目的ありと見、なしと見る、共に理智の作用のみ。理智の眼を抉出して目的を見ざる處に、至味存す。
理想は幻影のみ。
凡人は存在の中に住す、其一生は觀念なり。詩人哲學者は存在の外に遊離す、觀念は其一生なり。
凡人は聖人の縮圖なり。
人生の眞味は思想に上らず、思想を超脱せる者は幸なり。
二十世紀の文明は思想を超脱せんとする人間の努力たるべし。
此様な事ならまだ幾らでも列べられるだらうが、列べたって詰らない。皆腔だ。Йでない事を一つ書いて置かう、
私はポチが殺された當座は、人間の顔が皆犬殺しに見えた。是丈は本當の事だ。
二十一
小學から中學を終るまで、落第をも込めて前後十何年の間、毎日々々の學校通ひ、——考へてみれば面白くもない話だが、
併し其を左程にも思はなかった。小學校の中は、内で親に小蒼ffiく世話を燒かれるよりも、學校へ行って友達を騒ぐ方が面白
い位に思ってゐたし、中學へ移ってからも、人間は斯うしたものと合點して、何とも思はなかった。
しかし、凡そ學科に面白いといふものは一つも無かった。何の學科も何の學科も、皆卒氣もない®蹙する物ばかりだった
が、就中私の最も閉口したのは數學であった。小學校から然うだったが、中學へ移ってからも是ばかりは變らなかった。此
次は代數の時間とか、幾何の時間とかなると、もう其が胸に支へて、溜息が出て、何となく世の中が悲觀された。
算術は四則だけは如何やら斯うやら了解めたが、整數分數となると大分怪しくなって、正比例で一寸息を吐く。が、其お隣
の反比例から又亡羊し出して、按分比例で途方に暮れ、開平開立求積となると、何が何だか無茶苦茶になって、詰り算術の長
の道中を浮の空で通して了ったが、代數も矢張り其通り。一次方程式、二次方程式、簡単なのは如何にかなっても、少し複雑
のになると、АとЕとが紛糾かつて、何時迄經ってもXに膠着いていて離れない。況や不整方程式には、頭も亂次になり、無
理方程式を無理に強付けられては、げんなりして、便所へ立ってホッと一息吐く。代數も分らなかったが幾何や三角術は尚分
らなかった。初の中は全く相合せ得る物の大さは相等しなどと眞顔で敎へられて、馬鹿扱ひにするのかと不平だったが、其
中に切賣の西瓜のやうな弓月形や、ニ枚屏風を開いたやうなー一面角が出て來て、大きなお供に小さいお供が附着いてヤッサ
モッサを始める段になると' もう氣が逆上ッて了ひ、丸呑にさせられたギコチない定義や定理が、頭の中でしゃちこばって、
其心持の惡いこと一通りでない。試驗が濟むと、早速咽喉へ指を突込んで留飮の黄水と一緒に吐出せるものなら、吐出して了
って淸々したくなる。
何の因果で此様な可厭な想をさせられる事か、其は薩張分らないが、唯此可厭な想を忍ばなければ、學年試驗に及第させ
て貰へない。學年試驗に及第が出來ぬと、最終の目的物の卒業證書が貰へないから、それで誠に止むことを得ず、眼を閉って
毒を飮む氣で辛抱した。
尤も是は數學ばかりではない。何の學科も皆多少とも此氣味がある。味はって樂むなどといふのは一つもない、又樂むで
ゐる暇もない。後から後からと他の學科が急立てるから、狼狽てゝ片端から及第のお呪ひの御符の積で鵜呑にして' 而して
試驗が濟むと、直ぐ吐出してケロリと忘れて了ふ。
徳富蘆花
『みゝずのたはこと』より「麥の穗稲穗」
村の一年
都近い此邊の村では、陽暦陰暦を折衷して一月晩れで年中行事をやる。陽暦正月は村役塲の正月、小學校の正月である。い
さゝか神樂の心得ある若者連が、松の内の賑合を見物かたがた東京に獅子舞に出かけたり、甲州街道を紅白美々しく飾り立て
た初荷の荷馬車が新宿さして軋らしたり、黑の帽子に紫の袈裟、白足袋に高下駄の街道筋の坊さんが、年玉を入れた萌黄の
大風呂敷包みを頸からつるして兩手で抱へた草鞋ばきの寺男を連れて檀家の廻禮をしたりする以外は、村は餅搗くでもなく'
門松一本立つるでなく、至極平氣な一月である。唯農閑なので、靑年の夜學がはじまる。井浚へ、木小屋の作事、屋根の葺き
更へ、農具の修繕なども、此隙にする。日なたぼこりで孫いぢりにも飽いた爺の仕事は、啣へ煙管の背手で、ヒョイヒョイ
と野らの麥踏。若い者の仕事は東京行の下肥取りだ。寒中の下肥には、蛆が涌かぬ。堆肥製造には持て來いの季節、所謂寒練
である。夜永の夜延べには、親子兄弟大きな爐側で、コトコト藁を攜っては、俺ア幾括だ卿は何足かと競爭しての繩絢
ひ草履草鞋作り。かみさんや娘は、油煙立つランプの傍でぼろつぎ、兵隊に出て居る自家の兼公の噂も出やう。東京歸りに兄
が見て來た都の嫁入車の話もあらう。
都では晴の春着も夙に箪笥の中に入って、歌留多會の手疵も痕になり、お座敷つヾきのあとに大妓小妓のぐったりとして
欠伸を嚙む一月末が、村の師走の煤掃き、つヾいて餅搗きだ。寒餅はわるくならぬ。水に浸して置いて、年中の茶受、忙しい
時の飯代り、多い家では一石も二石も搗く。縁者親類加勢し合って、歌聲賑やかに、東でもぼったん、西でもぼったん、深夜
の眼を驚かして、夜の十二時頃から夕方までも搗く。陽暦で正月を濟ましてとくに餅は食ふてしまふた美的百姓の家へ、にこ
にこ顔の糸ちゃん春ちゃんが朝飯前に牡丹餅を持て來てくれる。辰爺さん家のは大きくて他家の3倍もあるが、搗きが細かで、
上手に紅入りの寶袋なぞ捋へてよこす。篠田の金さんの處は、餡は黑砂糖だが、手奇麗で、小奇麗な蓋物に入れてよこす。氣
取ったおかず媼さんからは、餡がお氣に召すまいからと云って、唯搗き立てをちぎったまゝで一重よこす。禮に往って見ると、
奥は正月前らしく奇麗に掃かれて、土間にはちゃんと鹽鮭のニ枚もつるしてある。
二月は村の正月だ。松立てぬ家はあるとも、着物更へて長閑に遊ばぬ人は無い。甲州街道には木戸ハ錢十錢の芝居が立つ。
浪花節が入り込む。小學校で幻燈會がある。大きな天理敎會、小さな耶蘇敎會で、東京から人を呼んで説敎會がある。府郡の
技師が來て、農事講習會がある。節分は豆撒き。七日が七草。十一日が倉開き。十四日が左義長。古風にやる家も、手輕でや
らぬ家もあるが、要するに年々昔は遠くなって行く。名物は秩父жの乾風と霜解けだ。武藏野は雪は少ない。一尺の上も積
るは稀で、五日と消えぬは珍しい。ある年四月に入ってー一尺の餘も積ったのは、李節からも量からも井伊掃部さん以來の雪だ
と村の爺さん達も驚いた。武藏野は霜の野だ。十二月から三月一ぱいは、夥しい霜解けで、草鞋か足駄長靴でなくては歩か
れぬ。霜枯れの武藏野を乾風がひうひうと吹きまくる。霜と風とで、人間の手足も、土の皮膚も、悉く鞭赤ぎれになる。乾
いた畑の土は直ぐ塵に化ける。風が吹くと、雲と舞ひ立つ。遠くから見れば正に火事の煙だ。火事もよくある。乾き切った藁葺
の家は、此上も無い火事の燃料、それにЙも風呂も藁屑をぼうぼう燃すのだからたまらぬ。火事の少ないのが寧不思議で
ある。村々字々に消防はあるが、無論間に合ふ事じゃない。夜遊び歸りの誰かヾ火を見つけて、「お、い、火事だよウ」と呼
はる。「火事だっさ、火事は何處だンベか、——火事だよウ」と傳へる。「火事だよウ」 「火事だアよウ」彼方此方で消防
の若者が聞きつけ、家に歸って火事祥纏を着て、村の眞中の火の番小屋の錠をあけて消防道具を持出し、わッしよいわッしよ
い駆けつける頃は' 大概の火事は灰になって居る。人家が獨立して周圍に立樹がある爲に、人家櫛比の街道筋を除いては、村
の火事は滅多に大火にはならぬ。然し火の粉一つ飛むだらば、必燒けるにきまって居る。東京は火事があぶねえから、好い着
物は預けとけや、と云って、東京の息子の家の目ぼしい着物を悉皆預って居て丸燒けになった家もある。
梅は中々二月には咲かぬ。尤も南をうけた崖下の暖かい隈なぞには、ドウやらすると、堇の一輪、紫に笑むで居ることも
あるが、二月には中々寒い。下旬になると。雲雀が鳴きはじめる。チ、チ、チ、ドウやら雲雀が鳴いた樣だと思ふと、翌日は
聞こえず' 又の日いと明瞭に鳴き出す。あ、雲雀が鳴いて居る。例令遠山は雪であらうとも、武藏野の霜や氷は厚からうと
も、落葉木は皆裸で松の綠は黄ばみ杉の綠は鳶色に焦げて居やうとも、秩父жは寒から二/」、雲雀が鳴いて居る、冴えかへ
る初春の空に白光する羽た、きして雲雀が鳴いて居る。春の驪喜は聞く人の心に湧いて來る。雲雀は麥の伶人である。雲雀の
歌から武藏野の春は立つのだ。
武藏野に春は來た。暖い日は、甲州の山が雪ながらほのかに霞む。庭の梅の雪とこぼるゝ邊に耳珍しくも薮鶯の初音が
響く。然しまだ冴え返へる日が多い。三月もまだ中々寒い月である。初午には、輪番に稻荷講の馳走。各自に米が五合に錢十
五錢宛持寄って、飮んだり、食ったり驢を盡すのだ'まだまだと思ふて居る内に、そろそろ畑の用が出て來る。落葉搔き寄
せて、甘Йや南瓜胡瓜の温床の仕度もせねばならぬ。馬鈴薯も植ゑねばならぬ。
彼岸前の農家の一大事は、奉公男女の出代りである。田舎も年々人出が妙なく、好い奉公人は引張り合だ。近くに東京と
云ふ大渦がある、何處へ往っても直ぐ錢になる種々の工塲があるので、男も女も愚圖々々云はれると直ぐぷいと出て往って了
ふ。寺本さんの作代は今年も勤續と云ふが、盆暮の仕着せで九十圓、彼様な好い作代なら廉いもンだ、と皆が羨む。亥太郎さ
んの末の子は今年十二で、篠田さんの子守に月五十錢で雇はれて行く。下唇の厚い久さんは、本家で仕事の暇を、大盡の伊三
郎さん處で、月十日のきめで一ー十五圓。石山さんが隣村の葬式に往って居ると、娘が駆けて來て、作代が逃げ出すと云ふので、
石山さんは遽て、葬式の塲から尻引っからげて作代引とめに走って行く。勘さんの嗣子の作さんは草鞋ばきで女中を探してあ
るいて居る。些好さゝうな養蠶傭の女なぞは、去年の内に相談がきまってしまふ。メレンスの半襟一かけ、足袋の一足、窃と
他の女中の袂にしのばせて、來年の餌にする家もある。其等の出代りも濟むで、われ一安心と息をつけば、最早彼岸だ。
線香、花、水桶なぞ持った墓參が續々とやって來る。丸髻や紋付は東京から墓参に來たのだ。寂しい墓塲にも人聲がする。
線香の煙が上る。沈丁花や赤椿が、竹筒に挿される。新しい卒塔婆が立つ。緋の袈裟を被た坊さんが畑の向ふを通る。中日は
村の路普請。遊び半分若者總出で、道側にさし出た木の枝を伐り拂ったり、些ばかりの芝土を道の眞中に抛り出したり、路
壊しか路普請か分からぬ。
四
四月になる。愈春だ。村の三月、三日には雛を飾る家もある。菱餅草餅は、何家でも出来る。小學校の新學年。つい去年
まで碌に□も利けなかった近所の喜左坊が、兵隊帽子に新しいカバンをつるし、今日から小學一年生だと小さな大手を振って
行く。五六年前には、式日以外女生の袴など滅多に見たこともなかったが、此頃では日々の登校にも海老茶が大分殖えた。
小學校に女教員が來て以来の現象である。桃之夭々、其葉秦々、桃の節句は昔から婚嫁の季節だ。村の嫁入婿取は多く此頃に
行はれる。三日三晩村中呼んでの飮明しだの、「目出度、目出度の若松樣よ」の歌で十七荷の嫁入荷物を練込むなぞは、大々
盡の家の事。大抵は萬事手輕の田舎風、花嫁自身髪結の家から島田で歸って着物を更へ、車は贅澤、甲州街道まで歩いてガタ
馬車で嫁入るなぞはまだ好い方だ。足入れと云ってこっそり嫁を呼び、都合の好い時あらためて腰入をする家もある。はずむ
だところで調布あたりから料理を呼んでの饗宴は、唯親類縁者まで、村方一同へは、婿は紋付で組内若くは親類の男に連れら
れ' 軒別に手拭の一筋半紙の一帖も持って挨拶に廻るか、嫁は真白に塗って、搔巻程の紋付の裾を赤い太い手で持って、後見
の婆さんかかみさんに連れられ、お辭儀をして廻れば、所謂顔見せの義理は濟む。村は一月晩れでも、寺は案外陽曆で行くの
があって、四月ハ日はお釋迦樣の誕生會。寺々の鐘が子供を呼ぶと、爺か孃か姉に連れられた子供が、小さな竹筒を提げて、
嬉々として片集を汲みに行く。
東京は櫻の盛、車も通れぬ程の人出だった、と麹町まで下肥ひきに往った音吉の話。村には櫻は少いが、それでも桃が咲
く、李が咲く。野はすみれ、たんぽゝ、春龍膽、草木瓜、薊が咲き亂るゝ。「木瓜薊、旅して見たく野はなりぬ」忆しくな
る前に' 此花の季節を、御嶽詣、三峰かけて榛名詣汽車と草鞋で遊んで來る講中の者も少くない。子供連れて花見、潮干に
出かける村のハイカラも稀にはある。浮かれて蝶が舞ひはじめる。意地惡の蛇も穴を出る。空では雲雀がますます勢よく鳴
きつれる。其れに喚び出される樣に、麥がついついと伸びて穗に出る。子供がぴい——っと吹く麥笛に、武藏野の日は永く
なる。三寸になった玉川の鮎が、密漁者の手から窃と旦那の勝手に運ばれる。仁左衛門さん宅の大權が春の空を摩でて淡褐
色に煙りそめる。雜木林の«が逸早く、櫟はやゝ晩れて、芽を吐きそめる。貯藏の里芋も芽を吐くので、里芋を植ゑねばな
らぬ。月の終は、若葉の盛季だ。若々とした武藏野に復活の生氣が盈ち溢れる。色々の虫が生れる。田甫に蛙が泥聲をあげ
る。水がぬるむ。そろそろ種籾を浸さねばならぬ。桑の葉がほぐれる。彼方も此方も養蠶前の大掃除、蠶具を乾したり、ばた
ばた筵をはたいたり。月末には早い處では掃き立てる。蠶室を有つ家は少いが、何様な家でも少くもーーー枚飼はぬ家はない。
筍 の出さかりで、孟宗薮を有つ家は、朝々早起きが樂だ。肥料もかゝるが、一反八十圓から百圓にもなるので、雜木山は
追々孟宗薮に化けて行く。
五
五月だ。來月の忙さを見越して、村でも此月ばかりは陽曆で行く。大麥も小麥も見渡す限り穗になって、綠の畑は夜の白々
と明ける樣に、總々とした白い穂波を漂はす。其が朝露を帶びる時、夕日に榮えて白金色に光る時、人は雲雀と歌聲を競ひ
たくなるのである。五日は«餅の節句だ。目もさむる若葉の綠から、黑い赤い紙の鯉がぬうと出てほらほら跳って居る。五
月五日は府中大國魂神社所謂六所様の御祭禮。新しい紺の腹掛、紺股引、下ろし立てのはだし足袋、切り立ての手拭を顋の下
でチョツキリ結びの若い衆が、爺をせびった小使の三圓五圓腹掛に捻込んで、四尺もある手製の杉の撥を擔いで、勇んで府
中に出かける。六所樣には徑六尺の上もある大太鼓が一個、中太鼓が幾個かある。若い逞しい兩腕が、撥と名づくる棍棒で力
任せに打つ音は、四里を隔てゝ鑿々と遠雷の如く響くのである。府中の祭りと云へば、昔から阪東男の元氣任せに微塵になる
程御神輿の衝撞あひ、太鼓の撥のた、き合、十二時の合圖に燈明と云ふ燈明を消して、眞闇の中に人死が出來たり處女が女に
なったり、亂暴の限を盡したものだが、警察の世話が届いて、此頃では滅多な事はなくなった。
落葉木は若葉から漸次靑葉になり、杉松樫などの常綠木が古葉を落し落して最後の衣更をする。田は紫雲英の花ざかり。林
iんらんМんらん 打〇び や L
には金蘭銀蘭の花が咲く。ぜんまいや、稀に蕨も立つが、滅多に見かへる者も無い。ハ十八夜だ。其れ茶も摘まねばならぬ。
茶は大抵葉のまゝで賣るのだ。隱元、玉蜀黍、大豆も蒔かねばならぬ。降って來さうだ、桑は伐ったか。桑つきが惡いはお蠶
樣が如何ぞしたのじゃあるまいか。養蠶敎師はまだ廻って來ないか。種籾は如何した。田の荒おこしもせねばならぬ。苗代搔
きもせねばならぬ。最早早生の陸稻も蒔かねばならぬ。何かと云ふ内、胡瓜、南瓜、甘Йや茄子も植ゑねばならぬ。稗や黍の
秋作も蒔かねばならぬ。月の中旬には最早大麥が色づきはじめる。三寸の綠から鳴きはじめた麥の伶人の雲雀は、麥が熟れる
ぞ、起きろ、急げと朝未明から哺づる。折も折とて徴兵の檢査。五分莉頭で紋付羽織でも引かけた體は逞しい顔は子供々々し
た若者が、此村からも彼村からも府中に集まる。川端の嘉ちゃんは甲種合格だつてね。俺が家の忠はまだ抽籤は濟まねえが、
海軍に採られべって事だ、俺も稼げる男の子はなし、忠をとられりゃ作代でも雇ふべい、國家の爲だ、仕方が無えな、と輿右
衛門さんが舌鼓うつ。篠田の銀さん宅では、去年は兄貴が抽籤で免れたが、今年は稻公が彼體格で、砲兵にとられることにな
った。當人は勇んで居るが、阿母が今から萎れて居る。
頓着なく日は立って行く。わかれ霜を気遣ふたは昨日の樣でも、最早春蝉が鳴き出して、靑葉の風がそヾろ戀しい日もある。
詩人が歌ふ綠蔭幽草白花を點ずるの時節となって、畑の境には雪の樣に卯の花が咲きこぼれる。林端には白いエゴの花がこぼ
れる。田川の畔には花茨が芳しく咲き亂れる。然し見かへる者はない。大切の大切のお蠶樣が大きくなって居るのだ。然し
月の中に一度雹祭だけは屹度鎮守の宮でする。甲武の山近い三多摩の地は、甲府の盆地から發生する低氣壓が東京灣へぬけ
る通路に當って居るので、雹や雷雨は名物である。秋の風もだが、春暮初夏の雹が殊に恐ろしいものになって居る。雹の通る
路筋はほヾきまつて居る。大抵上流地から多摩川に沿ふて下り、此邊の村を掠めて、東南に過ぎて行く。既に五年前も成人の
举大の恐ろしい雹を降らした。一昨年も唯十分か十五分の間に地が白くなる程降って、塲所によっては大麥小麥は種も殘さ
ず、桑、茶、其外靑物一切全滅した處もある。可なりの生活をして居ながら、錢になると云へば、井浚へでも屋根葺の手傳で
も何でもする隣字の九右衛門爺さんは、此雹に畑を見舞はれ、失望し切って蒲團をかぶって寢てしまふた。ゾラの小説「土」
に、ある慾深の若い百姓が雹に降られて天に向って拳をふり上げ、「何ちう事をしくさるか」と怒鳴ることろがあるが、無
理はない。此邊では「雹亂」と云って、雹は戰争よりも恐れられる。そこで雹祭をする。榛名様に願をかける。然し榛名樣
も、鎮守のハ幡も、如何ともしかね玉ふ塲合がある。出水の患が無い此村も、雹の賜物は折々受けねばならぬ。村の天に納
める租税である。
六
六月になった。麥秋である。「富士 一つ埋み殘して靑葉かな」其靑葉の靑閤い間々を、熟れた麥が一面日の出の樣に明るく
する。陽暦六月は「農功五月急於弦」と云ふ農家の五月だ。農家の戰争で最劇戰は六月である。六月初旬は、小學校も臨時
農繁休をする。猫の手でも使ひたい時だ。子供一人、ドウして中々馬鹿にはならぬ。初旬には最早蠶が上るのだ。中旬には大
麥、下旬には小麥を莉るのだ。
最早梅雨に入って、じめじめした日がつヾく。寰笠で田も植ゑねばならぬ。畑勝ちの村では、田植は一仕事、「植田をしま
ふとさばさばするね」と皆が云ふ。雨間を見ては、莉り殘りの麥も莉らねばならぬ。莉りおくれると、畑の麥が立ったまゝに
粒から芽をふく、油斷を見すまして作物其方退けに增長して來た草もとらねばならぬ。甘Йの蔓もかへさねばならぬ。陸稻や
黍、稗、大豆の中耕もしなければならぬ。ーー番茶も摘まねばならぬ。お屋敷に叱られるので、東京の下肥ひきにも行かねばな
らぬ。時も時とて飯料の麥をきらしたので、水車に持て行って一晩寢ずの番をして搗いて來ねばならぬ。最早甲州の繭買が甲
州街道に入り込むだ。今年は値が好くて、川端さんの岩さん家では、四圓十五錢に賣ったと云ふ噂が立つ。隣村の濱田さん
も繭買をはじめた。工女の四五人入れて足踏器械で製糸をやる仙ちゃん、長さんも、即座師の鑑札を受けて繭買をはじめた。
自家のお春つ子お兼つ子に一貫目何錢の搔き賃をくれて、大急ぎで搔いた繭を車に積んで、重い車を引張って此處其處相場を
聞き合はせ、一錢でも高い買手をやっと見つけて、一切合切屑繭まで賣ってのけて、手取が四十九圓と二十五錢。夜の目も寢
ずに五十兩足らずかと思ふても、矢張まとまった金だ。持て歸って、古箪笥の奥にしまって、茶ーぱい飮むと直ぐ畑に出なけ
ればならぬ。
空ではまだ雲雀が根氣よく鳴いて居る。村の木立の中では、何時の間にか栗の花が咲いて居る。田甫の小川では、葭切が□
やかましく終日騒いで居る。杜鵠が啼いて行く夜もある。梟が鳴く日もある。水鶏がコトコトたゝく宵もある。蛍が出る。
蝉が鳴く。蛙が鳴く。蚊が出る。ブヨが出る。Йが眞黑にたかる。蚤が跋扈する。カナブン、瓜蝇、テントウ虫、野菜にっ
く虫は限もない。皆生命だ。皆生きねばならぬのだ。到底取りきれる事ではないが' うっちゃって置けば野菜が全滅になる'
取れるだけは取らねばならぬ、此方も生きねばならぬ人間である。手が足りぬ。手が足りぬ。自家の人數ではやりきれぬ。果
ては甲州街道から地所にはなれた百姓を雇ふて、一反何程の請負で、田も植ゑさす、麥も莉らす。それでもまだやり切れぬ。
墓地の骸骨でも引張り出して來て使ひたい此頃には、死人か大病人の外は手をあけて居る者は無い。盲目の婆さんでも、手さ
ぐりで茶位は沸かす。豌豆や隠元は畑に珠數生りでも、もいで煮て食ふ暇は無い。如才ない東京塲末の煮豆屋が鈴を鳴らして
來る。飯の代りに黍の餅で濟ます日もある。近い所は、起きぬけに朝飯前の朝作り、遠い畑へはお春つ子が片手に大きな藥罐、
片手に茶受の里芋か餅かを入れた風呂敷包みを重さうに提げ、小さな體を歪めてお八つを持て行く。斯季節に農家を訪へば、
大抵は門をしめてある。猫一疋居ぬ家もある。何を問ふても、くるくるとした眼を瞠って、「知ンね工や」と答ふる五六歳の
女の子が赤ン坊と唯二人留守して居る家もある。斯様な時によく子供の大怪我がある。家の内は麥の芒だらけ、墓地は草だら
けで、お寺や敎會では坊さん敎師が大欠伸して居る。後生なんか願ふて居る暇が無いのだ。
七
忙しい中に、月は遠慮なく七月に入る。六月は忙しかったが、七月も忙しい。
忙しい、忙しい。何度云ふても忙しい。日は永くても' 仕事は終へない。夜は短くてもおちおち眠ることが出來ぬ。何處の
娘も赤い眼をして居る。何處のかみさんも、半病人の蒼い顔をして居る。短氣の石山さんが、純な久さんを慳貪に叱りつける。
「車の心棒は鐵だが、鐵だアて使や耗るからナ、俺ア段々稼げなくなるのも無理はねえや」と、小男ながら小氣味よく稼ぐ辰
爺さんがこぼす。「違ねえ、俺ア辰さんよか年の十も下だンベが、何糞ツ若け者に負けるもンかつてやり出しても、第一卑
がつヾかんからナ」と岩疊づくりの輿右衛門さんが相槌をうつ。然し耗っても銹びても、心棒は心棒だ。心棒が廻はらぬと家
が廻はらぬ。折角莉り入れた麥も早く扱いて撲って俵にしなければ蝶々になる。今日も雨かと思ふたりや、さあお天道様が出
なさったぞ'皆來うと呼ばって、胡麻監頭に向鉢巻、手垢に光るくるり棒押取って禾塲に出る。それっと子供が飛び出す。兄
が出る。弟が出る。嫁が出る。娘が出る。腰痛でなければ婆さんも出る。奇麗に掃いた禾塲に一面の穗麥を敷いて、男は男、
女は女と相並むでの差向ひ、片足踏出し、氣合を入れて、一上一下とかはるがはる打下ろす。男は股引に腹かけ一つ、黑鉢
巻の經木眞田の帽子を阿彌陀にかぶって、赤銅色の逞しい腕に撚をかけ、菅笠若くは手拭で姉樣冠りの若い女は赤榛手甲かけ、
腕で額の汗を拭き拭き、くるり棒の調子を合はして、ドウ、ドウ、バッタ、バタ、時々群の一人が「ヨウ」と勇みを入れて、
大地も挫げと打下ろす。「お前さんとならばヨウ、何處までもウ、親を離れて彼世までもウ」若い女の好い聲が歌ふ。ーコラ
コラ」皆が囉す。禾塲の日はかんかん照って居る。くるり棒がぴかりと光る。若い男女の顔は、熟した牡丹杏の樣に光って居
る。空には白光りする岩雲が 堆く涌いて居る。
七月中旬、梅雨があけると、眞劎に暑くなる。明るい麥が取り去られて、田も畑も綠に返へる。然し其は春暮の嫩ら力な綠
では無い、日中は綠の焰を吐く綠である。朝夕は 蜩 の聲で涼しいが、畫間は油蝉の音の煎りつく樣に暑い。涼しい茅屋で
も、九十度に上る日がある。家の内では大抵誰も裸體である。畑でもスボラの武太さんは 禅一つで陸稻のサクを切って居る。
十五六日は、東京のお盆で、此處其處に薮入姿の小さな白足袋があるく。甲州街道の馬車は、此等の小僧さんで満員である。
八
暴風にも靜な中心がある。忙しい農家の夏の戰闘にも休戰の期がある。
七月末からハ月初か、麥も仕舞ひ、草も一先づ取りしまふた程よい頃を見はからって、月番から總郷上り正月のふれを出
す。總郷業を休み足を洗ふて上るの意である。其期は三日、中日は村總出の草莉り路普請の日とする。右左から恣 に公道
を侵した雜草や雜木の枝を、一同磨ぎ耗らした鎌で遠慮會釋もなく切拂ふ。人よく道を弘むを、文義通りやるのである。慾張
と名のある不人望な人の畑や林は、此時こそと思ひ切り切りまくる。昔は兎に角、此頃では世の中せち辛くなって、物日にも
稼ぐことが流行する。總郷上り正月にも、畑に田にぼつぼつ働く影を見うける。
ハ月は小學校も休業だ。ハ月七日は村の七夕、五色の短冊さげた笹を立つる家もある。やかて盂蘭盆會。芋殻のかはりに麥
からで手輕に迎火を焚いて、それでも盆だけに墓地にも家内にも可なり賑合ひ、緋の袈裟をかけた坊さんや、仕着せの浴衣單衣
で薮入に行く奉公男女の影や、斷續して來る物貰ひや、盆らしい氣もちを見せて通る。然し其貧しい小さな野の村では、昔か
ら盆踊と云ふものを知らぬ。一年中で一番好い水々しい大きな月が上っても、其れは斷片的に若者の歌を嗾るばかりである。
まるまるとした月を象どる環を作って、大勢の若い男女が、白い地を踐み、黑い影を落して、歌ひつ踊りつ夜を探して、傾
く月に一人減り二人寢に行き、到頭「四五人に月落ちか\る踊かな」の 趣は、此邊の村では見ることが出來ぬ。
夏蠶を飼ふ家は少いが、秋蠶を飼ふ家は澤山ある。秋蠶を飼へば、ハ月はまだ忙しい月だ。然し秋蠶のまだ忙しくならぬ隙
を狙ふて、富士詣、大山詣、江の島鎌倉見物をして來る者も少くない。大山へは、夜立ちして十三里日着きする。五圓持て夜徹
し歩るき、眠たくなれば堂宮に寢て、唯一人富士に上って來る元氣な若者もある。夏の命は日と水だ。照らねばならず、降ら
ねばならぬ。多摩川遠い此村里では、水害の患は無いかはり、旱teの恐れがある。大抵は都合よく夕立が來てくれる。雨乞
は六年間に唯一度あった。降って欲しい時に降れば、直ぐ「おしめり正月」である。傳染病が襲ふて來るも此月だ。赤痢、窒扶斯
で草葺の避病院が一ぱいになる年がある。眞白い診察衣を着た醫員が歩く。大至急清潔法施行の布令が來る。村の衞生係が草鞋
ばきの巡査さんとどぶ、掃溜を見てあるく。其巡査さんの細君が赤痢になったと云ふ評判が立つ。鐘や太鼓で念佛唱へてねり
あるき、疫病禳ひする村もある。
其様な騒ぎも何時しか下火になって、暑い暑いと云ふ下から、ある日秋蝉がせはしなく鳴きそめる。武藏野の秋が立つ。
早稻が穗を出す。尾花が出て覗く。甘藉を手堀りすると、早生は赤兒の腕程になって居る。大根、漬菜を蒔かねばならぬ。
蕎麦、秋馬鈴薯もそろそろ蒔かねばならぬ。暫く綠一色であった田は、白っぽい早稻の穗の色になり、畑では稗が黑く、黍
が黄に、栗が褐色に熟れて來る。栗や黍は餅にしてもまだ食へる、稗は乃木さんでなければ中々食へぬ。此邊では、米を非
常、挽割麥を常食にして、よくよく家でなければ純稗の飯は食はぬ。下肥ひきの辨當に稗の飯でも持て行けば、冷たい稗はザ
ラザラして咽を通らぬ。湯でも水でもぶっかけてざぶざぶ流し込むのである。若い者の 樂の一は、食ふ事である。主人は麥
を食って、自分に稗を食はした' と忿って飛び出した作代もある。
九
9月は農家の厄月。二百十日、二百二十日を目の前に控へて、朔日には風祭をする。麥桑に雹を氣づかった農家は、稻に
風を氣づかはねばならぬ。九月は農家の鳴戸の瀬戸だ。瀬戸を過ぐれば秋の彼岸、蚊帳を仕舞ふ。おかみや娘の夜延仕事が忙
しくなる。秋の田園詩人の百舌鳥が、高い栗の梢から聲高々と鳴きちぎる。栗が笑む。豆の葉が黄ばむ。腳弑綽が染むを相圖
に、夜は空高く雁の音がする。林の中、道草の中、家の中まで入り込んで、虫と云ふ虫が鳴き立てる。勒秽が歆ろくなりそめ
る。蕎麦の花は雪の樣だ。彼岸花と云ふ曼珠沙華は、此邊に少い。此あたりの彼岸花は、荻、女郎花、嫁菜の花、何よりも初秋
に榮を見せるのが、紅く白く»々と絹總を靡かす樣な花薄である。子供が其れを剪って來て、十五夜の名月樣に上げる。萱
は葺料にして長もちするので、小麥がらの一束五厘に對し、萱は一錢も其上もする。そこで萱野を仕立て、置く家もある。然
し東京がますます西へ寄って來るので、萱野も雜木山も年々減って行くばかりである。
九月は農家の祭月、大事な交際季節である。風の心配も兎やら恁うやら通り越して、先収穫の見込がつくと、何處の村でも
祭をやる。木戸錢御無用、先客萬来の芝居、お神樂、其れが出來なければ詮方無しのお神酒祭。今日は粕谷か、明日は廻澤、
烏山は何日で、給田が何日、船橋では、上下祖師ヶ谷では、ハ幡山では、隣村の北澤では、と皆が指折數へて浮き立つ。彼
方の村には太鼓が鳴る。此方の字では舞臺がけ。一村ハ字寄合ふて大きくやればよさゝうなものゝ、八つの字にはハつの意志
と感情と歴史があって、二百戸以上の烏山はもとより、二十七戸の粕谷でも十九軒の八幡山でも、各自に自家の祭をせねば氣
が濟まぬ。祭となれば、何様な家でも、強飯を蒸す、煮染をこさへる、噩純をうつ、甘酒を作って、他村の親類縁者を招く。
東京に縁づいた娘も、子を抱き亭主や縁者を連れて來る。今日は此方のお神樂で、平生は眞白な鳥の糞だらけの鎮守の宮も眞
黑になる程人が寄って、安小間物屋、駄菓子屋、鰭屋、おでん屋、水菓子屋などの店が立つ。神樂は村の能狂言、神官が家
元で、村の器用な若者等が神樂師をする。無口で大兵の鐵さんが氣輕に太鼓をうったり、氣輕の龜さんが髪鬚蓬々とした面
をかぶって眞面目に舞臺に立ちはだかる。「あ、彼りゃ龜さんだと、まア」と可笑しざかりのお島がくつくつ笑ふ。今日自家
の祭に酒に醉ふた仁左衛門さんが、明日は隣字の芝居で、透綾の羽織でも引被け、寸志の紙包を懐中して、芝居へ出かける。
毎日近所で顔を合して居ながら、畑の畔の立話にも、「今日は」 「今日は」と仰天氣の挨拶からゆるゆるとはじめる田舎
氣質で、仁左衛門さんと隣字の幹部の忠五郎さんとの間には、芝居の科白の受取渡しよろしくと云ふ挨拶が鄭重に交換され
る。輪番に主になったり、客になったり、呼びつ喚ばれつ、祭は村の親睦會だ。三多摩は昔から人の氣の荒い處で、政黨騒
ぎではよく血の雨を降らし、氣の立った日露戰争時代は、農家の子弟が面寵手かついで調布まで一里半撃劍の朝稽古に通った
り柔道を習ったりしたものだが、六年前に一度粕谷ハ幡山對烏山の間に大喧嘩があって、仕込杖が光ったり怪我人が出來たり
長い間揉めくった以來、此と云ふ喧嘩の沙汰も聞かぬ。泰平有象村々酒、祭が繁昌すれば、田舎は長閑である。
十
十月だ。稻の秋。地に再び黄金の穗波が明るく照り渡る。早稻から米になって行く。性急に百舌鳥が鳴く。日が短くなる。
赤蜻蛉が夕日の空に數限りもなく亂れる。柿が好い色に照って來る。ある寒い朝、不圖見ると富士の北の一角に白いものが見
える。雨でも降ったあとの冷たい朝には、水霜がある。
十月は雨の月だ。雨がつヾいたあとでは、雜木林に茸が立つ。野ら仕事をせぬ腰の曲った爺さんや、赤兒を負ったお春つ子
が、笊をか、へて採りに來る。«茸、濕地茸、稀に紅茸、初茸は滅多になく、多いのが油坊主と云ふ茸だ。一雨一雨に氣は冷
えて行く。田も林も日に日に色づいて行く。甘Йが掘られて續々都に運ばれる。田舎は金が乏しい。村會議員の石山さんも、
一錢違ふと謂ふて甲州街道の馬車にも烏山から乘らずに山谷から乘る。だから、村の者が甘蒔を出すにも、一貫目につき五厘
も値がよければ、二里の幡ケ谷に下ろすより四里の神田へ持って行く。
茶の花が咲く。雜木林のйに絡むだ自然薯の蔓の葉が黄になり、薮からさし出る白膠木が眼ざむる樣な紅 になって、お納戸
色の小さなコップを幾箇も列ねて龍膽が咲く。樫の木の下は、ドングリが箒で掃く程だ。最早豌豆や蠶豆も蒔かねばならぬ。
蕎麦も霜前に莉らねばならぬ。まだ其れよりも農家の一大事、月の下旬から來月初旬にかけて、最早麥蒔きがはじまる。後押
しの二人もついて、山の如く堆肥を積んだ車が頻に通る。先づ小麥を蒔いて、後に大麥を蒔くのである。奇麗に平した畑は、
一條一條丁寧に尺竹をあて、繩すりして、眞直ぐに西から東へ畝を立て、堆肥を置いて土をかけ。七藏が種を振れば、赤兒を
負った若いかみさんが竹杖ついて、片足かはりに南から北へと足で土をかけて、奇麗に踏んづけて行く。燻炭肥料の、條播の
と、農會の勸誘で'ーー一年やっては見ても、矢張仕來りの勝手がよい方でやって行くのが多い。
十一
霜らしい霜は、例年明治天皇の天長節、十一月三日頃に來る。手を浄める前夜雨戸をあくれば、緘先を吹つかくる樣な水氣
が面を撲って、遽てゝもぐり込む蒲團の中でも足の先が縮こまる程いやに冷たい、と思ふと明くる朝は武藏野一面の霜だ。草
屋根と云はず、禾塲と云はず、檐下から轉び出た木臼の上と云はず、出し忘れた物干竿の上のつぎ股引と云はず、田も畑も路
も鳥の羽の上までも、眞白だ。日が出ると、晶々とした白金末になり、紫水晶末 になるのである。山嵐をあらしと云へば、
霜の威力を何に譬へやう。地の上の白火事とでも云はう。大抵のものは爛れてしまふ。桑と云ふ桑の葉は、ぐったりとなって、
二日もすれば、齒がぬける樣にひとりでにぽろりと落ちる。生々として居た甘諸の蔓は、唯一夜に正しく湯煎られた樣に凋れ
て、明くる日は最早眞黑になり、觸ればぼろぼろの粉になる。シャンとして居た里芋の莖も、ぐっちゃりと腐った樣になる。
畑が斯うだから、園の内も靑い物は全滅、色ある物は一夜に爛れて了ふのである。霜にめげぬは、靑々とした大根の葉と、霜
で甘くなる漬菜の類と、それから綠の縞を土に織り出して最早ぼつぼつ生えて來た大麦小麥ばかりである。
霜は霽に伴ふ。霜の十一月は、日本晴の明るい明るい月である。富士は眞白になる。武藏野の空は高く、た、けばカンカン
しさうな碧琉璃になる。朝日夕日が美しい。月や星が冴える。田は黄色から白茶になって行く。此處其處の雜木林や、村々の
落葉木が、最後の榮を示して黄に褐に紅に照り渡る。綠の葉の中に、柚子が金の珠を掛ける。光明は空から降り、地から
も涌いて来る。小學校の運動會で、父兄が招かれる。村の恵比壽講で、白米五合錢十五錢の持寄りで、夜徹の食ったり飮んだ
り話したりがある。日もいよいよ短くなる。甘Йや里芋を掘って、土窖に藏はねばならぬ。中稻も莉らねばならぬ。其内に晩稻
も莉らねばならぬ。でも、夏の戰闘に比べては、何を云っても最早しめたものである。朝霜、夜嵐、晝は長閑な小春日和がつヾ
く。「小春曰や田舎に廻る肴賣」。「しこは?しこ?」「秋刀魚や、秋刀魚!」のふれ聲が村から村を廻ってあるく。牛豚
肉は滅多に食はず、川魚は少し、稀に鼬に吸はれた鶏でも食へば骨までた、いて食ひ、土の物の外は大抵鹽鮭、めざし、棒
憎にのみ海の恩恵を知る農家も、斯様な時には炙れば焰立つ脂ぎった生魚を買って舌鼓うつのである。
月の末方には、除隊の兵士が歸って來る。近衞か第一師團か、せめて横須賀位ならまだしも、運惡く北海道三界旭川へでも
やられた者は、二年ぶり三年ぶりで歸って來るのだ。親類縁者は遠出の出迎、村では村内少年音樂隊を先に立て、迎何々君
之歸還の旗立てゝ、村界まで迎ひに出かける。二年三年の兵營生活で大分世慣れ人ずれて來た丑之助君が、羽織袴、靴、中
折帽、派手をする向きは新調のカーキ!服にギュウギュウ云ふ磨き立ての長靴、腰の淋しいのを氣にしながら、胸に眞新しい
在郷軍人徽章をつるして、澄まし返って歩いて來る。面々各自の挨拶がある。鎮守の宮にねり込んで、取りあへず神酒一献、
古顔の在郷軍人若くは若者頭の音頭で、大日本帝國、天皇陛下、大日本帝國陸海軍、何々丑之助君の萬歳がある。丑之助君が
何々有志諸君の萬歳を呼ぶ。其れから丑之助君を宅に送って、いよいよ飮食だ。赤の飯、刻錫蔑W里芋蓮根の煎染、豆腐に
芋の汁、はずむだ家では菰冠りを一樽とって、主も客も芽出度と云っては飮み、萬歳と云っては食ひ、満腹満足、眞赤にな
って祝ふのだ。二三日すると歸り新參の丑之助君が、歸った時の服装で神妙に禮廻りする。軒別に手拭か半紙、入營に餞別で
も貰った家へは、隊名姓名を金字で入れた盃や塗盆を持參する。兵士 一人出す家の物入も、大抵では無い。
兵隊さんの出代りで、除隊を迎へると、直ぐ入營送りだ。體格がよく、男の子が多くて、陸海軍擴張の今日と來て居るので、
何れの字からも二人三人兵士を出さぬ年は無い。白羽の箭が立った若者には、勇んで出かける者もある。抽籤を遁れた禮參り
に、わざわざ鴻の巣在の何宮さんまで出かける若者もある。二十歳前後が一番百姓仕事に實が入る時ですから、とこぼす若い
爺さんもある。然し全國皆兵の今日だ。一人息子でも、可愛息子でも、云ひ聞かされた「國家の爲」だ、出せとあったら出さ
ねばならぬ。出さぬと云ったら、お上に濟まぬ、近所に濟まぬ。そこで父の右腕、母のおもひ子の岩吉も、頭は五分莉、中折
帽、紋付羽織、袴、靴、凛とした装で、少しは怯々した然し澄ました顔をして、鎮守の宮で神酒を飮まされ、萬歳の聲と、祝入營
の旗五六本と、村樂隊と、一字總出の戸主連に村はづれまで見送られ、知らぬ生活に入る可く往ってしまふ。二三日、七八日
過ぐると、軒別に入營濟の御禮のはがきが來る。
十二
兵隊さんの出代りを村の一年の賑合にして、あとは寂しい初冬の十二月に入る。
「稼収平野濶」晚稻も卄刈られて、田甫は一望ガランとして居る。畑の桑は一株づゝ髻を結はれる。一束づ、奇麗に結はへ
おくて
た新藁は、風除けかはりにずらりと家の周圍にかけられる。ざらざらと稻を扱ぐ音。カラカラと唐箕車を廻す響。大根引、»
菜洗ひ、若い者は眞赤な手をして居る。晝は北を圍ふた南向きの小屋の薦の上、夜は爐の傍でかみさんはさっせと股引、足
袋を繕ふ。夜は晩くまで納屋に籾ずりの響がする。突然にざあと時雨が來る。はらはらと庇をうって霰が來る。ちらちらと
風花が降る。北から乐が吹いて來て、騒々しく落葉した村の木立を鳴らす。乾いた落葉が、遽てゝカラカラと舞ひ奔る。箒
を逆に立てた樣な雜木山に、長い鋸を持った樵夫が入って、啣へ煙管で猶や櫟を薪に伐る。海苔疎朶を積んだ車が村を出る。
冬至までは、日がますますつまって行く。六時にまだ小暗く、五時には最早闇い。流しもとに氷が張る。霜が日に日に深くな
るー
十五日が世田ヶ谷のボロ市。世田ヶ谷のボロ市は見ものである。松陰神社の入り口から、世田ヶ谷の上宿下宿を打通して、
約一里が間は、兩側にずらり店が並んで、農家日用の新しい品々は素より、東京中の煤掃きの塵箱を此處へ打明けた樣なあら
ゆる檻褸やガラクタをずらりと並べて、賣る者も賣る、買ふ者も買ふ、と唯驚かるゝばかりである。見世物が出る。手輕な飮
食店も出る。咽を稗が通る樣に、店の間を押し合ひへし合いひしてぞろぞろ人間が通る。近郷近在の爺さん婆さん若い者女子
供が、股引草鞋で大風呂敷を持ったり、荷車を挽いたり、目籠を背負ったりして、早い者は夜半から出かける。新しいЙ、
筍堀器、天秤棒を買って歸る者、草履の材料やっぎ切れにする檻褸を買ふ者、古靴を値切る者、古帽子、古洋燈、講談物の古
本を冷かす者、稻荷鰭を頰張る者、玉乘の見世物の前に立つ者、人さまざま物さまざまの限を盡す。世田ヶ谷のボロ市を觀
て悟らねばならぬ、世に無用のものは無い、而して悲觀は單に高慢であることを。
ボロ市過ぎて、冬至もやがてあとになり、行く行く年も暮になる。蛇は穴に入り人は家に籠って、霜枯の武藏野は、靜かな
晝にはさながら白日の夢の定に入る。寂しそうな烏が、此樫の村からを®々と鳴きながら彼棒の村へと渡る。稀には何處か
ら迷ひ込んだか洋服ゲートルの獵者が銃先に嶋や鵜のけたゝたましく鳴いて飛び立つこともあるが、また直ぐともとの寂しさ
に返へる。»の騒ぐ夜は、海の樣な響が武藏野に起って、人の心を遠く遠く誘ふて行く。但東京の屋敷に頼まれて餅を搗く
家や、小使取りに餅舂きに東京に出る若者はあっても、村其ものには何處に師走の忙しさも無い。二十五日、二十八日' 晦
日、大晦日、都の年の瀬は日一日と斷崖に近づいて行く、三里東の東京には、二百萬の人の海、噬さまざまの波も立たう。日
頃眺むる東京の煙も、此四五日は大息吐息の息巻荒くあがる樣に見える。然し此處は田舎である。都の師走は、田舎の霜月で
ある。冬枯の寂しい武藏野は、復活の春を約して、麥が今ー 一寸に伸びて居る。氣に入りの息子を月の初に兵隊にとられて、寂
しい心の辰爺さんは、冬至が過ぎれば日が疊の目一つずつ永くなる、冬のあとには春が來る、と云ふ信仰の下に、時々竹篦で
鍬の刃につく土を落しつ、、悠々と二寸になった麥のサクを切って居る。
国木田独歩
「畫の悲み」
畫を好かぬ小供は先づ少ないとして其中にも自分は小供の時、何よりも畫が好きであった。(と岡本某が語りだした)。
好きこそ物の上手とやらで、自分も他の學課の中畫では同級生の中自分に及ぶものがない。畫と數學となら、憚りながら
誰でも來いなんて' 自分も大に得意がつて居たのである。しかし得意といふことは多少競爭を意味する。自分の畫の好きな
ことは全く天性といっても可からう、自分を獨で置けば畫ばかり書いて居たものだ。
獨で畫を書いて居るといへば至極温順しく聞えるが、其癖自分ほど腕白者は同級生の中にないばかりか、校長が持て餘して
數々退校を以て嚇したのでも全校第一といふことが分る。
全校第一腕白でも數學でも。しかるに天性好きな畫では全校第一の名譽を志村といふ少年に奪はれて居た。この少年は數學
は勿論、其他の學力も全校生徒中、第二流以下であるが、畫の天才に至っては全く並ぶものがないので、僅に壘を摩さうか
とも言はれる者は自分一人、其他は 悉く志村の天才を崇め奉って居るばかりであった。ところが自分は志村を崇拝しない、
今に見ろといふ意氣込で頻りと勵げんで居た。
元來志村は自分よりか歳も兄、級もー年上であったが、自分は學力優等といふので自分の居る級と志村の居る級とを同時
にやるべく校長から特別の處置をせられるので自然志村は自分の競爭者となって居た。
然るに全校の人氣、校長敎員を始め何百の生徒の人氣は、温順しい志村に傾いて居る、 志村は色の白い柔和な、女にして見
たいやうな少年、自分は美少年ではあったが、亂暴な傲慢、喧嘩好きの少年、おまけに何時も級の一番を占めて居て、試驗の
時は必らず最優等の成蹟を得る處から教員は自分の高慢が«に觸り、生徒は自分の壓制が痛に觸り、自分にはどうしても人氣
が薄い。そこで衆人の心持は、せめて畫でなりと志村を第一として、岡本の鼻柱を挫いてやれといふ積であった。自分はよ
く此消息を解して居た。そして心中ひそかに不平でならぬのは志村の畫必ずしも能く出來て居ない時でも校長をはじめ衆人が
これを激賞し、自分の畫は確かに上出來であっても、さまで賞めて呉れ手のないことである。少年ながらも自分は人氣といふ
ものを惡んで居た。
或日學校で生徒の製作物の展覧會が開かれた。其出品は重に習字、圖畫、女子は仕立物等で、生徒の父兄姉妹は朝からぞろ
ぞろと押かける。取りどりの評判。製作物を出した生徒は氣が氣でない、皆なそはそはして展覧室を出たり入ったりして居る
自分も此展覧會に出品する積りで畫紙一枚に大きく馬の頭を書いた。馬の顔を斜に見た處で、無論少年の手には餘る畫題であ
るのを、自分は此一擧に由て是非志村に打勝うといふ意氣込だから一生懸命、學校から宅に歸ると一室に籠って書く、手本を
本にして生意氣にも實物の寫生を試み、幸ひ自分の宅から一丁ばかり離れた桑畑の中に借馬屋があるので、幾度となく其處
の厩に通った。輪廓といひ、陰影と云ひ、運筆といひ、自分は確にこれまで自分の書いたものは勿論、志村が書いたもの、
中でこれに比ぶべき出來はないと自信して、これならば必ず志村に勝つ、いかに不公平な敎員や生徒でも、今度こそは自分の
實力に壓倒さる、だらうと、大勝利を豫期して出品した。
出品の製作は皆な自宅で書くのだから、何人も誰が何を書くのか知らない、又互に秘密にして居た。殊に志村と自分は互の
畫題を最も秘密にして知らさないやうにして居た。であるから自分は馬を書きながらも志村は何を書いて居るかといふ問を常
に懐いて居たのである。
さて展覧會の當日、恐らく全校數百の生徒中尤も胸を轟かして、展覧室に入った者は自分であらう。圖書室は既に生徒及
び生徒の父兄姉妹で充満になって居る。そして二枚の大畫《今日に所謂る大作》が並べて掲げてある前は最も見物人が集って
居る。ニ枚の大畫は言はずとも志村の作と自分の作。
一見自分は先づ荒膽を拔かれてしまった。志村の畫題はコロンブスの肖像ならんとは!而もチョークで書いてある。元來學
校では鉛筆畫ばかりでチョーク畫は敎へない。自分もチョークで畫くなど思ひもつかんことであるから、畫の善惡は兎も角、
先づ此一事で自分は驚いてしまった。その上ならず、馬の頭と髭鬚面を被ふ堂々たるコロンブスの肖像とは、一見まるで比べ
者にならんのである。且つ鉛筆の色はどんなに巧みに書いても到底チョ—クの色には及ばない。畫題といひ色彩といひ、自分
のは要するに少年が書いた畫、志村のは本物である。技術の巧拙は問ふ處でない、掲げて以て衆人の展覽に供すべき製作とし
ては、いかに我慢強い自分も自分の方が佳いとは言へなかった。さなきだに志村崇拝の連中は、これを見て歡呼して居る。
『馬も佳いがコロンブスは如何だ!』といふ聲が彼處でも此處でもする。
自分は學校の門を走り出た。そして家には歸らず、直ぐ田甫へ出た。止めやうと思ふても涙が止まらない。口惜いやら情け
ないやら、前後夢中で川の岸まで走って、川原の草の中に打倒れてしまった。
足をばたばたやって大聲を上げて泣いて、それでも飽き足らず起上って其處らの石を拾ひ、四方八方に投げ付けて居た。か
う暴れて居るうちにも自分は、彼奴何時の間にチョーク畫を習ったらう、何人が彼奴に敎へたらうと其ればかり思ひ續けた。
泣いたのと暴れたので幾干か胸がすくと共に、次第に疲れて來たので、いっか其處に臥てしまひ、自分は蒼々たる大空を
見上げて居ると、川瀬の音が淙々として聞える' 若草を薙いで來る風が、得ならぬ春の香を送って面を掠める。佳い心持にな
って、自分は暫時くぢつとして居たが、突然、さうだ自分もチョークで畫いてみやう、さうだといふ一念に打たれたので' 其
儘飛び起き急いで宅に歸へり、父の許を得て、直ぐチョークを買ひ整へ畫板を提げて直ぐ又外に飛び出した。
この時まで自分はチョークを持ったことが無い。どういふ風に書くものやら全然不案内であったがチョークで書いた畫を見
たことは度々あり、たヾこれまで自分で書かないのは到底未だ自分どもの力に及ばぬものとあきらめて居たからなので、志村
があの位ゐ書けるものなら自分も幾干か出來るだらうと思ったのである。
再び先の川邊へ出た。そして先づ自分の思ひついた畫題は水車、この水車は其以前鉛筆で書いたことがあるので、チョ1
クの手始めに今一度これを寫生してやらうと、堤を辿って上流の方へと、足を向けた。
水車は川向にあって其古めかしい處、木立の繁みに半ば被はれて居る案排、蔦葛が這ひ纏ふて居る具合、少年心にも面白
い畫題と心得て居たのである。これを對岸から寫すので、自分は堤を下りて川原の草原に出ると、今まで川柳の蔭で見えなか
まと
ったが、一人の少年が草の中に坐って頻りに水車を寫生して居るのを見つけた。自分と少年とは四五十間隔たって居たが自分
は一見して志村であることを知った。彼は一心になって居るので自分の近いたのにも氣もつかぬらしかった。
おやおや、彼奴が來て居る、どうして彼奴は自分の先へ先へと廻はるだらう、忌々しい奴だと大に«に觸ったが、さりと
て引返へすのは猶ほ憔だし、如何して呉れやうと、其儘突立って志村の方を見て居た。
彼は熱心に書いて居る草の上に腰から上が出て、其立てた膝に畫板が寄掛けてある、そして川柳の影が後から彼の全身を
被ひ、たヾ其白い顔の邊から肩先へかけて楊を洩れた薄い光が穩かに落ちて居る。これは面白ろい、彼奴を寫してやらうと、
自分は其儘其處に腰を下して、志村其人の寫生に取りか、った。それでも感心なことには、畫板に向うと最早志村もいまいま
しい奴など思ふ心は消文て書く方に全く心を奪られてしまった。
彼は頭を上げては水車を見、又畫板に向ふ、そして折々左も愉快らしい微笑を頰に浮べて居た。彼が微笑する毎に、自分
も我知らず微笑せざるを得なかった。
さうする中に、志村は突然起上がって、其拍子に自分の方を向いた、そして何とも言ひ難き柔和な顔をしてにっこりと笑っ
た。自分も思はず笑った。
『君は何を書いて居るのだ、』とМくから、
『君を寫生して居たのだ。』
『僕は最早水車を書いてしまったよ。』
『さうか、僕は未だ出來ないのだ。』
『さうか、』と言って志村は其儘再び腰を下ろし、もとの姿勢になって、
『書き給へ、僕は其間にこれを直すから。』
自分は畫き初めたが、畫いて居るうち、彼を忌々しいと思った心は全く消えてしまひ、却て彼が可愛くなって來た。其うち
に書き終ったので、
『出來た、出來た!』と叫ぶと、志村は自分の傍に來り、
『をや君はチョークで書いたね。』
『初めてだから全然畫にならん、君はチョーク畫を誰に習った。』
『そら先達東京から歸って來た奥野さんに習った然し未だ習ひたてだから何にも書けない。』
『コロンブスは佳く出來て居たね' 僕は驚いちゃツた。』
それから二人は連立って學校へ行った。此以後自分と志村は全く仲が善くなり、自分は心から志村の天才に服し、志村もま
た元來が温順しい少年であるから、自分を又無き朋友として親しんで呉れた。二人で畫板を携へ野山を寫生して歩いたことも
幾度か知れない。
間もなく自分も志村も中學校に入ること、なり、故郷の村を離れて、縣の中央なる某町に寄留することゝなった。中學に入
っても二人は畫を書くことを何よりの 樂 にして、以前と同じく相伴ふて寫生に出掛けて居た。
此某町から我村落まで七里、若し車道をゆけば十三里の大迁廻になるので我々は中學校の寄宿舎から村落に歸る時、決して
車に乘らず、夏と冬と定期休業毎に必ず、此七里の途を草鞋がけで歩いたものである。
七里の途はたヾ山ばかり、坂あり、谷あり、渓流あり、淵あり、瀧あり、村落あり、兒童あり、林あり、森あり、寄宿舎の
門を朝早く出て日の暮に家に着くまでの間、自分は此等の形、色、光、趣を如何いふ風に畫いたら、自分の心を夢のやうに
鎖ざして居る謎を解くことが出來るかと、それのみに心を奪られて歩いた。志村も同じ心、後になり先になり、二人で歩いて
居ると、時々は路傍に腰を下ろして鉛筆の寫生を試み、彼が起たずば我も起たず、我筆をやめずんば彼も止めないと云ふ風で、
思はず時が經ち、驚いて二人とも、次の一里を駆足で飛んだこともあった。
爾來數年、志村は故ありて中學校を退いて村落に歸り、自分は國を去って東京に遊學すること、なり、いっしか二人の間
には音信もなくなって、忽ち又四五年経ってしまった。東京に出てから、自分は畫を思ひっゝも畫を自ら書かなくなり、たヾ
都會の大家の名作を見て、僅かに自分の畫心を満足さして居たのである。
處が自分の二十の時であった、久しぶりで故郷の村落に歸った。宅の物置に曾て自分が持あるいた畫板が有ったのを見っ
け、同時に志村のことを思ひだしたので、早速人に聞いて見ると、驚くまいことか、彼は十七の歳病死したとのことである。
自分は久しぶりで畫板と鉛筆を提げて家を出た。故郷の風景は舊の通りである、然し自分は最早以前の少年ではない、自
分はたヾ幾歳かの歳を增したばかりでなく、幸か不幸か、人生の問題になやまされ、生死の問題に深入りし、等しく自然に對
しても以前の心には全く趣を變へて居たのである。言ひ難き暗愁は暫時も自分を安めない。
時は夏の最中自分はたヾ畫板を提げたといふばかり、何を書いて見る氣にもならん、獨りぶらぶらと野末に出た。曾て志村
と共に能く寫生に出た野末に。
か<?しみ う ひさし かむた ニなた
闇にも歡びあり、光にも悲あり麥藁帽の廂を傾けて、彼方の丘、此方の林を望めば、まじまじと照る日に輝いて眩ゆき
ばかりの景色。自分は思はず泣いた。
「巡査」
この頃ふとした事から自分は一人の巡査、山田銃太郎といふのに懇意になった。年齡は三十四五でもあらうか、骨格の逞し
い、背の高い堂々たる偉丈夫である。
自分は人相のことはよく知らぬが、圓い顔の、口髭頰鬚ともに眞黑で、鼻も眼も大きな、見た處は柔和な相貌とは言へない
がさて實際はなかなか好人物なのが世間には随分ある、この巡査も其種類に屬するらしい。
若し其人が沈默であったなら斯ういふのは餘り受の可い人相ではない。處が能く語り能く笑ふ、笑ふ時は其眼元に一種の愛
嬌がこぼれる、語る時は相手の迷惑もなにも無頓着で、のべ つに行る。そこで思ひもつかぬ比喩など用ゐて、それを得意でーー
度も三度も繰返す。如何だらう、斯ういふ人物は他の憎惡を受けるだらうか。
或日、明日は非番で宅に居ますから是非入來しゃいと頻りに促がされたから、午後一時ごろ自分は山田巡査を訪ねて見た。
『ね、是非入來しゃい、何にもないが寒いから……これをやって饒舌りましょう』とグイ飮の手眞似をして見せた。
指物屋の二階の一室が先生の住居である。仕事場の横から急な狭い梯子段を上ると、直ぐ當面に炭俵が置いてある、靴が
基のやうに一隅に眠って居る、太い棒が其傍に突立って番をして居る、多分ステッキといふのだらう。別の一室には書生でも
居るか、微吟の聲が洩れて居たが其前の薄暗い板間を通ると突當の部屋が山田巡査の宅。
『やッ、よく入來しゃいました。サア此方へ、サア—』と言ひながら急に起って押入から座蒲團を一枚、長火鉢の向へ投出
した。
©
先生一杯やりはじめて、やゝ醉の廻って居る時分であった。
『獨身者の生活は斯んなものでしてナ。御覧の通りで狭いも狭いし、世帶道具がこの一室にあるのだから、まア何のことはな
い豚小屋ですな、豚小屋で……』と其處らをきょろきよろ、何か探して居るやうであったが、急に前の 杯をグイと呑干して
『まアーツ!御飯が濟んだのなら酒だけーツ、この酒は決して頭へ來るやうな酒じゃア御座いませんから。』
自分は受けてちゃぶ臺に置いた。成程狭いが、狭いなりに一室がきちんと整理いて居る。作出しの押入が一間、室内にはみ
出して其唐紙は補修だらけ、壁はきたなく落書がしてある、疊は黑い、障子は煤けて居る、成程むさくるしい部屋であるが、
これ又何處となく掃事が届いてサッパリして居る。どうして、豚小屋どころか!
窓の下に机、机の右に書籍箱、横に長火鉢、火鉢に並んでちゃぶ臺、右手の壁に沿ふて箪笥鼠入らず、其上に違棚、總て
が古いが、總てが淸潔である、煙草箱、菓子器、茶入、
の上には盆栽の小鉢が三ツ四ッ置いてある。
自分は杯を返しながら
『流石警官だけに貴様は大變清潔ずきですね。』
蓋物、帙入の書籍、總てが其處を得て、行儀よく並んで居る書籍箱
これが 私の性分でしてナ、どうも惡い性分でしてナ、他人のするこ
とは氣に入らんていふんだから困って了います、殊に食器ですナア、茶碗でもなんでも他人に爲て貰うと如何も心持が惡い、
それで悉皆自分でやりますがね:::』
『ぢやアいよいよ獨身者訣向といふ性分ですね、ハヽヽヽヽ』
『ハヽヽヽ、、イヤ清潔ずきていふ程のこともないが、
『全くさうです'だから國に女房もありますが决して呼びません、一人で不自由を感じないんですから。』
『夫人がお有りンなるんですか、さうですか' それじゃア何にも獨身者の詫住居を好んでするにやア當らないでしょう、そし
てお兒さんは?』
『小兒もあります、五才になる男の兒が一人あります、がです、矢張一人のはうが氣樂ですナア』と手酌で飮みながら『尤も
私の妻を呼ばないのは他にも理由がありますがね。』
『どんな理由がありますか知りませんが、兎も角妻子があれば一家團樂の樂を亨けないのは嘘でしょう?、貴様さびしく思
ひませんか。』
『イヤ全く孤獨く感じないこともないですがナ、ナニ私も時々歸るし妻もちょいちょいやって來ますよ、汽車で日往復が出來
ますからナニ便利な世の中ですよ、御心配には及びません夜具も二人前備へてあります、ハッハツ'、ヽ、』
『ハヽヽヽ、先づさう諦めて居れば仔細はありませんナ』
『サア何か食って下さい、ろくなものは御座いませんがね、どうです豆は、蜜柑でも。』
ちゃぶ臺には煮豆、數子、蜜柑、酢章魚といふ風なものが雜然と並べてある。柱にかけた花挿には印ばかりの松ヶ枝、冬の
日脚は傾いて西の窓をまともに射し、主人の顔は赤く眼はとろりとして矢張正月は正月らしい。
主人は專賣特許の厨爐にかけた鐵瓶から德利を出しながら
『全く 一人のはうが氣樂ですよ。サア熱いことろを一ツ、それに私は敢えて好んで妻を持ったわけじゃアないんですからナ。
ふとした處から養子に貰はれたので、若しそれで無かったら今でも獨身でサア、第一巡査をして妻子を養って樂をしような
んテ、ちっと出來にくい藝ですナ、蛇の綱渡よりか困難いことです、工、貴様は蛇の綱渡を見たことがありますか、私はー
ツ見ました。姓名は言はれませんが、私どもの仲間に妻と小供の三人と母親とを養って、それで小ザッパリと暮して居るもの
がある、感心なものでしょう、尤も酒は呑ません、煙草もやりません。こんな男は例外です。私どもには到底出來ない藝です。』
『然し田舎に細君を置いた處で費ものは費るから同じ事でしょう、文句を言はないで一所におなんなさい、細君が可愛さう
だ。』
『ハヽヽヽヽツ貴様は大に細君孝行だ、イヤ私だってね、まんざら女房を可愛がらないわけはないんだが、田舎には多少の
資産があるんです、それに未だ父母も居ますから却て妻は先方に居たはうが相方の便利なんです'まア私なんざア全く道樂で
斯んな職をやって居るんでサア、イヤになれば直ぐ止めて田舎に引込んだって食うに困るやうなことはないんですからナア。』
『氣樂ですね工。』
『全く氣樂です!だから酒は石崎から斯うやって樽で取ってグイグイ飮むのですが、澤之鶴も可いが私どもにやア少し甘味が
勝って居るやうで却てキ印の方が口に合ひます、どうも料理屋の混成酒だけは閉口しますナア。』
と先生頻りに酒の品評をはじめ、混成酒の攻撃をやって居たが醉は益々發して來たらしい
『どうです'ーツ隠藝をお出しなさい、工、僕ですか、僕は全く無藝、たヾ飮めば則ち眠る、直ぐ寢て了います!』
成程さも眠むさうな、とろんこな眼をして居る'
『僕でも貴様方のやうにナア、文章が書けるなら隨分書いて見たい事があるんだが、だめだ!』
と暫く眼を閉じて默って居たが、急ににっこり笑って、
『ウンさうだ! ーツ見て貰うものがある。』
と机の抽出から草稿らしい藻のを五六枚出して、其一枚を自分の前へ突出した。見ると漢文で
『題警察法』といふ一編である。
『夫れ警察の法たる事無きを以て至れりと爲す』
と一種の口調で體躯をゆりながら漢文を朗讀しだした。
『事を治むる之に次ぐ、工、どうです。』
『贊成々々』
『功無きを以て盡すと爲す、功を立つる之に次ぐ、故に、どうです、故に日夜奔走して而して事を治め、千辛萬苦して而して
功を立つる者は上の上なる者に非ざる也。』
『だから臥て居るてンですか。』
『ハヽヽヽヽツまア先を聞いて下さい。最上の法は事を治むるに非ず、功を立つるに非ず、常に無形に見、無形に聽き、以て
其機先を制す、故に事有るなくして而して自ら治り、功爲す無くして而して自ら成る、是れ所謂る爲し易きに為し而して治
め易きに治むる者也、どうです名論でしょう!是の故に善く警察の道を盡す者は功名無く、治跡無く、神機妙道只だ其人に存
す焉、愚者解す可からざる也、夫子曰く人飮食せざる莫き也、能く味を知る鮮き也!文章は拙いが主意はどうです。』
『文章も面白ろい、主意は大贊成です!』
『神機妙道只だ其人に存す、愚者解すべからざるなりか、ハヽヽヽヽッ』と頗る得意である。
『先づ酒でも飲んで十分精神を養って其機先を制すと行くのです、工、どうです熱い處を。』
『もう僕は澤山!何か外に面白いものはありませんか、詩のやうな者は。』
『詩ですか、あります、有りますもすさまじいが幼學便覧出來といふのが二三ダースあります。』
と»紙に清書したのを四五枚出して見せたが、
『イヤ讀まれちゃア困ります、一ッニッ僕が吟じます、さてと、どれもまずいなア、春夜偶成かナ、朦朧烟月の下、一醉花に
對して眠る、風冷やかに夢驚き覺れば、飛紅枕邊を埋むはどうです\工、これは下田歌子さんの歌に何とかいふのが有りまし
たねエ、そら何と言ひましたなア、今ちょっと忘れましたが、それを飜譯したのですがまるで比較になりませんなア、あの婆
さん、と言っちゃア失禮だが全く歌はうまいもんですなア』と左右に身體を搖動ながら今一度春夜偶成を繰返した\『それか
ら此處にーツちよっと異なのが有ります、權門所見と題して、權門昏夜哀を乞ふ頻りなり、朝に見る揚々として意氣新なる
を、妻妾は知らず人の罵倒するを、醜郎満面鬚塵を帶ぶはどうです、工。』
『痛快ですなア。』
『これは或大臣の警衞をして居た時の作です、醜郎の満面、髯塵を帶ぶ——かね。』
『もーツ。』
『さうですなア』と草稿を繰返して居たが、突如として『故山の好景久しく相違う、斗米官遊未だ非を悟らず、杜宇呼び醒す
名利の夢、聲々、復た不如歸を喚ぶ——。ハッハツ、、、ヽ到々本音を吐いちゃツた!』
『ハッハツ、、ヽヽ到々本音が出ましたね。』
『ハツ、、ヽ、』と笑ったが山田巡査は眼を閉じたまゝ何を考えるともなくうつらうつらして居る様子であった、半分居眠
って居るのである。突然、
『イヤ矢張この方が氣樂だ!』と叫けんで、眼を見開き自分を見て莞爾笑ったが、直ぐ又居眠を始めた。
自分は暫時く凝然として居たが起すのも氣の毒とそっと起って室を出た。
指物屋の店から四五十間下ると四辻がある、自分は此處に來た時、後を振り向くと指物屋の二階の窓から山田巡査の髭髯だ
らけの顔が出て居た。頻りと點頭をして居た。
自分は全然この巡査が氣に入って了った。
「帽子」
春の日の午後四時頃、乘合馬車が一つの驛に止った。山岸に沿ふて流る、渓流が此處でー迁轉する其岸に二三十軒の田舎
町が出來て居る。
乘合の客五人ばかりは彈機も有るか無きかの亂暴な馬車で田舎道をがたがた行られた疲労を暫時でも休めんと、降りた。自
分もその一人。
見ると十二三の童が一人、小さな蒂を敷て其の上で獅子藝を行って居る、其週囘に町の小供や怠惰者、兒守娘など十四五
人取りかこんで見物して居た。乘合の者二三人もこれに加はった、自分も其一人。
童は其小さな身體をくるくる獨樂の様に廻轉て見せる、或は兩手を足にして倒に立つ。見物は誉めたり、笑たり、冷かし
たり、そして銅貨一つ興る者もない。其中馬の仕度が出來て御者は早く乘れと怒鳴り初めた。
自分は銅貨一つ出して、そっと童の傍に投げた、すると自分の傍に立って居た客の一人が銅貨一つ出すよと見るや、直に
手荒く之を童の頭に投っけた。額に中って鮮血がサッと流れ出る、人々は驚いたが投げた當人はにやりと冷笑って馬車の方へ
のそのそ行って了った。
童はと見ると、血まみれになった手で投げられたものを拾ひ取り羞恥しさうな笑を含み、見物を見廻したばかり。
馬車に歸ると自分は今の男と差向ひに座を取らされて、さなきだに此男の言葉から態度が二時間前より自分を苦しめて居る
のに、これからさき又二時間ばかり膝を突き合はし居なければならぬかと、不快に堪えなかった。
此男が某町の商人であることは先程からの彼の問ず語りで自分には解って居た、年は四十二三でもあらうか、骨格逞まし
く、木綿の筒袖を着て前垂に中折帽子、其帽子は新調の品で乘合の一人が眞面目か愛嬌かー寸賞めたら、これは先日大阪に上
った時何とかいふ大阪第一の店で買ったのだとか、羅紗が何だとか色々自慢話ありし末、「しかも此様ものは」と鼻にぬけた
聲で話頭を止められた品である。
車中は女が一人、此男が一人、自分の外二人、其二人は多少此男の身の上を知て居るらしく何時彼の言ふことに逆らはず合
槌を打つのを見て、自分は此男が町で中以上の富と勢力とを持て居るものと推測した。
彼の眼は異様に光って居る。そして土色を帶びた黑い顔は逞しい鼻と厚い唇とで凄味を加へ、聲は高くないが人を壓しのけ
るやうで、折り折り手荒く自分の額を摩る癖がある。自分は厭惡な男だと思ふ中にも如何しても彼の神經に多少の異常がある
ものと思はざるを得なかった、そうだと言って彼を厭う心は少しも薄らがない、何故ならば、人の性格の相違は神經作用の相
違とも言へるから純然たる狂人でない限り彼は厭惡な性格の男と言ふことも出來ると自分は斷定したのである。其外彼の顔を
見ては種々な感想に耽って、自分は全く沈默し、彼等の談話に加らなかった。
其處で物語は前に返り、馬の更りしため馬車は以前よりも景氣可く走り御者は亦た空模様を氣にしながら、無暗と鞭を加へ
る、どんより曇りし春の空は夕暮近くなるに連れ益々怪しくなり、山の頂、野の末は既に雨を帶びて來た。
自分は成るべく眼を閉ぢて前の男を見ないやうに力め、談話も耳に入らないやうにと空想を喚び起して其中に身を隱して居
た。其中夢心地になって半ば居睡をして居たが、ふと眼を開けて外を見ると、何時しか雨となって、春雨しとしとと野も山も
霞み、その靜けき、穩やかな景色の中を馬車は飛やうに走って居た。雨に濡て綠深き林を過たと思ふと直ぐ一簇の家村に出て
馬車は止まり、一人客が乘た。
「ヤア先生、何處に旅行になりました?」と自分を見て挨拶をする、これは某町に於ける自分の生徒の一人であったので、二
十七ハ歳の晩學を止め、今では家業に從事して居るのである。彼は自分に言葉をかけて傍に腰を下し、そして自分の前の男に
一寸と目禮した。先方は例の帽子に指先をかけたが、互に別に言葉を交さず。
馬車は直ぐ走り出した。自分は談話の對手が出來たので、不快から救はれ、今度の自分の遠足の事など語り、をりをり外を
眺めて居たが、夕暮近く、遠近の茅屋から上る炊烟は絲の如き雨に和して重く輕く樹林を包んで居る景色、田舎慣し自分にも
惡くはなかった。前の厭な男は相變らず他の者と饒舌って居たが、町へは最早十町とない所まで來た頃、彼は何と思った
か硝子窓を開けて身體を横に捻て外に頭を出した。其途端例の帽子が飛んだ。彼の對手はあっと驚き、彼も驚き、人々は御者
に馬車を止めろと叫んだが、御者臺の若者には此事が知れない。馬車はどしどし走る、此時彼は、
「何、あんな帽子、構ひませんわ!」と低い重い聲で言って、冷やかに笑みた。
「だって、捨るといふ事はありませんわ!」と相手の一人が息急んで言ふ。
「フ、ン!」と言って、彼は手荒く額を摩った。
其中馬車が靜かに止ったのが、如何した事かと自分も醉興に窓を開けて、來し方を見ると一人の 農夫が、「オイオイ」と
呼びながら帽子を持て懸命に追кけて來るのであった。
間もなく農夫は馬車の傍まで來て、其泥だらけの手にて帽子を捧げながら、麥に手入をして居た自分の傍に落たから拾って
來て進ぜたとの意を呼吸づかい苦しげに、とぎれとぎれに言った。すると帽子の主は、「そんな帽子お前に呉れてやる、欲け
りゃ持てゆけ不欲んなら捨てろ!」と言ひ放った。これを聞いて、さなきだに飛ぶが如き馬車を追кけた爲め、蒼ざめて凄味
を帶びて居た農夫の顔色は土の如く、唇は顫動き、眼光鋭く悲しげに、じっと前の男の顔を見つめて其處に直立った。
餘りの事に何人も一語も發し得ない。
「未か!」と御者臺の男は叫けんだ。
「早く出さんか!」と前の男は怒鳴り返した。鞭音高く馬背に響くや、馬車は遠慮なく騷だした。
前の男は外に帽子なき頭を出して後を見て、
「未だ此方を見て立って居やがる。フン!」
舌打ちして荒く窓を閉めた。
「折角だから取ってやれば可う御座んすに」
と對手の一人は僅かに口を開いた。
「何に彼な帽子、拾うたから與れば可え」
「けれど、彼の漢が可憐さうな」
「貰って結句、喜しからう」
對手は默って了まった。最早餘り口をきく者がない。其中間もなく馬車は町に着いて佇った。夕闇薄暗らく、家々は既に燈
を點けて居た。
合乘の者はそれぞれ挨拶をして車を出た。彼の男も外に下りて、駒下駄を爪立て、二足三足歩いたと見るや、アッと叫んで、
尻餅をついた。誰も驚ろいて何事かと近き、彼の知る人は、
「如何したの、如何なされた」と援け起しにかゝった。動かない、彼は殆ど氣絶の體である。其處で人々は愈々驚き側の店先
に擔ぎこんで水を呑すなど種々、介抱すると、漸く正氣づきし如く立上って四邊をきょろきよろ見廻して居たが、嘎れた聲
で、
「皆様今こゝで先刻の漢を見やしませんかノ」
「先刻の漢といふて何人?」と一人が聞く。
「そら先刻の農夫、あれが今、自分が馬車から出たと思ふと、眼の前にひよっくり出て來て彼の時と同じ顔をして帽子を突
出しましたと思ひなされ……」
人々は殆ど戰慄をした、恐らく何人も其刹那に彼の農夫の顔が眼先に顯はれたヾらうと思ふ。
兎も角、彼の男を慰めて一同は散じた。
それから三四日經っと、馬車に乘合はした彼の知人がやって來て、
「先生' 彼の男を如何思ひなさります。」と聞く、それは氣絶の一件である。
「實に妙な事もあるものだね。」
「實際農夫が現はれる筈はありませんが、先づ罰で御座いませうノ」
「そうかも知れんサハけれど我々にも彼時の農夫の顔は目にありありと殘って居るから、彼奴にだって左様だらう、それが出
たのサ。」
と自分は答へたが然し自分は此事を然く淡白に考へては居なかったので、實に言ひ難き或問題に觸れた氣がして、此二三日
は少なからず此に惱まされて居たのである、人の心に潜む殘忍、冷刻、又は他が之に觸れて傷いた心、そんな事ばかりでな
い、尚ほ或物。
ひて fccH よ か か扛これ
これらを對手の知人に話しても解らず、寧ろ彼から聞た方が可いので、彼の男の身の上を彼是と尋ねた。
彼男は町で評判は餘り可くないが、ロきゝで勢力は可なり有る上に商法にかけて拔目なく彼一代で今の一萬ばかりの身代
を作ったといふこと。彼は變物で、折々氣が變になる事があるといふ事。夫婦の間に子なく、其爲め姪を貰って育て、居る
が、不思議とそれを非常に可愛がるといふ事。以上よりも重大の事は、彼の今の妻は後妻で、先妻は彼が商用で旅行して居る
留守に、不義をして情夫と逃亡したといふ事。けれど氣の變になったのは其爲ではなく初めより彼は荒々しき氣性を有しやゝ
ともすると、妻を亂打して非常に虐待し、妻の不義をしたのも一つは其爲彼を厭ふたといふこと。そして彼の唯一の嗜好は
釣魚であるといふ事などを聞き得た。
其後、夏の初めである。自分は郊外に出て河岸をたどり散歩して居ると彼の釣を垂れて居るのを見た。自分は思ふところが
あるので、傍に倚り
「釣れますか」と輕く言葉をかけた、彼は振りかへって自分を見たが、直ぐ又た水面を熟視て居る。
「釣れますか」と自分は今一度言って、更に傍に近づいた。すると振向いて例の凄い顔で自分を見て、傍に在りし魚籠を取っ
て、自分からは見えぬ側に置き、そして何の返事もせず眼を水面に轉じた。
結局、自分までがやられて了まった。自分は物思に沈みながら暫らく散歩して居たが名殘りなく晴れた美しい蒼空も、聲
淸く啼く雲雀も面白くなくなって、間もなく歸路に就いた。
「都の友へ、Е生より」
(前略)
久しぶりで孤獨の生活を行って居る、これも病氣のお蔭かも知れない。色々なことを考へて久しぶりで自己の存在を自覺し
たやうな氣がする、これは全く孤獨のお蔭だらうと思ふ。此温泉が果して物質的に僕の健康に効能があるか無いか、そんな事
は解らないが何しろ温泉は惡くない。少くとも此處の、此家の温泉は惡くない。
森閑とした浴室、長方形の浴槽、透明って玉のやうな温泉、これを午後二時頃獨占して居ると、くだらない實感からも、夢
のやうな妄想からも脱却して了ふ。浴槽の一端へ後腦を乘て一端へ爪先を掛て、ふわりと身を浮べて眼を閉る。時に薄目を開
て天井際の光線窓を見る。碧に煌めく桐の葉の半分と、蒼々無際限の大空が見える。老人なら南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛と
ロの中で唱へる所だ。老人でなくとも此心持は同じである。
居室に歸って見ると、ちゃんと整頓て居る。出る時には書物やら反古やら亂雜極まって居たのが、物各々所を得て靜かに僕
を待て居る。ごろりと轉げて大の字なり、坐布團を引寄せて二つに折て枕にして又も手當次第の書を讀み初める。陶淵明の所謂
る『不求甚解』位は未だ可いが時にーページ讀むに一時間もかゝる事がある。何故なら全然で他の事を考へて居るからであ
る。昨日も君の送って呉れたチェホフの短篇集を讀んで居ると、ツイ何時の間にか「ボズ」さんの事を考へ出したС
ボズさんの本名は權十とか五郎兵衞とかいふのだらうけれど、此土地の者は唯だボズさんと呼び、本人も平氣で返事をして
此以前僕が此處へ來た時の事である、或日の午後僕は渓流の下流で香魚釣を行って居たと思ひ玉へ。其場所が全たく僕の氣
に入ったのである、後背の涯からは雜木が枝を重ねて被ひか、り、前は可り廣い澱が靜に渦を巻て流れて居る。足場はわざ
わざ作った様に思はれる程、具合が可い。此處を發見た時、僕は思った此處で釣るなら釣れないでも半日位は辛棒が出來ると
思った。處が僕が釣り初めると間もなく後背から『釣れますか』と唐突に聲を掛けた者がある。
振り向くと、それがボズさんと後に知った老爺であった。七十近い、背は低いが骨太の老人で矢張釣竿を持て居る。
『今初めた計りです。』と言ふ中、浮木がグイと沈んだから合すと、餌釣としては、中々大いのが上った。
『此處は可なり釣れます。』と老爺は僕の直ぐ傍に腰を下して煙草を喫ひだした。けれど一人が竿を出し得る丈の場處だから
ボズさんは唯見物をして居た。
間もなく又一尾上げるとボズさん、
『旦那はお上手だ。』
『だめだよ。』
『イヤさうでない。』
『これでも上手の中かね。』
『此温泉に來るお客さんの中じゃア旦那が一等だ。』と大げさに贊めそやす。
『何しろ道具が可い。』と言はれたので僕は思はず噴飯だし、
『それじア、道具が釣るのだ、ハヽハヽ・…:』
ボズさん少しく狼狽いて、
『イヤ其は誰だって道具に由ります。如何ら上手でも道具が惡いと十尾釣れるところは五尾も釣れません。』
それから二人種々の談話をして居る中に懇意になり、ボズさんが遠慮なく言ふ處によると僕の發見た場所はボズさんのあじ
ろの一で、足場はボズさんが作った事、東京の客が連れて行けといふから一緒に出ると下手の癖に釣れないと言って怒って
直ぐ止す事、釣れないと言って怒る奴が一番馬鹿だといふ事、温泉に來る東京の客には斯ういふ馬鹿が多い事、魚でも生命は
惜いといふ事等であった。
其日はそれで別れ、其後は互に誘ひ合って釣に出掛て居たが、ボズさんの家は一室しかない古い茅屋で其處へ獨でわびし
げに住んで居たのである。何でも無遠慮に話す老人が身の上の事は成る可く避けて言はないやうにして居た。けれど遠まはし
に聞き出した處によると、田之浦の者で枠夫婦は百姓をして可なりの生活をして居るが、其夫婦のしうちが氣に喰ぬと言って
十何年も前から一人で此處に住んで居るらしい、そして悴から食ふだけの仕送りを爲て貰ってる様子である。成程さう言へば
何處か固拗のところもあるが、僕の思ふには最初は頑固で行ったのながら後には却って孤獨のわび住ひが氣樂になって來たの
ではあるまいか。世を遁がれた人の趣があるのは其理由であらう。
其處で僕は昨日チェホフの『ブラックモンク』を讀さして思はずボズさんの事を考へ出し、其以前二人が渓流の奥深く沂
って「やまめ」を釣った事など、それからそれへと考へると堪らなくなって來た。實は今度來て見ると、ボズさんが居ない。
昨年田之浦の本家へ歸って亡なったとの事である。
事實、此世に亡い人かも知れないが、僕の眼にはありありと見える、菅笠を冠った老爺のボズさんが細雨の中に立て居る。
『病氣に良くない'』『雨が降りさうですから』など宿の者がとめるのも聞かず、僕は竿を持て出掛けた。人家を離れて四五
丁も沂ると既に路もなければ畑もない。たヾ左右の斷涯と其間を迂囘り流る、渓水ばかりである。瀬を辿って奥へ奥へと沂
るに連れて、此處彼處、舊遊の澱の小蔭にはボズさんの菅笠が見えるやうである。嘗てボズさんと辨當を食べた事のある、
平い岩まで來ると、流石に僕も疲れて了った。元より釣る氣は少しもない。岩の上へ立てジッとして居ると寂しいこと、靜
かなこと、深谷の氣が身に迫って來る。
暫時くすると箱根へ越す峻嶺から吹き下して來た、霧のやうな雨が斜に僕を掠めて飛ぶ。直ぐ頭の上の草山を灰色の雲が
切れ切れになって駆る。
『ボズさん!』と僕は思はず涙聲で呼んだ。君、狂氣の眞似をすると言ひ玉ふか、僕は實に満眼の涙を落つるに任かした。(略)
島崎藤村
「爺」
として吾儕木曾男子の常に感謝して居ることは、木曾川沿岸の風景でもなく、御嶽山脈の壮觀でもなく、五木の大森
林でも有ません。吾儕はもう御嶽山脈の崩雪に飽き果てゝ了った。森林の幽欝にも飽き果てた。木曾川は氾濫の恐怖より外に
何の新しい感も起しません。そこへ行くと見飽のしないのは淸しい眸です。土地の女の美しいことは、吾儕に取って何より
の天の惠なので。
『何故、あの手合は彼様に女を愛するのだらう。』と他國の方は仰るでせうが、又、吾儕木曾男子に言はせると、『何故、
吾儕は斯様に女を愛するのだらう、』と申上げたい。實に吾儕の故郷は、女ならでは夜も日も開けぬと言って宜しいのです。
愛と侠とは木曾男子の生命ですからな。
私も是精神にかけては、まあ敗を取らない薇なんです。
私ですか。私も今では故郷に歸って、淸酒の醸造をしたり、小作人の世話を燒いたり、時には鳥銃を肩に懸けて獵に出掛けた
りするといふやうな——まあ、氣樂な身分ですよ。都會の生活も萬更知らんでもない、といふのは、四五年東京の叔父の處
に書生で居た時代が有ますからね。
私は記臆といふ奴を憎んで居る。記臆は愛の敵ですから。愛したり、愛せられたりせずには、日を送れないよいふ性分に生れ
めぐみ
天の惠
り
つもり
て見ると' 記臆ほど邪魔になる者は有ません。私も仕合と、健忘の御蔭に過去った怨恨や苦痛を逃れて' 心を移して居るの
です。
しかし私見たやうな物覺の惡い男でも、不思議に忘れない一人の女が有る。お島といふのが其女の名なんです。お島と知合
になったのは、實は私が東京の叔父の家に居た頃の話で。
殖民——といふのも異なものですが、國を出まして東京に移住する木曾人の數も夥しいものです。江戸子の言草がまた面
白い。この山家から出稼に行く殖民を指して、『掠鳥』と言ひますね。叔父は掠鳥も、掠鳥も、大掠鳥で、しかも移住の歴史
から言ふと、古い殖民人の一人なんです。叔父の殖民地は、最初、京橋區。それから日本橋區。
私も掠鳥の群を放れて古巣へ歸ってから、もう彼是十年になりますよ。
七月の二十五日のこと、叔父の大病といふ報知を受けました。
不取敢出京。
本郷の某病院、外科室の二十號、と尋ねて見ますと、丁度叔父は治療室で博士の手術を受けて居る、といふことでした。見
違えるやうに成身した從弟に導かれて、上草履鳴して、廊下傳ひに參りますと、突當りの治療室の前の薄闇いところに、白壁
に倚り凭って立って居る女が有る。蒼白い神經質な額と、高慢な澄した目付とで、直にお島と知れた。私は十年振で此女に
めぐりあって、様子の變って居たのには驚いて了った。先方も驚いたやうでした。
初夏の光は白い窓掛を通して、蒸熱い治療室に射しこんで居りました。叔父の身體は半ば光を受けて、寢臺の上に正體も無い。
武士らしい威嚴を保った昔ながらの容貌は蒼ざめた上に、陰影になって、麻醉劑の香に苦痛の色を帶びて居る。博士は叔父の
腹部を切開した上、まさに直腸の癌を窺ふといふところで、手も刀も血潮に染みて居りました。
木曾殖民の王といふべき叔父も、博士の眼には寢臺の上に横はる一塊の肉としか見えない。急に叔父は熱を病む人の誰言の
やうに、
『操、 操。』
と二聲烈しく續けざまに呼びました。叔父の頭を押へて居た助手は、周章て、、呼吸器を宛行って、其上から麻醉劑を振注ぐ。
醫學生の群は互に顔を見合せて、意味もなく笑ひました。
操で私は思出した。まあ聞いて下さい。
斯いふ譯です。私が叔父の家に居た時分、あのお島が矢張手傳ひがてら來て掛って居りました。今でこそ彼様に艶が抜け、世
帶やつれもして、お婆さん染みて了って、額に蒼い神經質な筋なぞを顯すやうに成ったのですが、其頃は未だ盛りでしたよ。
吾儕の故郷の女は早くから世の中の歡しいやら哀しいが解って、信州北部の女なぞに比べると容姿が遥かに勝れて居る。空想
と情熱とは南部の女の特有です。お島は畢竟この血を多量に亨けたのですな。まあ私も、同じ故郷といふところからして、つ
い親しくするやうに成ました。ところがお島は叔父の家に掛りッきりといふのぢゃなくて、須永といふ遠い親戚にも厄介に成
って居たのです。須永も掠鳥です。ある夏の夜、須永の細君が叔父の留守に顔色を變へてやって來て、『蚊帳の内へでも入れ
て頂かなければ御話の出來ない件なんですよ』と言って、其頃は未だ生きて居た叔母と、今の隱居と、男を交ぜずの寢物語に
——お島が見るものを見ない、といふことから、縷々言って聞かせて泣いて責めたところが、其處へ須永が出て、頭を搔い
て、『實は』といふやうなことを言出した迄、涙まじりに話したのです。其時叔母の言ふには、『それ、御覧なさいな、貴方
は克く吾夫に限って其様なことは無いと仰ったけれど、男の堅いのは宛にならんぢゃ有ませんか』と笑へば、細君は嫉妬の
爲に身を悶えて、病み蓬けた叔母の手を握Xて泣いたそうです。この細君は珍しく分った女ではあるし、それに子は無し、
するからして、お島の産落した男の子を自分の子にして育てましたのです。この子の名が——それ操なんです。私は又、あ
の操が自分の子ではあるまいか、と思當ることが有ますので。
と申したやうな歴史を獨り繰返し乍ら、私は茫然と治療室の欄に倚り凭りました。
叔父の治療は三時間もか、りました。牡丹の花のやうに見えた腹部の切口は、終に紅い一條の線に閉ぢられて、人口の肛門
ばかり臍の下に殘りました。叔父の身黠が病室に運ばれる間に、博士は黑板の前に立って講義を始める、醫學生の群は階上の
一角に集りました。
二十號の病室は見舞の人々で座る處も無い位。須永も操を連れて來た。十年ばかり逢はない間に、須永も年をとりましたね。
この男の頭の禿たにも呆れましたが、操が成身して中學の制服を着て來たのにも驚きました。爭はれないものです、操の容貌
がお島の若い時に瓜二つで、子を褒めるぢゃ有ませんが、色白な行儀の好い美少年。すこし柔弱な處が無いでも無いが、さて
何處へ突出しても是が掠鳥の雛とは受取りかねる位。叔父の枕許で見舞に來た舊主人の奥様が操の顔をしげしげ凝視まして、
『この子は。』
と尋ねますと、隱居は手をついて、
『須永の息子で御座ます。』
『おや、さう、無いと思ってたに。』
『いえ、御座ましたんです。』
この『御座ましたんです。』が私を笑はせた。
『私は、まあ、無いとばかり思ってた。さう言へば母親さんに克く肖てるはねえ。』
©
と奥様に言はれて、操はすこし顔を紅くして、おづおづ御辭儀をしました。
私は操を忘れるどころぢや無い。しかし操は私を忘れて了って、思出さないといふ風でした。私の方から優しく出ても、妙に
旅人扱ひのやうな返事しか聞かせません。少年の時代には能く有る一種の恐怖から、操は反って私のこゝろやすだてを疑ひま
した。須永に慣々しくするのを見ると、私も羨しさは一通りで無い。あの淸しい目元、愛らしい音聲、あれを獨占するとは
——何たる果報者。私のお腹では、よし表面はどうあらうとも、陰へ廻っては打解けた話をして欲しかった。せめて彼の口唇
から、『御父さん、御父さん』といふ邪氣ない聲を一 □なりと利いて貰ひたかった。
慾望には際限が有ません。しかし、其と名のって言出すことは、今の場合が許さんから情ない。昔は罪、今は罰です。私は
操の他人行儀なのを見て、時々嘆息しました。
手術後の經過も好さそうなので、見舞いに來た人々は一先づ病院を引取る。隱居も留守を案じて濱町の家へ歸る。後は從弟
と、看護婦と、私とで引受け、かはるがはる寢ました。旅の疲勞で私も少し横になりましたが、夜の一時頃から起きて、叔父
の枕頭に寄添ひました。時とすると叔父の胸の動悸は波打つやうになって、呼吸の音も凄じく聞える。
『乃公も是度は絶念なければなるまい。斯なに苦しくちゃ——到底駄目だ。』
と堪えがたい身娜の苦痛を訴へる。廳て、叔父は『みんな寢たか』と念を押して、看護の疲勞に正驟もない從弟の高鼾を聞
澄して、何か私に頼みたさうな様子をしました。一生の臆出は亂れて叔父の胸に迫るといふ風で、何度か深い溜息を吐いて、
辛うじて斯いふ事を物語りました。あの操は——實は叔父の子だ、といふのです。これは亡くなった叔母にも、隱居にも、
誰にも知らせない秘密だ、といふのです。どうか彼子の後楣ともなって、從弟同様に見てやって呉れ、といふのです。『頼
むぞ』と言ひました時は、懺悔の涙が叔父の顔をったひました。
私は無量の感慨に打たれたのです。叔父が自身の最後を覺悟して' 後事を託するといふ場合にも' 財産とか、なんとか、そん
な吝嗇臭い事は小欠にも出さない。さすが木曾男子だけあって、死ちる間際迄も女を愛して、その佛を宿した忘形見の為に
は、懺悔を恥ぢないといふ心意氣が有るのです。愛は叔父の最後の呼吸です。私は叔父の精神を汲取って、お島を思ひ操を思
ふの情が一層深くなった。相手が同じ女だからと言って嫉むの恨むのといふ氣は毛頭起らない。吾儕が女を愛するのは——鳥
が鳥を戀ひ' 獸が獸を慕ふと同じなので、自分一己の私有物など、天の惠を考へるやうな、そんな偏見を抱いた男子は木曾
中に一人も無い。
して見ると、操の爺は——須永でもあり、叔父でもあり、又、私でもあるのです。
それ、叔父が治療室で手術を受けて居りました時に、夢中で『操、操』と呼びましたらう。其時になって、私も悉皆讀めた。
成程、思當ることが無いでも無い。叔母が長年の間病み煩って、一 と寢床を離れなかった事を憶出しました。叔父がお島を
愛して居て、今の夫へ嫁く時一通りならぬ心配をしてやった事まで憶出しました。
終夜、叔父は苦み悶えました。全く、私も途方に呉れて、空の白むのが待遠しかったことは、短い夏の夜とも思はれません
位。
暁の雨が病院の庭の紫陽花に降りそ、ぎました。
隱居を始め、須永、操、お島、お島の亭主、いづれも朝早くから詰妬ました。叔父とお島との關係を聞きましてからは、私は
一層あの女を憐むといふ心地になりましたのです。
掠鳥の群は鳥王の危篤と聞いて、いづれも病院に集りました。直腸の手術も、劇藥の注射もとうとう叔父の性命を救ふことが
出來なかったので、жて品川の海の潮が遠く沖のかなたに歸るといふ頃叔父の靈魂は永く眠りました。
ら、述懷を始めました。この古着屋は多少教育もあり、正直でもあるが、器用ゆゑに一生貧乏して居る男なので、私はこの人
の藏書が古びた新約全書と文章軌範と玉篇だといふことまで、熟く知って居るのです。
『僕は一つ懺悔話をしゃうかねえ。』と古着屋は乘出しました。
『君の懺悔話?君のやうな堅い人にも懺悔をすることが有るのかね。』と私は笑ひました。
『冗談言っちゃ不可。僕は毎日懺悔をしてる。え、僕だって木曾の人間ぢゃないか。』と古着屋は慾の無い聲で笑って、『ま
あ聞いて呉れ給へ。木曾の山の中から出て來て、僕ほど種々な事業をやった者も有るまいね。繪具屋の手代、紅製造業、紙漉
などから、朝鮮貿易と出掛け、歸って來て大阪で紀州炭を賣り、東京へ引越して來て先づ玻璃屋に雇はれ、其次が靴屋となっ
て洋傘屋を兼ね、それから岩代國黑森の鑛山監督、次に株式處仲買番頭かね。石嫌の製造職工ともなったし、針商ともなった
し、それから横濱へ行ったんだなあ。そのすこし前だけれど、電池製造の助手ともなりさ。再び復た針工商人となって、店を
やめてから、こんどは何に成ったか。まあ其も一つの何だ——煮染商と成った。
『えゝと、それから小學校事務員と成って、それが最後かなあ。いや、活版職工と成ったんだ。活版職工と成って、それか
らこんどは古着商と成った。其が最後だ。
『荒物屋もやったことが有るしなあ。
『靴屋をやってる時分に基督信者となったんです。基督信者となったのは、自分の子が死んで、その子の行先を確めんが爲に、
佛法では地獄極樂へ行くと言ふけれども、耶蘇ではどういふ處へ行くだらう、と基督を聞く氣になったんです。
『改宗は間もなくでしたよ。それから何ですねえ、パプテズマを受け、堅信禮を受けて、聖保羅敎會へ入って沈滌の禮を受け
た。沈滌の禮といふのは、ちょいと湯屋の舟見たやうなものねえ——あれが 造てあって、其處へ入るんです。僕もね、古
いになる。何度か私は切出さうとして、自分で自分の無法を制へました。
『操さん、君はすっかり私を忘れて了ったね。』
と誘をかけるやうに言へば、操は極り惡がって返事をしません。
『今夜は何か君の好なものを奢りませう。ねえ、君とは久し振だ。』
操は猶無言です。
『君、そんなに書生が遠慮するものぢゃ無いよ。言って見給へ、何でも君の好なものを。』
『 』
『さあ、行って氷でも飮まうぢゃないか。』
『あの……、』と操は小さくなって、すこし退却して、
ぷいと蚯出して行って了ひました。
私も手持無沙汰に引返した。歸って見れば線香の煙が夜の空氣に交って、家の内を朦朧とさせて居る。念佛の聲は盛に起つ
で、無宗敎な人々まで隨ひて唱へました。そのうちに十時過ぎ、十一時打ち、明治座も閉ね、往來の人通りも無くなって、隣
の肴屋も戸を閉め、向の紺屋も寐るやうになれば、木魚の音はいとヾ寂しさを增して來る。私は二三の掠鳥と例の小机を取
巻いて、雑談に耽りました。是ぞと言ってとりとめの無い話で、後で考へると茫然するやうなことばかり。尤も、木曾人は
斯ういふ談話をするのが得意でもあるのです。『此の叔父さんばかりぢゃない——今日東京の商人で、ちやんと店へかしこ
まって、賣揚許り勘定してるやうな、そんな間拔けがあって堪るものか。もし有ったら私は御目に懸りたいね。』など、言ひ
罵って居た男も、いっしか見えなくなる。叔父の何かに當る遠縁の者で、私も極懇意な古着屋はつくねんと小机の前に座り乍
『御父さんが先刻用が有るッて言ひましたから、僕は歸りますよ。』
まじ
•ノち たか
ら、述懷を始めました。この古着屋は多少教育もあり、正直でもあるが、器用ゆゑに一生貧乏して居る男なので、私はこの人
の藏書が古びた新約全書と文章軌範と玉篇だといふことまで、熟く知って居るのです。
『僕は一つ懺悔話をしゃうかねえ。』と古着屋は乘出しました。
『君の懺悔話?君のやうな堅い人にも懺悔をすることが有るのかね。』と私は笑ひました。
『冗談言っちゃ不可。僕は毎日懺悔をしてる。え、僕だって木曾の人間ぢゃないか。』と古着屋は慾の無い聲で笑って、『ま
あ聞いて呉れ給へ。木曾の山の中から出て來て、僕ほど種々な事業をやった者も有るまいね。繪具屋の手代、紅製造業、紙漉
などから、朝鮮貿易と出掛け、歸って來て大阪で紀州炭を賣り、東京へ引越して來て先づ玻璃屋に雇はれ、其次が靴屋となっ
て洋傘屋を兼ね、それから岩代國黑森の鑛山監督、次に株式處仲買番頭かね。石嫌の製造職工ともなったし、針商ともなった
し、それから横濱へ行ったんだなあ。そのすこし前だけれど、電池製造の助手ともなりさ。再び復た針工商人となって、店を
やめてから、こんどは何に成ったか。まあ其も一つの何だ——煮染商と成った。
『えゝと、それから小學校事務員と成って、それが最後かなあ。いや、活版職工と成ったんだ。活版職工と成って、それか
らこんどは古着商と成った。其が最後だ。
『荒物屋もやったことが有るしなあ。
『靴屋をやってる時分に基督信者となったんです。基督信者となったのは、自分の子が死んで、その子の行先を確めんが爲に、
佛法では地獄極樂へ行くと言ふけれども、耶蘇ではどういふ處へ行くだらう、と基督を聞く氣になったんです。
『改宗は間もなくでしたよ。それから何ですねえ、パプテズマを受け、堅信禮を受けて、聖保羅敎會へ入って沈滌の禮を受け
た。沈滌の禮といふのは、ちょいと湯屋の舟見たやうなものねえ——あれが 造 てあって、其處へ入るんです。僕もね、古
着屋を廢めて傳導師になれと言はれるんですが、傳導師といふものは信仰の高い人間がやるなら好けれど、我見たやうな傳
導の下手な者は駄目ですから。まあ實を結ぶ見込が無いから。自分に智慧の無いといふところを自覺して居ますからねえ。自
分の信仰丈は出來とるけれど、學力の有る者を支配して行かうといふ自覺が無いですから。
『えゝ、そりゃ、и落したことも有るさ。そりゃあ、もう屡々基督を見失ったことも有るさ。』
と思出したやうに震へて、さて話したのは——斯です。
古着屋の懺悔といふのは、矢張お島に關係したことでした。尤もこの男が叔父の家に居た時分は、廣い構でも有ったし、そ
れに叔父が部下の者を可愛がったところからして、この男も喜んで使はれて居たのです。古着屋に言はせると、あの操は——
また古着屋の子だ、と思ひ當ることが有るのださうでして、いよいよお島が嫁くと極った時、泣かれて弱ったといふこと迄、
悉皆物語りました。木曾男子はこれだから頼母しい。いかなる處へ流浪しても、いかなる生活を送って居ても、愛といふ旗印
は失ひません。
古着屋の顔には犯しがたい眞實が溢れて居て、眼は涙のために輝きました。他人の言ふことなら、いざ知らず、どうしてこ
の正直男の言葉を疑ふことが出來ませう。して見ると、お島は叔父と須永と私とに笑って見せた其同じ朱唇で、この無慾な古
着屋にも笑って見せたのです。
それにつけても私は思出したことが有る。吾儕の故郷では、斯ういふことは珍しくもない。吾儕が野の花のやうに女を思ふと
同じ道理で、あの手合は又、吾儕を蜜蜂のやうに心得て居る。あの手合は飯を食ふか、茶を飮むかのやうに、吾儕を愛して呉
れる。お島も都へ出てから、めっきり容姿が變りました。變るには變ったが、しかし其は外部です。内容は山家の姉妹と違
ふ筈がないのですから。
人にさまたげられて私共は話頭を轉へました。見れば其處此處に柱に凭れて睡って居る者もある。やがて古着屋も從弟の本箱
の傍に仆れて、疲勞の爲に正體もなくなりました。
短夜のことですから、一番鶏を聞いたは間も無くでした。鶏の鳴く音を聞いて、僧はまた讀經を始める、次第に明け放れて行
く空の光は靑白く家の内へ射しこんで、佛前の蝉燭ばかり力なげに燃りました。私も心は勞れる、身體は汗臭くなる、目は徹
夜の爲にしよぼしょぼする——そこに居た一人の年若な番頭を誘ひ合せて、ぶらぶら大河の方へ散歩に出掛けました。
私はこの番頭と一緒に濱町河岸を歩いたのです。柳の樹の蔭に立って隅田川を見れば、川の水は舊のやうに漾々と流れて、す
こし朝濁りのした波の面は黄に輝いて居りました。あそこの水泳場の側は叔父が釣をした處です。こ、の濡れた石は叔父が
腰を掛けた處です。爐の音をさせて深川へ下る幾艘の河舟は、まばゆい朝の光の中を流れるやうでした。脚氣患者は三々五々、
素足で岸の土を踏んで、私共の傍をあちこちと通る。
番頭といふのは叔父の金主に當る大店に奉公して居るので、私の書生時代には——未だほんの丁稚でした。
この男は思ひっ
いたやうに私の肩をた、いて、
『濱町に來てる子ねえ。君、あれはお島さんの子なんだよ。あの子についちゃあ大に歴史が有るんさ。』
『歴史が有る?』と私も釣られて、『君も何かあの子に關係があるのかね。』
『戯けちゃあ困りますぜ』と番頭は笑って、『僕もね、あの女の素振がどうも烏散臭いと思ったよ。母子だ。
た。見給へ、克く肖てること。』
『へえ、君もなかなか精しいねえ。』
『精しい譯が有るんさ。まああの子の爺は誰だか當て、見給へ。』
・ノさんくさ
それで悉皆解っ
『極ってらあね。須永サ。そんなに幾人も爺が有って堪るものか。』
『ところが、御氣の毒さま。』と番頭はくすくす思出し笑をして、『ホラ、由どんてのが僕の前に帳塲をして居ましたらう。
ちょいと色の白い ネ。』
『むゝ、居た、居た。』
『でせう、由どんが平素めかして居ましたらう。彼の子の容貌がかうどこか由どんに似てませう。は、ゝ、、ゝ、。と言っ
たやうな譯なんさ。』
私は是男が戯れて言ふとも思へなかった。
お島は香の高い夏の花です。是程澤山な蜜蜂がその香を慕って集ったことは、この出京で始めて知りました。吾儕は寄って群
って、お島のために一個の活きた紀念を作ったやうなものです。お島にもし操といふものが無かったなら、あの 佛は誰が傳
へやう。繪は物言ふぢゃなし、彫刻は冷たい石に過ぎない。お島自身ですら今は凋落して、昔の色香は花のやうに消失せて了
った。
『お島さん萬歳。』
と歡呼を揚げて、二人笑ひ乍ら引返しました。
其日の九時頃には、會葬の爲に集った人々が濱町の往來を埋めましたのです。叔父の亡骸を納めた寢棺は住み慣れた軒の下を
舁がれて出ました。數十臺の車が其後から續いたのを見ても、叔父の交際が多方面で、しかも深く惜まれたことが分る。須永
も、古着屋も、番頭も、操も、私も、徒歩で隨ひました。隱居は門口に泣仆れるばかりになって、お島の肩に取縄りながら見
送りました。芝の山内へさしかゝりました頃、私は操と一緒になりました。不圖、私は斯ういふ問をかけて見た。
『操さん、君はあのおаといふ女に何か縁故が有るの。』
すると操は振返って、
『お島ですか。れは元、僕の家に居た下女なんです。』
その調子がいかにも邪氣なかった。この可憐な少年の羽織袴、
と——私はお島を思出さずに居られませんのでした。實際、吾儕は畫エや彫刻家よりも大な事業を爲たのです。
杓さ•ソらМよ しか•ソ はしゃい
白足袋麻裏穿といふ黠裁で、乾燥だ土を踏んで行く後姿を見る
ゑかよ НПА- しごと
「無言の人」
麹町の見附内にある敎會堂では、質素な弔ひの儀式が濟んだ。風琴の前に腰掛けて居た婦人は讚美歌の譜を閉ぢて、元の
席に戻った。親戚一同の代りとして起った人が、會葬者の方へ向いて、丁寧に挨拶し、猶墓地は靑山であるけれども、遠方の
ことでもあり、見送りは御斷りする'それが親戚一同よりの願ひであると述べた。
黑い布を掛け、二つの花輪を飾った寢棺はアルタアの下に置いてあった。その中には肺病で亡くなった耶蘇信徒の遺骸が納
めてあった。やがて寢棺は牧師や友人などに前後左右を持ち支へられて、中央の腰掛椅子の間を通り、壁に添うて會堂の出入
ロの方へ運ばれて行った。
斯の寢棺に手を掛けて行った二人の男が引返して來ると、灰色な壁のところには一人の仲間も立って居た。斯の三人は亡く
なった信徒の舊友で、一緒に同じ學校を卒業したのは二十一年も前に當った。
『吾儕の仲間はこれだけかい。』
と一人が言って、同窓の友達を探すやうな眼附をした。
『誰かまだ見えさうなものだ。』
と他の一人も言った。
會葬の爲に集った人達は思ひ思ひに散じつ、あった。しばらく三人の舊友は會堂の内に殘って、歸り行く信徒の群などを眺
めて立って居た。二階棧敷風に出來た柱の下の方から來て、三人の立って居るところに近づいたのは、親戚の代りに挨拶を述
べた人だ。以前の學校の幹事さんだ。
『遠藤も可哀さうなことをしました。』
幹事さんは三人に挨拶した後で、亡くなった信徒のことを言った。
『遠藤さんは子供は幾人あったんですか。』と一人が尋ねた。
『四人』
と幹事さんは言って見せて、『後がすこし困るテ』といふ言葉を殘しながら、三人に別れて行った。
『一寸、牧師さんに挨拶して來るか。』
と一人は言出した。
牧師は風琴の置いてある方に手を拱いて腰掛けて居た。亡くなった人の爲には、極く若い學生時代に敎を説いて聞かせる
から、今また弔ひの説敎までして面倒を見た牧師だ。舊友等は連立って挨拶に行った。
『先生、私の顔が御分りになりますか。』
『え、分ります。』
と牧師も笑って挨拶した。
三人が歸りかけた頃は、會葬者は大抵出て行って了った。人氣の少い會堂の建物だけ殘った。正面にある尖ったアーチ風の
飾、高い壁、質素なアルタア、すべてまだ割合に新しく見えて心地の好いペンキの色で塗った柱と柱の間には澤山掛椅子が
並べてある。模倣の様式で成り立って居るやうな建物の内部には左右の壁に瀟洒な梯子などを渡して、新意を加味したところ
も有った。窓々に射す五月の光線はアルタアの横にある大きな花瓶の花や葉に映って、高い天井の下を靜かに見せた。一方の
出入口に近い壁の側には、信徒らしい二人の女が並んで立って居た。こゝは亡くなった遠藤が生前來てはよく腰掛けたところ
だ。
早や棺も墓地の方へ舁がれて行った後だ。會堂の前には車に乘らうとする女連が殘って居た。三人は一緒に石階を降りた。
かうむ г\ 垛つけ •ソち
靑山まで行かうといふものも有ったが、そこで御免蒙って、三人とも見附をさして歩いた。久し振で一人の仲間の家の方
へ誘はれて行った。
『何年振で會堂へ來て見たか……矢張會堂の内は靜で好いネ。』
『僕も復た來やうかナ。』
『あの敎會は、僕が以前籍を置いたとこだ。』
『君は左様だっけネ。』
『兎に角、靜かな場所の一つだよ……人が居ないと、猶好い……』
話し話し行くうちに、三人は舊い見附跡に近い空地のところへ出た。風の多い塵埃の立つ日で、黄ばんだ煙が渦を巻いてや
って來る。其度に三人は背中をそむけて、塵埃の通り過ぎるのを待った。
蒸々と熱い日あたりは三人の眼にあった。牧師がアルタアの上で讀んだ遠藤の畧傳——四十五年の平凡な人の人生——互い
にその舊友のことを思ひながら、城下らしい地勢の殘ったところについて、緩慢な坂の道を靜かに上って行った。
『先刻の説敎も惜しいことに、終の方へ行ってすこし誇張した氣味だネ。』
『でも。まだ彼の牧師だから、あれだけに厭味がなу聞かせるんだよ。下手な牧師と來て見給へ——貴方がたも敎を信じて
置かないと、斯う成りますよ。左様いふ調子だ。』
『牧師も彼様なれば立派なものだ。感心した。矢張年を取らんけりゃ駄目だネ。』
『今日は、あまり説敎などを聞きたくなかった。もっと僕は悼むやうな言葉でも聞きたかった:::吾家からやって來る途中
では、しきりに遠藤君の死んだことを考へたつけが、會堂へ入ってから反って其様な心が起らなかった……』
』 \
祈祷だよ……あれで、敎會の内がもっと樹蔭のやうな淸しい氣分のするとこ
『一體、あの祈祷といふものは變なものだネ。
『しかし會堂へ行って一番聞いて見たいのは、
ろだったら好からうと思ふネ。』
『左様あるべき性質のものだらう。』
同じ會堂でも、簡素を重んずる新敎の方と、
との比較などをして、それを佛敎の寺院に宛嵌めて見たり、中世の敎會を引合に出したりして、思ひ思ひのことを話して行く
三人は長い坂の道を餘程上つた。
僕が吾家から出掛けて來ると、丁度御濠端のところで皆なに遭遇した。僕は棺に隨いて會堂までやって行った。』
さう 』
人の官能に訴へる部分の多い、色彩とか音樂とか、香料とかに富んだ舊敎の方
うちに、
『先刻、
『アヽ、
『面白い話がある。一體' 君と僕とは何方が宗敎に返るポッシビリチイが有るだらう、とк君が聞くからネ——遠藤の許で
一緒に成った時の話サ——そりゃ僕の方が有ます、と言ったサ。』
『さあねえ……』
『するとк君が、「左様ですか、私共から見ると丁度反對に考へられます」ッて……何故と言ふに、君は耶蘇敎を惡く言ふ
が、僕は好いとも惡いとも言はない……惡く言ふだけ、まだ君の方には脈が有るかと思ふとサ……』
何時の間にか土手の向ふに靑葉まじりの町々を望むところへ出た。
『吾儕のクラスでは、最早幾人亡くなってる?』
『二十人の卒業生の中が、四人缺けて居たんだらう。遠藤君を入れて五人目だ。』
『まだ誰か死んでやしないか。もっと居ない様な氣がするぜ。V
『この次は誰の番だらう。』
『さあ……』
暫時、三人は默って歩いた。
『この三人の中ぢゃ、一番先へ僕が行きさうだ。』
『いや僕の方が怪しい。』
『ナニ、君は大丈夫だよ。僕こそー番先かも知れない。』
『ところがネ、僕はマヰるものなら、斯の一二年にマヰって了ひさうな氣がする
っと長く生きられるかも知れないが……』
復た煙のやうな風塵が恐しくやって來た。三人は口の中がヂヤリヂヤリするほど、砂を浴びた。
斯の人達はある見附跡を越して、一層塵埃の舞ひ揚る濠端へ出た。そこまで行くと、仲間の一人の家に近かった。
無事にこゝのところを通り越せば、ず
『葬式の歸りがけに押掛けるなんて。』
『いや、どうして¬—斯うして揃って來て貰ふことは、めったに無い。』
斯様なことを言ひ合って、やがて三人は眺めのある二階の座敷に寛いだ。今迄歩いて來た土手のつヾきは反對にそこから
望むことが出來る。遠見の草は靑々として心地が好い。
『遠藤君などと一緒に學校を出た時分——あの頃は、何か面白さうな事が先の方に待ってるやうな氣がしたよ
居るのが、是が君、人生かねえ……』
『左様サ、是が人生だ。僕は左様思ふと變な氣のすることがあ勺』
『もうすこし奈様かいふことは無いものかナア。』
『そんなに面白いことが有ると思ふのが、間違ひだよ。』
『ツマラない。』
『ツマラないと言へば、誰だって君、ツマラないさ。』
『眞實にツマラない。どうしても斯の儘ぢや、僕には死に切れない。』
『ラブでも始めるサ。』
『何か面白い話でもしょうぢゃないか。』
と言って、それから一人が次のやうな話を始めた。
斯うして
ある海岸の寺院のことだ、長いことそこの部屋を借りて數學を勉強して居た男があった。寺院には、和尚さんに、大黑さん
に、それから娘が二人もあった。皆な質朴な、い人達だから長く居るうちに男はすっかり懇意に成って、寺院のものも同様
に思はれるほど親しくした。
男も質朴な、好い人だった。毎年極りで數學の試驗を受けに都會の方へ出掛けて、歸って來ては復た寺院に籠って勉強した。
早いもので、和尚さんの娘は二人とも相應な年頃に成るし、姉さんの方などはウッカリすると最早お嫁に行き損ふ位の年に
成った。ある夏のこと、男は例のやうに試驗を受けに出掛けたが、不思議にも口の利けない人に成って歸って來た。
奈何したといふんだらう。と和尚さん始め寺院の人達は呆れた。和尚さんは考へた。いづれ數學にでも凝り過ぎて斯様なこ
とに成ったに相違ない。そこで、紙と筆を渡して、男に書かせて見ると、全く口の利けないといふことが解った。姉娘などは
悲しがって、男の勉強して居る部屋へ行って見るが、言葉といふものは一語も聞かれなかった。
斯の無言な人は時々海岸の方へ走って行って、遠く寺院を離れて、誰も知った人の居ない砂山へ駆け上り、松林の間へでも
出ると、そこで思ふさま大きな聲を出して叫んだ。男は砂山を下りて、復た岸づたひに口の利けない人に成って寺院の方へ戻
った。
ある日も、男は沈默の苦痛に堪へられなく成った。寺院のある漁村から一里ばかり離れて、同じ海岸に可成賑かな湊町が
ある。そこに面白い、隱れた田舎醫者が有る——そんな田舎には過ぎた人だと言はれる位——書生の好きな、よく若いもの、
世話をするやうな人物だから、自然と男もその醫者に知られて、有望な靑年と思はれて居た。斯の田舎醫者は何でもやるやう
な人だった。鶏も飼ふ、野菜も造る、菊も植ゑる、學門も相應にあって、聞けば和算のことなども知って居る、そこへ男が訪
ねて行った。丁度醫者は病家廻りに出掛けた留守だったから、細君や子供を相手にして、草臥れるほど種々と喋舌り續けて歸
った。
寺院の大黑さんが湊町の醫者の家へ寄ったことがあった。男の噂が出た。S者の細君は何事も知らないから、男が來て、い
ろいろな話をして行ったことを告げた。口の利けない人だとばかり思って居た、と大黑さんは非常に立腹して、早速寺院へ歸
り、そのことを和尚さんにも姉娘にも告げた。
0
到頭、男は寺院にも居られないやうに成った。湊町の醫者の許へやって行った、何故、そんなトボけた眞似をした、と醫
者が聞いたら、男も實に正直な人で、書生らしく頭を搔いた。斯の男の答は、堅い、質朴な性質をよく顯はした。和尚さん始
め大黑さんでも、姉娘でも、寺院の人達の眼は物を言って困ったから……
亡くなった舊友の噂は、斯様な話の後で、復た三人の間に引出されて行った。
『何か遠藤君の置いて行ったやうな話は無いかねえ。
『さうさ……別に是と言って、置いて行ったやうな話も無かったナ……』
夏目漱石
「夢十夜」
第一夜
こんな夢を見た。
腕組をして枕元に坐ってゐると、仰向に寝た女が、靜かな聲でもう死にますと云ふ。女は長い髪を枕に敷いて、輪廓の柔
らかな瓜實顔をその中に横たへてゐる。眞白な頰の底に温かい血の色がほどよく差して、唇の色は無論赤い。到底死にさうに
は見えない。しかし女は靜かな声で、もう死にますと判然云った。自分も確に是れは死ぬなと思った。そこで、さうかね、
もう死ぬのかね、と上から覗き込む樣にして聞いて見た。死にますとも、と云ひながら、女はぱっちりと眼を開けた。大きな
潤のある眼で、長い睫に包まれた中は、只一面に眞黑であった。その眞黑な眸の奥に、自分の姿が 鮮に浮かんでゐる。
自分は透き徹るほど深く見える此の黑眼の色澤を眺めて、是でも死ぬのかと思った。それで、ねんごろに枕の傍へ口を付け
て、死ぬんぢゃなからうね、大丈夫だらうね、と又聞き返した。すると女は黑い眼を眠さうに瞠た儘、矢張り靜かな聲で、
でも、死ぬんですもの、仕方がないわと云った。
ぢや、私の顔が見えるかいと一心に聞くと、見えるかいって、そら、そこに、寫ってるぢゃありませんかと、にこりと笑
って見せた。自分は默って、顔を枕から離した。腕組をしながら、どうしても死ぬのかなと思った。
しばらくして、女が又かう云った。
「死んだら、埋めて下さい。大きな眞珠貝で穴を掘って。さうして天から落ちて來る星の破片を墓標に置いて下さい。さう
して墓の傍に待ってゐて下さい。又逢ひに来ますから」
自分は、何時逢ひに來るかねと聞いた。
「日が出るでせう。それから日が沈むでせう。それから又出るでせう、さうして又沈むでせう。——赤い日が東から西へ'
東から西へと落ちて行くうちに、——あなた、待ってゐられますか」
自分は默って首肯た。女は靜かな調子を一段張り上げて、
「百年待ってゐて下さい」と思ひ切た聲で云った。「百年、私の墓の傍に坐って待ってゐて下さい。屹度逢ひに來ますから」
自分は只待ってゐると答へた。すると、黑い眸のなかに鮮に見えた自分の姿が、ぼうっと崩れて來た。靜かな水が動い
て寫る影を亂した樣に、流れ出したと思ったら、女の眼がぱちりと閉ぢた。長い睫の間から涙が頰へ垂れた。——もう死ん
で居た。
自分は夫れから庭へ下りて、眞珠貝で穴を掘った。眞珠貝は大きな滑かな縁の鋭どい貝であった。土をすくふ度に、貝の
裏に月の光が差してきらきらした。濕った土の匂もした。穴はしばらくして掘れた。女を其の中に入れた。さうして柔らかい
土を、上からそっと掛けた。掛ける毎に眞珠貝の裏に月の光が差した。
それから星の破片の落ちたのを拾って來て、かろく土の上へ乘せた。星の破片は丸かった。長い間大空を落ちてゐる間に、
角が取れて滑かになつたんだらうと思った、抱き上げて土の上へ 置くうちに、自分の胸と手が少し暖くなった。
自分は苔の上に坐った。是から百年の間かうして待ってゐるんだなと考へながら、腕組をして、丸い墓石を眺めてゐた。そ
のうちに、女の云った通り日が東から出た。大きな赤い日であった。それが又女の云った通り、やがて西へ落ちた。
までのっと落ちて行った。一っと自分は勘定した。
しばらくすると又唐紅の天道がのそりと上って來た。さうして默って沈んで仕舞った。二っと又勘定をした。
赤いまん
自分はかう云ふ風に一つ二っと勘定して行くうちに、赤い日をいくつ見たか分らない。勘定しても、勘定しても、
ないほど赤い日が頭の上を通り越して行った。それでも百年がまだ來ない。仕舞には、苔の生えた丸い石を眺めて、
に欺されたのではなからうかと思ひ出した。
すると石の下から斜に自分の方へ向いて青い莖が伸びて來た。見る間に長くなって丁度自分の胸のあたり迄來て留まった。
と思ふと、すらりと搖ぐ莖の頂に、心持首を傾けてゐた細長い一輪の蕾が、ふっくらと瓣を開いた。眞白な百合が鼻の
先で骨に徹へる程匂った。そこへ遥の上から、ぽたりと露が落ちたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を
前へ出して冷たい露の滴る、白い花瓣に接吻した。自分が百合から顔を離す拍子に思はず、遠い空を見たら、曉 の星がた
った一つ瞬いてゐた。
しっくせ
自分は女
「百年はもう來てゐたんだな」と此時始めて氣が付いた。
第二夜
こんな夢を見た。
和尚の室を退がって、廊下傳ひに自分の部屋へ歸ると行燈がぼんやり點ってゐる。片膝を座蒲團の上に突いて、燈心を搔き
立てたとき、花の樣な兆子がぱたりと朱塗の臺に落ちた。同時に部屋がぱっと明かるくなった。
ふすま ぶそん をちこち \ かたふ とこ かい
襖の畫は蕪村の筆である。黑い柳を濃く薄く、遠近とかいて、寒むさうな漁夫が笠を傾けて土手の上を通る。床には海
中文殊の軸が懸ってゐる。焚き殘した線香が暗い方でいまだに臭ってゐる。廣い寺だから森閑として、人氣がない。黑い天井
に差す丸行燈の丸い影が、仰向く途端に生きてる樣に見えた。
立膝をした儘、左の手で座蒲團を捲って、右を差し込んで見ると、思った所に、ちゃんとあった。あれば安心だから、蒲團
をもとの如く直して、其上にどっかり坐った。
お前は侍である。侍なら悟れぬ筈はなからうと和尚が云った。さう何日迄も悟れぬ所を以て見ると、御前は侍ではあるま
いと言った。人間の屑ぢゃと云った。は、あ怒ったなと云って笑った。口惜しければ悟った證據を持って來いと云ってぷいと
向ふをむいた。怪しからん。
隣の廣間の床に据ゑてある置時計が次の刻を打つまでには、屹度悟って見せる。悟った上で、今夜又入室する。さうして和
尚の首と悟りと引替にしてやる。悟らなければ、和尚の命が取れない。どうしても悟らなければならない。自分は侍である。
もし悟れなければ自刃する。侍が辱しめられて、生きて居る譯には行かない。奇麗に死んで仕舞ふ。
かう考へた時、自分の手は又思はず布團の下へ這入った。そうして朱鞘の短刀を引き摺り出した。ぐっと束を握って、赤い
鞘を向へ拂ったら、冷たい刃が、一度に暗い部屋で光った。凄いものが手元から、すうすうと逃げて行く樣に思はれる。さ
うして、悉く切先へ集まって、殺氣を一點に籠めてゐる。自分は此の鋭い刃が、無念にも針の頭の樣に縮められて、九寸五
分の先へ來て己を得ず尖ってるのを見て、忽ちぐさりと遣り度なった。身體の血が右の手首の方へ流れて來て、握ってゐる束
がにちゃにちゃする。唇が顫えた。
短刀を鞘へ収めて右脇へ引きつけて置いて、それから全伽を組んだ。——趙州云く無と。無とは何だ。糞坊主めと齒嚙を
した。 ゝ
奥歯を強く咬み締めたので、鼻から熱い息が荒く出る。米嚙が釣って痛い。眼は普通の倍も大きく開けてやった。
懸物が見える。行燈が見える。疊が見える。和尚の藥«頭がありありと見える。鰐口を開いて嘲笑った聲まで聞える。怪
しからん坊主だ。どうしてもあの藥鐘を首にしなくてはならん。悟ってやる。無だ、無だと舌の根で念じた。無だと云ふのに
矢つ張り線香の香がした。何だ線香の癖に。
自分はいきなり拳骨を固めて自分の頭をいやと云ふ程擲った。さうして奥齒をぎりぎりと«んだ。兩腋から汗が出る。背
中が棒の樣になった。膝の接目が急に痛くなった。膝が折れたってどうあるものかと思った。けれども痛い。苦しい。無は中々
出て來ない。出て來ると思ふとすぐ痛くなる。腹が立つ。無念になる。非常に口惜しくなる。涙がほろほろ出る。一と思に
身を巨巌の上に打けて、骨も肉も滅茶々々に碎いて仕舞ひたくなる。
それでも我慢して凝と坐ってゐた。堪へがたい程切ないものを胸に盛れて忍んでゐた。其切ないものが身體中の筋肉を下か
ら持上げて、毛穴から外へ吹き出やう吹き出やうと焦るけれども、何處も一面に塞がって、丸で出口がない樣な殘刻極まる状
態であった。
其の内に頭が變になった。行燈も蕪村の畫も、疊も、違棚も有って無い樣な、無くって有る樣に見えた。と云って無はち
っとも現前しない。たヾ好加減に坐ってゐた樣である。所へ忽然隣座敷の時計がチーンと鳴り始めた。
はっと思った。右の手をすぐ短刀にかけた。時計が二つ目をチーンと打った。
第三«
こんな夢を見た。 、
六つになる子供を負ってる。愷に自分の子である。只不思議な事には何時の間にか眼が潰れて、靑坊主になってゐる。自
分が御前の眼は何時潰れたのかいと聞くと、なに昔からさと答へた。聲は子供の聲に相違ないが、言葉つきは丸で大人である。
しかも對等だ。
左右は靑田である。路は細い。鷺の影が時々闇に差す。
「田圃へ掛かったね」と脊中で云った。
「どうして解る」と顔を後ろへ振り向ける樣にして聞いたら、
「だって鷺が鳴くぢゃないか」と答へた。
すると鷺が果して二聲程鳴いた。
自分は我子ながら少し怖くなった。こんなものを脊負ってゐては、この先どうなるか分らない。どこか打遣やる所はなから
うかと向ふを見ると闇の中に大きな森が見えた。あすこならばと考へ出す途端に、脊中で、
「ふ、ん」と云ふ聲がした。
「何を笑ふんだ」
子供は返事をしなかった。只
「御父さん、重いかい」と聞いた。
「重かあない」と答へると
「今に重くなるよ」と云った。
自分は默って森を目標にあるいて行った。田の中の路が不規則にうねって中々思ふ樣に出られない。しばらくすると二股に
なった。自分は股の根に立って、一寸休んだ。
「石が立ってる筈だがな」と小僧が云った。
成程ハ寸角の石が腰程の高さに立ってゐる。表には左り日ヶ窪、右堀田原とある。闇だのに赤い字が明かに見えた。赤い字
は井守の腹の樣な色であった。
「左が好いだろう」と小僧が命令した。左を見ると最先の森が闇の影を、高い空から自分等の頭の上へ抛げかけていた。自分
は一寸躊躇した。
「遠慮しないでもいゝ」と小僧が又云った。自分は仕方なしに森の方へ歩き出した。腹の中では、よく盲目の癖に何でも知っ
てるなと考へながら一筋道を森へ近づいてくると、脊中で、「どうも盲目は不自由で不可いね」と云った。
「だから負ってやるから可いぢゃないか」
「負ぶって貰って濟まないが、どうも人に馬鹿にされて不可い。親に迄馬鹿にされるから不可い」
何だか厭になった。早く森へ行って捨て、仕舞ふと思って急いだ。
「もう少し行くと解る。——丁度こんな晩だったな」と脊中で獨言の樣に云ってゐる。
「何が」と際どい聲を出して聞いた。
「何がって、知ってるぢゃないか」と子供は嘲ける樣に答へた。すると何だか知ってる樣な氣がし出した。けれども判然とは
分らない。只こんな晚であった樣に思へる。さうしてもう少し行けば分るように.思へる。分っては大變だから、分らないうち
に早く捨て、仕舞って、安心しなくってはならない樣に思へる。自分は益 足を早めた。
雨は最先から降ってゐる。路はだんだん暗くなる。殆んど夢中である賃脊中に小さい小僧が食付いてゐて、其の小僧が自
分の過去、現在、未来を悉く照して、寸分の事實も洩らさない鏡の樣に光ってゐる。しかもそれが自分の子である。さうし
て盲目である。自分は堪らなくなった。
「此處だ、此處だ。丁度其の杉の根の處だ」
雨の中で小僧の聲は判然聞えた。自分は覺えず留った。何時しか森の中へ這入てゐた。一間ばかり先にある黑いものは®
に小僧の云ふ通り杉の木と見えた。
「御父さん、其の杉の根の處だったね」
「うん、さうだ」と思はず答へて仕舞った。
「文化五年辰年だろう」
成程文化五年辰年らしく思はれた。
「御前がおれを殺したのは今から丁度百年前だね」
自分は此の言葉を聞くや否や、今から百年前文化五年の辰年のこんな闇の晩に、此の杉の根で、一人の盲目を殺したと云ふ自
覺が、忽然として頭の中に起った。おれは人殺であったんだなと始めて氣がついた途端に、脊中の子が急に石地藏の樣に重
くなった。
第四夜
廣い土間の眞中に涼み臺の樣なものを据ゑて、其周圍に小さい床几が並べてある。臺は黑光りに光ってゐる。片隅には四角
な膳を前に置いて爺さんが一人で酒を飮んでゐる。肴は煮しめらしい。 (
爺さんは酒の加減で中々赤くなってゐる。其の上顔中澤々して皺と云ふ程のものはどこにも見當らない。只白い髯をありた
け生やしてゐるから年寄と云ふ事丈は別る。自分は子供ながら、此の爺さんの年は幾何なんだろうと思った。所へ裏の寛か
ら手桶に水を汲んで來た神さんが、前垂で手を拭きながら、
「御範さんは幾年かね」と聞いた。爺さんは頰張った煮Xを呑み込んで、
「幾年か忘れたよ」と澄ましてゐた。神さんは拭いた手を、細い帶の間に挟んで横から爺さんの顔を見て立ってゐた。爺さん
は茶碗の樣な大きなもので酒をぐいと飮んで、さうして、ふうと長い息を白い髯の間から吹き出した。すると神さんが、
「御爺さんの家は何處かね」と聞いた。爺さんは長い息を途中で切って、
「臍の奥だよ」と云った。神さんは手を細い帶の間に突込んだ儘、
「どこへ行くかね」と又聞いた。すると爺さんが、又茶碗の樣な大きなもので熱い酒をぐいと飮んで、前の樣な息をふうと吹
いて、
「あっちへ行くよ」と云った。
「眞直かい」と神さんが聞いた時、ふうと吹いた息が、障子を通り越して柳の下を抜けて、河原の方へ眞直に行った。
爺さんが表へ出た。自分も後から出た。爺さんの腰に小さい瓢箪がぶら下がってゐる。肩から四角な箱を腋の下へ釣るして
ゐる。淺黄の股引を穿いて、淺黄の袖無しを着てゐる。足袋丈が黄色い。何だか皮で作った足袋の樣に見えた。
爺さんが眞直に柳の下迄來た。柳の下に子供が三四人居た。爺さんは笑ひながら腰から淺黄の手拭を出した。それを肝心絢
の樣に細長く絢った。さうして地面の眞中に置いた。それから手拭の周®12、大きな丸い輪を描いた。しまいに肩にかけた箱
の中から眞鑰で製らえた飴屋の笛を出した。 )
「今に其の手拭が蛇になるから、見て居らう。見て居らう」と繰返して云った。
子供は一生懸命に手拭を見て居た。自分も見て居た。
「見て居らう、見て居らう。好いか」と云ひながら爺さんが笛を吹いて、輪の上をぐるぐる廻り出した。自分は手拭許り見て
いた。けれども手拭は一向動かなかった。
爺さんは笛をぴいぴい吹いた。さうして輪の上を何遍も廻った。草鞋を爪立てる樣に、拔足をする樣に、手拭に遠慮をする
樣に、廻った。怖さうにも見えた。面白さうにもあった。
やがて爺さんは笛をぴたりと己めた。さうして、肩に掛けた箱の口を開けて、手拭の首を、ちょいと撮んで、ぽっと放り込
んだ。
「かうして置くと、箱の中で蛇になる。今に見せてやる。今に見せてやる」と云ひながら、爺さんが眞直に歩き出した。柳の
下を拔けて、細い路を眞直に下て行った。自分は蛇が見たいから、細い道を何處までも追いて行った。爺さんは時々「今にな
る」と云ったり、「蛇になる」と云ったりして歩いて行く。仕舞には、
「今になる、蛇になる、
屹度なる、 笛が鳴る、」
と唄ひながら、とうとう河の岸へ出た。橋も舟もないから、此處で休んで箱の中の蛇を見せるだらうと思ってゐると、爺さん
はざぶざぶ河の中へ這入り出した。始めは膝位の深さであったが、段々腰から、胸の方迄水に浸って見えなくなる。それでも
爺さんは
「深くなる、夜になる、
眞直になる」
と唄ひながら、どこ迄も眞直に歩いて行った。さうして髯も顔も頭も頭巾も丸で見えなくなって仕舞った。
自分は爺さんが向岸へ上がった時に、蛇を見せるだらうと思って、蘆の鳴る所に立って、たった一人何時迄も待ってゐた。
けれども爺さんは、とうとう上がって來なかった。
第五夜
こんな夢を見た。
何でも餘程古い事で、神代に近い昔と思はれるが、自分が軍をして運惡く敗北た爲に、生擒になって、敵の大将の前に引
き据ゑられた。
其の頃の人はみんな脊が高かった。さうして、みんな長い髯を生やしてゐた。革の帶を締めて、それへ棒の樣な劎を釣る
してゐた。.弓は藤蔓の太いのを其の儘用ひた樣に見えた。漆も塗ってなければ磨きも掛けてない。極めて素樸なものであっ
た。
©
敵の大將は、弓の眞中を右の手で握って、其弓を草の上へ突いて、酒甕を伏せた樣なものゝ上に腰を掛けてゐた。其顔を見
ると、鼻の上で、左右の眉が太く接續ってゐる。其頃髪剃と云ふものは無論なかった。
自分は虜だから、腰を掛ける譯に行かない。草の上に胡坐をかいてゐた。足には大きな藁沓を穿いてゐた。此の時代の藁
沓は深いものであった。立つと膝頭迄來た。其の端の所は藁を少し編殘して、房の樣に下げて、歩くとばらばら動く樣にし
わらぐつ
て、飾りとしてゐた。
大將は篝火で自分の顔を見て、死ぬか生きるかと聞いた。其れは其の頃の習慣で、捕虜にはだれでも一應はかう聞いたもの
である。生きると答へると降參した意味で、死ぬと云ふと屈服しないと云ふ事になる。自分は一言死ぬと答へた。大將は草の
上に突いてゐた弓を向ふへ抛げて、腰に釣るした棒の樣な劎をするりと拔き掛けた。それへ風に靡いた篝火が横から吹きつけ
た。自分は右の手を楓の樣に開いて、掌を大將の方へ向けて、眼の上へ差し上げた。待てと云ふ相圖である。大將は太い
劎をかちゃりと鞘に收めた。
其の頃でも戀はあった。自分は死ぬ前に一目思ふ女に逢ひたいと云った。大將は夜が開けて鶏が鳴く迄なら待っと云った。
鶏が鳴く迄に女を此處へ呼ばなければならない。鶏が鳴いても女が來なければ、自分は逢はずに殺されて仕舞ふ。
大將は腰を掛けた儘、篝火を眺めてゐる。自分は大きな藁沓を組み合はした儘、草の上で女を待ってゐる。夜は段々更ける。
時々篝火が崩れる音がする。崩れる度に狼狽た樣に焰が大將になだれか、る。眞黒な眉の下で、大將の眼がぴかぴかと光っ
てゐる。すると誰やら來て、新しい枝を澤山火の中へ抛げ込んで行く。しばらくすると、火がぱちぱちと鳴る。暗闇を彈き返
すような勇ましい音であった。
此時女は、裏の猶の木に繋いである、白い馬を引き出した。熬を三度撫で、高い脊にひらりと飛び乘った。鞍もない鎧
もない裸馬であった。長く白い足で、太腹を蹴ると、馬は一散に駆け出した。誰か•ゝ篝りを繼ぎ足したので' 遠くの空が薄
明るく見える。馬は此の明るいものを目懸けて闇の中を飛んで來る。鼻から火の柱の樣な息を二本出して飛んで來る。それで
も女は細い足でしきりなしに馬の腹を蹴てゐる。馬は蹄の音が宙で鳴るほど早く飛んで來る。女の髪は吹流しの樣に闇の中
に尾を曳いた。それでもまだ篝のある所迄來られない。
すると眞闇な道の傍で、忽ちこけこっこうという鶏の聲がした。女は身を空様に、兩手に握った手綱をうんと控へた。馬は
前足の蹄を堅い岩の上に發矢と刻み込んだ。
こけこっこうと鶏がまた一聲鳴いた。
女はあっと云って、緊めた手綱を一度に緩めた。馬は諸膝を折る。乘った人と共に眞向へ前へのめった。岩の下は深い淵で
あった。
蹄の跡はいまだに岩の上に殘って居る。鶏の鳴く眞似をしたものは天探女である。この蹄の痕の岩に刻みつけられてゐる
間、天探女は自分の敵である。
第六夜
運慶が護國寺の山門で仁王を刻んでゐると云ふ評判だから、散歩ながら行って見ると、自分より先にもう大勢集まって、し
きりに下馬評をやってゐた。
山門の前五六間の所には、大きな赤松があって、其幹が斜めに山門の«を隱して、遠い青空迄伸びて居る。松の綠と朱塗
の門が互ひに照り合って美事に見える。其の上松の位地が好い。門の左の端を眼障にならない樣に、斜に切って行って、上に
なる程幅を廣く屋根迄突出してゐるのが何となく古風である。鎌倉時代とも思はれる。
所が見て居るものは、みんな自分と同じく、明治の人間である。其の中でも車夫が一番多い。辻待をして退屈だから立って
ゐるに相違ない。
「大きなもんだなあ」と云ってゐる。
「人間を捋 へるよりも餘つ程骨が折れるだらう」とも云ってゐる。
さうかと思ふと、「へえ仁王だね。今でも仁王を彫るのかね。へえさうかね。私や又仁王はみんな古いのばかりかと思って
た」と云った男がある。
「どうも強さうですね。なんだってえますぜ。昔から誰が強いって、仁王程強い人あ無いって云ひますぜ。何でも日本武尊
よりも強いんだってえからね」と話しかけた男もある。此の男は尻を端折って、帽子を被らずにゐた。餘程無敎育な男と見え
る。
運慶は見物人の評判には委細頓着なく鑿と槌を動かしてゐる。一向振り向きもしない。高い所に乘って、仁王の顔の邊を
しきりに彫り拔いて行く。
運慶は頭に小さい烏帽子の樣なものを乘せて、素袍だか何だ別らない大きな袖を脊中で括ってゐる。其の樣子が如何にも古
くさい。わいわい云ってる見物人とは丸で釣り合が取れない樣である。自分はどうして今時分迄運慶が生きてゐるのかなと思
った。どうも不思議な事があるものだと考へながら、矢張り立って見てゐた。
然し運慶の方では不思議とも奇體とも頓と感じ得ない樣子で一生懸命に彫てゐる。仰向いて此の態度を眺めて居た一人の若
い男が、自分の方を振り向いて、
「流石は運慶だな。眼中に我々なしだ。天下の英雄はたヾ仁王と我れとあるのみと云ふ態度だ。天晴れだ」 と云って賞め出
した。
自分は此の言葉を面白いと思った。それで一寸若い男の方を見ると、若い男は、すかさず、
「あの鑿と槌の使ひ方を見給へ。大自在の妙境に達してゐる」と云った。
運慶は今太い眉を一寸の高さに横へ彫り拔いて、鑿の齒を竪に返すや否や斜すに、上から槌を打ち下した。堅い木をーと刻
みに削って、厚い木屑が槌、の聲に應じて飛んだと思ったら、小鼻のおつ開いた怒り鼻の側面が忽ち浮き上がって來た。其の刀
の入れ方が如何にも無遠慮であった。さうして少しも疑念を挾 んで居らん樣に見えた。
「能くあゝ無造作に鑿を使って、思ふ樣な眉や鼻が出來るものだな」と自分はあんまり感心したから獨言の樣に言った。す
るとさつきの若い男が、
「なに、あれは眉や鼻を鑿で作るんぢゃない。あの通りの眉や鼻が木の中に埋ってゐるのを、鑿と槌の力で掘り出す迄だ。
丸で土の中から石を掘り出す樣なものだから決して間違ふ筈はない」と云った。
自分は此の時始めて彫刻とはそんなものかと思ひ出した。果してさうなら誰にでも出來る事だと思ひ出した。それで急に自
分も仁王が彫って見たくなったから見物をやめて早速家へ帰った。
道具箱から鑿と金槌を持ち出して、裏へ出て見ると、先達の暴風で倒れた樫を、薪にする積りで、木挽に挽かせた手頃な奴
が、澤山積んであった。
自分は一番大きいのを選んで、勢ひよく彫り始めて見たが、不幸にして、仁王は見當らなかった。其の次のにも運惡く掘り
當る事が出來なかった。三番目のにも仁王は居なかった。自分は積んである薪を片つ端から彫って見たが、どれもこれも仁王
を藏してゐるのはなかった。遂に明治の木には到底仁王は埋ってゐないものだと悟った。それで運慶が今日迄生きてゐる理由
も略解った。
第七夜
何でも大きな船に乘ってゐる。
此の船が毎日毎夜すこしの絶間なく黑い煙を吐いて浪を切って進んで行く。凄じい音である。けれども何處へ行くんだか
分らない。只波の底から燒火箸の樣な太陽が出る。それが高い帆柱の眞上迄來てしばらく挂ってゐるかと思ふと、何時の間に
か大きな船を追ひ越して、先へ行って仕舞ふ。さうして、仕舞には焼火箸の樣にぢゆっといって又波の底に沈んで行く。其の
度に蒼い波が遠くの向ふで、蘇杭の色に沸き返る。すると船は凄じい音を立て、其の跡を追掛けて行く。けれども決して追附
かない。
ある時自分は、船の男を捕まへて聞いて見た。
「此の船は西へ行くんですか」
船の男は怪訝な顔をして、しばらく自分を見て居たが、やがて、
「何故」と問ひ返した。
「落ちて行く日を追懸る樣だから」
船の男は呵々と笑った。さうして向ふの方へ行って仕舞った。
「西へ行く日の、果は東か。それは本眞か。東出る日の、御里は西か。それも本真か。身は波の上。楫枕。流せ流せ」と難
してゐる。舶へ行って見たら、水夫が大勢寄って、太い帆綱を手繰ってゐた。
自分は大變心細くなった。何時陸へ上がれる事か分らない。さうして、何處へ行くのだか知れない。只黑い煙を吐いて波
を切って行く事丈は储かである。其の波は頗る廣いものであった。際限もなく蒼く見える。時には紫にもなった。只船の動
く周圍丈は何時でも眞白に泡を吹いてゐた。自分は大變心細かった。こんな船にゐるより一層身を投て死んで仕舞はうかと思
った。
乘合は澤山居た。大抵は異人の樣であった。然し色々な顔をしてゐた。空が曇って船が搖れた時、一人の女が欄に倚りか
かつて、しきりに泣いて居た。眼を拭く半巾の色が白く見えた。然し身體には更紗の樣な洋服を着てゐた。此女を見た時に、
悲しいのは自分ばかりではないのだと氣が附いた。
ある晚甲板の上に出て、一人で星を眺めてゐたら、一人の異人が來て、天文學を知ってるかと尋ねた。自分は詰らないから
死なうとさへ思ってゐる。天文學抹を知る必要がない。默ってゐた。すると其の異人が金牛宮の 頂にある七星の話をして聞
かせた。さうして星も海もみんな神の作ったものだと云った。最後に自分に神を信仰するかと尋ねた。自分は空を見て默って
居た。
或時サローンに這入ったら派出な衣裳を着た若い女が向ふむきになって、洋琴を彈いてゐた。其の傍に脊の高い立派な男が
立って、唱歌を唄ってゐる。其口が大變大きく見えた。けれども二人は二人以外の事には丸で頓着してゐない樣子であった。
船に乘ってゐる事さへ忘れてゐる樣であった。
自分は益詰らなくなった。とうとう死ぬ事に決心した。それである晩、あたりに人の居ない時分、思ひ切って海の中へ飛
び込んだ。所が——自分の足が甲板を離れて、船と縁が切れた其の刹那に、急に命が惜くなった。心の底からよせばよかった
と思った。けれども、もう遅い。自分は厭でも應でも海の中へ這入らなければならない。只大變高く出來てゐた船と見えて、
身體は船を離れたけれども、足は容易に水に着かない。然し捕まへるものがないから、次第々々に水に近附いて來る。いくら
足を縮めても近附いて來る。水の色は黑かった。
そのうち船は例の通り黑い煙を吐いて、通り過ぎて仕舞った。自分は何處へ行くんだか判らない船でも、矢つ張り乘って居
る方がよかったと始めて悟りながら、しかも其の悟りを利用する事が出來ずに、無限の後悔と恐怖とを抱いて黑い波の方へ靜
かに落ちて行った。
第八夜
床屋の敷居を跨いだら、白い着物を着てかたまって居た三四人が、一度に入らっしゃいと云った。
眞中に立って見廻すと、四角な部屋である。窓が二方に開いて殘る二方に鏡が懸ってゐる。鏡の數を勘定したら六つあった。
自分は其一つの前へ來て腰を卸した。すると御尻がぶくりと云った。餘程坐り心地が好く出來た椅子である。鏡には自分の
顔が立派に映った。顔の後には窓が見えた。それから帳塲格子が斜に見えた。格子の中には人がゐなかった。窓の外を通る
往來の人の腰から上がよく見えた。
庄太郎が女を連れて通る。庄太郎は何時の間にかパナマの帽子を買て被ってゐる。女も何時の間に捋らへたものやら。一寸
解らない。雙方共得意の樣であった。よく女の顔を見やうと思ふうちに通り過ぎて仕舞った。
豆腐屋が喇叭を吹いて通った。喇叭を口へ宛がってゐるんで、頰。へたが蜂に螫されたように膨れてゐた。膨れたまんまで通
り越したものだから、氣掛りで堪らない。生涯蜂に螫されてゐる樣に思ふ。
藝者が出た。まだ御化粧をしてゐない。島田の根が緩んで、何だか頭に締りがない。顔も寢ぼけてゐる。色澤が氣の毒な程
惡い。それで御辭儀をして、どうも何とかですと云ったが、相手はどうしても鏡の中へ出て來ない。
すると白い着物を着た大きな男が、自分の後ろへ來て、缺と櫛を持って自分の頭を眺め出した。自分は薄い捱を扳って、
どうだらう物になるだらうかと尋ねた。白い男は、何にも云はずに、手に持った琥珀色の櫛で輕く自分の頭を叩いた。
「さあ、頭もだが、どうだらう、物になるだらうか」と自分は白い男に聞いた。白い男は矢張り何も答へずに、ちゃきちゃき
と缺を鳴らし始めた。
鏡に映る影を一つ殘らず見る積りで眼を瞠ってゐたが、缺の鳴るたんびに黑い毛が飛んで來るので、恐ろしくなって、やが
て眼を閉ぢた。すると白い男が、かう云った。
「旦那は表の金魚賣を御覧なすったか」
自分は見ないと云った。白い男はそれぎりで、頻と缺を鳴らしていた。すると突然大きな聲で危險と云ったものがある。
はっと眼を開けると、白い男の袖の下に自転車の輪が見えた。人力の梶棒が見えた。と思ふと、白い男が兩手で自分の頭を押
へてうんと横へ向けた。自轉車と人力車は丸で見えなくなった。缺の音がちゃきちゃきする。
やがて、白い男は自分の横へ廻って、耳の所を刈り始めた。毛が前の方へ飛ばなくなったから、安心して眼を開けた。粟餅
や、餅やあ、餅や、と云ふ聲がすぐ、そこでする。小さい杵をわざと臼へ中て、、拍子を取って餅を搗いてゐる。粟餅屋は子
供の時に見たばかりだから、一寸樣子が見たい。けれども粟餅屋は決して鏡の中に出て來ない。只餅を搗く音丈する。
自分はあるたけの視力で鏡の角を覗き込む樣にして見た。すると帳塲格子のうちに、いつの間にか一人の女が坐ってゐる。
色の淺黑い眉毛の濃い大柄な女で、髪を銀杏返しに結って、黑»子の半襟の掛った素衿で、立膝の儘、札の勘定をしてゐる。
札は十圓札らしい。女は長い睫を伏せて薄い唇を結んで一生懸命に、札の数を讀んでゐるが、其の讀み方がいかにも早い。
しかも札の數はどこ迄行っても盡きる樣子がない。膝の上に乘ってゐるのは高々百枚位だが、其百枚がいつ迄勘定しても百枚
である。
自分は茫然として此女の顔と十圓札を見詰めて居た。すると耳の元で白い男が大きな聲で「洗いませう」と云った。丁度う
まい折だから、椅子から立ち上がるや否や、帳塲格子の方を振り返って見た。けれども格子のうちには女も札も何にも見えな
かった。
代を拂って表へ出ると、門口の左側に、小判なりの桶が五つ許り並べてあって、其の中に赤い金魚や、斑入の金魚や、瘦せ
た金魚や、肥った金魚が澤山入れてあった。さうして金魚賣が其の後にゐた。金魚賣は自分の前に並べた金魚を見詰めた儘、
頰杖を突いて、じっとして居る。騒がしい往來の活動には殆ど心を留めてゐない。自分はしばらく立って此の金魚賣を眺め
て居た。けれども自分が眺めてゐる間、金魚賣はちっとも動かなかった。
第九夜
世の中が何となくざわつき始めた。今にも戰争が起りさうに見える。燒け出された裸馬が、夜畫となく、屋敷の周圍を暴
れ廻ると、それを夜畫となく足輕共が無きながら追掛けてゐる樣な心持がする。それでゐて家のうちは粼として靜かである。
家には若い母と三つになる子供がゐる。父は何處かへ行った。父が何處かへ行ったのは、月の出てゐない夜中であった。府
の上で草鞋を穿いて、黑い頭巾を被って、勝手口から出て行った。其の時母の持ってゐた雪洞の灯が暗い闇に細長く射して、
生垣の手前にある古い檜を照した。
父はそれ限歸って來なかった。母は毎日三つになる子供に「御父樣は」と聞いてゐる。子供は何とも云はなかった。しばら
くしてから「あっち」と答へる樣になった。母が「何時御歸り」と聞いても矢張り「あっち」と答へて笑ってゐた。其時は母
も笑った。さうして「今に御歸り」と云ふ言葉を何遍となく繰返して敎へた。けれども子供は「今に」丈を覺えたのみである。
時々は「御父樣は何處」と聞かれて「今に」と答へる事もあった。
夜になって、四隣が靜まると、母は帶を締め直して、絞鞘の短刀を帶の間へ差して、子供を細帶で脊中へ脊負って、そっと
潜りから出て行く。母はいつでも草履を穿いてゐた。子供は此の草履の音を聞きながら母の脊中で寢て仕舞ふ事もあった。
土塀の續いてゐる屋敷町を西へ下って、だらだら坂を降り盡すと、大きな銀杏がある。此の銀杏を目標に右に切れると、
一 丁許り奥に石の鳥居がある。片側は田圃で、片側は熊笹ばかりの中を鳥居迄來て、それを潜り拔けると、暗い杉の木立にな
る。それから二十間許り敷石傳ひに突き當ると、古い拜殿の階段の下に出る。鼠色に洗ひ出された賽銭箱の上に、大きな鈴の
紐がぶら下がって畫間見ると、其の鈴の傍に八幡宮と云ふ額が懸ってゐる。八の字が、鳩が二羽向ひあった樣な書體に出來て
ゐるのが面白い。其の外にも色々の額がある。大抵は家中のもの、射抜いた金的を、射抜いたもの、名前に添へたのが多い。
偶には太刀を納めたのもある。
鳥居を潜ると杉の梢で何時でも梟が鳴いてゐる。さうして、冷飯草履の音がぴちゃぴちゃする。それが拜殿の前で己むと、
母は先ず鈴を鳴らして置いて、直ぐにしゃがんで柏手を打つ。大抵は此の時梟が急に鳴かなくなる。それから母は一心不亂に
夫の無事を祈る。母の考へでは、夫が侍であるから、弓矢の神の八幡へ、かうやって是非ない願をかけたら、よもや聽かれ
ぬ道理はなからうとー圖に思い詰めて居る。
子供は能く此の鈴の音で眼を覺まして、四邊を見ると眞暗だものだから、急に脊中で泣き出す事がある。其の時母は口の内
で何か祈りながら、脊を振ってあやさうとする。すると旨く泣き己む事もある。又 益 烈しく泣き立てる事もある。いづれに
しても母は容易に立たない。
一通り夫の身の上を祈って仕舞ふと、今度は細帶を解いて、脊中の子を摺り卸ろすやうに、脊中から前へ廻して、兩手に抱
きながら拜殿を上って行って、「好い子だから、少しの間、待って御出よ」と屹度自分の頰を子供の頰へ擦り附ける。さうし
て細帶を長くして、子供を縛って置いて、其の片端を拜殿の欄干に括り附ける。それから段々を下りて來て二十間の敷石を往
ったり來たり御百度を踏む。
拜殿に括りつけられた子は、暗闇の中で、細帶の丈のゆるす限り、廣縁の上を這ひ廻ってゐる。さう云ふ時は母に取って、
甚だ樂な夜である。けれども縛った子にひいひい泣かれると、母は氣が氣でない。御百度の足が非常に早くなる。大變息が切
れる。仕方のない時は、中途で拜殿へ上って來て、色々すかして置いて、又御百度を踏み直す事もある。
かう云ふ風に、幾晩となく母が氣を揉んで、夜の目も寢ずに心配してゐた父は、とくの昔に浪士の爲に殺されてゐたので
ある。
こんな悲い話を、夢の中で母から聞た。
第十夜
庄太郎が女に攫はれてから七日目の晩にふらりと歸って來て、急に熱が出てどっと、床に就いてゐると云って健さんが知ら
せに來た。
庄太郎は町内ーの好男子で、至極善良な正直者である。たヾ一っの道樂がある。パナマの帽子を被って、夕方になると水菓
子屋の店先へ腰をかけて、往來の女の顔を眺めてゐる。さうして頻に感心してゐる。其の外には是と云ふ程の特色もない。
あまり女が通らない時は、往來を見ないで水菓子を見てゐる。水菓子には色々ある。水蜜桃や、林檎や、枇杷や、バナヽを
奇麗に籠に盛って、すぐ見舞物に持って行ける樣に二列に並べてある。庄太郎は此の籠を見ては奇麗だと云ってゐる。商賣を
するなら水菓子屋に限ると云ってゐる。其の癖自分はパナマの帽子を被ってぶらぶら遊んでゐる。
此の色がいゝと云って、夏蜜柑抹を品評する事もある。けれども、曾て銭を出して水菓子を買った事がない。只では無論食
はない。色許り賞めて居る。
ある夕方一人の女が、不意に店先に立った。身分のある人と見えて立派な服装をしてゐる。其の着物の色がひどく庄太郎の
氣に入った。其の上庄太郎は大變女の顔に感心して仕舞った。そこで大事なパナマの帽子を脱って丁寧に挨拶をしたら、女は
籠詰の一番大きいのを指して、これを下さいと云ふんで、庄太郎はすぐ其の籠を取って渡した。すると女はそれを一寸提げて
見て、大變重い事と云った。
庄太郎は元來閑人の上に、頗る氣作な男だから、ではお宅迄持って參りませうと云って、女と一所に水菓子屋を出た。そ
れぎり歸って來なかった。
©
如何な庄太郎でも、餘まり呑氣過ぎる。只事ぢや無からうと云って、親類や友達が騒ぎ出して居ると、七日目の晩になって、
ふらりと歸って來た。そこで大勢寄ってたかって、庄さん何處へ行ってゐたんだいと聞くと、庄太郎は電車へ乘って山へ行っ
たんだと答へた。
何でも餘程長い電車に違ひない。庄太郎の云ふ所によると、電車を下りるとすぐと原へ出たさうである。非常に廣い原で、
何處を見廻しても青い草ばかり生えてゐた。女と一所に草の上を歩いて行くと、急に絶壁の天邊へ出た。其の時女が庄太郎
に、此處から飛び込んで御覧なさいと云った。底を覗いて見ると、切岸は見えるが底は見えない。庄太郎は又パナマの帽子を
脱いで再三辭退した。すると女が、もし思ひ切って飛び込まなければ、豚に舐められますが好う御座んすかと聞いた。庄太郎
は豚と雲右衛門が大嫌だった。けれども命には易へられないと思って、矢つ張り飛び込むのを見合せてゐた。所へ豚が一匹
鼻を鳴らして來た。庄太郎は仕方なしに、持って居た細い檳榔樹の洋杖で、豚の鼻頭を打った。豚はぐうと云ひながら、ころ
りと引つ繰り返って、絶壁の下へ落ちて行った。庄太郎はほっとーと息接いでゐると又一匹の豚が大きな鼻を庄太郎に擦り附
けに來た。庄太郎は己を得ず又洋杖を振り上げた。豚はぐうと鳴いて又眞逆樣に穴の底へ轉げ込んだ。すると又一匹あらはれ
た、此の時庄太郎は不圖氣が附いて、向ふを見ると、遙の靑草原の盡きる邊から幾萬匹か數へ切れぬ豚が、群をなして一直
線に、此絶壁の上に立ってゐる庄太郎を見懸けて鼻を鳴らしてくる。庄太郎は心から恐縮した。けれども仕方がないから、近
寄ってくる豚の鼻頭を、一つ一つ丁寧に檳榔樹の洋杖で打ってゐた。不思議な事に洋杖が鼻へ觸りさへすれば豚はころりと谷
の底へ落ちて行く。覗いて見ると底の見えない絶壁を、逆さになった豚が行列して落ちて行く。自分が此の位多くの豚を谷へ
落したかと思ふと、庄太郎は我ながら怖くなった。けれども豚は續々くる。黑雲に足が生えて、靑草を踏み分ける樣な勢ひで
無盡藏に鼻を鳴らしてくる。
庄太郎は必死の勇を振って、豚の鼻頭を七日六晩叩いた。けれども、とうとう精根が盡きて、手がio樣に弱って' 仕
舞に豚に舐められてしまった。さうして絶壁の上へ倒れた。
健さんは、庄太郎の話を此處迄して、だから餘り女を見るのは善くないよと云った。自分も尤もだと思った。けれども健さ
んは庄太郎のパナマの帽子が貰ひたいと云ってゐた。
庄太郎は助かるまい。パナマは健さんのものだらう。
永井荷風
「樂屋十二時」
▲朝ハ時
樂屋口番の斜め樂屋の入口へ數十足の上草履を丁寧に並べながらの話。『源さん、どうだね、此ア今日もどうやら雨にな
りさうな樣子だが、降って來りゃア芝&日和と云って旦那方は大儲だらうが、此輩ア降りは大難義だ。』『違え無え、恁う
この節の樣に何處の芝居も會社になって萬事が吝嗇になつ了っちゃア、全く此輩ア腮が干上つ了ふ、其を思ふとな、又昔の
事を云ふ人ぢや無えが、艺居町の時分は大した物だったよ。猿若町に三座櫓が並んでる所ア本統に見せ度い樣だ。乃公ア其時
分から樂屋に建ルって居るが、全く長副は爲るものぢゃア無え。日に五十錢の給金を貰って朝は早くから、晩は何時も九時頃
迄、一日彼方此方と駆役はれてさ、本統に考へると自分ながら情無え位の者だ。』と愚痴を溢し居る所へ、出方の吉公通り
掛る。『おヽ、わ*さんかい。今度は表の方はどんな景氣だね、定めし羨しい話が澤山あるだらうの。』『冗談云ひねえ、景
氣ばかりで、から駄目なんだが、今日あたりは出揃になると云ふ事で、昨夜からお茶屋さんの方も付込が大分あった樣だ力ら\
雨にでも成ったら賣切り度えと思ってるのよ。』『さうかい、其ぢやア何にしろ晚は饒と飮めるね。』『はゝ、ゝゝ。どうか、
さう行きてえ者だ。』と行過ぎる。下駄の音して入來るは樂屋頭取、爺は急ぎ會釋して、『お早う御座い。』『傘を持って
來なかったが最うぼつぼつ降って來たから、歸り迄に何處かで傘一本工面して置いてお呉れ。』『へいへい、最う何ですか、
降って參りましたか。』『大降りになりさうだ。』と頭取部屋へ這入り、頭取臺の上に到着の板を並べ 酬して居る。部屋の時
計を見て、『おヽ、最う八時過ぎだのに。口番さん、お囉子の人は誰も這入って居ないのかい。』と聞て居る所へ唏子部屋の
者來る、頭取呼び止めて、『お囉子さん、遲う御座んすぜ、早く 一番を入れて、其から十時に着到を入れて下さいよ。』囉子
方慌忙て、駆け過ぎると、間も無く一番の太鼓の音、ドロン、ドロンドロドロドロドロドロドロドロンドンドンドンドンドン
ドロンガドンガドンガドンガドン
▲朝九時
作者部屋には狂言方四五人己に詰め掛け居て、『龜さんどうでせう、巧く時間迄に出揃へば可いが、今年からは何處の座も
興行時間が嚴しくなって、五分が十分でも時間外に演ってる事が出來なくなったんだから、餘程早く正格序幕を明けて置か
ないと追込んで來てからは爲様が無くなりますぜ。』『何でも、十時が三十分廻ったら、最う搆はずに二度目を入れて、十一
時きっかりにチョンチョン廻って行くんです。』『さうでも爲なけりゃ爲様がありませんや。』と隣室の頭取に向って『頭取
さん、未だ着到は這入らないんですかい。』『え、、未だ寺島の旦那がお出でになりませんが、奥役さん'ーツ龜井橋へ電話
でお聞き合せなすって 』と奥役は電話を掛けに行かうとする所へ、『堀越の旦那がお這入りです。』と聲する。頭取奥
役門弟ii:どやどや樂屋口ヘ迎ひに出る間もなく、堀越の樂屋入り。奥役は電話を掛けて來て、『今朝湯からお上りなすった所
だと云ふから、搆はず時間通り着到を入れて置かうぢや在りませんか。』『さう爲ませう、最う序幕の人數は揃ってるんです
から 』と此内囉子方着到の太鼓を入れる。役者共彼方此方と風呂塲へ通ふ草履の音バタバタ。
▲朝十時
風呂塲の湯氣立上る中に、役者三四人身»を洗ひながら、『〇〇さん、大分眠むさうな眼をしてえるが、昨夜は又何處かで始
めたと見えるね。』『此ればっかりは病えで止められ無えよ。』『何うだね、儲けなすったか。』『どうして、吟味へ行って
全然やられ了った。相手が惡いんだから 』『竹の家かい。』『さうだ。先お聞き下され、竹の家の一件に彼處の花ちゃ
ん、其から中二階の時代さんなんて云ふ顔なんだがね、皆手付きが黑ッぽいや。最初の中は其でも何うか恁うか車輪にやった
丈け、役が起きたけれど、大詰に行って悉皆駄目をこい了った始末さ。ーー時頃迄に悉皆絞られ了って、瘵に觸って成ら無え
から、例の奴を呼んで貰って、一杯飮直さうと思ふとね、驚くぢや無えか、何處で飮んで來やがったか、先ア最う愚顛々々
に聞召して居やがって、來ると早々人を種々と病付かせやがるんだ。本統に昨夜位役廻りの惡るかった事ア有りや爲無え。』
『は、は、。たまに泣きを喰ふのも罪滅しになるから可いや。乃公ア又昨夜は飛んだ失敗をした話があるんだ。昨夜此座が閉場
てから、鳥渡梅本へ寄るとね、丁度庵崎の若旦那が來てお居でなさるんで、其から一緒にお供をして角の菊住へ行ったんだが、
其には些と曰くがあるんだ。若旦那が那の新濱岡の濱坊に話を付け樣と爲て居なさるんだけれども、先がいやいやを極めて居
て為様が無えから、是非乃公に取持って呉れと云ふ事なんでね、其なら恁う云ふ風に段取りをしませうと、道々を話しを爲
た。先ね若旦那と乃公と濱坊と三人で飮んで居る。可い時分を計って若旦那が煙管で灰吹をニツ叩くと、其を切掛に、乃公が
便所に行く振りで、何處か廊下へでも出て樣子を見て居る。内では若旦那が濱坊を口説いて見て、いよいよ承知しさうもなか
ったら、其時乃公がずっと出て先づ、「其思案惡からう。」と意見をして靡かせ樣と云ふ事でね、菊住へ行って、無暗と飮ん
だ。若旦那は時分を計って本讀通り灰吹を叩きなすったのは可いが、乃公は例の惡い酒で、全然切掛を忘れ了って、へヾれけ
に成了った始末で、後から若旦那に散々の御折檻よ。飛んでも無え面目玉を失って歸って來て了ったが、考へると可笑しくっ
て成ら無え。』『はゝは、ゝ、ゝ。』と笑ひながら身иを拭き浴衣を着て、部屋へ»り各々鏡畫の前へ坐って顏に掛かる其中
に狂言方二度目の拍子木をチョンチョン。
▲朝十一時
舞«には大道具の職人共、道具を飾り了りて、『吉公、此度の道具は序幕から手の掛かる道具ばっかりだなア。』『大詰の屋
Й崩しなんかと來た日にやア本統に泣かせるぜ。』『全く落付いてるгаが無えや。』抒と愚痴を溢して居る中、チョンチョン
と狂言方木を打って廻って來る。『そら、最うяりだぜ。』«子方の者供慌忙てゝ黑簾の中へ並ぶ。役者の仕出し舞畫へ來る。
拍子木の音を聽いて幕外の見物はゝ俄に勢付いて手を打つ。«てチョンチョンと直りて幕が明く。
▲軒二畤
役者の男衆aけて來て口番の爺に向ひ、『親方のЯСは未だ持って*ねえかい。』『何Йへ規へたんだ•花月か花月なら最
少し前に來てSって行った。』『爲様が無えな、來たら催促しといて呉んなよ。』とЙ戻って行くと、精養軒の出前持ち、汚
れた白«衣の上に同じく白の前掛を締めゝ西洋料理のН持を提げ、『〇〇屋さんのお部屋は何處です。』口番『突當りの梯子
を上って直ぐ右«のお部屋だ。』煮しめ屋・«屋天・屋、辨當屋»入れ變り立ち變り出入りする-四十ばかりの牛»屋の亭主•
向ふより小僧を引йって來ながら、『やい、此小僧奴、手前は本統に那程云っとくのに何故SH々々して居やがるんだ。出前
を持って來たら、何畤までも芝居を«いて居ないで直ぐвって來いッて云ふに本統に爲様の無え野郎だ。』『芝居を見て居た
んぢや無いよ。』『えゝ未だ其様なことを吐かしゃアがるか。』と大聲で叱ると、頭取見て、『おい、牛肉屋さん、聲が大き
過ぎるぜ、幕が明いてるんだから、小言なら歸ってから云ひなせへよ。』
▲晝一時
新聞社の訪問記者、役者衆の部屋に悠然と尻を据えて、『はゝア、成程、警視廳で脚本の驗閲が嚴しくなったので、其であの
塲をお取りなすったのですか。いや、實に何うも此頃は些細ぬ事を喧しく云ふんで、芝居の方ばかりではありません。小説
や又私等の新聞の記事抹も惡くすると直ぐ停止を喰ので實に困り切るのです。』と仔細らしく薄鬚を捻って、『時に此度の狂
言は此で貴君は何度程お勤めになったのです。實に何うもお手に入った物ですな。』『いや、何うも御賞めに預っちゃ恐入
りやすよ。手前は那を勤めましたのは、一 丁目で演った時が初役なんで、半四郎仲藏彦三郎なんてえ顔でしたが、今度で丁度
六度目ですかね。』『は、ア、成程、今度で六度目 。』と頷付いて居る所へ、禿頭に白髯の爺手に掛物の軸を風呂敷
に包みたるを持ち、『いや今日は 。』『おヽ、先生、此ア何うも、今日は態々御見物で御座えますか。』『否、鳥渡作
者部屋へ話がありまして參りましたから、其でお寄り申したのですが、先日お話し爲た歌丸の掛物を持って來ましたが、何う
です、鳥渡御覧になって下さい。』『成程、此奴ア大えした物で御座えますね。』とひろげて見る、此中新聞記者は歸って行
く。後に此の怪し氣な老先生徐々と内職の骨董屋を始める事。
▲晝二時
『新聞屋と欲野様とに話込まれて弱つ了ひましたよ。表からは幕間を早く爲ろと云って來るし、さうかと云って催促に行けば
直ぐ冠を曲げられて大變な事になつ了ふし本統に今は大弱りを爲ましたよ。』『其でも先卅分に明いたから能御座んさア。』
と頭取部屋にて奥役頭取話を爲て居る所へ、ぼろ長と綽名されたる古着屋荷を背負って來り、『今日は。』と挨拶する。『長
松さん、何か變ったのが有りますかね。』『へえ、大分な廉價なのが出まして御座います。』と怪し氣な。へら。へらの小袖を廣
げ初めた。
▲晝三時——四時
左右二列に汚き鏡臺を並べたる三階の大部屋の片隅には、下廻連ハ九人斗り、中には鬟を付けたる、衣裳丈け着たる、或は
汚れたる浴衣一枚など、思ひ思ひの風俗にて、大車坐になり、長か半かと骰子を茶碗での大騒ぎ最中。『さアさア、早く張っ
て了は無えか、よ、何を愚圖々々して居るんだ。乃公ア最う構はねえ、ピンと一番張っとくんだ。』『ようよう、扇公がやっ
たら乃公も出るぞ。』『さア、今度は音公、しっかりやって呉れよ。』と夢中になって居る、見張番を爲し居たる一人駆けて
來て、『おいおい大變だ大變だ。頭取が上って來るぜ。』『何に、頭取が來ると、おい、皆薦を伏せ了ひねえ。』と皆々大騒
ぎに慌忙て居る處へ樂屋頭取出て來り『皆さん、お蕎麦の切符を此處へ置いて行きますぜ。賣切蕎麦の切符ですよ。』
▲タ五時
黑衣を着たる下廻りの後見、頭取部屋へ來て、『もし頭取さん、舞臺が暗くって不可いから、早く電氣を付けて下さいよ。』
と云捨て行く。頭取り大聲にて、『もし、電氣掛りさん、電氣掛りさん。早く電氣を捻って呉れないぢや困りますぜ。』『は
いはい只今捻ったんですけれども、未だ電氣が來て居ないんです。』『其ア困るぢやア無いか、早く電話で會社へさう云って
遣ってお呉んなせいよ。』と大騒をして居る所へ、中二階の役者一人馳せ來り、『頭取さん、橘江さんが病氣だか何だか、
未だ來て居ないんですがね、一寸届けて置きますよ。』と云捨てゝ去る。後に頭取作者部屋に來て、『もし、大詰へ腰元に出
て居ます橘江が參って居りませんさうですが、誰に代りを爲せませうか。』作者『誰?腰元の橘江ですか、其なら誰れでも
能御座んす、別に臺詩を云ってる役ぢゃア無いんですから、誰に代りをさせても搆ひませんよ。』『其ぢやア、相互で誰かの
代りをさせときませう。』と頭取は人頭の木札を調べ始める。
▲夜六時——七時
囉子部屋に借本屋の爺入込み、種々の講釋本を廣げて居る。『オイ六之助さん、もう好加減にして、其様本なんぞ見て居な
いで、早く一杯洗湯へ行って來ようぢや無か、此の幕が濟むと、最う直ぐ大切の出嚥子だよ。』『何、出囉子に出るからと云
って、何も洗湯なんぞへ入りに行くにも當らねえぢや無えか、佃島ぢや無えけれども赤い 祥を着て雛段の上へ三絃を以って
出並んだ所が、誰が見て呉れるもんかね。』『おいおい、六壽さん、さうぴしぴし云って遣んなさるなよ。六代さんはね、今
夜是非磨き立てた所を見せてやるお方がお出なすって被居るんだから、然も土間のね極く近い所へだよ。』『えッ、土間へ
お出でなさるのかえ。え、六代さん、今夜は我等達は只どうしても歸らないからね。可いかい、何をお馳走して呉れるんだ
い。』抹と大騒ぎをして居る。其の中に貸本屋は立去り、二三人の囉子連中は狐鼠狐鼠と樂屋外の角の洗湯へ入浴りに出掛け
る、後に殘りし一兩人は例の噂の女を覗きにと舞臺の方へ是も狐鼠狐鼠。
▲夜ハ時
大切所作事の幕明くと' 最早二三十分にて打出しになる事とて、樂屋口には口番の爺二人、銘々樂屋の者の下駄を並べ抹して
居る。樂屋の外には役者衆の車夫己に用意して各提燈を點し腰に毛布を巻いて待って居る。近所の小娘子守共、歸り掛の殳
者の素顔を拜まんとて己に七八人づつも隊をなして群れ集り居る始末。大道具や床山挥いふ職人の若者連の間には、例のお極
りの女郎買の相談、『どうだい、常公、今夜も一つ品川へ繰り込まうぢゃないか。乃公は最う今夜は到底降るだらうと思った
から、一晚繰込んでしっぽりと濡れの塲をやる心算だったのだ。』『へん、仕出しヾみた臺詩はもう止しに爲て呉れ。手前見
た樣な野郎は毎晩通ったって、到底駄目の皮だから、好加減に諦を付けて家へ歸ってせめて女房の尻にでも敷かれて居ろ
い。』とわやわや相談の中間もなく、幕になって、打出しの太鼓ドロンドロンと響勇しき中に、樂屋□は歸りの者にて大混雜。
『好い鹽梅に雨が晴って、先づ馬車代の三錢が助ったわい。』と眩きつゝ、頭取は皆々歸り去りたる後の樂屋を見廻り了り
て下駄を穿き歸り行く。奥役も同じく歸り去れば、今迄湧き返へす樣な囂ぎの樂屋も俄に火の消えた樣になれり。
「風邪ごゝち」
梅一輪一輪づつの暖かさ。春の日向に解けやすき雪の中裏なかなかに、憂き事つもる假住居。それさへ兼て米八が、三筋
のいとし可愛さの、女の一念信實に、思込んだる仕送りを、請けてその日の活業は、世間つくる丹次郎
と差向ひの置炬Й。男が中音に讀み聞かしてゐた「春色梅暦」の一節は、突然梯子段の下から鳴り出す消魂しい電話の鈴の音
に遮られた。
女は今朝方からの風邪心地、惡感をしのぐハ反のどてらの襟に埋めた其頤を起し、眉を颦めて、聞耳立てる間もあらず、
勝手の方からは障子の開閉物荒く、あはて、馳け出る下女の足音。やがて梯子を二三段みしみし踏み鳴し、
「姐さん、揚箱からもうお仕度に上ってもよござんすかって。」
「もうそんな時間なのかい。」 いかにも驚いたらしく女は用箪笥の上なる置時計を顧みたが、男はいつもより今日は一層朝
M ちк か <ご おちっ かけぶとん
寐した冬の日の短さは斯くもあらうと以前から覺悟してゐたやうな沈着いた聲で、「もう五時なんだね。」掛蒲團の下から
煙管を捜り出しながら、「お前、心持はどうなんだい。何なら一晩位、無理をしないがい、よ。」
ん
女は默って考へてゐたが、梯子段の欄干を片手につかまへて、下から顔を出してゐる下女に心付き、「今すぐ此方から電話
をかけると然う云ってお置き。」
下女は再び 頑丈な足音をさして姿をかくした。
「三日も前からのお約束なんですからね。それに地の事で春若さんからもくれぐれ頼まれてるのよ。」
「春若が踊るのか。いゝ度胸だね。」
「私の地ならわざわざ手合せしないでも濟むからって……昨日も電話で念を押されてるんですよ。困ったわね。」
「一體、心持はい、のか惡いのか。」と男は手を差伸して女の額を押える。
「まだ熱があって?」
「うむ。少しあるやうだね。」
「わるいでせうか。」
「わるいにやア極ってらアね。お前は兎に角あたり前の人の身體だと思っちゃ、大間違ひだぜ。」
「ほんとうね。。去年から見るとまた痩せた事よ。もう後何年位生きられるんでせう。」
女は氣味惡いほど沈着いた調子で云ったが、男は最早やそれには答へなかった。そして女の視線から避けるやうに置炬煙の
上なる梅暦を開閉ぢつ、、處々の挿繪をさがして眺めてゐた。かう云ふ差向ひの傷しい沈默は、日に一度か二度は必ず二人
の間に襲ひかゝって來るのである。けれども二人は、云はヾもう馴れ切って仕舞ったと云ふやうに、初めの中は實に堪えられ
ぬばかりの悲痛に覺えず涙を浮べた事も度々であったし、又中頃はお互によしない事は口にせぬやうにと、出來るかぎり氣
をつけてゐた事もあったのであるが、遂には凡ての事を成行次第にまかして仕舞って、敢て事新しくは悲しまぬやうにまで
立到ってゐるのである。悲しいと思ふことがあれば、あるだけ、故意と反抗的にそれ等の悲しい事を云って見て、せめての腹
癒にするのである。
思へばー昨年の秋の事であった。まだ自前の增吉にはならずに、玉扇屋から分で出てゐた時分、急性の肋膜炎にかゝった後、
女は不治の肺病といふ醫者からの宣告を受ける身となった。然しこの一大不幸はその當時の增吉の身に取っては、同時にまた
幾分かの幸福を齎し來たる原因ともなったのである。四五年に渡って增吉を世話をしてゐた旦那は、增吉が肺を惡くしたか
らと云って、流石に薄情な切れ方もできない處から、入院中の手當一切を支拂ってやった上に、猶若干の見舞金をやって、此
の後も商賣をつヾけるのなら、奇麗に呼んでляにするとの事。又抱え主の玉扇屋では、煉瓦地の狭い二階に四五人の抱えと、
これから仕込んで出さうといふ小供の二三人も、ごたごたに雜居さしてあるので、若し傳染りでもしてはといふ見え透いた實
をばそれとは云はずに、唯だ增吉の方さへ其の心持ならば今までの借金は月々出來るだけを入れる事にして、自前の看板を分
けてやらうとの事であった。增吉は抱主と旦那とからつまり敬遠主義を取られた事を能く承知しながら、寧ろそれをば有難い
と嬉しく感じた。
外の理由ではない。增吉は丁度其の當時、同じ家の朋輩に對して、藝者したものでなければ分らない藝者特有の意地とし
て、縦えどんな無理をしても早晩自前の看板を出さねばならぬ時期に迫られてゐたからである。玉扇屋から出てゐる藝者の中
で一番古顔の姐さん株と云へば、增吉と小兼との二人で、後の三四人は皆二三年も後れて弘めをした二十前後の若い子ばかり
である。小兼といふ意地惡は5年前の同じ年、增吉よりも三月ばかり晩く弘めをしたのであるが、好い旦那がついて、己に三
月ばかりも前に立派な自前になると同時に、抱えの二人まで置いて貰って、豪儀な姐さん面をし出した始末に、日頃から何か
につけて自然と競爭の地位に立ってゐた增吉は、自分から世間を狭めて、寧そ外の土地へ住替へしやうかとまで思込んでゐた
矢先、病氣に取りつかれて仕舞ったのである。
それ等の事情に加へて、こゝにまた一層增吉の嬉しく思った理由は、此れまでも度々新聞などに書かれて旦那をもしくじ
りかけた程思ひ込んだ男をば' 自前にさへなれば' 自由に自分の家に引入れて夫婦同樣に暮されるといふ事である。增吉は其
の思ふ男が萬一病氣が傳染したつて、戀の爲めなら命を捨てゝも惜しくはないと云ふに到って' 一夜を涙に明すほど嬉しく
思ひ、まだ病み上りの血色もすぐれぬ中から、二人して金春、仲通り、板新道から信樂新道と、それぞれに名のついた横町や
路地の貸家をさがし歩いて、丁度今から一年ほど前增玉屋といふ新看板を掲げたのであった。
「足掛け二年になるわね。斯うして一緒に暮してゐられたんだから、もう私やいつ死んだって、實際のところ思殘りはない
tったく
のよ。」
增吉は默ってゐる男の顔を覗き込むやうに、炬健の上に前身をのしかけた後、退儀らしく立上った。長らく此の社會に沈淪
してゐる男は、藝者と云ふものがお座敷の掛った其時に抱く 一種特別の感情をば飽くまでもよく了解してゐるので、其の眼は
依然として梅暦の挿繪を眺めたま、ながら、獨語のやうに、
「それぢや、早く行って、早く歸って來るさ。」
「でも、無理をして又どっしり寢込むやうだと困るわねえ。」
「だからさ。風邪でも引いた時なんぞは、順當な身體ぢゃないんだから、後口へ廻らうなんて慾を出しなさんなと云ふのさ。」
「なんぼ私が向見ずだからッて。」
增吉は調子だけ腹立たしさうに云ひすて、、梯子段の下口から「政や。」と大きく女中を呼んで、「揚箱へ電話をかけてを
くれ。そろそろ仕度に來てもいゝから。」
一足ばかり梯子段を下りかけたが、突然立戻って用箪笥の曳出から小菊の紙を取出し、空解けの伊達巻を引きしめながら、
增吉は降りて行ったが、再び上って來ると、直様電燈を向うの方へ引張って行って、窓際に据えた鏡«の前に坐った。下女が
癖直しのお湯を持って來る。增吉はもう今朝からの風邪心地をも、今日一日は湯にも行かずに頭痛がすると云ってゐたのをも、
萬事は全く忘れ果て、仕舞ったやうに、あるかぎりの全身の魂と精力とを鏡の中に打込んで、火の氣の乏しい裏二階の、しか
も二月の大寒の夕まぐれと云ふのをも更に頓着する氣色なく、くるりと兩肌をぬぎすてたのである。そして電光石火の如くに
挿してゐる櫛と簪と雹留などを抜き取るかと思ふと、前髪の中と兩鬢の翼の下に入れた梳毛の珠とを取り出し、熱湯にひた
した布片を摘んで適度に絞るや否や、髪の毛は根元からも抜け落ちよとばかり、カ任かせに兩鬢を揉んで擦った。
男は電話を掛終った下女が姐さんの長襦祥を炬煙へかけに來るのを機會に、少し後じさりに後方の壁にせをよせかけ、半ば
感嘆に、半ば傷しさに堪えぬやうな目容で、弱々しい撫肩に貝殻骨の痩立って見える後から、その化粧するさまをばちっ
と打目戍った。無論二人ともに交すべき話もない。話をしかけたとて、男は女が髪に氣を取られた時には碌々返事をする餘裕
もない事を承知してゐるに於てをや。外には日暮をいそぐ下駄の音。人力車の鈴、羅宇屋のピーピー、齒入屋の鼓の音。此
方は折々ぢれったさうな舌打の響につれて、明放した鏡臺の曳出しの幾個と知れぬ櫛や毛筋棒の中から氣に入ったのを取り
出さうとする手荒な物音と共に、風邪心地に寐亂れた銀杏返しは、昨日の晝過ぎこの土地で老手のお若さんが結った時のやう
に變ってしまった。卷は長く粛然として金鶏鳥の尾の如く、意氣な柔味の中に幾分の氣品をさへ帶びて、浮立つやうに鮮か
な襟足から梢々蒼白に頸の上に伸び、兩の鬢は左右から挿す毛筋棒の上に、水櫛の齒の曲線を鮮かに、ふうわり休んでゐる
と、前髪は凛として勇しく額の上に直立し、髯の兩輪は電燈の光を浴びて膝のやうな輝きを示してゐるのである。
然も增吉も、己れの製作品を眺めやる美術家が、此れで満足したのではないが、満足して置くより仕樣がない、手をつけ出
すと切がないからと云ったやうな、寧ろ遣瀬のないやうな目容で、合鏡の一瞥を終ったかと思ふと、一秒間の休息もせずに、
今度は白粉下の花筏を取って溢る、ばかり掌のくぼみにつぎ' 兩手で顔から頸から、咽喉から胸から、肩の後も手の届く
かぎりぺたぺた塗りつけた後には、つヾいて御園白粉を水刷毛にしたして目も鼻もないやうに一面に塗り立て' しよぼしょぼ
瞬きする睫毛と眼の縁を手拭でふき、次には粉白粉のついた大きな軟い毛の牡丹刷毛で、鼻の上から顔中襟元、耳朶の後ま
で、水白粉の濃淡のないやうに磨きをかけた。
「箱屋で御座ます。」と云ふ聲と共に格子戸のあく音。下女は出し忘れた着物の叱言を喰ぬ中にと周章て梯子段を駆け上り、
「姉さん、お召はどれを出すんです。」
增吉は頰紅を淡くぼかして、樂屋使ひの引眉毛を施しながら、
「さうだったね。あなた、鳥渡その引出の中の帳面を見て下さい。」
「二十五日……しま屋さま……五時……」と男は女が覺書の帳面を讀みにくさうに讀む。
「へい。今晩は。どうもお寒う御在ます。」と唐棧の羽織に同じゃうな着物の裾を端折った四十年輩の、頭をくるくると削っ
た揚箱の男は、幫間や落語家などにも見るやうな、何處となく角のとれた腰の低い態度で、梯子段を上りきった壁際に小く
身を寄せて膝をついた。
「爲さん。着物は出でなくっても可かったんだね。」
「へい。別に何ともついちゃ參りません。」
「それぢゃ、あのお召の……雪輪の裾模樣を出しておくれ。」
增吉は下女に命じながら音高く鏡臺の曳出を閉めると共に、白粉のほごれた寢衣の膝をぱたぱたと叩いて立ち上った。箱屋
の爲さんも同じく坐を立ち、增吉が新しい足袋をはき替へて立直るや否や、下女が取出す置炬煙の長襦祥を引取って、後か
ら着せかける。增吉はその裾を踵に踏へながら、縫模樣の半襟をかけた衣紋を正して、博多の伊達巻を少しは胴のくびれる
ほどに堅く引き締めると、箱屋は直ちに裾模樣の二枚重を取って、後ろから着せかけて置いて、女がその襟を合せてゐる暇に
は、もう兩膝をついて片手では長く敷く裾前を直してやり、片手では薦の上なる紋羽二重の長さは全一反のあらうと云ふしご
きを、さッと捌いて其の端を女の手に渡してやった。着せかけるものにも、着せられるものにも、共々に飽くまで専門家的の
熟練と沈着とが備ってゐて、聊かの混雑も漩滯もなく、凡ては輕妙に迅速に取扱はれて行くのである。
この年月、見馴れに見馴れた事ながら、男は流石に始終肱枕の眼を離さず眺めてゐる中、これも今夜初めてと云ふでない
が、藝者がお座敷といふ一聲に、病を冒して新粧を凝し、勇しくも出立って行く時の樣子は、恰も遠寄せの陣太鼓に戀も
涙も抛って、武智重次郎のやうな花武者が緋緘の鎧美々しく出陣する、その後姿を見送るやうな悲哀を催させるものだ…
••・と思った。
箱屋は袋につ、んだ三味線を持って、這入って來た時のやうに腰をかヾめて出て行くと、增吉は男の傍に膝をつき、締め
たての帶の間から、今挟んだばかりの煙草入を抜き出しながら、
「お化粧したら却って氣がさっぱりしたやうだわ。それぢやア、私行って來ますよ。早く貰ってすぐ歸って來るから、待つ
てゝ頂戴よ。晚の御飯一人で食べちまっちゃアいやですよ。」
「姐さん。車が來ました。」と下の方で下女の聲。
男は半身を起して唯だ頷付いてゐると、女は其の手を輕く握って、
「お腹が空いたら、私の牛乳があるから、あれでも呑んでお置きなさい。」それから何ともつかずに唯だ'「よくッて?」と
嫣然して見せて、增吉は棲を取って梯子段を下りた。
直樣切火をかける音が聞える。男は再びごろりと置炬懐へ 肱枕をして、大きな長い 叭をしながら、置時計を眺めると、丁
度六時を指す針と共に、其の中に仕掛けたオルゴールが點滴の落ちるやうに懶、く、「宮さん宮さんお馬の前で。」を奏し出
した。
日の全く暮れ果てた屋外の寒さは、建付の歪んだ西洋窓の隙間から、糸を引くやうに侵入して來る。男は仕樣事のない退屈
しきった身體を如何にも持扱ひかねると云ふやうに起き直らして、再び置炬燧の上に梅曆を開いたが、もう挿繪を見るので
もなく、唯だ茫然と電燈の光に照らされた亂雜な二階の身のまはりを眺めるのであった。たっぷり夜になると共に、電燈の光
は屋外の薄明かった夕方よりは、幾分か其の力を增したらしく、四邊一體を何ともなく新しく見せるやうに思はれたからでも
あらう。
俗に三等煉瓦の貸長家と云はれてゐる此の家の二階は、今日では明治初年を追想させる荒廢した一種の紀念物とも見られる
だけに、不思議な程拙なく不便に出來てゐる。立てば丈身の届くほど低い天井は紙張りにしてある爲めに、二目とは見られぬ
ばかり、鼠の小便と雨漏りの班點と、數知れぬ切張りとに汚され、間數は襖を引き得べき敷居の溝を以て境とすれば三間と
數へられるのであるが、梯子の下口の一間と、それに續いた次の間とには、丁度西洋室の煖«の煙筒を見るやうな太い煉瓦
の柱が突出してゐる爲めに、孰れも二疊半に三疊半と云ふやうな不思議な疊の半數を示してゐる。他の一間だけは稍廣くハ
疊ほどの疊が敷かれてあるが、後から付け出した一間半の押入がこゝにも亦邪魔らしく突出してゐる上に、次の間を區切る敷
居の上には、どう考へても解釋のつかない、飛んでもない處に、細い柱が然もーー本並んで立ってゐる。最初男は增吉と二人で
此の貸家を見に來た時、猫に爪を磨せる爲めわざわざこんな柱を立てたのぢゃないかと云って、笑った事があった。
男は一昨年の秋から毎夜々々同じ電燈の光で、增吉のお座敷へ行った後一人でぼんやり眺め廻はす三間打通しての此の二階
をば、今夜もまた仕樣事なしに眺め廻すにつけて、此れもまた毎夜のやうに、自分の身の行末はどうなるのであらうと、矢張
同じ事を思ひつヾけるのである。近所の女達から兄さんとも旦那とも或は單に進さんなぞとも呼ばれずに、歴とした祖先の姓
を名乘って、親の家から丸の内の會社へ通勤してゐた時分には、凡て正當なる事は馬鹿々々しく思はれ、一日半日の怠惰をも
許さぬ職務の束縛には遂に堪えられずして、恰も日に解される雪達磨の下から次第に崩れ出すやうに、この藝者家の二階に
主人同樣に入りびたって仕舞ったのであるが、それも今となっては、あまりに爲す事なき退屈の折々には、自分から抛った
規則正しい生活の活氣ある勇しさを、成程返って來ない昔の夢だと追囘して見たくもなる。けれども男は直様、かうまでに持
ち崩してしまった現在の身體では、唯でさへ根氣の續かなかった勤勉な生活なぞには到底復歸されるものではあるまい。寒い
寒い冬の朝目覺し時計に起されて慌忙しく洋一服を着る辛さ。雨の降る堀端に電車を待つ果敢さ、乘ってからは雜踏の苦しさ。
それから漸く會社の入口を潜れば、人々皆それぞれの階級に從って、其れ相應に立身出世の野望をば、唯だ謹直と云ふ名の
下に押隱して、凡そ、人間の多く集る處には必ず免れがたい反目やら競爭やら阿諛やら讒訴やら、其れ等一切の不快な陰險
な感情をば亦もや交際と云ふ假面の下に何事もないやうに包みかくして行く。そんな事を思ひ出すと、こゝに斯うして藝者家
の二階にごろついてゐる現在の方が、どれだけ幸福だか比較にはなるまい。會社の人達が蟻のやうに働いて、明けても暮れて
も、月給と賞與金との增額をのみ夢みつヾけるのも、其の最終の目的は榮華と安樂に耽りたいと云ふに過ぎない。詩人でもな
く仙人でもない吾々の安樂榮華とは、つまる處美衣と美食と美人とに圍繞されたい事を意味するのであらう。然りとすれば、
自分は社會的名譽を抛てた報酬としては己に業に餘りある程の安樂を得てゐるではないか。惜しむ事は無い、悔る事は更に
無い……男は重ねて二階中から自分の身のまはりを見廻した。
押入と相對した一方の壁際には、新しい桐の箪笥が二棹と、時代の知れぬ程古びたのが一棹と並べてあって、其の上には用
箪笥やら箱の人形やら羽子板やら、稽古本を入れる見臺やら、其の他さまざまな玩具や小道具が、天井の片隅なる酉の市の熊手
や、穴守樣の河豚の提灯なぞと一緒になって、どう云ふ譯か堅氣の家には決して見られない 艶しさ帶びて見える。向うの窓
際には大小の鏡臺があり、此方の窓に添ふ壁にはお召の不斷着が古びた長襦祥を重ねたまゝ、だらりと下ってゐる。置炬燒の
掛蒲團が古疊の上に其の花やかな更紗模樣を延べた端には、紋縮緬の裏をつけた八反のどてらと浴衣を重ねた絹の寐衣とが
細帶と共に、脱ぎすてたなり、其の襟のあたりの處なぞは丁度見脱の殻のやうに女が着てゐた時の儘の形をさへ殘して、花薦
の上に狼籍としてゐる。見廻す二階中の壁と疊と天井のいたましいまで古びた汚れ目に對して、いかにも優しい其等の家財道
具と見るからに艶なる女の衣類は、全く一致しない各自の特徴を互に鋭く引立たせ合ってゐるので、それをば同時に眺めや
る男の心には、いつも斯うした藝者家の二階といふものに對して、ーツは放蕩の身の末の尾羽打ちからした哀傷と、又一ツに
は云はれない柔かな住心地を感じさせるのであった。それは今夜のやうに女のいない留守の間に於てさへも、其のすぎ捨てた
衣服のさまざまからは絶えず一種の重い生暖 い氣が吐き出されてゐて、譬へる事のできない程手觸りょく、男の身を蔽ひ包
むやうな心持とでも云はうか。この快感と同時に古びた家から感じられる彼の哀傷とは、常に相混和して、遂に遂に今ある如
くに男の良心と、男が誰でも持ってゐる生活に對する固有の奮闘力とを根底から麻痺させてしまったので、男は此の頃になっ
ては朝湯の行き歸りなぞ、女着を仕立直した半纏を引掛けて戸外へ出る折々、横町の彼方に見える銀座の大通りの忙しさうな
生活を傍觀してさへも、何となく其の空氣の荒々しさに堪え得ぬやうな心持ちがして、直樣この二階なる絹の柔かみと白粉
の匂ひの古巣へもぐり込んでしまふのであった。されば男が一向に增吉の病気を恐れず、傳染したとて構はぬと云ってゐるの
も、つまりは何うにも斯うにもならぬ程じだらくに持崩してしまったわが身の成行の、寧そ早く片が付いてくれる事を絶望的
に希ふ爲に外ならぬ。否、男は死といふ事よりも今は、增吉が先きに死んで自分ばかりが無病息災で後に殘されたら其れこ
そ見じめなものだと氣遣はずにはいられないのである。
三
自働車が二階の箪笥の環をゆすぶる程、恐しい地響を立て、通った。裏隣りになってゐる小待合の二階からはサノサ節を
歌ふお客の聲が聞え出すと、横町の彼方からは、「これ今年の九星ハ封よみに御在ます……。」といふ皺枯れた讀賣の聲が次
第に近付いて來る。下女が澤庵臭い噫をしながら增吉の寐衣を炬煙にかけに來た。
「大分腹がへって來た。何かないかなア。」
男は振向くと、斯うした稼業の家には年久しく使ひ馴らされた三十前後の下女は、わざと調子をすげなくさして、「旦那ー
人に先へ御飯なんぞ上げると、後で私が姐さんに叱られます。」
「だって食はずにや居られないぢゃないか。この間の雀燒はもうなくなったのか。」
ーもう暫くだから御辛棒なさいよ。姐さんだって楽しみにしてお腹をすかして居らっしゃるんぢゃ有りませんか。」
下女は丁度物馴れた新造が若いお客をすかすやうな調子で答へながら、其の邊を取りかたづけて階下へ行ってしまった。
同時に電話が鳴出す。男はまだ少し時間が早過ぎるけれど、もしゃ增吉がお座敷から迎ひの車を寄越せとの事ではないかと、
取次ぎに出る下女の聲に耳を濟したが' 矢張り像想通りさうではなくて' 他のお茶屋から明日の何時にお約束といふ電話とい
ねま・
ふ電話なのであった。
「旦那。」と階下から下女が聲をかけて、「あちらへ直ぐ通して置きませうかね。」
「受けてしまったのか。」
「いゝえ。唯今お座敷ですからと云って置いたんですよ。」
「さうかい。そんなら出先へさう云ってやってお呉れ。」
かく吩附けたものゝ、男は家の下女からまで、そんな商賣のお座敷に關する相談なぞ仕掛けられないと云ふ心の苦痛を、眉
の間の皴に現はさずには居られなかった。自分より外には誰もゐない二階の中ながらも、猶人に見られはせぬかといふやうに、
其の顔をさへさあらぬ方に外向けさした。下女は增吉がお座敷へ出た留守に起る家業の用事や掛引の少し込み入って來る塲合
には、其の挨拶や返事のしゃうをば、「旦那々々。」と云っては何時としもなく男に相談しかけるのも、思へば既に久しい以
前からの事であるのだ。實は男も最初は面白半分に增吉が稼ぐ玉帳の總高を算盤にはじいて見るやうな事も無いではなかった
が、いざ全くの無職業の身になって、二階にごろごろしてゐる外には仕樣のない現在に至っては、時に觸れ物に感じる折々、
云ふに云はれない慚愧と苦痛の念に迫められてならぬ事がある。
休みなく鳴し立てる電話の鈴の音につヾいて、階下からはまたもや下女の聲。「旦那。困ってしまひますよ。電話がいくら
掛けてもお話中なんですよ。」
男は今度はもう答へなかった。今方火を入れ直した炬煙に燒き立てられる苦しさに、男は坐りくたぶれ寢くたぶれた身體を
立ち上らせ、ゆるんだ帶を締め直したついでに、階下の便所へでも行って置かうかと思ひついたが、突然又何か思ひ返したら
しく、梯子段の下り口から窃と階下を覗いて見ながら、其の儘立戻って座敷の眞中の細い柱に脊をよせかけてしまった。階下
©
の座敷といふのは元來は二階同樣の廣さであったらしいのを、手で押せば直ぐに拔けるかとまで危まれる薄壁に境して、今
の煎餅屋との二軒に後から分割したものらしく、僅かに三疊の一間も勝手道具のさまざまに狭められて下女一人やっと寐起き
されるばかりになってゐる。下女より外には誰もゐないのである。けれども男は其の三疊に置いてある長火鉢を見ると、左官
をしてゐる增吉の實父が、折々こゝへ酒を呑みに來る度々、極って娘と口喧嘩を初める事から、つヾいて增吉が毎月その親に
仕送る二十圓の爲に、優れぬ健康を犠牲にしてまで思はぬお客をさへ取ってゐるやうな秘密を連想せねばならぬし、猶其より
も一層避けたく思ふのは、薄い隣りの壁越しに絶間なく聞える年寄った煎餅屋の老母の咳嗽の聲である。それは何と云ふ事な
しに男の不身持を嘆いてゐる自分の母親の事を思ひ出させてならぬからである。
鍋燒うどん。焦立て豆やの呼聲と、支那饅頭の鈴の音に、横町の夜も少し更け出したかと思はれる頃、男はいつか又置炬懐
にもぐり込んで、獨りで淋しく、梅暦の痴話口説に強ひても興味を得やうと勉めてゐる時、突然格子戸の外に車夫の聲がして、
思ったよりも早く增吉が歸って來た。
「政、すぐ御膳の仕度をするんだよ。」甲走った聲と共に梯子段を踏む音が一段一段上って來ると、此方は幾分か待ち詫びて
ゐたといふ弱點のあるだけに、瞬間に起る男の意地が、自然とその塲合、男をして歌澤の文句にある通りな思はせぶりな空寢入。
女は梯子段を上り終るや否や、襟巻を解き捨てながら歩みよって、「早かったでせう。」と小聲に云ひながら男の肩の上に身
體を載せかけた。
氷のやうに冷えきった絹の女着の冷さに頰を撫でられ、男は覺えず身顫ひして女の手を取ったが、「大變な熱ぢゃないか。」
「背中がぞくぞくしてとてもお座敷にゐられなかったのよ。矢張無理をしたのが惡かったんだわね。」力のない調子で申譯
らしく男の顔を見た。
「だからさ。云はない事ッちゃない。」
「もう叱らないで頂戴よ。私が惡かったんだから。」と艶しく謝罪ると同時に、女は又甘へるやうに其の不平を訴へて、
「それでも今夜は一杯もお 盃なんぞ受けやしなかったのよ。この上身體をわるくしちゃ大變ですもの。いつだって少し頂
いたと思ふと、直ぐ内所で 厠 へ行っちゃ頰紅を薄く塗って、醉拂ったやうな眞似をしてゐる位にそれア用心してゐるんぢや
有りませんか。」
「だから、何もお前が好んで不養生すると云やしないぢや無いか。いゝから早く着換へておしまひ。何かよく暖まるもんで
も食べて早く寝た方がいゝよ。」
「あなた。お腹が空いたでせう。もう一體何時です。」男の身體に凭りか、った儘で羽織を脱ぎ帶留の金具をはづしながら、
置時計を見送って、
わり
「九時過ぎたばかり……割に早いわね。」
「お醫者さまを呼ぶのなら、今の中に早く政に行って貰ったらどうだい。」
「さうね
ー。」と考へて、「ほんのちょいと風邪を引いたヾけなんだから、此の間の頓服がまだ殘ってるから
下の方から其の時強い葱鮪の匂ひが立ち昇って來た。女は何も彼も忘れてしまつて、
「あ、嬉しい。政やが葱鮪をこしらへたわ。」
「さア早く脱いでおしまひ。襦祥一枚でどうするんだよ。」
「あッ。暑い。燒けどするわ。あなた。」
增吉は男が炬煙から取出して着せ掛ける寢衣の陰に、早や«祥もない眞白な肌身を艶めかしく悶えさせた。
格子戸があいて箱屋の聲。「姐さん、もうお歸りで御在ますか。」
「どうも御苦勞さま。」暫して、お政が香の物でもきざむらしい肴板の音がし出した。
二人は唯だ何ともいふ事もなしに顔を見合すと共に、さも嬉しさうに笑った。
辺
森鷗外
「心中」
お金がどの客にも一度はきっとする話であった。どうかして間違って二度話し掛けて、その客に「ひゅうひゅうと云ふのだ
らう」なんぞと、先を越して云はれやうものなら、お金の悔やしがりゃうは一通りではない。なぜと云ふに、あの女は一度來
た客を忘れると云ふことはないと云って、ひどく自分の記憶を恃んでゐたからである。
それを客の方から頼んで二度話して貰ったものは、恐らくは僕一人であらう。それは好く聞いて覺えて置いて、いつか書か
うと思ったからである。
お金はあの頃いくつ位だったかしら。「をばさん、今晩は」なんと云ふと、「まあ、あんまり可哀さうぢゃありませんか」
と眞面目に云って、救を求めるやうに一座を見渡したものだ。「おい、一萬年新造」と云ふと、「でも新造だけは難有いわね
え」と云って、心から嬉しいのを隱し切れなかったやうである。兎に角三十は愷かに越してゐた。
僕は思ひ出しても可笑しくなる。お金は妙な癖のある奴だった。妙な癖だとは思ひながら、あいつのゐないところで、その
癖をはっきり思ひ浮かべて見やうとしても、どうも分からなかった。併し度々見るうちに、僕はとうとう覺えてしまった。お
金を知ってゐ人は澤山あるが、こんな事をはっきり覺えてゐるのは、これも矢つ張僕一人かも知れない。癖と云ふのはかうで
ある。
「さうでせうねえ。わたし一時間は愷かに寐たやうだから。寢る前程寒かないことね。」
「宵のうち寒かったのは、雪が降り出す前だったからだよ。降ってゐる間は寒かないのさ。」
「そうかしら。どれ憚りに行つて來やう。お金さん附き合わなくって。」
「寒くないと云ったって、矢つ張寝てゐ方が勝手だわ。」
「友達甲斐のない人ね。そんなら爲方がないから一人で行くわ。」
お松は夜着の中から滑り出て、鬆んだ細帶を締め直しながら、梯子段の方へ歩き出した。二階の上がり口は長方形の間の、
お松やお金の寝てゐる方角と反對の方角に附いてゐるので、二列に頭を衝き合せて寝てゐる大勢の間を、お松は通って行かな
くてはならない。
お松が電灯の下がってゐる下の處まで歩いて行ったとき、風がごうと鳴って、だだだあと云ふ音がした。雪のなだれ落ちた
音である。多分庭の眞ん中の立石の傍にある大きい松の木の雪が落ちたのだらう。お松は覺えず一寸立ち留まった。
此時突然お松の立ってゐる處と、上がり口との中途あたりで、「お松さん、待って頂戴、一しょに行くから」と叫ぶやうに
云った女中がある。
そう云ふ聲と共に、むっくり島田髻を擡げたのは、新參のお花と云ふ、色の白い、髪のちぢれた、おかめのやうな顔の、十
六七の娘である。
「來るなら、早くおし。」お松は寝巻の前を搔き合せながら一足進んで、お花の方へ向いた。
「わたしこはいから我慢しゃうかと思ってゐたんだけれど、お松さんと一しよなら、矢つ張行った方が好いわ。」かう云ひな
がら、お花は半身起き上がって、ぐづぐづしてゐる。
寢てゐる女中の布團を片端からまくって歩いた。朝起は勤勉の第一要件である。お爺いさんのする事は至って四殊勝なやうで
あるが、女中達は一向敬服してゐなかった。そればかりではない。女中達はお爺いさんを、蔭で助兵衛爺さんと呼んでゐた。
これはお爺いさんが爲めにする所あって布團をまくるのだと思って附けた渾名である。そしてそれが全くの五寃罪でもなかっ
たらしい。
暮に押し詰まって、毎晩のやうに忘年会の大一座があって、女中達は目の廻るやうに忙しい頃の事であった。或る晩例の目
刺の一疋になって寝てゐるお金が、夜なかにふいと目を醒ました。外の女ならこんな時手水にでも起きるのだが、お金は小用
の遠い性で、寒い晩でも十二時過ぎに手水に行って寢ると、夜の明けるまで行かずに濟ますのである。お金はぼんやりして、
廣間の眞中に吊るしてある電灯を見てゐた。女中達は皆好く寐てゐる樣子で、所々で齒ぎしりの音がする。
その晩は雪の夜であった。寢る前に手水に行った時には綿をちぎったやうな、大きい雪が盛んに降って、手水鉢の向うの南
天と六竹柏の木とに大ぶ積って、竹柏の木の方は飲み過ぎたお客のやうに、よろけて倒れさうになってゐた。お金はまだ降っ
てうづ"も
てゐるかしらと思って、耳を澄まして聞いてゐるが、折々風がごうと鳴って、庭木の枝に積もった雪のなだれ落ちる音らしい
音がする外には、只方々の戸がことこと震ふやうに鳴るばかりで、まだ降ってゐるのだか、もう歇んでゐるのだか分からない。
暫くすると、お金の右隣に寝てゐ女中が、むっくり銀杏返しの頭を擡げて、お金と目を見合せた。お松と云って、痩せた、
色の淺黑い、氣丈な女で、年は十九だと云ってゐるが、その頃二十五になってゐたお金が、自分より精々二つ位しか若くはな
いと思ってゐたと云ふのである。
「あら。お金さん。目が醒めてゐるの。わたし大ぶ寐たやうだわ。もう何時。」
「さうさね。わたしも目が醒めてから、まだ時計は聞かないが、二時頃だらうと思ふわ。」
「さうでせうねえ。わたし一時間は愷かに寐たやうだから。寢る前程寒かないことね。」
「宵のうち寒かったのは、雪が降り出す前だったからだよ。降ってゐる間は寒かないのさ。」
「そうかしら。どれ憚りに行つて來やう。お金さん附き合わなくって。」
「寒くないと云ったって、矢つ張寝てゐ方が勝手だわ。」
「友達甲斐のない人ね。そんなら爲方がないから一人で行くわ。」
お松は夜着の中から滑り出て、鬆んだ細帶を締め直しながら、梯子段の方へ歩き出した。二階の上がり口は長方形の間の、
お松やお金の寝てゐる方角と反對の方角に附いてゐるので、二列に頭を衝き合せて寝てゐる大勢の間を、お松は通って行かな
くてはならない。
お松が電灯の下がってゐる下の處まで歩いて行ったとき、風がごうと鳴って、だだだあと云ふ音がした。雪のなだれ落ちた
音である。多分庭の眞ん中の立石の傍にある大きい松の木の雪が落ちたのだらう。お松は覺えず一寸立ち留まった。
此時突然お松の立ってゐる處と、上がり口との中途あたりで、「お松さん、待って頂戴、一しょに行くから」と叫ぶやうに
云った女中がある。
そう云ふ聲と共に、むっくり島田髻を擡げたのは、新參のお花と云ふ、色の白い、髪のちぢれた、おかめのやうな顔の、十
六七の娘である。
「來るなら、早くおし。」お松は寝巻の前を搔き合せながら一足進んで、お花の方へ向いた。
「わたしこはいから我慢しゃうかと思ってゐたんだけれど、お松さんと一しよなら、矢つ張行った方が好いわ。」かう云ひな
がら' お花は半身起き上がって、ぐづぐづしてゐる。
「早くおしよ。何をしてゐるの。」
「わたし脱いで寢た足袋を穿いてゐるの。」
「じれったいねえ。」お松は足踏をした。
「もう穿けてよ。勘辨して頂戴、ね。」お花はしどけない風をして、お松に附いて梯子を降りて行った。
便所は女中達の寢るる二階からは、生憎遠い處にある。梯子を降りてから、長い、狭い廊下を通って行く。その行き留まり
にあるのである。廊下の横手には、お客を通す八疊の間が兩側に二つ宛並んでゐてそのはづれの處と便所との間が、右の方は
七女竹が二三十本立ってゐる下に、小さい石燈籠の据ゑてある小庭になってゐて、左の方に茶室賽いの四疊半があるのである
いつも夜なかに小用に行く女中は、竹のさらさらと摩れ合ふ音をこはがったり、花崗石の石燈寵を、白い着物を着た人がし
やがんでゐるやうに見えると云ってこはがったりする。或る時又用を足してゐる間ぢゆう、四疊半の中で、女の泣いてゐる聲
がしたので、歸りに障子を開けて見たが、人はゐなかったと云ったものがある。これは友達をこはがらせる爲めに、造り事を
言ったのであるが、その話を聞いてからは、便所の往き返りに、兎角四疊半が氣になってならないのである。殊に可笑しいの
は、その造り事を言った當人が、それを言ってからは四疊半がこはくなって、とうとう一度は四疊半の中で、本當に泣聲がし
たやうに思って、便處の歸りに大聲を出して人を呼んだことがあったのである。
お金は二人が小用に立った跡で、今まで氣の附かなかった事に氣が附いた。それはお花の空床の隣が矢張空床になってゐる
ことであった。二つ並んで明いてゐるので、目立ったのである。
そして、「ああお蝶さんがまだ寢てゐないが、どうしたのだらう」と思った。お花の隣の空床の主はお蝶と云って、今年の
夏田舎から初奉公に出た、十七になる娘である。お蝶は八下野の九結城で5機屋をして、困らずに暮してゐるものの一人娘で
あるが、婿を嫌って逃げ出して來たと云ふことであった。間もなく親元から連れ戻しに親類が出たが、強情を張って歸らない。
親類も川桝の店が、料理店ではあっても、堅い店だと云ふことを呑み込んで、とうとう娘の身の上を此内のお上さんに頼んで
置いて歸ってしまった。それが歸ると、又間もなく親類だと云つて、お蝶を尋ねて來た男がある。十八九ばかりの書生風の男
で、浴帷子に小倉袴を穿いて、麦藁帽子を被って來たのを、女中達が覗いて見て、ーー高麗藏のした「一二魔風戀風」の一三東吾
に似た書生さんだと云って騒いだ。それから寄ってたかってお蝶を揶揄ったところが、おとなしいことはおとなしくても、意
氣地のある、張りの強いお蝶は、佐野と云ふその書生さんの身の上を、さっぱりと友達に打ち明けた。佐野さんは親が坊さん
にすると云って、例の一四殺生石の傳説で名高い、源翁禅師を一五開基としてゐる一六安隱寺に預けて置くと、お蝶が見初めて、
いろいろにして近附いて、最初は容易に聽かなかったのを納得させた。婿を嫌ったのは、佐野さんがあるからの事であった。
安隱寺の住職は東京で新しい敎育を受けた、物分りの好い人なので、佐野さんの人柄を見て、うるさく品行を非難するやうな
事をせずに、「君は僧侶になる柄の人ではないから、今のうちに廃し給え」と云って、寺を何がなしに逐ひ出してしまった。
そこで佐野さんは、内情を知らない親達が、住職の難癖を附けずに出家を止めるのを聞いて、げにもと思ふらしいのに勢を得
て、お蝶より先きに東京に出て、或る私立學校に這入った。お蝶が東京に出たのは、佐野さんの跡を慕って來たのであった。
佐野さんはその後も、度々川桝へお蝶に逢ひに來て、一寸話しては歸って行く。お客になって來たことはない。お蝶の親元
からも度々人が出て來る。婿取の話が矢張續いてゐるらしい。婿は機屋と取引上の關係のある男で、それをことわっては、機
屋で困るやうな事情があるらしい。佐野さんは、初めはお蝶をなだめ賺すやうにしてあしらってゐる樣子であったが' 段々深
くお蝶に同情して來て、後にはお蝶と一しょになって、機屋一家に對してどうしようか、こうしようかと相談をする立場にな
ったらしい。
かう云ふ入り組んだ事情のある女を、そのまま使ってゐると云ふことは、川桝ではこれまでついひぞなかった。それを目を
ねむって使ってゐるには、わけがある。一つはお蝶がひどくお上さんの氣に入ってゐる爲めである。田舎から出た娘のやうで
はなく、何事にも好く氣が附いて、好く立ち働くので、お蝶はお客の褒めものになってゐる。國から來た親類には、隨分やか
ましい事を言はれる樣子で、お蝶はいつも神妙に俯向いて話を聞いてゐても、その人を歸した跡では、直ぐ何事もなかったや
うに弾力を囘復して、元氣よく立ち働く。そしてその口の周囲には微笑の影さへ漂ってゐる。一體お蝶は主人に間違った事で
小言を言はれても、友達に意地惡くいぢめられても、その時は困ったやうな樣子で、謹んで聞いてゐるが、直ぐ跡で機嫌を直
して働く。そして例の微笑んでゐる。それが決して人を馬鹿にしたやうな微笑ではない。怜俐で何もかも分かって、それで堪
忍して、おこるの怨むのと云ふことはしないと云ふ微笑である。「あの、笑sよりは、口の端の處に、竪にちょいとした皴が
寄って、それが本當に可哀うございましたの」と、お金が云った。僕はその時一七リオナルドオ•ダア•ヰンチのかゐたモン
ナ•リザの画を思ひ出した。お客に褒められ、友達の折合も好い、愛敬のあるお蝶が、この内のお上さんに氣に入ってゐる
のは無理もない。
今一つ川桝でお蝶に非難を言ふことの出來ないわけがある。それは外の女中がいろいろの口實を捋 へて暇を貰ふのに、お
蝶は一晚も外泊をしないばかりでなく、畫間も休んだことがない。佐野さんが來るのを傍輩が彼此云っても、これも生帳面に
一八素話をして歸るに極まってゐる。どんな約束をしてゐるか、どう云ふ中か分からないが、みだらな振舞をしないから、不行跡
だと云ふことは出來ない。これもお蝶の信用を固うする本になってゐるのである。
お金は宵に大分遲くなってから、佐野さんが來たのを知ってゐる。外の女中も知ってゐる。こんな事はこれまでもあったが、
女中達が先きに寝て、暫く立ってから目が醒めて見れば、いつもお蝶はちゃんと來て寝てゐたのである。それが今夜は二時を
過ぎたかと思ふのに、まだ床に戻ってゐない。何と云ふ理由もなく、お金はそれが直ぐに氣になった。どうも一九色になって
ゐる二人が逢って話をしてゐるのだと云ふ感じではなくて、何か變った事でもありはしないかと氣遣はれるやうな感じがした
のである。
お花はお松の跡に附いて、「お松さん、そんなに急がないで下さいよ」と云ひながら、一しょに梯子段を降りて、例の狭い、
長い廊下に掛かった。
二階から差してゐる明りは廊下へ曲る角までしか届かない。それから先きは便所の前に、一燭ばかりの電灯が一つ附いて
ゐる丈である。それが遠い、遠い向うにちょんぼり見えてゐて、却てそれが見える爲めに、途中の暗黑が暗黑として感ぜら
れるやうである。心理學者が「闇その物が見える」と云ふ場合に似た感じである。
「こはいわねえ」とお花は自分の足の指が、先きに立って歩いてゐるお松の踵に障るやうに、食つ附いて歩きながら云った。
「笑談お言ひでない。」お松も實は餘り心丈夫でもなかったが、半分は意地で強そうな返事をした。
二階では稀に一しきり強い風が吹き渡る時、その音が聞えるばかりであったが、下に降りて見ると、その間にも絶えず庭の
木立の戰ぐ音や、どこかの開き戸の蝶番の弛んだのが、風にあふられて鳴る音がする。その間に一種特別な、ひゅうひゅう
と、微かに長く引くやうな音がする。どこかの戸の隙間から風が吹き込む音ででもあるだらうか。その斷えては續く工合が、
譬 へ ば人がゆっくり息をするやうである。
「お松さん。ちょいとお待ちよ。」お花はお松の袖を控へて、自分は足を止めた。
「なんだねえ。出し拔けに袖にぶら下がるのだもの。わたしびっくりしたわ。」お松もかうは云ったが、足を止めた。
「あの、ひゅうひゅうと云ふのはなんでしせう。」
「さうさねえ。梯子を降りた時から聞えてるわねえ。どこかここいらの隙間から風が吹き込むのだわ。」
二人は暫く耳を欹てて聞いてゐた。そしてお松がこう云った。「なんでもあんまり遠いとこぢゃなくってよ。それに板の
隙間では、あんな音はしまいと思ふわ。なんでも障子の紙かなんかの破れた處から吹き込むやうだねえ。あの手水場の高い處
にある小窓の障子かも知れないわ。表の手水場のは硝子戸だけれども、裏のは紙障子だわね。」
「さうでしせうか。いやあねえ。わたしもう手水なんか我慢して、二階へ歸って寝やうかしら。」
「馬鹿な事をお言ひでない。わたしそんなお附合ひなんか御免だわ。歸りたけりやあ、花ちゃんひとりでお歸り。」
「ひとりではこはいから、そんなら一しょに行ってよ。」
二人は又歩き出した。一足歩くごとに、ひゅうひゅうと云ふ音が心持近くなるやうである。障子の穴に當たる風の音だらう
とは、二人共思ってゐるが、なんとなく變な音だと云ふ感じが底にあって、それがいつまでも消えない。
お花は息を屏めてお松の跡に附いて歩いてゐるが、頭に血が昇って、自分の耳の中でいろいろな音がする。それでゐて、ひ
ゆうひゅうと云ふ音丈は矢張際立って聞えるのである。お松も余り好い氣持はしない。お花が陽にお松を力にしてゐるやうに、
お松も陰にはお花を力にしてゐるのである。
便所が段々近くなって、電灯の小さい明りの照し出す範圍が段々廣くなって來るのがせめてもの頼みである。
二人はとうとう四疊半の處まで來た。右手の壁は腰の邊から硝子戸になってゐるので、始て外が見えた。石灯籠の笠には雪
が五六寸もあらうかと思ふ程積もってゐて、竹は何本か雪に撓んで地に着きさうになってゐる。今立ってゐる竹は雪が堕ちた
かさ
跡で、はね上がったのであらう。雪はもう降ってゐなかった。
二人は覺えず足を止めて、硝子戸の外を見て、それから顔を見合せた。二人共相手の顔がひどく靑いと思った。電灯が小さ
いので、雪明りに負けてゐるからである。
ひゅうひゅうと云ふ音は、此時これまでになく近く聞えてゐる。
「それ御覽なさい。あの音は手水場でしてゐるのだわ。」お松はかう云ったが、自分の聲が不斷と變ってゐるのに氣が附いて、
それと同時にぞっと寒けがした。
お花はこはくて物が言へないのか、黙って合點々々をした。
二人は急いで用を足してしまった。そして前に便所に這入る前に立ち留まった處へ出て來ると、お松が又立ち留まって、か
・つ云った。
「手水場の障子は破れてゐなかったのねえ。」
「さう。わたし見なかったわ。それどこぢゃないのですもの。さあ、こんなとこにゐないで、早く行きませう。」お花の聲は
震へてゐる。
「まあ、ちょいとお待ちよ。どうも變だわ。あの音をお聞き。手水場の中よりか、矢つ張ここの方が近く聞えるわ。わたしき
っとこの四疊半の障子だと思ふの。ちよつと開けて見やうぢゃないか。」お松はこん度常の聲が出たので' 自分ながら氣強く
思った。
「あら。およしなさいよ。」お花は慌てて、又お松の袖にしがみ附いた。
お松は袖を攫まへられながら、ぢっと耳を澄まして聞いてゐる。直き傍のやうに聞えるかと思ふと、又そうでないやうにも
ある。愷かに四疊半の中だと思はれる時もあるが、又どうかすると便所の方角のやうにも聞える。どうも聞き定めることが出
來ない。
僕にお金が話す時、「どうしても方角がしっかり分からなかったと云ふのが不思議ぢゃありませんか」と云ったが、僕は格
別不思議にも思わない。聽くと云ふことは二〇空間的感覺ではないからである。それを強ひて空間的感覺にしようと思ふと、
三ミユンステルベ ルヒのやうにニニ内耳の迷路で方角を聞き定めるなどと云ふ無理な議論も出るのである。
お松は少し二三依怙地になったのと、内々はお花のゐるのを力にしてゐるのとで、表面だけは強そうに見せてゐる。
「わたし開けてよ」と云ひさま、攫まへられた袖を佛って、障子をさっと開けた。
廊下の硝子障子から差し込む雪明りで、微かではあるが、薄暗い廊下に慣れた目には、何もかも输郭丈はっきり知れる。ー
目室内を見込むや否や、お松もお花も一しょに聲を立てた。
お花はその儘氣絶したのを、お松は棄てて置いて、廊下をばたばたと母屋の方へкけ出した。
*
©
川桝の内では一人も殘らず起きて、廊下の隅々の電灯まで附けて、主人と隱居とが大勢のものの騒ぐのを制しながら、四疊
半に來て見た。直ぐに使を出したので、醫師が來る。巡査が來る。續いて刑事係が來る。警察署長が來る。氣絶してゐるお花
を隣の明間へ抱へて行く。狭い、長い廊下に人が押し合って、がやがやと罵る。非常な混雑であった。
四疊半には鋭利な刃物で、氣管を横に切られたお蝶が、まだ息が絶えずに倒れてゐた。ひゅうひゅうと云ふのは、切られた
氣管の疵口から呼吸をする音であった。お蝶の傍には、佐野さんが自分の頸を深くえぐった、白鞘の短刀の柄を握って死んで
ゐた。頸動脉が斷たれて、血が夥しく出てゐる。火鉢の火には灰が掛けて埋めてある。電灯には血の痕が附いてゐる。佐野
さんがお蝶の吭を切ってから、明りを消して置いて、自分が死んだのだらうと、刑事係が云った。佐野さんの手で書いて連署
した遺書が床の間に置いてあって、その上に佐野さんの二四銀時計が文鎮にしてあった。お蝶の名丈はお蝶が自筆で書いてゐ
る。文面の概略はかうである。「今年の暮に機屋一家は破産しさうである。それはお蝶が親の詞に背いた爲めである。お蝶
が死んだら、債権者も過酷な手段は取るまい。佐野も東京には出て見たが、神經衰弱の爲めに、學業の成績は面白くなく、そ
れに親戚から長く學費を給してくれる見込みもないから、お蝶が切に願ふに任せて、自分は甘んじて犠牲になる。」書いてあ
る事は、ざっとこんな筋であったさうだ。
川桝へ行く客には、お金が一人も殘さず話すのだから、この話を知ってゐる人は世間に澤山あるだらう。事によると、もう
何かに書いて出した人があるかも知れない。
四
八
萬年新造いつまでも若い婦人であるという、いくらかひやかしたことば。「新造」は、ここでは二十歳前後の女の意。
鼬の道 鼬は同じ道を二度通らないことから、往来、交際の絶えること、訪ねないことのたとえ。
マンション•オノレエル manchon honorarie (仏)光栄ある紋切形。
殊勝 ことにすぐれていること。感心。
冤罪むじつの罪。
竹柏の木 まき科の常喬木。葉が強靭で光沢がある。雌雄異株。
女竹
竹の一種。細く、節が平らで、竹の皮が年を経ても脱落しない。なよたけ、しのだけ。
下野
旧国名。茨城県。
九結城
-O機屋織物業。
茨城県の地名。現在は結城市。機業地で結城紬•結城木綿が名産。
二高麗藏 ハ代目市川高麗蔵。のち七代目松本幸四郎(187〇〜1949)
ーニ魔風戀風小杉天外の小説。明治三十六年「読売新聞」に発表。
三東吾 右の女主人公初野を崇拝する令嬢芳江の許婚者。帝国大学法科の学生。
一四殺生石の傳説 鳥羽天皇の寵妃玉藻の前(実は老狐)が殺されて石と化し、これに触れるものに災したのを、後深草天皇
の時代、源翁が通りかかり、杖で一打ちすると、石が二つに割れ、中から石の霊が現われて成仏したという伝説。石は栃
木県那須高原にある。
一五
一八
-九
二〇
ニニ
二四
©
開基開山。
安隱寺 結城市鍛冶町にある曹洞宗の寺。
リオナルドオ•ダア•ヰンチ しeonardo da Vinci (1452〜1519)イタリア文芸復興期の画家•建築家•彫刻家。絵画に
「聖告の図」 「キリスト洗礼の図」•「最後の晩餐」などがある。
素話 ただ話合いをするだけのこと。
色情人。恋愛関係。
空間的感覺方向の感覚。
ミユンステルベルヒHugo Munsterberg (1863〜1916)ドイツの心理学者•哲学者。著書「心理学概論」 「価値哲学」
などがある。
内耳の迷路 内耳は耳の最深部で、音響を感受する部分。迷路ともいわれる。
依怙地かたいじ。
銀時計 銀側の懐中時計。
「電車の窓」
冬の午後四時半である。
時によると恐ろしく電車の支へてゐることのある停留場なのに、どうしたわけか、往く車も返る車も暫く絶えてある。
赤と靑の旗を巻いて、きたない外套のポッケットに挿した男が、ぼんやりとポストの傍に立ち竦んでゐる。
ここは屋敷町である。
四條の線路が三方に分かれて、長く寂しく横たはってゐる上を、をりをり風がさっと渡ると、黄いろい砂埃がむらむらと
起って、横に這って消えてしまふ。
車を待ってゐるものは、遲退の一屬官らしい男が二三人、絆纏を着た職人が一人、お互に顔を見合ふのも面倒だといふ風を
して、はなればなれに立ってゐる。
この人達と反對の側には、女が一人俯向き加減になって、兩袖を搔き合せて立ってゐる。鼠の縞羅紗のコオトの袖である。
ニ銀杏返しのほつれ毛が三縹色のショオルの上に翻れ掛かってゐる。
僕の乘らうと思った方向は、女の立ってゐる側なので、ずっと背後の方に離れて立ち留まって、もう車が來さうなものだと、
坂上の方を見てゐた。
電車はなかなか來ない。
ふいと横町から自動車が飛び出して來て、ぶつぶつぶつと、厭な音をさせて線路を横ぎって行った。
靑い、臭い烟がきれぎれにその跡に殘る。
女が一足二足退く拍子に、僕は女の顔を見た。美しいが、殆ど血の色がない、寂しい顔である。
女の目も始て僕といふものの存在を認めた。
四互の長い目で、瞳が黑い星のやうに輝いた。
この目がこんな事を言ふのである。「あなたも千萬人の男といふものの中のお一人でございますね。多分わたくしの事を
一寸好い女だとお思ひでございませう。そして好い女だが五闌れてゐるとお思ひでございませう。事に依ったら、わたくしの
樣子を御覧なすったばかりでも、わたくしの胸にせつない事のあるのもお分かりでございませう。でも、わたくしの胸にある
事は、誰にでも慰めて貰はれるやうな事ではございません。誰にでもではございません。永遠に誰にも慰めて貰ふことの出來
ない事なのかも知れません。ですから、わたしの顔なんか御覧なさることはお廢なさいまし。駄目でございますから。」
僕は坂の上を見た。夕日の橙黄色に殘ってゐる空に透かして、最初に觸角を現はして、それから甲らを出して、胴を出して、
這ひ寄って來た電車が見える。電車は薄黑く見えてゐる。
針金がしゅうと鳴り出す。それからごうといふ音がする。やうやう其札に丁度僕の志ざす先が書いてあるのが讀めた。
ちんちんと云って、停留場に來て留まった。客が二三人降りた。
女が乘りさうにするので、僕は一足後れて車の傍に歩み寄った。
運轉手のゐる方の入口である。
正面の窓の處に席が明いてゐたので、女はそこに掛けた。
掛けると、鼠のコオトの袖を搔き合せる。これが癖と見える。頭は相變らず俯向加減になる。
僕は直前の革にぶら下がった。
女の頭が僕の腮の處にある。象牙に何か假名文字の蒔繪をした櫛と、六翡翠の玉の附いた七燻しの釵とが目に附く。黑く
光る、筋の太さうな髪である。
車掌の鈴が唱へて、運轉手の鈴が和する。
車がすうと動き出す。
どっどっと衝き上げるやうな音がして、ごうと地鳴がする。どっどつ、ごう、どっどつ、ごう。車は次第に速度を加へる。
僕は櫛の蒔繪の文字を讀まうとしたが讀めない。隙間風が横に吹いてゐるのに、ふいと髪の油の匂がして、忽ち消えた。
「ハ鏡花の女だ。」腹の中で僕はかう思った。
どっどつ、ごう。どっどつ、ごう。
車の窓の外は、靑み掛かった鼠色に、あらゆる物が浸されてゐる。
役所や大きな屋敷の前を行く。
往來は極少い。をりをり遲退の屬官らしいのが通る。中に一人、短い外套から、痩せた首が斜に前上方に突き出されて、長
い細い足が二本、九參謀官の兩脚規が地圖の上を歩くやうに、歩いてゐる男がある。その姿を見ると、一〇毛を引いたしゃもが
思ひ出される。
忽ち窓の外が一ぱいの赤いの幟になる。ーー倶樂部洗粉の廣告隊である。人足は赤地に白く洗粉の名を出したーニ引廻しのや
うな物を着てゐる。車ぢゆうの目が一瞬間悉く赤い幟に注がれる。
一瞬間である。電車は早いのに、廣告隊も急ぎで通り過ぎる。こんな處には廣告の甲斐はない。或る方面を歩いた歸道であ
らうー
©
赤い幟を見送らない人が只一人ゐる。それは鏡花の女である。
鏡花の女は矢張鼠のコオトを搔き合せて、俯向加減になってゐる。
その姿勢がこんな事を言ふのである。「まあ、なんといふ詰まらない身の上だらう。こんなに大勢の人が此電車に乘ってゐ
ても、わたしがこれから行って聞を跨がねばならない家のやうな家に行く人はあるまい。わたしがこれから行って詞を換は
さなくてはならない人達のやうな人と話をする人はあるまい。それでも其家に行かないわけには行かない。その人達と話をし
ないわけには行かない。なんといふ詰まらない身の上だらう。それに内を出れば、道を歩いてゐても、電車に乘ってゐても、
人がいやに顔を見る。それも只當り前に行き逢った人の樣に、見るともなしに見るばかりなら好い。摩れ違ってから振り返っ
て見る。連のある人は連に何かささやく。一頃はそれが嬉しかった事もある。それが嬉しいので、誰の爲めといふこともなく、
一三身じまひをした。着物や髪の物に氣を附けた。あの頃の事を思へば、本當に氣樂だった。向ひに二人並んで腰を掛けて、
何か話し合っては、くすくす笑ってゐる一四廂髪なんぞは、おほかたわたしのあの頃のやうな心持でゐるのだらう。もう一度
あんな心持になって見たい。」
電車は兩側に店のある町に出た。
ちんちんといふ車掌の合圖で、電車は留まった。
二三人降りて二三人乘る。前の方からも降りる人があるので戸が開く。冷たい風が砂埃を吹き込む。僕は體を横にして降
りる人を通して遣った。併し此停留場での客の昇降は、僕の革に吊り下がってゐる一角には、格別變動をも來さなかった。
ちんちん。ちんちん。電車が動き出した。どっどつ、ごう。
店に明りの附いたのが段々多くなる。街燈が附く。繁華な通りも人通りは少い。どこでも夕飯を食ふ時刻なのである。
電車にぱっと明りが附いた。
或る町の角を電車が鋭く曲った。
鏡花の女が一寸肩をゆさぶって頸を縮めた。電車が角を曲ったので、女の背後の開いてゐた窓から、冷たい風が吹き込んで
來たのである。
女は買った儘で、指尖で撮まんで持ってゐた切符を帶に挟んで、身をよぢって、背後の窓を締めようとした。
締まらない。どこか引つ掛かってゐるやうである。
女は立って、膝を腰掛の縁に當てがって、兩手を窓の戸に掛けて、引き上げようとした。
鬢のほつれ毛がはらはらと動いた。
窓の戸は上がらない。
女の身をよぢった時から、痩せた、しなやかな體の運動を眺めてゐた僕は、女が細い片手を窓に掛けた時、締めて遣らうか
と思った。
併し何物かが僕の一五肘を掣してゐたのである。
女の手を借すのがニハハイカラアらしいのを嫌ったわけではない。女の隣に、二人分以上の幅を取って、坐を占めて、毛皮
の襟の附いた大外套の中に體を埋めてゐるやうな男の、手を出すのを待ってゐたわけでもない。
どうも鏡花の女は人の助を借るのを厭ふらしく思はれてならなかったのである。
窓の戸は上がらない。
僕は默って伸ばした右の手を窓の戸に掛けた。窓はわけなく締まった。
「憚様。」
思の外に力がある、はっきりした聲である。そして窓から手を放して、振り向きしなに、黑い星のやうな瞳が電灯の下で、
一秒時の分數ほどの間、僕の顔の上に息んでゐた。
女の 唇 の語ったのは、只「憚樣」の一語であったが、その瞳はそれよりも多くのものを僕に語ったのである。「あなたの
手を借して下すったのは、わたくしだから手を借して下すったのではありますまい。併し丸でわたくしだから手を借して下す
ったのでないのでもございますまい。あなただって、あの開いてゐた窓をしめようとしてゐたのが誰であっても、きっと手を
貸してお遣なすったといふわけでもございますまい。わたくしはどういふ側であなたのお目に留まったのか存じませんが、兎
に角車に乘ります前からお目に留まって丈はゐましたのでせう。あなたはどんなお方だか好くは分かりません。併しどうもこ
れまで暗い横町で摩れ違ったとき手を握ったり、往來の少い處で聲を掛けたりした、何百人かの男とは違って入らっしゃるや
うでございます。あなたは手を借して置いてどうするといふお考はおありなさいますまい。あなたのなすった事は報の爲め
になすったのではございますまい。事によったら、わたくしのどこかヾお氣に召して、お慰になった報だと仰やるかも知れ
ませんが、それは報の爲めになすったといふものではございません。何事を致すにも、その位の機勢はなくてはなりますまい。
それは報の爲めとは申されますまい。若しそんな機勢もなくて何か致すのが宜しいのでございましたら、それは理屈があって、
思慮があって致すので、その致す事が 温 みのないものになってしまひませう。あなたが報の爲めでなく、わたくしにお手を
お借しなすったのが、わたくしは嬉しうございます。わたくしにはあれ丈の事も、世の中にまだ身勝手や慾心からではなく、
何かしらする人のある兆のやうに思はれます。これから厭な内へ參って、厭な人達に物を言はなくてはならないわたくしに
は、それ丈の信仰でも、餘程力になるのでございます。」
瞳がかう云った迹で、不思議な事には、それまで俯向いてばかりゐた鏡花の女が頭を擡げてゐた。兩袖は相變らず搔き合せ
てゐるが、頭を擡げてゐる。その視線は水平になってゐる。
向側にゐる廂髪の二人は、新しく乘った人をでも見るやうに、鏡花の女を見た。そして隣同志目で相圖をしてゐる。
ちんちん。ちんちん。電車は或る廣場の停留場に來て留まった。
僕は大勢の客と一しょに、鏡花の女を跡に殘して置いて、電燈の光の簇がってゐる中に降り立った。
廂髪の二人もここで降りたが、互いに肘突つ突き合って囁いて、それから聲高に笑ひながら、忽ち人込に隱れてしまった。
屬官各官庁に従属する下級官吏。
銀杏返し 女の髪の結い方。鬢の上を両方し、左右に曲げて輪形に結んだもの。
縹色薄い藍色。
四
八
互の長い目切れの長いこと。
闌れてゐる盛りが過ぎている。
翡翠宝石の一種。翠緑色の硬玉。
燻し 硫黄でいぶして金物に煤色をつけること。
鏡花の女 泉鏡花(1873〜1939)の小説に出るような女。悲しい運命を負うた美しい花柳界の女性が多い。「湯島詣」
の芸妓蝶吉など。
九參謀官の…やうに 軍の参謀官が作戦を考える時、コンパスの両脚を交る交る立てて動かしながら地図上の距離を測るよ
うに。
〇
四
毛を引いたしゃも 毛をむしったしゃも。しゃもは鶏の一品種。闘鶏に使われる。
倶樂部洗粉 中山太陽堂から発売されていた洗顔料。
引廻し丸合羽。
身じまひ身支度。
廂髪束髪の一種。前髪と鬢を特に前方に出して結うもの。明治三十七、ハ年頃から女学生などの間に流行した。
肘を掣し 掣肘。干渉して自由に行動させないこと。
ハイカラア high.collol:(英)高い襟。転じて西洋風を気どること。その人。
有島武郎
「潮霧」
南洋に醍酵して本州の東海岸を洗ひながら北に走る黑潮が、津輕の鼻から方向を變へて東に流れて行く。樺太の氷に閉され
てゐた海の水が、寒い重々しい一脈の流れとなって、根室釧路の沖をかすめ西南に突進する。而してこの二つの潮流の尅する
所に濃霧が起る。北人の云ふ潮霧とはそれだ。
六月の或る日、陽のくれぐれに室蘭を出て函館に向ふ汽船と云ふ程にもない小さな汽船があった。
彼れはその甲板に立ってゐた。吹き落ちた西風の向うに陽が沈む所だった。駒ヶ嶽は雲に隱れて勿論見えない。禮分華峠の
突角すら、魔女の髪のやうに亂れた初夏の雲の一部かと思はれる程朧ろである。陽は叢がり立って®み付かうとする雲を光の
鞭でた、き分けながら沈んで行く。笞を受けた雲は眩むばかりの血潮を浴びる。餘った血潮は怖れをなして飛び退いた無數の
鱗雲を、黄に紅に紫に染める。
陽もやがて疲れて、叢雲の血煙を自分の身にも受けて燃え爛れた銅のやうになった。堅く積み重なった雲の死骸の間を、斷
末魔の苦悶にきりきりと獨樂のやうに舞ひながら沈んで行く。垂死の人が死に急ぐやうに陽は夜に急ぐ。彼れは氣息を飮んで
其れを見つめた。
陽は見る間に少し隱れた。見る間に半分隱れた。見る間に全く隱れた。海は蒼茫として靑み渡った。ほの黄色い緩やかな呼
吸を續けながら空も海の嘆きを傳へた。
その瞬間に萬象は聲を絶えた。黄昏は無聲である。そこには叫ぶ晝もない。又さゝやく夜もない。臨終の恐ろしい沈默が天
と海とを領した。天と海が沈默そのものになった。
汽罐の騒音と云ふか。そんなものは音ではない、況して聲ではない。陽は永久に死んだ。復た生きる事はないだらう。彼れ
は身を慄はしてさう思った。
來た方を振り返ると大黑島の燈臺の灯だけが、聖者の涅槃のやうな光景の中に、小賢くも消えたり光ったりしてゐる。室蘭
はもう見えない。
その燈臺の灯もやがて視界から消え失せた。今は夜だ。聞耳を立てるとすっと遠退いてしまふ夜の囁きが海からも空からも
聞こえはじめた。何事でも起り得る、又何事も起り得ない夜、意志のやうな又運命のやうな夜、その夜が永久に自分を取りま
くのだなと思ふと彼れはすくみ上って船首樓に凝立したまゝ、時の經つのも忘れてゐた。同じ畫ながら時のす、むにつれて明
るみの增すやうに、同じ夜ながら更の闌けるにつれて闇は深まって行く。あたりには人氣が絶えた。どうすれば船客等は船底
にやすやすと眠ることが出來るのだらう。今朝陽が上った故に明日又陽が上るものとは誰れが保證し得るのだ。先刻陽の沈む
のを見たものは陽の死ぬのを見たのだ。それだのに彼等は平氣だ。一體彼等は何物に自分々々の運命を任せてゐるのだらう。
神にか、佛にか。無智にか。彼等は明日の朝この船が函館に着くものと思ってゐるのだ、思ひだもしてはゐないのだ。而して
神々よりも勇ましく安心して等しなみに聲も立てずに眠ってゐる。
かく思ひめぐらして彼れは夜露にしとった肩をたゝきながら、船橋の方を見送った。眞暗な中に唯〃一人眠らないものがゐ
た。それは船長だ。その人は夜の隈取りをした朧ろげな姿を動かしながら天を仰いで六分儀を使ってゐた。彼れも亦それに引
き入れられて空を見上げた。永遠を思はせる程高くもなり、眉に逼るほど低くもなる夜の空は無數の星に燐光を放って遠く擴
がってゐた。
彼れはまた思った。大海の中心に漂ふ小舟を幾千萬哩の彼方に在るあの星々が導いて行くのだ。人の力がこの卑しい勞役を
星に命じたのだ。船長は一箇の六分儀を以て星を使役する自身を持ってゐる。而して幾百の、少くとも幾十の生命に對する責
任を輕々とその肩に乘せて居る。船客の總ては、船長の頭に宿った數千年の人智の蓄積に全く信頼して、些かの疑ひも抱かず
にゐるのだ。人が己れの智識に信頼する、是れは人の誇りであらねばならぬ。それを躊躇する自分はおほそれた卑怯者と云ふ
べきである。
半時間毎に淋しい鐘が鳴って又若干の時が過ぎた。船は暖潮に乘り入れたらしい。彼れは無風の暑苦しさに堪へかねて船首
から船尾の方へ行った。而してそこにある手舵に身をよせて立って見た。冷々する風がそっと耳をかすめて通る。彼れは眼を
細めてその涼しさになぶられてゐた。
かくて又若干の時が過ぎた。
突然彼れは寒さを顔に覺えて何時のまにか陥った假睡から眼をさました。風は習々と東方から船尾を拂って船首へと吹き出
してゐるのだ。彼れの總身は身戰ひするまで冷え切ってゐた。見ると東の空は眼通りほど幕を張りつめたやうに眞黑な物に蔽
はれてゐた。海面が急に高まったかと思はれる彼方には星一つ光ってはゐなかった。その黑いものは刻々高さを增して近づい
て來る。風が東に廻って潮霧が襲って來るのだと氣がついた時には、その黑かったものは黑眞珠のやうな銀灰色に光って二三
町と思はれる距離に逼ってゐた。海に接した部分は風に吹かれる幕の裾のやうに煽られながら惡夢の物凄さを以て近よって來
る。見る見る近よって來る。突然吹きちぎられた濃霧の一塊が彼れを包んだ。彼れの眼は盲ひた。然しそれは直ぐ船首の方
へ飛び去った。と思ふと第二の塊が來た。それも去った。第三、第四、それも去ったと思ふ間もなく、彼れはとうとうむせ返
るやうな寒い白さの中に包まれてしまった。眼の前に圓く擴がってゐた海は段々圓周をせばめて遂には眼前一尺の先きも見透
す事が出來なくなった。彼れは驚き慌てて探るやうに手舵を握ると、それを包んだカンバスはぐつしより濕ってかんかんにこ
はばってゐた。檣頭に掲げられた灯が見る見る薄れて、唯〃有るか無きかの圓光に變ってしまった。
彼れは船長の居る方へ眼をやった。その頭に宿る幾千年間の人智の蓄積にすがらうとしたのだ。然し一かたまりの霧は幾千
年の人間の努力を塵の如くに踏みにじってしまったのではないか。今は姿さへ見えない船長は、胸をさわがせながら茫然とし
て、舷橋の上に案山子のやうに立ってゐる事だらう。
暫らくの間船は事もなげに進路を取って進むやうに見えた。然しそれが徐行に變ったのは十分とはたゝない短い間だった。
突然この不思議な灰色の闇を劈いて時を知らせる鐘が續けさまに鳴り出した。思ふまゝに渦巻き過ぎる濃霧に閉ぢこめられて
その鐘の音は陰々として淋しく響いた。
船はかく警戒しながら又十分程進んだが、やがて彼れは足の下にプロペラーのゆらめきを感じなくなった。同時に船足の停
った船體は、三口目の茶の湯茶碗のやうな無氣味な搖れ方をしたま、停って、波のまにまに漂ひ始めた。
彼れの心臓をどきんとさせて突然汽笛が鳴りはためいた。屠所に引かれる牛の吼聲のやうなその汽笛。かすれては吼え、か
すれては吠えて、吼えやむと物淋しい鐘が鳴り續く。
彼れの肺臓には空気よりも多く水氣が注ぎ込まれるやうに思へた。彼れは實際むせて咳いた。髪の毛からは滴が襟に傳はっ
た。而して耳と鼻とは氷のやうに冷えた。陽は復たと生れて來ない、さう思った彼れの豫覺は悲しくも裏書きされて見えた。
彼れは幾人もの男女が群盲のやうに手さぐりしながら彼れに近づくのに氣がつくと、何んとも云へぬ哀れみを覺えながらさう
思った。
汽笛が船中の人の眼をさましたのだ。而して眼をさまされたものは殘らず甲板に這ひ上って來たのだ。
鐘の音と汽笛の聲との間に総ての船客の歎きと訴へとの聲が泡のはじけるやうに聞こえ出した。
潮霧は東の空から寄せて來る。彼れの乘って來た船は霧の大河の水底に沈んだ一枚の病葉に過ぎない。船客は極度の不安に
達した。矢よりも早く流れて行くのに、濃霧の果ては何時來るとも思はれない。狂氣のやうなす、り泣きが女と小兒とから
慘らしく起り出した。葬ひのやうな淋しい鐘は鳴り續ける。總ての人を醉はさないでは置かぬやうに船は停ったまゝかしぎ
搖れる。
彼れの心には死に捕へられた人の上にのみ臨む物凄いあきらめが首を擡げかけた。
その時奇蹟のやうに風が方向を變へた。西へ西へと走って居た霧は足をすくはれたやうに暫らくたじろぐと見えたが、見る
見る人々の眼がかすかな視力を回復した。空はぼうっと明るくなって人々の身のまはりに小さな世界が開けて行った。やがて
遠く高く微笑むやうな靑空の一片が望まれた。と思ふ中に潮霧は夢のさめるやうに跡形もなく消えてなくなった。それは慌
たヾしい心よりもなほ慌たヾしく。
霧が晴れて見ると夜は明けはなれてゐた。眞靑な海、眞靑な空、而して新らしい朝の太陽。
然し霧の過ぎ去ると共に、船の右舷に被ひか\るやうに聳え立った惠山の峭壁を見た時には、船員も船客も呀っと魂を消し
て立ちすくむのみだった。濃霧に漂ひ流れて居る間に船は知らず知らずかゝる危地に臨んでゐたのを船員すらが知らずにゐた
のだ。もう五分霧の晴れるのがおくれたならば!船自身が魂でもあるやうに驚いて向きをかへなかったならば!この惡魔のや
うな峭壁は遂に船をかみくだいてゐたに違ひないのだ。
函館に錨を下した汽船の舷梯から船客はいそいそと笑ひ興じながら岸をめざして降りて行った。先刻何事が起ったかも忘れ
果てた如く彼等は安々と眼を開いて珍らしげもなくあたりを見て居た。
彼れはさうはしてゐられなかった。彼れは始めて陽を仰ぐやうに陽を仰いだ、始めて函館を見るやうに函館を見た。新らし
い世界が又彼れの前に開け亙った。而して彼れは涙ぐんでゐた。
志賀直哉
「好人物の夫婦」
深い秋の静かな晩だった。沼の上を雁が啼いて通る。細君は食台の上の洋燈を端の方に引き寄せてその下で針仕事をして
いる。良人はその傍に長々と仰向けに寝ころんで、ぼんやりと天井を眺めていた。二人は永い間黙っていた。
「もう何時?」と細君が下を向いたまま云った。時計は細君の頭の上の柱に懸っている。
「十二時十五分だ」
「お寝みに致しましょうか」細君はやはり下を向いたまま云った。
「もう少しして」と良人が答えた。
二人は又少時黙った。
細君は良人が余り静かなので、漸く顔を挙げた。そして縫った糸を扱きながら、
「一体何していらっしゃるの?そんな大きな眼をして……」と云った。
「考えているんだ」
「お考え事なの?」
又二人は黙った。細君は仕事が或切りまで来ると、糸を断り、針を針差しに差して仕事を片付け始めた。
「オイ俺は旅行するよ」
「何いっていらっしゃるの?考え事だなんて今までそんな事を考えていらしたの」
「そうさ」
「幾日位行っていらっしゃるの?」
「半月と1卜月の間だ」
「そんなに永く?」
「うん。上方から九州、それから朝鮮の金剛山あたりまで行くかも知れない」
「そんなに永いの、いや」
「いやだって仕方がない」
「旅行おしんなってもいいんだけど、——いやな事をおしんなちゃあいやよ」
「そりゃあ請け合わない」
「そんならいや。旅行だけならいいんですけれど、自家で淋しい気をしながらお待ちしているのに貴方が何処かで今頃そん
な……」こう云いかけて細君は急に「もう、いやいや」と烈しくその言葉をほうり出して了った。
「馬鹿」良人は意地悪な眼つきをして細君を見た。細君も少しうらめしそうな眼でそれを見返した。
「貴方がそんな事をしないとはっきり云って下されば少し位淋しくてもこの間から旅行はしたがっていらしたんだから我慢
してお留守しているんですけど」
「きっとそんな事を仕ようと云うんじゃないよ。仕ないかも知れない。そんなら多分しない。なるべくそうする。——然し必
ずしも仕なくないかも知れない」
「そら御覧なさい。何云ってらっしゃるの。いやな方ね」
良人は笑った。
「仕ないとはっきり仰有い」
「どうだか自分でもわからない」
「わからなければいけません」
「いけなくても出掛ける」
細君はもうそれには応じなかった。そして「貴方が仕ないとはっきり仰有って下されば安心してお待ちしているんだけど…
•:男の方って何故そうなの?」と云った。
「男が皆そうじゃないさ」
「皆そうよ。そうにきまってるわ。貴方でもそうなんですもの」
「そんな事はないさ、俺でもハ年前まではそうじゃなかったもの」
「じゃあ、何故今はそうじゃなくおなりになれないの?」
「今か。今は前と異って了ったんだ。今でもいいとは思ってないよ。然し前程非常に悪いと云う気がしなくなったんだ」
「非常に悪いわ」細君は或興奮からさえぎるように云った。「私にとっては非常に悪いわ」
その調子には、良人の怠けた気持を細君のその気持へぐいと引き寄せるだけの力がこもっていた。
「うん、そりゃそうだ」良人はその時、腹からそれに賛成して了った。
「そりゃそうだって、そんならはっきりそんな事仕ないって云って下さるの?」
「うう?断言するのか?そりゃ一寸待ってくれ」
「そんな事を仰有っちゃあ、もう駄目」
「よし、もう旅行はやめた」
「まあ!」
「まあでも何でも旅行はもうよす」
「そんな事を仰有らなくていいのよ。御旅行遊ばせよ。いいわ、多分仕ないって云って下すったんですもの。私が何か云って
おやめさせしちゃあ悪いわ。おいで遊ばせよ。上方なら大阪のお祖母さんの所へ行っていらっしゃればいいわ。お祖母さんに
貴方の監督をお頼みして置くわ」
「旅行はよすよ。お前のお祖母さんの所へ泊っていてもつまらないし、第一行くとすると上方だけじゃないもの」
「悪かったわ。折角思い立ちになったんだからおいで遊ばせ。そうして頂戴」
「うるさい奴だな、もうやめると決めたんだ」
「:::赤城にいらっしゃらない?赤城なら私本統に何とも思いませんわ。紅葉はもう過ぎたでしょうか」
「うるさい。もうよせ」
「お怒りになったの?」
「怒ったんじゃない」
細君は良人はやはり怒っているんだと思った。そして何か云うと尚怒らしそうなので黙る事にした。然し良人は少しも怒っ
てはいなかった。その時は実は旅行も少し億劫な気持になっていた。
「それはそうと大阪のお祖母さんのお加減はこの頃どうなんだ。お見舞いを時々出すか」
「今朝も出しました。又例のですから、そう心配はないと思いますの」
「ハ十お幾つだ?」
「ハ十四」
細君は針箱や、たたんだ仕立かけなどを持って隣室へ起って行った。そして今度は良人の寝間着を持って入って来た。良人
は起き上って裸になった。細君は後から寝間着を着せかけながら、こう云った。
「何だか段々嫉妬が烈しくなるようよ。京都でお仙が来た時、貴方だけ残して出掛けて行った事なんか今考えると不思議なよ
うですわ」
「あれは安心して出掛けて行ったお前の方が余程利口だった。お前が出掛けて行ったら尚話も何にも無くなって閉口した」
「ですけど、今は到底そんな事、出来ませんわ」
「俺がそんな不安心な人間に見えるかね」
「いいえ、貴方がそうだと云うんでもないのよ」
「そんなら先方が危いと云うのか」
「それもありますわ」
「慾目だね、俺は余り女に好かれる方じゃないよ」
「でも旅行だと如何だか知れないんじゃ有りませんか」
良人は一寸不快な顔をした。
「それとは又異う話をしているんだ'馬鹿」
「何故?」
•「もうよそう。その話は止だ」
翌朝大阪から良人宛の手紙が来た。朝寝坊な良人は未だ眠っていた。名は書いてなくても、自分宛にもなっていると田心う
と、勝手によく開封する細君はその手紙も直ぐ開封した。
それを書いたのは他へ縁付いている細君の一番上の姉で、祖母の病気が今度はどうも面白くないと書いてあった。祖母は貴
方にお気の毒だから妹は呼ばなくていいと申しますが、会いたい事の山々なのは他目にも明かで、昔気質でそうと云えない所
が尚可哀想ですと書いてあった。都合出来たらどうか二三日でいいから妹を寄越して頂きたい。私共と異って妹は赤ん坊の時
から殆ど祖母の手だけで育った児ですから、それが会わずに若し眼をねむることでもあると祖母や妹は勿論私共にも甚だ心残
りの事となります。こんな事が書いてあった。
「又姉さんが余計な事まで書いて:::」こう思いながら猶細君の眼からはポタポタと涙が手紙の上に落ちて来た。
寝室の方で、
「おい。おい」と良人の呼ぶ声がした。
細君は湯殿へ行き、泣きはらした眼を一寸冷してからその手紙と、それからその日の新聞を持って寝室に入って行った。
「お祖母さんが少しお悪いらしいのよ」仰向けになって夜着の上に両手を出している良人に新聞と一緒にそれを手渡しなが
ら云った。
良人は細君の赤い眼を見た。それからその手紙を読んだ。
「直ぐ行くといい」
「そう?行くなら早い方がいいかも知れませんわね」
「そうだよ。東京を今夜の急行で出掛けられるように早速仕度をするといい」
「そんならそうしましょうか。早く行って早く帰って来る方がいいわ。同じ事ですもの」
「早く帰る必要はないから、ゆっくり看護をして上げるといいよ」
「そりゃきっとお祖母さんの方で早く帰れ帰れって仰有ってよ。顔を見ればいいんだから早く帰っておくれって、きっとそう
仰有ってよ。私もいやだわ。そんなに永く自家を空けるのは」
「よくなられるようなら、それでいいが、万一そうでなかったら、なるべく永く居て上げなくちゃいけない。お前とお祖母さ
んとは特別な関係なんだから」
「そう?ありがとう」こう云っている内に細君の眼からは又涙が流れて来た。
「お前は余程気持をしっかり持ってないと駄目だよ。看護して上げるうえにも自分の感情に負けないように気を貼ってないと
駄目だよ」
「でも、なるべく早く帰りますわ。自家の事も心配ですもの」
良人は細君の云う意味がそんな事でないのを知りながら、つい口から出るままに、
ゝ俺も品行方正にしているからね」と笑談らしく云った。
,そりゃあ安心していますわ」と涙を拭きながら細君も笑顔をした。「けど、そう仰有って下されば尚嬉しいわ」
細君はそこそこに支度をして出発て行った。
細君からは手紙が度々来た。祖母のは肺気腫と云う病気だった。風邪から段々進んで来たものである。痰が肺へ溜る為に呼
吸する場所が狭くなる。そしてその痰を出す為にせく。せいてもせいても中々痰が出ないと呼吸が出来なくなって非常な苦し
み方をする。見ていられない。病気そのものはそれ程危険ではないが、その苦しみの為に段々衰弱する。それが心配だと書い
て来た。然し何しろ気の勝った人の事で、気で病気に抵抗しているのが——残酷な気のする事もあるが——嬉しいと書いて
来た。
細君は中々帰れなかった。祖母の病気はよくも悪くもならなかった。それは実際気で持っているらしかった。
細君が行って四週間程して良人も其処へ出掛けて行った。然しその頃から祖母は幾らかずついい方へ向った。気丈は遂に病
気に勝った。良人は十日程居て妻と一緒に帰って来た。それは大晦日に間もない頃だった。
祖母はそれからもニタ月余り床を離れる事は出来なかった。然し三月初めの或日、夫婦は小包郵便で大阪からの床あげの祝
きじょう
物を受け取った。
三
それは春の春らしい長閑な日の午前だった。良人は四五日前から巣についている鶏に卵を抱かしてやろうと思って、巣函の
藁をとり更えていると、不図妙な吐気の声を聴いた。滝だ。女中部屋の窓から顔を出して頻りに何か吐こうとしている。吐こ
うとするが何も出ないので只生唾を吐き捨てていた。
彼は籾殻を敷いた菓子折から叮噪に卵を一つ一つ巣函へ移していた。そしてああ云う吐気の声は前にも一度聴いた事がある
と考えた。父の家に居た頃、門番のかみさんがよくああいう声を出していたと思った。彼はその時それを母に話すと、母は「赤
ん坊が出来たので悪阻でそんな声を出すんだろうよ」と云った。母の云うようにそれは実際妊娠だった。
彼はそれを憶い出して、滝のも妊娠かなと思った。——彼は翌日もその声を聴いた。それからその翌日も聴いた。
四
滝のが妊娠だとすると、これは先ず自分が疑われる、と良人は考えた。何しろ過去が過去だし、それに独身時代ではあった
にしろ、女中とのそう云う事も一度ならずあったし、又現在にしろ、それを細君に疑われた場合、「飛んでもない」と驚いた
り怒ったりするのは我ながら少し空々しい自分だと考えた。これは恥ずべき事に違いないと彼は思った。
彼は結婚した時からそう云う事には自信がなかった。彼はそれを細君に云った。一人で外国へ行った場合とか、ート月或い
はニタ月位の旅行をする場合とか、と云った。その時は細君も或程度に認めるような返事をしていた。
それからも良人はその危険性の自分にある事を半分笑談にして云った。又或時は既にそれを冒しているようにも云った。そ
して後のを云う場合には知らず知らず意地悪い厭がらせを云う調子で云っていた。これは狡い事だ。その場合、彼では打ち明
ける事が主であった。然し聴く者には厭がらせが主であると解れるように彼は云っていた。聴く者にとって厭がらせを主とし
て感ずれば、それだけ云われた事実は多少半信半疑の事がらになる。良人は故意でそうするのではなかった。知らず知らずそ
んな調子になるのだ。尤も細君もそれを露骨に打ち明けられる事は恐れていた。自身でもそれを云っていた。そして最初或
程度に認めるように云っていた細君も何時とはなしに、それは認めないと云うようになった。
滝のが結果から、或いは医者の診察から、若し細君の留守中に起った事と云う事になればそれは尚厄介な事だと良人は思っ
た。然し実際は疑われても仕方がない。事実にそう云う事はなかったにしろ、そう云う気を全く起さなかったとは云えないか
らと思った。
彼は滝を嫌ではなかった。それは細君の留守中の事ではあったが、例えば狭い廊下で偶然出会頭に滝と衝突しかけた事が
ある。そして両方で一寸まごついて危く身をかわし、漸くすり抜けて行き過ぎるような場合がある。そういう時彼は胸でド
キドキと血の動くのを感ずる事があった。それは不思議な悩しい快感であった。それが彼の胸を通り抜けて行く時、彼は興奮
に似た何ものかで自分の顔の紅くなるのを感じた。それは咄嗟に来た。彼にはそれを道義的に批判する余裕はなかった。それ
程不意に来て不意に通り抜けていく。が、これはまだよかった。
然しそうでない場合、例えば夜座敷で本を見ているような場合、或いは既に寝室にいるような場合、其処に家の習慣に従っ
て滝が寝る前の「御機嫌よう」を云いに来る。すると、彼は毎時のように只「うん」と答えるだけでは何か物足りない気のす
る事がよくあった。彼は現在廊下を帰りつつある滝を追って行く或気持の自身にある事を感ずる事がよくあった。彼はそれを
余りに明かに感ずる時、何かしら用を云いつける。「一寸書斎からペンを取って来てくれ」とか或いは「少し寒いから上へ毛
布を掛けてくれ」とか云う。云いながら底意の為に自分ながらそれが不自然に聴えて困った。彼は自分の底意を滝に見抜かれ
ていると思う事もよくあった。然しこんなにも考えた。滝は自分の底意を見抜いている。そしてそれに気味悪さを感じている。
然し気味悪がりながら尚その冒険に或快感を感じている——彼は実際そんな気がした。彼は自身と共通な気持が滝にもその場
合起っていると思った。そして全体滝はまだ処女かしら?それとも、——こんな考の頭をもたげる事もあった。
細君が大阪へ出発てからは必要からも滝はもっとの用を彼の為にしなければならなかった。滝はそれを忠実にした。彼の底
意が見られたと彼が思ってからも滝の忠実さは少しも変わらなかった。それは尚忠実になったような気が彼にはした。しかも
その忠実さは淫奔女の親切ではないと思った。——けれどもとにかく、それは淡い放蕩には違いなかった。
そう思って、彼は前の咄嗟に彼の胸を通り抜けて行く悩しい快感の場合を考えた。然し、それを放蕩と云う気はしなかった。
根本で二つは変りなかった。——然しゃはりそれを同じに云う事は出来ないと思った。
滝は十八位だった。色は少し黒い方だが可愛い顔だと彼は思っていた。それよりも彼は滝の声音の色を愛した。それは女と
しては太いが、丸味のある柔かい、いい感じがした。
彼は然し滝に恋するような気持は持っていなかった。若し彼に細君がなかったらそれは或いはもっと進んだかも知れない。
然し彼には家庭の調子を乱したくない気が知らず知らずの間に働いていた。そしてそれを越えるまでの誘惑を彼は滝には感じ
なかった。或いは感じないように自身を不知掌理していたのかも知れない。そういう事も或程度までは出来るものだと彼は思
っている。
五
良人はこれはやはり自分から云い出さなければけないと思った。そう思えばこの四五日細君は何だか元気がなくなっている。
然し未だ児を生んだ事のない細君が悪阻を知っているかしら?そう良人は思った。とにかく、元気のない理由がそれなら早
く云ってやらなければ可哀想だと思った。それに滝の方も田舎によくある若し不自然な真似でもする事があっては大変だと思
った。そして一体相手は誰かしらと考えた。それは一寸見当が付かなかった。何しろ自分達が余り不愉快を感じない人間であ
ってくれればいいがと思った。彼は淡い嫉妬を感じていたが、それは自身を不愉快にする程度のものではなかった。
良人は細君が大概それを素直に受け入れるだろうと思った。然し若し素直に受け入れなかったら困ると思った。その場合自
分には到底むきになって弁解する事は出来まいと思った。弁解する場合その誤解を不当だという気が此方になければそうむき
になれるものではない。しかも疑われれば誤解だが、自分の持った気持まで立入られればそれは必ずしも誤解とは云えないの
だから、と思った。
とにかく、このままにして置いては不可ない。彼はそう思って、書斎を出て行った。
細君は座敷の次の間に坐って滝が物干から取り込んで置いた襦祥だの、タオルだの、シーツだのを畳んでいた。細君は良人
が良人が行っても何故か顔を挙げなかった。
「おい」と良人は割に気軽に声を掛けた。
「何?」細君は艶のない声で物憂そうな眼を挙げた。
「そんな元気のない顔をして如何したんだ」
「別に如何もしませんわ」
「如何もしなければいいが……お前は滝が時々吐くような変な声を出しているのを気がついているか?」
「ええ」そう云った時細君の物憂そうな眼が一寸光ったように良人は思った。
「どうしたんだ」
「お医者さんに診て貰ったらいいだろうって云うんですけど、中々出掛けませんわ」
「全体何の病気なんだ」
「解りませんわ」細君は一寸不愉快な顔をして眼を落して了った。
「お前は知ってるね」良人は追いかけるように云った。
細君は下を向いたまま、返事をしなかった。良人は続けた。
「知ってるなら尚いい。然しそれは俺じゃないよ」
細君は驚いたように顔を挙げた。良人は今度は明かに細君の眼の光ったのを見た。そして見ている内に細君の胸は浪打って
来た。
「俺はそう云う事を仕兼ねない人間だが、今度の場合、それは俺じゃあない」
細君は立っている良人の眼を凝っと見つめていたが、更にその眼を中段の的のない遠い所へやって、黙っている。
「おい」と良人は促すように強くいった。
細君は脣を震わしていたが、漸く、
「ありがとう」と云うとその大きく開いていた眼からは涙が止途なく流れて来た。
「よしよし。そうそれでいい」良人は坐ってその膝に細君を抱くようにした。彼は実際しなかったにしろ、それに近い気持を
持った事を今更に心に恥じた。然し今はそれを打明ける時ではないと思った。
「それを伺えば私にはもう何も云う事は御座いませんわ。貴方が何時それを云って下さるか待っていたの」細君は泣きながら
云った。
「お前はやっぱり疑っていたのか」
「いいえ、信じていましたわ。でも、此方から伺うのは可恐かったの」
「それ見ろ、やっぱり疑っていたんだ」
「いいえ、本統に信じていたの」
「嘘つけ、そう信じれば、それが本統になってくれるような気がしたんだろう。ともかくそれでいい、お前は中々利口だ。お
前は素直に受け入れてくれるだろうとは思っていたが、若し素直に受け入れなければ俺は疑われても仕方がないと思っていた
のだ。然し素直に信じてくれたので大変よかった。疑いだせば、疑う種は幾らでも出て来るだろうし、その為に両方で不愉快
な思いをしなければならないところだった。俺は明かな嘘は云わないつもりだ。笑談や厭がらせを云う時、反って嘘に近い
事を知らずに云うかも知れないが、断言的に嘘は云わないつもりだ……」
「もう仰有らないで頂戴。よく解ってます」細君は妙な興奮から苛々した調子で良人の言葉を遮った。
良人は苦笑しながら一寸黙った。
「然しあとはどうする」
「あとの事なんか、今云わないで……。滝が好きならその男と一緒にするようにしてやればいいじゃありませんか」
「そう簡単に行くものか」
「まあそれは後にして頂戴って云うのに……。もういや。そんな他の話は如何でもいいじゃありませんか」
「他の話じゃない」
「もういいのよ。……貴方もこれからそんな事で私に心配を掛けちゃあ、いやですよ」細君は濡れた眼をすえて良人を睨んだ。
「よしよし。解ったらもうそれでいい。又無闇と興奮すると後で困るぞ」
「何故もっと早く云って下さらなかったの?いやな方ね、人の気も知らずに」
「全体お前は悪阻と云う事を知っているのか」
「その位知っていますわ。清さんの生れる時に姉さんの悪阻は随分ひどかったんですもの」
「知ってるのか」
「そりゃあ知ってますわ、それより貴方の知っていらっしゃる方が余程可笑しいわ。男の癖に」
「俺は知ってる訳があるんだ」
「又そんないやな事を仰有る」
「お前は滝のは何時頃から気がついたんだ」
「もう四五日前からよ」
「俺は一昨日からだ。その間お前はよく黙っていられたな。やっぱり疑っていたんだな」
「貴方こそ、よく三日も黙っていらしたのね」
そんな事を云いながら、細君は身体をブルブル震"していた。
「どうしたんだ」良人は手を延ばして今は対座している細君の肩へ触ってみた。
「何だか妙に震えて困るわ」こう云いながら細君は頤を引いて自分の胸から肩の辺を見廻した。
「興奮したんだ。馬鹿な奴だな」
「本統にどうしたんでしょう。どうしても止まらないわ」
「寝るといい。此処でいいから暫く静かに横になってて御覽」
「お湯を飲んで見ましょう」そういって細君は起って茶の間へ行った。そして戸棚から湯呑みを出しながら、
「滝には出来るだけの事をしてやりましょうね」と云った。
「うん。それがいい。それはお前に任せるからね。そして云うなら早い方がいいよ。そんな事もあるまいが、不自然な事でも
すると取り返しが附かないからね」
「本統にそうね。明日早速お医者さんに診せましょう。——まあ、如何したの?未だ止まらないわ」こういまいましそうに云
いながら細君は長火鉢の鉄瓶から湯を注いだ。そしてそれを口へ持って行こうとするとその手は可笑しい程ブルブル震えた。
芥川龍之介
「運」
目のあらい簾が、入口にぶらさげてあるので、往来の容子は仕事場にいても、よく見えた。清水へ通う往来は、さつきか
ら、人通りが絶えない。金鼓をかけた法師が通る。壺装束をした女が通る。その後からは、めずらしく、黄牛に曳かせた網代車
が通った。それが皆、疎な蒲の簾の目を、右からも左からも、来たかと思うと、通りぬけてしまう。その中で変らないのは、
午後の日が暖に春を炙っている、狭い往来の土の色ばかりである。
その人の往来を、仕事場の中から、何と云う事もなく眺めていた、一人の青侍が、この時、ふと思いついたように、主の
陶器師へ声をかけた。
「相不変、観音様へ参詣する人が多いようだね。」
「左様でございます。」
陶器師は、仕事に気をとられていたせいか、少し迷惑そうに、こう答えた。が、これは眼の小さい、鼻の上を向いた、何処
かひょうきんな所のある老人で、顔つきにも容子にも、悪気らしいものは、微塵もない。着ているのは、麻の帷子であろう。
それに萎えた揉烏帽子をかけたのが、この頃評判の高い鳥羽僧正の絵巻の中の人物を見るようである。
「私も一つ、日参でもして見ようか。こう、うだつが上らなくちゃ、やりきれない。」
「御冗談で。」
「なに、これで善い運が授かるとなれば、私だって、信心をするよ。日参をしたって、参籠をしたって、そうとすれば、安い
ものだからね。つまり、神仏を相手に、一商売をするようなものさ。」
青侍は、年相応な上調子なもの言いをして、下唇を舐めながら、きょろきよろ、仕事場の中を見廻した。——竹藪を後に
して建てた、藁葺きのあばら家だから、中は鼻がつかえるほど狭い。が、簾の外の往来が、目まぐるしく動くのに引換えて、
此処では、甕でも瓶子でも、皆赭ちゃけた土器の肌をのどかな春風に吹かせながら、百年も昔からそうしていたように、ひっ
そりかんと静まっている。どうやらこの家の棟ばかりは、燕さえも巣を食わないらしい。……
翁が返事をしないので、青侍はまた語を継いだ。
「お爺さんなんぞも、この年までには、随分いろんな事を見たり聞いたりしたろうね。どうだい。観音様は、ほんとうに運を
授けて下さるものかね。」
「左様でございます。昔は折々、そんな事もあったように聞いておりますが。」
「どんな事があったね。」
「どんな事と云って、そう一 口には申せませんがな。——しかし、貴方がたは、そんな話をお聞きなすっても、格別面白くも
ございますまい。」
「可哀そうに、これでも少しは信心気のある男なんだぜ。愈〃運が授かるとなれば、明日にも——」
「信心気でございますかな。商売気でございますかな。」
翁は、眦に皺をよせて笑った。捏ねていた土が、壺の形になったので、やっと気が楽になったと云う調子である。
「神仏の御考えなどと申すものは、貴方がたくらいの御年では、中々わからないものでございますよ。」
「それはわからなかろうさ。わからないから、お爺さんに聞くんだあね。」
「いやさ、神仏が運をお授けになる、ならないと云う事じゃございません。そのお授けになる運の善し悪しと云う事が。」
「だって、授けて貰えばわかるじゃないか。善い運だとか、悪い運だとか。」
「それが、どうも貴方がたには、ちとおわかりになり兼ねましょうて。」
「私には運の善し悪しより、そう云う理窟の方がわからなそうだね。」
日が傾き出したのであろう。さっきから見ると、往来へ落ちる物の影が、心もち長くなった。その長い影をひきながら、頭
に桶をのせた物売りの女が二人、簾の目を横に、通りすぎる。一人は手に宿への土産らしい桜の枝を持っていた。
「今、西の市で、績麻の店を出している女なぞもそうでございますが。」
「だから、私はさっきから、お爺さんの話を聞きたがっているじゃないか。」
二人は、暫 の間、黙った。青侍は、爪で頤のひげを抜きながら、ぼんやり往来を眺めている。貝殻のように白く光るのは、
大方さっきの桜の花がこぼれたのであろう。
「話さないかね。お爺さん。」
やがて、眠むそうな声で、青侍が云った。
「では、御免を蒙って、一つ御話し申しましょうか。また、何時もの昔話でございますが。」
こう前置きをして、陶器師の翁は、徐に話し出した。日の長い短いも知らない人でなくては、話せないような、悠長な□
ぶりで話し出したのである。
「もうかれこれ三四十年前になりましょう。あの女がまだ娘の時分に、この清水の観音様へ、願をかけた事がございました。
どうぞー生安楽に暮せますようにと申しましてな。何しろ、その時分は、あの女もたった一人のおふくろに死別れた後で、そ
れこそ日々の暮しにも差支えるような身の上でございましたから、そう云う願をかけたのも、満更無理はございません。
「死んだおふくろと申すのは、もと白朱社の巫子で、一しきりは大そう流行ったものでございますが、狐を使うと云う噂を
立てられてからは、めっきり人も来なくなってしまったようでございます。これがまた、白あばたの、年に似合わず水々しい、
大がらな婆さんでございましてな、何さま、あの容子じゃ、狐どころか男でも
「おふくろの話よりは、その娘の話の方を伺いたいね。」
「いや、これは御挨拶で。——そのおふくろが死んだので、後は娘一人の痩せ腕でございますから、いくらかせいでも、暮し
の立てられようがございませぬ。そこで、あの容貌のよい、利発者の娘が、お籠りをするにも、檻褸故に、あたりへ気がひけ
ると云う始末でございました。」
「へえ。そんなに好い女だったかい。」
「左様でございます。気だてと云い、顔と云い、手前の欲目では、先どこへ出しても、恥しくないと思いましたがな。」
「惜しい事に、昔さね。」
青侍は、色のさめた藍の水干の袖口を、ちょいとひっぱりながら、こんな事を云う。翁は、笑声を鼻から抜いて、またゆっ
くり話しつづけた。後の竹藪では、頻に鶯が啼いている。
「それが、三七日の間、御籠りをして、今日が満願と云う夜に、ふと夢を見ました。何でも、同じ御堂に詣っていた連中の中
に、背むしの坊主が一人いて、そいつが何か陀羅尼のようなものを、くどくど誦していたそうでございます。大方それが、気
になったせいでございましょう。うとうと眠気がさして来ても、その声ばかりは、どうしても耳をはなれませぬ。とんと、縁
の下で蚯蚓でも鳴いているような心もちで——すると、その声が、何時の間にやら人間の語になって、『ここから帰る路で、
そなたに云いよる男がある。その男の云う事を聞くがよい。』と、こう聞えると申すのでございますな。
「はっと思って、眼がさめると、坊主はやっぱり陀羅尼三昧でございます。が、何と云っているのだか、いくら耳を澄まして
も、わかりませぬ。その時、何気なく、ひょいと向うを見ると、常夜燈のぼんやりした明りで、観音様の御顔が見えました。
日頃拝みなれた、端厳微妙の御顔でございますが、それを見ると、不思議にも又耳もとで、『その男の云う事を聞くがよい。』
と、誰だか云うような気がしたそうでございます。そこで、娘はそれを観音様の御告だと、一図に思いこんでしまいましたげ
な。」
「はてね。」
「さて、夜がふけてから、御寺を出て、だらだら下りの坂路を、五条へくだろうとしますと、案の定後から、男が一人抱き
つきました。丁度、春さきの暖い晩でございましたが、生憎の暗で、相手の男の顔も見えなければ、着ている物などは、猶の
事わかりませぬ。唯、ふり離そうとする拍子に、手が向うの口髭にさわりました。いやはや、とんだ時が、満願の夜に当った
ものでございます。
「その上、相手は、名を訊かれても、名を申しませぬ。所を訊かれても、所を申しませぬ。ただ、云う事を聞けと云うばかり
で、坂下の路を北へ北へ、抱きすくめたまま、引きずるようにして、つれて行きます。泣こうにも、喚こうにも、まるで人通
りのない時分なのだから、仕方がございませぬ。」
「ははあ、それから。」
「それから、とうとうハ坂寺の塔の中へ、つれこまれて、その晩は其処ですごしたそうでございます。——いや、その辺の事
なら、何も年よりの手前などが、わざわざ申し上げるまでもございますまい。」
翁は、また眦に皺をよせて、笑った。往来の影は、愈〃長くなったらしい。吹くともなく渡る風のせいであろう、其処此
処に散っている桜の花も、いつの間にかこっちへ吹きよせられて、今では、雨落ちの石の間に、点々と白い色をこぼしている。
「冗談云っちゃいけない。」
青侍は、思い出したように、顋のひげを抜き抜き、こう云った。
あご
「それで、もうおしまいかい。」
「それだけなら、何もわざわざお話し申すがものはございませぬ。」翁は、やはり壺をいじりながら、「夜があけると、その
男が、こうなるのも大方宿世の縁だろうから、とてもの事に夫婦になってくれと申したそうでございます。」
晟程。」
「夢の御告げでもないならともかく、娘は、観音様のお思召し通りになるのだと思ったものでございますから、とうとう首
を竪にふりました。さて形ばかりの 盃事をすませると、先、当座の用にと云って、塔の奥から出して来てくれたのが綾を十
疋に絹を十疋でございます。——この真似ばかりは、いくら貴方にもちとむずかしいかも存じませんな。」
青侍は、にやにや笑うばかりで、返事をしない。鶯も、もう啼かなくなった。
「やがて、男は、日の暮に帰ると云って、娘一人を留守居に、慌しく何処かへ出て参りました。その後の淋しさは、又一倍
でございます。いくら利発者でも、こうなると、さすがに心細くなるのでございましょう。そこで、心晴らしに、何気なく塔
の奥へ行って見ると、どうでございましょう。綾や絹は愚な事、珠玉とか砂金とか云う金目の物が、皮匣に幾つともなく、
並べてあると云うじゃございませぬか。これにはああ云う気丈な娘でも、思わず吐胸をついたそうでございます。
「物にもよりますが、こんな財物を持っているからは、もう疑はございませぬ。引剥でなければ、物盗りでございます。!
!そう思うと、今までは唯、さびしいだけだったのが、急に、怖いのも手伝って、'何だか片時も此処にこうしては、いられな
いような気になりました。何さま、悪く放免の手にでもかかろうものなら、どんな目に遭うかも知れませぬ。
「そこで、逃げ場をさがす気で、急いで戸口の方へ引返そうと致しますと、誰だか、皮匣の後から、しわがれた声で呼びとめ
ました。何しろ、人はいないとばかり思っていた所でございますから、驚いたの驚かないのじゃございませぬ。見ると、人間
とも海鼠ともつかないようなものが、砂金の袋を積んだ中に、円くなって、坐っております。——これが目くされの、皺だら
けの' 腰のまがった、背の低い、六十ばかりの尼法師でございました。しかも娘の思惑を知ってか、知らないでか、膝で前へ
のり出しながら、見かけによらない猫撫声で、初対面の挨拶をするのでございます。
「こっちは' それどころの騒ぎではないのでございますが、何しろ逃げようと云う巧みをけどられなどしては大変だと思った
ので、しぶしぶ皮匣の上に肘をつきながら心にもない世間話をはじめました。どうも話の容子では、この婆さんが、今まであ
の男の炊女か何かつとめていたらしいのでございます。が、男の商売の事になると、妙に一 □も話しませぬ。それさえ、娘の
方では、気になるのに、その尼が又、少し耳が遠いと来ているものでございますから、一つ話を何度となく、云い直したり聞
き直したりするので、こっちはもう泣き出したいほど、気がじれます。——
「そんな事が、かれこれ午までつづいたでございましょう。すると、やれ清水の桜が咲いたの、やれ五条の橋普請が出来たの
と云っている中に、幸、年の加減か、この婆さんが、そろそろ居睡りをはじめました。一つは娘の返答が、はかばかしくな
かったせいもあるのでございましょう。そこで、娘は、折を計って、相手の寝息を窺いながら、そっと入口まで這って行っ
て、戸を細目にあけて見ました。外にも、いい案配に、人のけはいはございませぬ。——
「此処でそのまま、逃げ出してしまえば、何事もなかったのでございますが、ふと今朝貰った綾と絹との事を思い出したので、
それを取りに、またそっと皮匣の所まで帰って参りました。すると、どうした拍子か、砂金の袋にけっまずいて、思わず手が
婆さんの膝にさわったから、たまりませぬ。尼の奴め驚いて眼をさますと、暫 は唯、あっけにとられて' いたようでござい
ますが' 急に気ちがいのようになって、娘の足にかじりつきました。そうして、半分泣き声で、早口に何かしゃべり立てます。
切れ切れに、語が耳へはいる所では、万一娘に逃げられたら、自分がどんなひどい目に遇うかも知れないと、こう云ってい
るらしいのでございますな。が、こっちも此処にいては命にかかわると云う時でございますから、元よりそんな事に耳をかす
訳がございませぬ。そこで、とうとう、女同志のつかみ合がはじまりました。
「打つ。蹴る。砂金の袋をなげつける。——梁に巣を食った鼠も、落ちそうな騒ぎでございます。それに、こうなると、死
物狂いだけに、婆さんのヵも、莫迦には出来ませぬ。が、そこは年のちがいでございましょう。間もなく、娘が、綾と絹とを
小脇にかかえて、息を切らしながら、塔の戸口をこっそり、忍び出た時には、尼はもう、□もきかないようになって居りまし
た。これは、後で聞いたのでございますが、屍骸は、鼻から血を少し出して、頭から砂金を浴びせられたまま、薄暗い隅の方
に、仰向けになって、臥ていたそうでございます。
「こっちはハ坂寺を出ると、町家の多い所は、さすがに気がさしたと見えて、五条京極辺の知人の家をたずねました。この
知人と云うのも、その日暮しの貧乏人なのでございますが、絹の一疋もやったからでございましょう、湯を沸かすやら、粥を
煮るやら、いろいろ経営してくれたそうでございます。そこで、娘もж く、ほっと一息つく事が出来ました。」
「私も、やっと安心したよ。」
青侍は、帯にはさんでいた扇をぬいて、簾の外の夕日を眺めながら、それを器用に、ぱちっかせた。その夕日の中を、今し
がた白丁が五六人、騒々しく笑い興じながら、通りすぎたが、影はまだ往来に残っている。……
「じゃそれで愈〃けりがついたと云う訳だね。」
を見いと、
たものか、
「ところが」翁は大仰に首を振って、「その知人の家に居りますと、急に往来の人通りがはげしくなって、あれを見い、あれ
罵り合う声が聞えます。何しろ、後暗い体ですから、娘は又、胸を痛めました。あの物盗りが仕返ししにでも来
検非違使の追手がかかりでもしたものか、——そう思うともう、おちおち、粥を啜っても居られま
さもなければ、
せぬ。」
晟程。」
「そこで、
戸の隙間から、
そっと外を覗いて見ると、見物の男女の中を、放免が五六人、それに看督長が一人ついて、物々し
げに通りました。それからその連中にかこまれて、縄にかかった男が一人、所々裂けた水干を着て烏帽子もかぶらず、曳かれ
て参ります。どうも物盗りを捕えて、これからその住家へ、実録をしに行く所らしいのでございますな。
「しかも、その物盗りと云うのが、昨夜、五条の坂で云いよった、あの男だそうじゃございませぬか。娘はそれを見ると、何
故か、涙がこみ上げて来たそうでございます。これは、当人が、手前に話しました——何も、その男に惚れていたの、どうし
たのと云う訳じゃない。が、その縄目をうけた姿を見たら、急に自分で、自分がいじらしくなって、思わず泣いてしまったと、
まあこう云うのでございますがな。まことにその話を聞いた時には、手前もつくづくそう思いましたよ——」
「何とね。」
「観音様へ 願をかけるのも考え物だとな。」
「だが、お爺さん。その女は、それから、どうにかやって行けるようになったのだろう。」
「どうにかどころか、今では何不自由ない身の上になっております。その綾や絹を売ったのを本に致しましてな。観音様も、
これだけは、御約束をおちがえになりません。」
「それなら、そのくらいな目に遇っても、結構じゃないか。」
外の日の光は、いつの間にか、黄いろくタづいた。その中を、風だった竹藪の音が、かすかながら其処此処から聞えて来る。
往来の人通りも、暫くはとだえたらしい。
「人を殺したって、物盗りの女房になったって、する気でしたんでなければ仕方がないやね。」
青侍は、扇を帯へさしながら、立上った。翁も、もう提の水で、泥にまみれた手を洗っている——二人とも、どうやら、
暮れてゆく春の日と、相手の心もちとに、物足りない何ものかを、感じてでもいるような容子である。
「とにかく、その女は仕合せ者だよ。」
「御冗談で。」
「まったくさ。お爺さんも、そう思うだろう。」
「手前でございますか。手前なら、そう云う運はまっぴらでございますな。」
「へええ、そうかね。私なら、二つ返事で、授けて頂くがね。」
「じゃ観音様を、御信心なさいまし。」
「そうそう、明日から私も、お籠でもしょうよ。」
「蜜柑」
或曇った冬の日暮である。私は横須賀發上り二等客車の隅に腰を下して、ぼんやり發車の笛を待ってゐた。とうに電燈のっ
いた客車の中には、珍らしく私の外に一人も乘客はゐなかった。外を覗くと、うす暗いプラットフォオムにも、今日は珍しく
見送りの人影さへ跡を絶って、唯、檻に入れられた小犬が一匹、時時悲しさうに、吠え立ててゐた。これらはその時の私の心
もちと、不思議な位似つかはしい景色だった。私の頭の中には云ひゃうのない疲勞と倦怠とが、まるで雪曇りの空のやうなど
んよりした影を落してゐた。私は外套のポケットへぢつと兩手をつっこんだ儘、そこにはいってゐる夕刊を出して見ようと云
ふ元氣さへ起らなかった。
が、やがて發車の笛が鳴った。私はかすかな心の寛ぎを感じながら、後の窓枠へ頭をもたせて、眼の前の停車場がずるず
ると後ずさりを始めるのを待つともなく待ちかまへてゐた。處がそれよりも先にけたたましい日和下駄の音が、改札口の方か
ら聞え出したと思ふと、間もなく車掌の何か云ひ罵る聲と共に、私の乘ってゐる二等室の戸ががらりと開いて、十三四の小
娘が一人、慌しく中へはいって來た、と同時に一つづしりと揺れて、徐に汽車は動き出した。一本づつ眼をくぎって行くプ
ラットフォオムの柱、置き忘れたやうな運水車、それから車内の誰かに祝儀の禮を云ってゐる赤帽——さう云ふすべては、窓
へ吹きつける煤煙の中に、未練がましく後へ倒れて行った。私は漸くほっとした心もちになって、巻煙草に火をつけながら、
始めて懶い瞼をあげて、前の席に腰を下してゐた小娘の顔を一瞥した。
それは油氣のない髪をひっつめの銀杏返しに結って、横なでの痕のある鞭だらけの兩頰を気持の惡い程赤く火照らせた、如
何にも田舎者らしい娘だった。しかも垢じみた萌葱色の毛絲の襟巻がだらりと垂れ下った膝の上には、大きな風呂敷包みがあ
った。その又包みを抱いた霜燒けの手の中には、三等の赤切符が大事さうにしっかり握られてゐた。私はこの小娘の下品な顔
だちを好まなかった。それから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった。最後にその二等と三等との區別さへも辨へない
愚鈍な心が腹立たしかった。だから巻煙草に火をつけた私は、一つにはこの小娘の存在を忘れたいと云ふ心もちもあって、今
度はポケットの夕刊を漫然と膝の上へひろげて見た。すると其時夕刊の紙面に落ちてゐた外光が、突然電燈の光に變って、
刷の惡い何欄かの活字が意外な位鮮 に私の眼の前へ浮んで來た。云ふまでもなく汽車は今、横須賀線に多い隧道の最初のそ
れへはいったのである。
しかしその電燈の光に照らされた夕刊の紙面を見渡しても、やはり私の憂欝を慰むべく、世間は餘りに平凡な出來事ばかり
で持ち切ってゐた。講和問題、新婦、新郎、流職事件、死亡廣告——私は隧道へはいった一瞬間、汽車の走ってゐる方向が
逆になったやうな錯覺を感じながら、それらの索漠とした記事から記事へ 殆、機械的に眼を通した。が、その間も勿論あ
の小娘が、恰も卑俗な現實を人間にしたやうな面もちで、私の前に坐ってゐる事を絶えず意識せずにはゐられなかった。こ
の隧道の中の汽車と、この田舎者の小娘と、さうして又この平凡な記事に埋ってゐる夕刊と、——これが象徵でなくて何であ
らう。不可解な、下等な、退屈な人生の象徴でなくて何であらう。私は一切がくだらなくなって、讀みかけた夕刊を抛り出す
と、又窓枠に頭を靠せながら、死んだやうに眼をつぶって、うつらうつらし始めた。
それから幾分か過ぎた後であった。ふと何かに脅されたやうな心もちがして、思はずあたりを見まはすと、何時の間にか
例の小娘が、向う側から席を私の隣へ移して、頻に窓を開けようとしてゐる。が、重い硝子戸は中中思ふやうにあがらないら
しい。あの鞭だらけの頰は愈、赤くなって、時時演をすすりこむ音が、小さな息の切れる聲と一しょに、せはしなく耳へは
いって來る。これは勿論私にも、幾分ながら同情を惹くに足るものには相違なかった。しかし汽車が今将に隧道の口へさしか
からうとしてゐる事は、暮色の中に枯草ばかり明い兩側の山腹が、間近く窓側に迫って来たのでも、すぐに合點の行く事であ
った。にも關らずこの小娘は、わざわざしめてある窓の戸を下さうとする、——その理由が私には呑みこめなかった。いや、
それが私には、單にこの小娘の氣まぐれだとしか考へられなかった。だから私は腹の底に依然として險しい感情を蓄へながら、
あの霜燒けの手が硝子戸を«げようとして惡戦苦闘する樣子を、まるでそれが永久に成功しない事でも祈るやうな冷酷な眼で
眺めてゐた。すると間もなく凄じい音をはためかせて、汽車が隧道へなだれこむと同時に、小娘の開けようとした硝子戸は、
とうとうばたりと下へ落ちた。さうしてその四角な穴の中から、煤を溶したやうなどす黑い空気が、俄に息苦しい煙になっ
て、濠濠と車内へ 漲り出した。元來咽喉を害してゐた私は、手巾を顔に當てる暇さへなく、この煙を満面に浴びせられたお
かげで、殆、息もつけない程咳きこまなければならなかった。が、小娘は私に頓着する氣色も見えず、窓から外へ首をのば
して、иを吹く風に銀杏返しの鬢の毛を戰がせながら、ぢっと汽車の進む方向を見やってゐる。その姿を煤煙と電燈の光と
の中に眺めた時、もう窓の外が見る見る明くなって、そこから土の匂や枯草の匂や水の匂が冷かに流れこんで來なかったな
ら、漸く咳きゃんだ私は、この見知らない小娘を頭ごなしに叱りつけてでも、又元の通り窓の戸をしめさせたのに相違なか
ったのである。
しかし汽車はその時分には、もう安安と隧道を」」りぬけて、枯草の山と山との間に挾まれた、或貧しい町はづれの踏切りに
通りかかってゐた。踏切りの近くには、いづれも見すぼらしい藁屋根や瓦屋根がごみごみと狭苦しく建てこんで、踏切り番が
振るのであらう、唯一旎のうす白い旗が懶げに暮色を搖ってゐた。やっと隧道を出たと思ふ——その時その蕭索とした踏切
りの柵の向うに、私は頰の赤い三人の男の子が、目白押しに並んで立ってゐるのを見た。彼等は皆、この曇天に押しすくめら
れたかと思ふ程、揃って背が低かった。さうして又この町はづれの陰慘たる風物と同じゃうな色の着物を着てゐた。それが汽
車の通るのを仰ぎ見ながら、一齊に手を擧げるが早いか、いたいけな喉を高く反らせて、何とも意味の分らない喊聲を一生懸
命に 迸らせた。するとその瞬間である。窓から半身を乗り出してゐた例の娘が、あの霜燒けの手をっとのばして、勢よく左
右に振ったと思ふと、忽ち心を躍らすばかり暖な日の色に染まってゐる蜜柑が凡そ五つ六つ、汽車を見送った子供たちの上へ
ばらばらと空から降って來た。私は思はず息を呑んだ。さうして刹那に一切を了解した。小娘は、恐らくはこれから奉公先へ
赴かうとしてゐる小娘は、その懐に藏してゐた幾顆の蜜柑を窓から投げて、わざわざ踏切りまで見送りに來た弟たちの勞に
報いたのである。
暮色を帶びた町はづれの踏切りと、小鳥のやうに聲を擧げた三人の子供たちと、さうしてその上に亂落する鮮な蜜柑の色と
——すべては汽車の窓の外に、瞬く暇もなく通り過ぎた。が、私の心の上には、切ない程はっきりと、この光景が燒きつけ
られた。さうしてそこから、或得體の知れない 朗な心もちが湧き上って來るのを意識した。私は昂然と頭を擧げて、まるで
別人を見るやうにあの小娘を注視した。小娘は何時かもう私の前の席に返って、不相變鞭だらけの頰を萌葱色の毛絲の襟巻に
埋めながら、大きな風呂敷包みを抱へた手に、しっかりと三等切符を握ってゐる。
私はこの時始めて、云ひゃうのない疲勞と倦怠とを、さうして又不可解な、下等な、退屈な人生を纔に忘れる事が出來た
のである。
宮本百合子
「おもかげ」
睡りからさめるといふより、悲しさで目がさまされたといふふうに朝子はぽっかり枕の上で目をあけた。
夏のおそい午後の光線が、細長くて白い部屋の壁の上に窓外の菩提樹の綠をかすかに映しながら踊ってゐる。その小さい部
屋に湛へられてゐる隈ない明るさと靜寂とはそとの往來やこの町いっぱいつづいてゐる感じのもので、臥てゐる朝子の今の悲
しさとよくつりあった。明るさも海のやうで、朝子はその中に仰向けに浮んだやうに目瞬きもしなかった。
桃花心木色の半圓形のテーブルの上のコップに、日本の狐のしっぽのやうな穗草や紫色の野草の花が挿さってゐる。一昨日、
この下宿のあるデヱーッコヱ・セローの公園のずっと先の廣い野原で夏雲を眺めながら摘んで來た花であった。しかし一昨日
の宵からけふまでの間は、ぽっとなってゐ、朝子に思ひ出せるのはその間に一度いつだったか素子に抱きおこされてベッドの
上で何かのス!プをのまされたことだけである。電報を讀んだのは一昨日、夕飯がすんで皆が食堂から廣間へ出た時であった。
廣間の帽子かけには大きい水色リボンのついた帽子が一つかかってゐた。その横でそれを受けとって、あけて、讀みにくい□
—マ綴りの字を辿ると、そこにはハガッーヒタモッドゾウチカシッニテシスアトフミと一並び書いてあった。それは返電で、
二日前にシキウキチョウアリタシと打たれて來た。そのとき朝子は電報をみて、説明も與へずいきなりさう云はれてゐること
に心持を害された。ジジョウシレセ。直ぐさう云ってやった。待ってゐた電報であり待ってゐる間の落着かなさから、その午
後も素子と二人きりで草臥れるほど遠くの原っぱの方までも行ったのであった。
ハガッーヒタモッドゾウチカシッニテシスアトフミ。
朝子は無言のまんま、一足おくれて食堂を出て來た素子にその電報をつきつけるやうに渡した。ひき搾られるやうな朝子の
顔つきに駭いて素子が電報に目を落した。堪へがたい全身の心持をどう表現していいか分からず、朝子は握りつめた片手で
何度も空をうつやうにしながら呻いた。本當に何てばかだらう。こんなことをするなんて。何てばかだらう。朝子は激しく鳴
咽しながら廊下を足早に歩いた。もすこしで部屋のドアといふところまで來たとき、黑と白の市松模様の床石が足の下でず一
んと一遍もち上って急に沈んでゆくやうな工合になって、立ってゐられなくなった。そこまでのことははっきりと思ひだすこ
とができるのであった。それから、部屋で、震へがとまらないでゐる體から着物をぬがされながら、自分が頻りに、よくて?
私は歸ったりしないことよ。よくって?と繰返したことも。涙で顔をよごした素子が、ああいい、わかってる、わかってる、
と云ひながらベッドに入れた朝子のまはりをきつく掛けものでつつんだ。とびとびにだが、情景がみんな思ひ出せる。けれど
も、それらは如何にも遠いことのやうで、僅か一昨日のできごとと信じられないやうな氣分がする。しかも、半分失神してゐ
たやうな状態から意識をとり戻した今、朝子が感じてゐるのは、あのときまではまるで生活になかった一つの眞新しい飾り氣
ない悲しみである。保が死んだ。——涙の出ない歔欷のやうなものが再び腹の底から起って、仰向いてゐる朝子の唇を震は
せた。
足許のドアがそっと開いて、素子が入って來た。ベッドに近づいて朝子が目をあいてゐるのを見ると、咄嗟に表情に出た安
堵と憐憫の感動をそれとなし押へた聲で、
「氣分は?」
と云った。
「眠ったらしいから、もう大丈夫だ、ね」
そして、わざと心持にはふれずに、
「ともかく電報うっといたから」
と云った。
「歸らないといふこととお悔みをうっておいたから」
「それでいいわ。ありがたう」
その畫、朝子はすこしおくれて素子に扶けられながら食堂へ出た。壁に並んでゐるゼラニウムの赤や桃色の満開の花鉢、白
い布のかかった食卓の上に並べられてゐる食器も、それに向ってかけてゐる男女の顔ぶれも、いかにも下宿らしく、何ひとつ
一昨日と變ったことはない。けれども衰弱してゐる朝子の神經にはそこいらにあるのが妙に目新しく、一人一人の顔もくつき
りとした輪郭をもって心に映った。食事がすむと、頭をすっかり犍S1風の丸剃りにした技師をはじめ居合はせた人々が、朝子
に握手して悔みをのべた。ヴェルデル博士と呼ばれてゐる小柄で眞面目な老人が最後に朝子の手を執って、地味な楔形の顎
髯と同じに黑い落着いた眼差しを向けながら、
「さうやって勇氣を失はずにゐられることは結構です。あなたはまだお若い。苦痛もしのげます」
さう云ひながら懇ろな風で執ってゐる朝子の丸々とした手の甲を輕くたたいた。「ありがたうございます」朝子はつい泣
けさうになった。ヴェルデル博士の勵ましかたは、何かのときよく父親の佐々が朝子の手をとってすると全く同じ表現であっ
た。ヴェルデル博士の情のこもった輕打をされると、その刹那に朝子の心には悲しさうに伏目になって唇の兩端を拇指と藥
指とで押へるやうにしてゐる父親の親愛な表情が泛んだ。高校生であった保を喪った父の悲痛な氣持がたまらなく思ひやら
れた。もし朝子がゐたら、父は自分で涙をこぼしながらも、きっとやはりさういふ風に娘の手をとって、それを握って、そし
て自分と朝子とを勵ましただらう。自分がこのことで歸ったりはしないといふ氣持をもってゐる。その心持も、苦しさや悲し
さがかうして相通じてゐるその心の流れのなかで父にはわかるだらう。朝子は考へに沈みながら、露臺の方へ出て行った。
昔プーシキンが勉強した學校の校長の住居であったといふその下宿は、菩提樹や楡の繁った大公園に向ってゐて、二階の廣
間から、木の手摺のついた露臺に出られた。隣りとの境に扇形に梢をひろげた楓の大木があって、その蔭に灰色の塀がめぐ
された隣の家の扉が見える。往來をへだてて公園の入口があった。綠の間に鐵柵が見え、午睡の時刻で、そのあたりには人影
も絶えてゐる。綠の濃さと強い日に光ってゐる廣い道の寂しさには、北ヨーロッパらしい風景の或る美しさがあった。籐のは
ぜかかった古い搖り椅子がそこにあった。
一昨日電報を讀んだ瞬間、受けた衝撃・のうちに、既に實に複雑なものがこもってゐた。朝子は自分が氣を失ふやうになった
打舉のうちには、いはば自分がここにかうしてゐる、その現實をもたらしてゐるあらゆるものが、まるで逆にとめられてゐる
ことを身に迫って感じた。
十を越したばかりの妹のつや子のことはわからなかったが、上の弟の和一郎とも朝子自身とも保の氣質はすっかり違った。
保が、赤いポンポンのついた帽子をかぶってゐた小學のーー年ぐらゐのとき、或る朝、學校の前にある緩くて長い坂のところで
同級の友達たちが何人か群になって、そこをギーギー云ひながらのろくさくのぼって來る電車を追越さうとして、一生懸命電
車のわきを走ってゐるのを見つけた。保はその電車にのってゐるのであった。殆ど同時に學校についた。そしたらハアハア云
って背中のランドセルの中で筆入を鳴らしながら駆けて來た友達たちが、先生!先生!僕たち電車とかけっこして來たんです
よ、と叫んだ。「そしたら先生が、そりやえらかったね、ってほめたの。でも僕ほめるなんて變だと思ふなア、ねえ。人間よ
り電車が早いにきまってるのに。心臓わるくしちゃふだけだ。ねえ」さういふ意見で保は母に話した。多計代は、それを保の
思慮のふかさの例として家庭のひとつ話にした。朝子は保と九つ年がちがった。そして何度かその話をきいてゐるうちに、追々
多計代とはちがった感情できくやうになった。朝子には、保のさういふ合理的なやうなところが却って少年っぽさの無さに思
へ、何となし性格としての不安を抱いたのであった。
數年前離婚した佃と朝子が結婚したのは、多計代の反對をおし切ってのことであったから、當時、佐々の家のなかは、そ
のことを中心として絶えずごたついた。娘に對して多計代もゆづらなかったし、朝子も娘だからといふ理由だけでゆづるべき
ところはないと思ったし、しまひには兩方ともが泣きながら激しい言葉をぶつけ合ふやうな場合も起った。或る日、やはりさ
ういふ場面に立ち到った。昂奮した多計代は上氣した頰へ涙をこぼしながら朝子を罵った。すると、それまで默って影の方に
ゐた保が、紺緋の筒袖姿で出て來て、坐ってゐる見下すところに佇んだ。自然多計代も朝子も默った。すると暫くして保が、
「姉さん、なぜ結婚なんかしたんだらう」いかにも深い嘆息をもって云った。朝子は思はず顔をあげた。保のふっくりとした
顔は蒼ざめてゐて、ただたださういふ衝突が堪へ難いといふ表情である。それを見て、朝子は口が利けなかった。それほど保
の表情にはしづかさや平和を切望する色が、殆ど肉體の必要のやうに滲み出てゐたのであった。
その時から四五年經ってゐる。けれども今、外國の下宿の眞畫の露臺で朝子の思ひ出の中に甦 って來たそのときの保の顔
つきと、・一番最近の印象にある保の表情とは、ざういへば何と似てゐるだらう。朝子の出發がきまったとき、,庭で家族が寫眞
を撮した。兩親の間に朝子がかけた。朝子の母親との間にあたる後列に、おかっぱに白リボンをつけたつや子と並んで保が立
った。その寫眞のなかで保は高校の制服をきちんとつけて、大柄なゆったりとした態度で立ってゐるのだけれども、口を結
び、瞼をぱっちりとあけきらず半眼のやうにしてその下から瞳の閃きを見せてゐる。その表情を細かく思ひ浮べると、朝子
は我を忘れて搖椅子から立ち上がった。
もう一つ思ひ出したことがある。あの時、保は何と云ったのだったらう。駒澤の奥にあった素子と二人の住家を疊んで、本
をつけたビール箱を、佐々の家へ運んで來た。なかで、もし欲しいと云ってよこしたら送って貰ひたいといふ分を別にして、
保を呼んで、見ておいてくれと頼んだ。その時も制服のまま勉強部屋から下りて來た保は何と云ったのだらう。責任をもって
失くなったりはしないやうにしておいてあげる。そんな風に云った。云ひかたの調子に、どこ直接自分とは離したところがあ
るやうで、朝子はそのときちよっと變な氣がした。弟の冷淡さのやうに感じられた。あの頃から、彼の心に何か計畫がされて
ゐたのであらうか。
柔毛の生えた保の若々しい上唇のところや、細かいほそい横書きのノートでならされた手紙の丸い字が忽然と目に浮んで來
て、朝子は露臺を歩きながら涙をおとした。最後に貰った手紙で、保はかう書いてゐた。「姉さん、僕はこの夏は一つテニス
でもやって大いに愉快にやって見ようと思ひます。科の選定はそれからのことです」その前のたよりでは、大學の科目をそろ
そろきめなければならないが多計代が哲學がいいといふし自分もさう思ふが、どうかとあった。その時分まだモスクワにゐ
て、白夜のはじまりかけた永い夕暮の明るみの中で、朝子は哲學にはすぐ賛成できないと、書いた。保が長四疊の勉強部屋の
入口の鴨居にMeditationと書いた紙を貼りつけてゐるのを朝子は思ひ出したのであった。さういふ氣質と哲學とは、常識の
なかで餘り結びつきすぎてゐて、いやに思へた。哲學がいいといふ多計代の氣持も分って、そしてやはりそこに反撥するもの
があった。朝子は、その手紙の中でくりかへし、保がいい友達をつくるやう、その人と相談して根本的な生活をすすめて行く
やう、夏休みにはうちの者とばかり暮さず友達と旅行でもした方がいい。そんなことを細々書いた。高校の仲間が、誰も誰も
議論のための議論をしたり、自分の物知りをひけらかしたりするために討論したりするからいやだと、保がよく云った。そ
れも尤ものやうであるけれども、同じ廿歳の高校生である保の言葉としては、朝子も沈着さとしてばかりは聽かれないのであ
った。
その一事につけても、多計代と朝子とでは感じかたがちがった。多計代は自分の翼の下へ從順な、勤勉な、つましい、やが
て大學生になる保をとめて置かうとし、常にその身構へで姉との間に立ってゐた。朝子の生きてゆきかたに保が全部は同意し
てゐないことも明かであったが、それならばと云って最後に保は彼をとめて置かうとしつづけて來たものによってもとどめら
れることはできなかったのだ。
あるひとつのことを思ひ出して、朝子は新しい聲のない歔欷で體をふるはした。その國で朝子が初めて過した冬からこの
春へのうつりかけ、日增しに暖くなる太陽で朝からひどい泥淳の雪解けがはじまり、市街ぢゆうはねだらけ、通行人の陽氣な
罵言だらけといふ季節、保から、今度大變いい温室ができたと知らしてよこした。本式にボイラー室のついたので、それは保
が高校へ入學したお祝ひに豫て約束のあったのを捋へてくれたものだといふのを讀んで、朝子はなんだかそのことに馴染めな
い氣がした。保は花作りがすきで、小學校時分からミカン箱へシクラメンの實生を育てたりしてゐた。できたものならば十分
使へばいいけれども、それだけの温室を建てるに使った金で貧しい高校生が恐らくーケ年以上生活できるだらう。それを保は
知ってゐるだらうか。朝子は自然の感情から何心なくさういふ意味を云ってやった。すると怒りが字にまで出てゐる多計代の
«で、純真な保の唯一のよろこびにまで傷をつけずにはゐないあなたは、云々と云って來、同時にまるで人目をしのんだやう
な一枚の外國葉書に、保自身が例の細いこまかい字の横書きで、手紙の禮と、温室については僕は一遍もさういふことは考へ
てみなかった、僕は大變愧しいことだと思った、と終りの一句にアンダラインしてよこした。
两
僕は大變愧しいことだと思った。そのなかに、今はもうゐない保の體の暖かさや、聲や、子供っぽく兩手で膝を叩いて大笑
ひする顔つきやが思ひ出され、朝子は愛着に耐へ得なかった。可愛い、可愛い弟の保の佛であった。
心配してさがしに來た素子の手を握りしめて、朝子はきれぎれに云った。
「保ぐらゐの若い人に死なれるのは、こたへかたがちがふ……全くこたへる」
さう云って涙をこぼした。
朝子たちの周圍には、平凡なやうでまたさうでもない夏の下宿らしい日々があった。
食卓についてゐるとき縫8一風に頭を丸剃りにして白麻の詰襟を着た四十がらみの技師と、一人おいた左隣りに坐ってゐる白
粉の濃い女との間に、何のきっかけからかトルストイが最後に家出をした氣持がわかるとかわからないとか云ふ問答がはじま
つた。技師は、間の一人をとばしてその女に話しかけるために縁無し眼鏡をかけた顔を食卓の上にのり出すやうにして、「總
阴なあなたにその心理が分らないことはないでせう」といふやうなことを云った。するとそのエレーナといふ女は「まあ」と
どことなく自然でない昂奮のかくされた笑顔で、
二でも、それでは、良人として家庭への義務を忘れたことですわ。ねえ、マーシア•フヨードロヴナ」
¬といきなり向ひ側にゐる技師の細君に話頭を向けた。
『私は、トルストイの場合として、理解されると思ひますよ」
白い髪の幾條か見える細君はおだやかにフォ—クを動かしながら普通に答へてゐる。そこには何か感じられる雰圍氣がある
のであった。
朝子と素子とヴェルデル博士と三人で、二哩ばかりはなれた野の中に建ってゐる廢寺へ壁畫を見に行って、ぐるりとその
堂の裏手へまはったら、思ひがけない潅木の蔭でその技師とエレーナと腕を組み合った散歩姿で來るのに出くはした。どっち
からも、もう避けることができなかった。するとエレーナがはしゃいだ高調子で、
「思ひがけないこと!」
そのまま眞直近づいて來た。
「お邪魔になりまして?」
ヴェルデル博士は黑い帽子の縁にちよっとふれて、きはめておだやかなうちに一抹の苦みをもって、
「私には誰が誰の邪魔をしたか分りませんよ」.
技師にも會釋して、こちらの一行は行きすぎた。そんなこともあった。
土曜、日曜にはゝ全くちがふ若々しい波が停車場からあふれ出て、美術館を中心の一公園から街路から一杯になった。下宿
の露臺から見える公園の入口の歩道の上には向日葵の種賣り、林檎賣り、揚饅頭賣りが並んだ。終日、髪をプラト—クで包
んだ若い娘たちゃ運動シャツにちひさい高架索帽を頭にのせた若者、赤いネクタイをひらひらさせた少年少女が列をつくって
通ったり、二人三人づれで行ったり來たりした。空氣は微かに鼻をくすぐるやうに暑く埃っぽくなって、聲量のある笑聲や歌
聲、叫び聲や駆ける楚音などがその中へ溶けた。
朝子は露臺から長い間さういふ光景を見てゐた。その浣剌とした、粗末な服装をした若者たちの動きのなかには、いかにも
朝子の情愛をひく何かがあった。見てゐるうちに、急に涙がつきあげて來ることもある。若い保がもってゐたそのやうな單純
な氣持のいい身振り、そのやうな罪のない大笑ひがそこにあった。生きて、無心にそこに溢れてゐるのであった。保は死んだ。
何たる思ひだらう。
朝子たちが出發して來たのは去年の冬であったが、その夏芥川龍之介が自殺した。四年ばかり前有島武郎が輕井澤でその生
涯を終ったとき、朝子は佃との破綻が収拾つかなくなって非常に苦しんでゐたときであったから、そのことから深い震撼を蒙
った。戀愛といふものがそれぞれの男女の成長的な面に立って生じるとだけ思ふことは誤りであって、現實には互ひの破诫的
な面がひきあふこともある、さういふことを示されてゐるやうに思った。實際には、もっと複雑ないくつかの面がその作家の
死の動機になったのだが、その時分の朝子には、自分の境遇から特にその面がつよくうけとれたのであった。
芥川龍之介の葬式のとき、文學の仕事をしてゐる朝子は、白い清らかな故人の柩のまはりに燦めきながら灯ってゐるたく
さんの嫌燭の綺麗な焰を見守って、總毛立ちながら、ときどき頰に涙をったはらせてゐた。朝子はこの作家の才能は知ってゐ
たが、好きかときかれれば、肯定した返事はできなかった。けれども、その死には、心をうつものがあった。精一杯がそこで
挫折してゐるその姿でうつものがあった。二人の作家の二つの死をつなぐ四年の間に朝子は妻の境遇からぬけて、そのときは、
いろんな題材でどうやら小説が樂に書けるといふこと、そしてそれなりに書いてゐるといふことが果して藝術家としての存在
を意味づけるに足ることなのだらうかといふ疑ひを抱く心になってゐたのであった。
三十五歳で命を絶ったこの作家の死は、それ故有島武郎の場合とはおのづから異った内容で朝子に衝撃を與へてゐた。保は
高校生であった。いろいろの生活ではもとより芥川龍之介とまるきりちがふのだが、保の死の報告をうけて日が經っにつれ、
朝子の心ではその二つがつながりをもつやうになって來た。靑いメリヤスの運動シャツなんか無雜作に着て、かぶった帽子を
片手で前のめりに押し出しながら何かしきりと論判してゐた靑年が、急に嬉しさうに白い齒並を輝やかしながら笑ひ出す樣子
などを眺めてゐると、朝子は肉體の靑春といふばかりでなくそこに見えてゐる歴史の世代の靑春のありゃうといふものはどう
いふものだったらう、さう考へるといっしか朝子の心の奥が遠い廣いところへ擴って、そこには、白い柩とそのまはりに燦い
てゐた焰の色が現れ、無限の哀れを誘はれると同時に、それが答へではない、と自身としての答へを執念くもとめてゐる自分
に心附くのであった。
朝子が電報をうけとって間もない或る朝、五十ばかりのダ—シャといふ女中が部屋掃除に來て、箒を入口の壁に立てかける
と、縞の前垂で手をふき、お悔み申しますよ、とその手を朝子にさし出した。
「弟さんでしたねえ。大方學生さんでおいでたんでせうね。こちらでも、もとは隨分さういふことがあったもんでしたよ」
さう云ってダーシャは、鎮魂の祈りを誦へ、胸の上で十字を切った。ダーシャは字を知らない女であった。日曜の浣剌とし
た人波を見てゐて、朝子はこのことをよく思ひ出した。そしてダーシャが過去の云ひかたでそれを語った、そのことについて
思った。
その下宿に滞在する最後の週に朝子は國から電報以來初めての手紙をうけとった。封筒は父の筆蹟であった。なかも父だけ
が書いてゐた。お前が知りたいだらうと思ふから苦痛を忍んで書くといふ前置で、細々と前後の有樣が述べられてゐた。保は
温室のメロンにつかふ藥品で死んだのであった。「その二三日來時に暑氣甚しく」といふやうなところに父だけおいて皆は避
暑に行ってゐる留守の家の氣配や父親としての追懐が滲み出てゐた。白緋にメリンスの兵兒帶をしめた保はその日の午すこし
前、女中部屋のわきを通って、ちよっと友達のところへ行って來るよ、と云ったさうだ。畫飯はあっちで食ふからいいよ。女
中が、では晩はどうするかときいたら、歩きながら、それもついでに御馳走になって來ようか、少し圖々しいかな、と笑って
門の方へ出て行った。それから戻ったことは誰も知らなかったのであった。
九月初旬の日曜で、表側の朝子の部屋は人通りがうるさく、素子の室で、朝子は讀み終った分から一枚づつ書簡箋を素子に
まはした。二日經って漸々保が發見されたとき、猛毒アリと大きく書いた紙が貼ってあって半地下室へ入れず、外から僅にガ
ラスを破壊して一刻も早く空氣交換をせんとすれども、折から雨にて余の手にある扇風機は間もなく故障を起し、といふとこ
ろへ來たら、朝子は涙が出て讀みつづけられなくなった。その雨には父の涙がまじって流れた。光景はまざまざと目に映るば
かりである。朝子はくひっくやうに何度もそこを繰りかへし讀んだ。多計代を愕ろかせないやうにと、わざわざ使がやられた。
使はわざと、保さんは來てゐませんかと云って、當時多計代やつや子のゐた田舎へ行った。その先へ讀み進んで朝子は涙も渇
いた二つの眼を瞠って居ずまひをなほした。三月下旬に一度保はストーヴの瓦斯を出し放しにした室にゐることろを深夜發見
され、その夜は母も保も共に泣き云々。保さんは來てゐませんかと云へば、それが多計代にとって十分一つの暗示になり得る
状態たったとは、何事だらう。温室のことでこの春多計代から來た手紙の調子を朝子は閃くやうに思ひ出した。同じことにっ
いて、僕は大變愧しいと思った、といふ文章の下にアンダラインした保の心持も、今は全く別の複雜さ鋭さで理解されること
であった。温室が建てられたのは、その直後だったのだから。この夏は一つ大いに愉快にやって見ようと思ふ、といって來た
のも、保の心にはサスペンスとしてあった気持の明るい方への最後の一搖れだったのだ。それらすべての局面は朝子からひた
隱しにされてゐた。それは母の希望によってさう計はれてゐた。では父は?さういふ問ひが朝子の心におこった。父もまた、
この不健全にいり組んだ家庭内の局面に對しては、最後まで何もなし得なかったのだ。悲觀にとり亂した多計代の姿は手紙の
なかに傳へられてゐず、そこには、田舎からかへって来ると、清浄無垢な保に對面するには心の準備がいると云ってその夜は
寢室にこもってゐて、翌朝紋服にきかへて保の遺骸の安置された室へ出て行った多計代の樣子が語られてゐた。この場合清浄
無垢とは、保の死に戀愛がかかはってゐないといふ表面のあらはれにっちて云はれてゐるのであった。
しまひの一枚を素子に渡してしまふと、朝子は沈鬱きはまる相貌で、窓の前まで枝垂れて來てゐる中庭の枫の葉の繁りに凝
っと目をやった。古びた黄っぽい建物の翼に射してゐる斜光が楓の葉の繁みを裏から透してゐて、窓べりはそとの濃い綠の反
射で空氣まで染められてゐるやうである。讀み終って素子も口をきかない。さうやって暫くゐた。
どこか遠くにきこえてゐた手風琴が、こんどは公園のすぐ近いところで鳴り出した。それに合はせて、非常に甲高な、野原
や山なら何處までも徹りさうな男の聲が旋律をひっぱって急に調子の迅まる民謠風な歌のひとくさりを謠ふと、一齊に手ばた
きが入って、ヘイ!何とか何とかと活浣な合唱が續いた。合唱が絶えるとーきは手風琴の音が冴えわたって、あちらこちらか
ら人の心を誘ふやうな旋律と聲とで獨唱が流れて來る。朝子は暗い目で頭をかしげるやうにして、色とりどりな休日の終りに
響いてゐるその音樂をきいた。涙ではとかされないものとなって迫って來てゐる樣々の苦しい感情のうちには、保の目で見送
られた自分の生きてゆく後姿もあるのであった。堪へ難いといふ顔色で、朝子は椅子をずらし、
「外へ行きませう」
素子の手をつかんで、ひっぱるやうにその靑っぽい窓べりをはなれた。朝子が歩いて行く廊下は、四週間前の宵に彼女がそ
の上へ倒れた白と黑の市松模様の石の床であった。
©
谷崎潤一郎
「靑い花」
「君は此の頃又少し痩せたね、どうかしたのかい?顔色が悪い、
さつき、尾張町の四つ角で出遭った友人のТにさう云はれてから、彼はゆうべの阿具里とのことを想ひ出して、一層歩くのに
疲勞を覺えた。Тはもちろんそんな事に氣が付いて云った譯ぢゃなからう、
彼とあぐりとの間柄は今更冷やかすほど
の事でもなし、二人が一緒に銀座通りを歩いて居たって別に不思議はないんだから、 が、神經質で見え坊の岡田には
その一と言が少からぬ打撃であった。自分は此の頃遇ふ人毎に「瘦せた」と云はれる。
實際此の一年來自分でも恐ろ
しいくらゐ眼に見えて瘦せる。殊に此の半年の間と云ふものは、嘗てはあんなにつやつやと肥えて居た肉と脂肪が、ーと月ー
と月削られるやうに殺げてゆく。どうかすると一日の間でもそれが目立って分ることがある。毎日々々、入浴の度びに全身を
鏡に映しては、そっと肉附きの衰へた工合を檢査するのが癖になってしまったが、もう近頃は鏡を見るのが恐ろしい氣がする。
昔.
と云っても今から二三年前までは、彼の體つきは女性的だと云はれて居た。友達と一緒に湯に這入ったりなんかす
ると、「どうだい、ちよっと斯う云ふ形をすると女のやうに見えるだらう、變な氣を起しちゃいかんぜ」などゝ自慢をしたも
就中女に似てゐたのは腰から下の部分だった。ムッチリした、色の白い、十八九の娘のそれのやうに
圓く隆起した臀の肉を、彼は屡〃鏡に映して愛撫しながらウットリとした覺えがある。股や膨らツ脛の線などが無恰好なくら
のだったのに、
ゐに太って居て、その脂ぎった、豚のやうな醜い脚を、あぐりと一緒に入浴しながら、彼女のそれに比べて見るのが好きであ
った。その當時やっと十五の少女だったあぐりの脚の西洋人のやうにスッキりしたのが牛屋の女中の脚みたいな彼のものと並
べられる時、一層美しく見えたのをあぐりも喜んだし彼も喜んだ。お轉婆な彼女は屡〃彼を仰向けに倒して團子を蹈んづける
やうに股の上を蹈んづけたり、渡って歩いたり、腰かけたりした。——然るにそれが、今は何といふ情ない、細ッこい脚に
なってしまったんだらう。膝や踝の關節など、しんこを括ったやうに可愛らしく括れてゑくぼが出來て居たのだが、いつから
とはなく傷々しく骨が突き出て、皮の下でグリグリと動くのが見える。血管が蚯蚓みたいに露出して居る。臀はだんだんぺッ
タンコになって、堅い物に腰をかけると板と板とが打つかるやうな感じがする。でもつい此の間までは、肋骨が見える程では
なかったのに、下の方から一枚々々トゲ立って來て、胃袋の上から喉の所まで、人體の構造はこんな工合に出來て居るのかと
薄氣味惡く思はれるくらゐ、ありありと透き徹って居る。大喰ひをするから此ればかりは大丈夫と思って居た太鼓腹が次第に
凹んで、此の鹽梅ぢゃ今に胃袋まで見え出すかも知れない、脚の次に「女らしい」ので自慢したのは腕だったけれど、——何
かと云ふとその腕を巻くって見せて女にも褒められ、自分でも「此の手で深みへ ハンマ千鳥」と惚れられた女にからかったも
のだけれどそれが今では杲眞目にも女らしいとは いや男らしいとも思はれない。人間の腕と云ふよりは棒ツ切れだ。
胴體の兩側に鉛筆がぶら下がって居るのだ。苟くも骨と骨との間にある凹みと云ふ凹みからは悉く肉が落ち、脂が取れ、かう
して何處まで瘦せて行くのか、 一體こんなに瘦せてしまって、それでも生きて動いて居るのが不思議でもあり、有難
さう考へると、もうそれだけでも彼の神經は脅やかされて急にグラグラと眩暈
がする。後頭部がずしんと痺れてそのま、後ろへ引き倒されるやうな、膝頭がガクガクと曲りさうな氣持になる-
氣持ばかりではない、神經が手傳ふには違ひないのだが、長い間に嘗め盡した歡樂と荒色の報いであることは、・
くもあり、自分ながら凄じくもある。
勿論
糖尿
©
病のせゐもあるけれどもそれも報いの一つであるから、 彼にはよく分って居る。今更嘆いても追つつかないやうなも
のゝヽたヾ恨めしいのはその報いが意外に早く、さうして而も彼の最も頼みとする肉體の上に、それも内臟の病氣でなく、外
形の上に來たことである。まだ三十臺だ、こんなに衰へなくってもいゝんだのに、 思ふと、彼は地團太ふんで泣きたく
なる。
「ちよっと、ちょっと、 あの指輪はアクアマリンぢゃなくって?ね、さうでせう、あたしに似合はないか知ら?」
ふいと、あぐりは立ち止まって彼の袖を忙しく突ツついてショオ・ウィンドオの中を覗いた。「あたしに似合はないか知ら」
と云ひながら、彼女は手の甲を岡田の鼻先へ持って來て五本の指を反らしたり縮めたりして見せる。 銀座通りの五月
の午後の日光が、明るくかっきりとその上に照つて居るせゐか、生れてからピアノのキイに觸れるより外一度も堅いものに觸
れたことのないやうな、柔かい、すんなりと伸びた指どもが、今日はーと入なまめかしい色つやを帶びて居る。嘗て支那に遊
んで、南京の妓館で何とか云ふ妓生の指がテ!ブルの上に載って居るのを眺めた時、あんまりしなやかで綺麗なので温室の花
のやうに思はれ、凡そ世の中に支那婦人の手ほど繊細の美を極めたものはないと感じたが、此の少女の手はたヾあれよりもほ
んの少し大きく、ほんの少し人間らしいだけである。あれが温室の花なら此れは野生の嫩草でもあらうか、そしてその人間ら
しいのが却って支那婦人のそれよりは親しみ深いとも云へるのである。若しこんな指が福壽草のやうに小さな鉢に植わって居
たら、どんなに可愛らしいだらう。
「ね、どう?似合はないか知ら?」
と云って、彼女は掌をウィンドオの前の手すりにあて、、踊りの手つきのやうにグッと反りを打たせる。そして問題のアクア
マリンの事は忘れたやうに自分の手ばかり視つめて居る。
が、岡田はどんな返事をしたか覺えはない。彼もあぐりと同じところを視つめたまゝ、
頭は自然と、此の美しい手に
附きまとふいろいろな空想で一杯になって居た。 考へて見ると、もう二三年も前から自分は此の手を朝な夕な.
此の愛着の深い一片の肉の枝を、
粘土のやうに掌上に弄び、懐爐のやうにふところに入れ、口の中に入れ、腕の下に
入れ、頤の下にいぢくったものだが、自分がだんだん年を取るのと反對に、此の手は不思議にも年一年と若々しさを增して來
る。まだ十四五の折りにはそれは黄色く萎びてゐて' 細かい皺が寄ってゐたのに、今では皮がピンと張り切って、白く滑かに
乾燥して、その癖どんな寒い日にでも粘ツこい膩味がじっとりと、指輪の金がSるくらゐに肌理に沁みてゐる。
けない手、子供のやうな手、赤ん坊のやうに弱々しくて淫婦のやうに阿娜っぽい手、
あど
あ、、此の手はこんなに若々し
く、昔も今も歡樂を追うて己まないのに、どうして自分は斯うも衰へてしまったのか。自分はもう、此の手を見るだけでもそ
れが挑發するさまヾまの密室の遊びを連想して、毒々しい刺戟に頭がヅキヅキする。
じっと見てゐると、岡田にはそれ
が手だとは思へなくなって來る。
白畫
銀座の往來で、此の十八の少女の裸體の一部、
手だけが此處に
むき出されてゐるのだが、
肩のこころもあ、なって居る、飆のところも
腹のところもあ、なって居る' 臀、
足、
それらが一つ一つ恐ろしくハッキリ浮かんで來て奇妙な這ふやうな形をする。見えるばかりでなく、それが
どっしりと、十三四貫の肉塊の重味になって感ぜられる。
一瞬間、岡田は氣が遠くなって後頭部がグラグラして、危
く後ろへ倒れさうになる。
馬鹿なッ、
岡田はハッとして妄想を打ち消す。
よろめきかゝった足を蹈みし
める。
「ぢゃ、横濱へ行って買ってくれる?」
「あゝ」
さう云ひながら、二人は新橋の方へ歩き出した。
此れから横濱へ行くのである。
今日はいろいろの物を買って貰ふのだから、あぐりは嬉しいに違ひない。山下町のアーサ—•ボンドや、レーン•クロフォー
ドや、何とか云ふ印度人の寶石商や、支那人の洋服屋や、横濱へ行けばお前に似合ふ物が何でもある。お前はエキゾティック・
ビューティーだ、在り来りの、その割につまらなく金のかゝる日本人臭い服装は似合はないのだ。西洋人や支那人を御覧、そ
んなに金を掛けないで、顔の輪郭や皮膚の色を引き立たせる法を知って居る。お前も此れからさうするがいゝ。
はれてあぐりは今日を樂しみにして居た。彼女は歩きながら、自分が今着てゐるフランネルの和服の下に、初夏の温氣で生暖
かく汗ばみっゝ靜かに喘ぎ息づいてゐる白い肌が、 のびのびと發達した子馬のやうな手足の肉が、やがてその「似合は
ない」和服を脱いで、耳には耳環をつけ、頸には頸飾をつけ、胸には絹だか麻だかのサラサラした半透明のブラウスをつけ、
踵の高いきやしゃな靴先でしなしなと 街を通る西洋人のやうになった姿を空想する。そしてさふ云ふ西洋人がやって來
ると、彼女はすかさずジロジロと見送っては、「あの頸飾はどう?あの帽子はどう?」と云ふ風にウルサク執念く岡田に尋
ねる。その心持は岡田も同じで、彼には若い西洋の婦人と云ふ婦人が悉く洋服を着たあぐりに見える。
やりたい、此れも買ってやりたい、と、さう思ふのであるが
.さう云
あれも買って
それで居て一向氣持が浮き立たないのはなぜであらう。此
れからあぐりを相手にして面白い遊びが始まるのだ。天氣は好し、風は爽やかだし、五月の空は何處へ行っても愉快である。
「蛾眉靑黛紅巾沓」 新しい、輕い衣裳を彼女に着けさせ、所謂紅巾の沓を穿かせて、可愛い小鳥のやうに仕立て、、
樂しい隱れ家を求むべく汽車に載せて連れて行く。靑々とした、見晴らしのいゝ海邊の突端のヴェランダでもよし、木々の若
葉がぎらぎらとガラス戸越しに眺められる温泉地の一室でもよし、又はちょいと氣の附かない外國人町の幽暗なホテルでも
いゝ。そこで遊びが始まるのだ'自分が始終夢に見て居る.
のだ。 その時彼女は豹の如くに横はる、
たヾその爲めにのみ生きて居る.
頸飾と耳環を附けた豹の如くに横はる、
面白い遊びが始まる
子供の時から飼ひ馴
らした、主人の物好きをよく呑み込んだ豹ではあるが、その精悍と敏捷とは屡〃主人を辟易さす。じゃれる、引ッ搔く、打つ、
跳び上る' 果てはずたずたに喰ひ裂いて骨の髄までしゃぶらうとする、
あ、その遊び!考へたヾけでも彼の魂
はエクスタシ!に惹き込まれる。彼は覺えず興奮の餘り身ぶるひする。突然、グラグラと眩暈がして再び氣が遠くなって、…
今、三十五歳を一期にして此の往來へ打つ倒れて死ぬんぢゃないかと思はれる。・•…
「あら、死んぢやったの?仕様がないわね。」
と、あぐりは足もとに轉がった屍骸を見てポカンとする。 屍骸の上には午後一ー時の日がかんかん照って、痩せて飛び
出た頰骨の凹みに濃い蔭を作る。
どうせ死ぬならもう半日も生きて居て、横濱へ行って買ひ物をしてくれゝば好かっ
たのに、
あぐりは忌々しくなって、チョッと舌打ちする。成るべく係り合ひになりたくはないが、しかし此のまゝ放
って置く譯にも行くまい、
が、此の屍骸のポッケットには何百圓かの金がある。此れはあたしの物になる筈だった、!
——せめてーと言、それを遺言して死んでくれるとよかったけれど、
此の男は馬鹿々々しいほどあたしの愛に溺れて
居たから、あたしが今ポッケットからその金を出し、好きな物を買ひ好きな男と浮氣をしても、あたしを恨む譯はないから、
彼はあたしが多情な女であることを知り、それを許して居たばかりか時には喜んでさへ居たんだから、
あぐりは自分
に云ひ譯しながら、ポッケットからその金を取り出す。たとひ化けて出て來たにしろ此の男なら恐ろしくはない、幽靈になっ
てもきっとあたしの云ふ事を聽くだらう。あたしの思ふ通りになるだらう。
「ちよっと、幽靈さん、お前の金であたしはこんな指輪を買った、こんな綺麗なレースの附いたスカートを買った、そら御覽、
©
(と、そのスカートを捲くって見せて)お前の好きな私の脚、
此の素晴らしい足を御覧、此の白い絹の靴下も、膝の
所を結んである桃色のリボンの靴下留めも、みんなお前のお金で買った、何とあたしは品物の見立が上手ぢゃなくって?あ
たしはまるで天使のやうに立派ぢゃなくって?お前は死んでもあたしはお前のお望み通りの、あたしの似合ふ衣裳を着て、
面白をかしく世間を飛んだり跳ねたりして居る。あたしは嬉しい、ほんとに嬉しい、お前が斯うしてくれたんだからお前だっ
て嬉しからう。お前の夢があたしになって、こんな美しいあたしになってピンピン生きて居るんだから。
さあ幽Sさ
んや、あたしに惚れた、死んでも浮ばれない幽®さんや、一つお笑ひ!」
さう云って、冷めたい骸を力まかせに抱きしめてやる、枯木のやうな骨と皮とがミシミシ云って、「もう溜らない、堪忍し
てくれ」と泣き聲を出すまで抱きしめてやる。それでも降參しなければまだいくらでも誘惑してやる。皮が破れて、ありもし
ない血がたらたらと流れて、シャリツ骨が一本々々バラバラになるまで可愛がってやる。そしたら幽靈も文句はなからう。
「どうしたの、何か考へ事して居るの?」
「う'
うゝん」と、岡田は口の中をもぐもぐやらした。
かうして一緒に、樂しさうに歩いて居ながら、
こんな樂しみはない筈だのに、自分の心は彼女と調子を合はせられな
い。悲しい連想がそれからそれへと湧き上って、遊びの「あ」の字が始まらぬうちから、體が弱り切って居る。ナニ神經だ\
大した事はない、此のお天氣に表に出れば直ってしまふ。
はない、手足が抜けるやうにだるくて、歩く度に腰が軋む。だるいと云ふ感覺は、時に依っては甘くなつかしいものだけれど
さう自ら勵まして出て來たのだが、やっぱり神經ばかりで
も、それが斯うまで度が強くなれば何か良くない徴候だと云ふ豫感がする。今、自分の知らぬ間に、重い病氣が刻々と組織を
冒しつ、あるのぢゃないか。自分はそれを放ったらかして、打つ倒れるまでフラフラ歩いて居るのぢゃないか。一旦打つ倒れ
たが最後、どッと病み着いてしまふのぢゃないか。
たい。そして柔かい蒲團の上にでもぐったり寢かして貰ひたい。事に依ると、自分の健康はもう疾っくにそれを要求して居る
のぢゃないか。「いけません、いけません、そんな體で出歩くなんて飛んでもない事です、眩暈がするのは當り前です。寢て
そこまで考へると一層がツかりし
あゝ、こんなにだるいくらゐなら、いっそ早くさうなってしまひ
居なけりゃいけません。」と醫者が見たらビックリして止める程なのぢゃないか。
て、歩くのが尚更大儀になる。銀座通りの舗装道路が、 健康な時はその上を濶歩することがいかに愉快だか知れない
ところの、堅い、コチコチの地面が、一歩々々に靴の踵から頭の頂邊へヅキン、ヅキンと響いて來る。第一、足の肉を型にハ
メたやうに締めつけて居る赤皮のボックスの靴が、恐ろしく窮屈な氣がする。元來洋服なんてものはピンシャンした達者な人
間が着るもので、衰弱した體ではとても持ち切れない。腰、肩、腋の下、頸ツたま、 關節といふ關節を締め金やボタ
ンやゴムや舔皮で二重にも三重にも絞られて居るのだから、何の事はない、十字架にかけられたまゝ歩いて居るやうなもので
ある。ちょいと考へたところでも靴の下には靴下と云ふ奴があって、その上の方が御丁寧にもガーターで脛にぴんと引つ張ら
れて居る。更にワイシャツを着、ヅボンを穿き、それをギュッとビジョーで以て骨盤の上に喰ひ込ませ、肩から榛がけに吊り
頤と胴との間にはカラアがカッチリと嵌め込まれ、又その上を嚴重にもネクタイで縛り、ピンを刺し込む。
下げる。
たっぷり太って居る人間だと、いくらギュウギュウ締めつけてもますますハチ切れさうで景氣がいゝが、痩せた人間はたまら
ない。そんなエライものを着て居るのかと思ふと、うんざりして手足が餘計疲れて來て、息が詰まりさうになる。洋服だから
が、歩けない體を無理やりに板の如く突つ張らされて、足枷手枷をはめられて、「さ
こそ兎に角かうして歩けるのだ。
あもう少しだ、しツかりしろ、倒れちゃいかんぞ!」と後ろから責め立てられて居るんだとしたら、誰だって泣きたくなるだ
らう。
画
ふと、岡田は、歩いてゐるうちにだんだん我慢が出來なくなって、急に氣が違ってだらしなく泣き出すところを想像した。…
……たった今まで、年頃のお孃さんを連れて、此のお天氣に何處か散歩にでも出かけるらしい輕快な服装をして、銀座通り
を歩いて居た中年の紳士、
そのお孃さんの伯父さんとも見る男が、急に顔の造作を縦横に歪めて「わあッ」と子供の
やうに泣き出す!「あぐりちゃん、あぐりちゃん、僕はもう歩けないんだよう!おんぶしておくれよう!」と、往來に立ち
止まってたヾを捏ねる。「何よ!どうしたのよ!お止しなさいよそんな眞似をして!みんなが見てるぢゃないの」と、あぐり
は突っけんどんに云って、恐い伯母さんのやうな眼つきで睨める。
彼女は彼が發狂したとは、ちょつとも氣が付かな
彼女に取って此の男の泣きッ面は珍しくもない。往來では始めてだけれど、二人きりの部屋の中ならい
っでも丁度こんな風に泣くのだから。 「馬鹿ね、此の男は何もおもてヾ泣かないだって、泣きたけりや後でいくらでも
泣かしてやるのに。」と、彼女はさうも思ふであらう。「しッ、お默りなさい。止して頂戴ツたら、極まりが惡いから。」—
いであらう、
——が、さう云っても何でも岡田は容易に泣き止まないで、果ては身をもがいて、カラ—やネクタイを滅茶々々にかなぐり捨
て、暴れ廻る。そしてスッカリ疲れ切って、息をせいせい彈ませてペッタリと地面へ倒れる。「もう歩けない' 己は
病人だ' 早く洋服を脱がせて柔かい物を着せておくれ、往來だって構はないから、此處へ蒲團を敷いてくれ。」と、半
分は諭語のやうに云ふ。あぐりは當惑して、耻かしさに火の出るやうな顔をする。 もう逃げるにも逃げられない、二人
の周りには眞ツ晝間黑山のやうな人だかりだ、巡査がやって來る、 あぐりは衆人環視の中で訊問される、 「あ
あぐりは衆人環視の中で訊問される'
の女は何者だらう」「令嬢かね」「いやさうぢゃない」「オペラの女優かね」など人々がコソコソ云ふ。
あなた、こんな所に寢て居ないで、起きて貰へませんかね」氣ちがひと見て巡査が助はるやうに云ふ。「いやです、いやです、
「どうです
僕は病人なんだってば!起きられるもんですか。」岡田は首を振りながらまだめそめそ泣いて居る'
そんな光景が、彼の眼にハッキリと映る。實際自分が、現にさうなって居るかのやうに、めそめそ泣く時の心持が其の通り
にしみじみ湧いて來る。…:
「お父さん、
お父さん、
と、何處やらで、あぐりとは全く違った、いたいけな、可愛らしい聲が微かに聞える。今年五つになる、圓々とメリンス友禪
の着物を着た女の兒が、頑是ない手をさし伸べて彼を招いて居るのである。その後ろには髭に結ったその兒の母らしい姿も居
「照子や、照子や、お父さんは此處に居るよ、 おゝ、お咲!お前もそこに居てくれたのか。」二三年前に
母は頻りに何か云はうとして居るのだ、それがあんまり遠すぎるせゐかもやもや
るー
亡くなった彼の母親の顔も見える、
とした霞に隔てられて居る。
たヾもどかしさうな身振りをして、心細い哀れっぽいことを云ひながら、さめざめと涙
で頰を濡らして居るのがぼんやり分る。
もう悲しい事なんか考へまい、母の事や、お咲の事や、子供の事や、死の事や、
それをひよっと想ひ出したヾけでこ
んなに悲しいのはどう云ふ事だらう。やっぱり體が弱って居るせゐではないか。二三年前、達者な時分には、悲しいには悲し
くってもこんなにエラクはなかった筈だが、今では悲しい心持が生理的の疲勞と一緒になって、體中の血管の中にどんより
とこだはって居る。そのこだはりが淫慾の爲めに煽られる時、ますます重苦しさを增して來て、
彼は五月の白日の街
を歩きながら、眼には外界の何物も見ず耳には何物も聞かない、そして執拗に、陰鬱に彼の心は内側へばかりめり込んで行く。
「もしね、買ひ物の都合でお金が剩ったら腕時計を買ってくれない?
あぐりはそんな事を云って居る。
ちゃうど新橋ステーションの前へ來たので、そこの大時計を見て、彼女は想ひ出し
たのであらう。
塔の聳える方へのどかな運河を棹さして行く。
「上海へ行くといゝ時計があるんだがな、お前に買って來ればよかったっけ。」
それから又一としきり、岡田の空想は支那へ飛んで行く、 蘇州の昌門外のほとりに、美しい畫舫を浮かべて、虎邱の
・船の中には若い二人が鴛鴛のやうに仲好く並んで腰かけて居る。
彼とあぐりとがいつの間にやら支那の紳士となり、妓生となって、
彼はあぐりを愛してゐるのか?さう聞かれたら岡田は勿論「さうだ」と答へる。が、あぐりと云ふものを考へる時、彼の頭
の中は恰も手品師が好んで使ふ舞臺面のやうな、眞ツ黑な天»絨の帷を垂らした暗室となる、 そしてその暗室の中央
に、裸體の女の大理石の像が立って居る。その「女」が果してあぐりであるかどうかは分らないけれども、彼はそれをあぐり
頭の中のその彫像でなければ
\であると考へる。少くとも、彼が愛して居るあぐりはその「女」でなければならない'
——それが此の世に動き出して生きて居るのがあぐりである。今、山下町の外國人街を彼と並んで歩いて居る
彼女、 その肉體が纏って居るゆるやかなフランネルの服を徹して、彼は彼女の原型を見る事が出來、その着物の下に
ある「女」の彫像を心に描く。一つ一つの優婉な鑿の痕をありありと胸に浮かべる。今日はその彫像をいろいろの寶石や鎖や
絹で飾ってやるのだ。彼女の肌からあの不似合な、不恰好な和服を剥ぎ取って、一旦ムキ出しの「女」にして、それのあらゆ
る部分々々の屈曲に、輝きを與へ、厚みを加へ、生き生きとした波を打たせ、むっくりとした凹凸を作らせ、手頸、足頸、襟
・頸と云ふ頸をしなやかに際立たせるべく、洋服を着せてやるのだ。さう思ふ時、愛する女の肢體の爲めに買ひ物を
ならない、
頸、
夢、
すると云ふ事は、まるで夢のやうに樂しいものぢゃないだらうか?
此の物靜かな、人通りの少い、どっしりとした洋館の並んで居る街を、ところどころのショオ•ウィンドオを覗
きながら歩いて居るのは、夢のやうな氣がしないでもない。銀座通りのやうにケバケバしくなく、畫も森閑と落ち着いて居て、
何處に人が住んで居るかと訝しまれるやうな、ひっそりとした灰色の分厚な壁の建物の中に'たヾウィンドオのガラスだけが
魚の眼のやうにきらりと光って、それへ靑空が映って居る。街とは云ふものゝ、それは恰も博物館の歩廊のやうな感じである。
そして兩側のガラスの中に飾ってある商品も、鮮やかではあるが、奇態に幽玄な色つやを帶びて、怪しくなまめかしく、たと
へば海の底の花園じみた幻想を與へる。ALL KINDS OF JAPANESE FINE АКТУ PAINTINNG0 PORCELAINSdRONZE
STATUES"
など、記した骨董商の看板が眼に留まる。MAN CHANG DRESS MAKER FOR LADIES AND
GENTLEMEN
かう書いてあるのは大方支那人の服屋であらう。JAMES BERGMAN JEWELLERY
RINGS EARRINGS NECKLACE0
と云ふのもある。E宙E CP FOREIGN DRY GOODS AND GROCHERIES…
……LADY.S UNDERWEARS DRAPERIE0 TAPESTRIE0 EMBROIDERIES" それらの言葉は何だか耳に聞
いたヾけでもピアノの音のやうに重々しく美しい。
東京から僅か一時間電車に乘ったヾけであるのに、非常に遠い所
へ來たやうな氣がする。
そして、買ひたいと思ふ物があっても、寂然と扉を鎖した店つきを見ると、何となく中へ這
入るのが躊曙せられる。銀座あたりの商店ではそんな事はないのだが、此れが外國人向きなのであらうか
此の街のシ
ヨオ•ウィンドオはたヾ冷然と商品とガラスの奥に並べて居るだけで、「買って下さい」と云ふやうな愛嬌がない。うす暗い
店の中には店員の働いて居さうなけはひもなく、いろいろな物を飾ってあるが佛壇のやうに沈鬱である。
一層そこにある商品を不思議に蠱惑的に見せるのでもあらう。
が、それが
あぐりと彼とはその街通りを暫く往ったり來たりした。彼の懐には金がある、そして彼女の服の下には白い肌がある。靴屋の
店、帽子屋の店、寶石商、雜貨商、毛皮屋、織物屋、 金さへ出せばそれらの店の品物がどれでも彼女の白い肌にはぴ
ったり纏はり、しなやかな四肢に絡まり、彼女の肉體の一部となる。
西洋の女の衣裳は「着る物」ではない、皮膚の
©
上層へもうーと重被さる第二の皮膚だ。外から體を包むのではなく、直接皮膚へべったりと滲み込む文身の一種だ。
う思って眺める時、到る所の飾り窓にあるものが皆あぐりの皮膚の一と片、肌の斑點、血のした、りであるとも思える。彼女
は其れらの品物の中から自分の好きな皮膚を買って、それを皮膚の一部へ貼り付ければよい。若しもお前が翡翠の耳環を買ふ
とすれば、お前はお前の耳朶に美しい綠の吹き出物が出來たと思へ。あの毛皮屋の店頭にある、栗鼠の外套を着るとすれば、
お前は毛なみがびろうどのやうにつやつやしい一匹の獣になったと思へ。あの雜貨店に吊るしてある靴下を求めるなら、お前
がそれを穿いた時からお前の足には絹の切れ地の皮が出來て、それへお前の暖かい血が通ふ。エナメルの沓を穿くとすればお
前の踵の軟かい肉は漆になってピカピカ光る。可愛いあぐりよ!彼處にある物はみんなお前と云ふ「女」の彫像へ當て«め
て作られたお前自身の脱け殻だ、お前の原型の部分々々だ。靑い脱け殼でも、紫のでも、紅いのでも、あれはお前の體から剥
お前はあんなに
さ
がした皮だ'「お前」を彼處で賣って居るのだ、彼處でお前の脱け殻がお前の魂を待って居るのだ'
素晴らしい「お前の物」を持って居るのに、なぜぶくぶくした不恰好のフランネルの服なんかにくるまって居る!
「はあ、
此のお孃さんがお召になる?
どんなのがよござんすかな。」
うす暗い奥から出て來た日本人の番頭は、さう云ひながらあぐりの様子をジロジロと見た。二人はとあるレデー・メ !ドの婦
人服屋へ這入ったのである。成るべく這入りよさゝうな、小じんまりした商店を選んだので中はそんなに立派ではないが、狭
い部屋の兩側にガラス張りのケースがあって、それへ幾つもの出來合ひの服が吊るしてある。ブラウスだのスカ!卜だのが、
「女の胸」や「女の腰」が、 衣紋架けにかけられて頭の上に下って居る。室の中央にも背の低いガラス棚があ
る。そしてそれにはペティコートや、シュミーズや' 靴下や、コルセットや、いろいろのレースの小切れやらが飾られて居る。
柔かい、ほんたうに女の皮膚よりも柔かい、チリチリとちヾれた縮緬だの、羽二重だの、編子だの、、滑らかな冷や冷やとし
た切れ地ばかりである。あぐりは自分が、やがてそんな切れ地を着せられて西洋人形のやうになるのかと思ふと、番頭にジロ
ジロ見られるのが耻かしくて、快活な、元氣のいゝ彼女にも似ず内氣に縮こまりながら、その癖「此れも欲しい、彼れも欲し
い」と云ふやうに眼を光らせる。
「あたし、どんなのがいゝのか分らないけれど、
ねえ、どれにしようか知ら?」
番頭の視線を避けるが如く岡田の蔭へ隱れながら、彼女は小聲で、當惑したやうに云ふ。
「さうですね、まあ此處いらならばどれでも似合ふと思ひますがね。」
さう云って番頭は、白い、麻のやうな服をひろげた。
「どうです、ちよっと此れを當てがって御覧なさい、 そこに鏡がありますから。」
あぐりは鏡の前に來て、その白いものをだらだらと頤の下へ垂らして見る。そして、子供がむづかる時のやうな陰鬱な顔つき
をして、上眼でじっと眺めて居る。
「どうだね、それにしたら
「えゝ、此れでもいゝわ。」
「此れは麻でもないやうだが、何だね物は?」
「それはコットン•ボイルですよ、サラサラして着心のいゝもんです。
「いくら?」
「さうですね、
えゝと此れはと、
•」
番頭は奥を向いて大きな聲を出す。
「おい、此のコットン•ボイルの服あ、此りあいくらだっけね、
え、四十五圓か?」
「體に合ふやうに直して貰はなきゃならないが今日中には間に合はないだらうか?」
「え?今日中に?明日の船で立つんですか。」
「いや、さうぢゃない、船へ乘る譯ぢゃないんだけれど、少し急ぐんだ。」
「おい、君、どうだい、
と、番頭は又奥へ向いて云ふ。
「今日中に直してくれって云ってるんだが、直してやれるかい、
直せるなら直してやってくれ給へ。」
ぞんざいな言葉づかひの、ぶっきらぼうな男であるが、親切な、人の好さゝうな番頭である。
「ぢや、直きに直して上げますがね、どうしたってもう二時間はか、りますよ。」
「そのくらゐは構はないよ、此れから帽子や靴を買って來て、此處で着換へさして貰ひたいんだ。洋服は始めてだもんだから
何も分らないんだけれど、下へ着る物はどんな物を揃へるんだらう?」
「よござんす、みんな店にありますからーと通り揃へて上げます。 此奴を一番下へ着てね、(と、番頭はガラス棚か
らするすると絹の胸當てを引き出して)それからその上へ此れを着けて、下へは此れと此れを穿くんです。こんな風に出來た
のもありますが、此奴あ此處が開いて居ないから、此れを穿くと小便が出來なくってね、だから西洋人は成るべく小便をしな
いやうにするんです。此奴は不便だから此の方がいゝでせう、此れなら此處にボタンがあって、ほら、此れを外せばちゃんと
此のシュミーズがハ圓です、此のペティコートが六圓ぐらゐです、日本の着物に比べると安いもん
それぢや寸法を取りますから此方へいらつしゃい。」
小便が出來ます。
ですが、此れだって、こんな綺麗な羽二重ですよ、
フランネルの布の上から、その下にある原型の圓みや長さが測られる。腕の下や脚の周りへ革の物差が巻きついて、彼女の肉
體の嵩と形とが檢べられる。
「此の女はいくらだね、:…
と、番頭がさう云ふやうのぢゃないか、自分は今、奴隸市場に居るのぢゃないか、そしてあぐりを賣り物に出して、値を付け
させて居るのぢゃないか、
.岡田はふいとそんな氣がした。
夕方の六時頃、彼とあぐりとは矢張その街の近所で買った紫水晶の耳環だの、眞珠の頸飾だの、靴だの帽子だの、包みを提げ
て婦人服屋の店へ戻った。
「やあお歸んなさい、好い物がありましたかね。」
と、番頭はすっかり馴れ馴れしい口調で云った。
出來上った服、
「もうみんな直って居ますよ、彼處にフィッティング・ルームがあります、 さ、彼處へ行って着換へて御覧なさい。」
しっとりと、一塊の雪のやうに柔かい物を片手にかゝへて、岡田はあぐりの後についてスクリーンの
蔭へ這入った。等身の姿見の前に進んで、彼女は相變らずむづかしい顔をしつ、も、靜かに帶を解き始める。
岡田の頭の中にある「女」の彫像が其處に立った。彼はチクチクと手に引っかゝる輕い絹を、彼女に手傳って肌へ貼
り着けてやりながら、ボタンを«め、ホックを押し、リボンを結び、彫像の周圍をぐるぐると廻る。あぐりの頰には其の時急
岡田は又グラグラと眩暈を感じる。
に嬉しさうな、生き生きとした笑ひが上る。
太宰治
「富嶽百景」
富士の頂角、広重の富士はハ十五度、文晁の富士もハ十四度くらい、けれども、陸軍の実測図によって東西及び南北に断
面図を作ってみると、東西縦断は頂角、百一 一十四度となり、南北は百十七度である。広重、文晁に限らずたいていの絵の富士
は、鋭角である。いただきが、細く、高く、華奢である。北斎にいたっては、その頂角、ほとんど三十度くらい、エッフェル
鉄塔のような富士をさえ描いている。けれども、実際の富士は、鈍角も鈍角、のろくさと拡がり、東西、百一 ー十四度、南北は
百十七度、決して、秀抜の、すらと高い山ではない。たとば私が、印度かどこかの国から、突然、鷲にさらわれ、すとんと日
本の沼津あたりの海岸に落されて、ふと、この山を見つけても、そんなに驚嘆しないだろう。ニッポンのフジヤマを、あらか
じめ憧れているからこそ、ワンダフルなのであって、そうでなくて、そのような俗な宣伝を、一さい知らず、素朴な、純粋
の、うつろな心に、果して、どれだけ訴え得るか、そのことになると、多少、心細い山である。低い。裾のひろがっている割
に、低い。あれくらいの裾を持っている山ならば、少くとも、もうー •五倍、高くなければいけない。
十国峠から見た富士だけは、高かった。あれは、よかった。はじめ、雲のために、いただきが見えず、私は、その裾の勾配
から判断して、たぶん、あそこあたりが、いただきであろうと、雲の一点にしるしをつけて、そのうちに、雲が切れて、見る
と、ちがった。私が、あらかじめ印をつけて置いたところより、その倍も高いところに、青い頂きが、すつと見えた。おどろ
いた、というよりも私は、へんにくすぐったく、げらげら笑った。やっていやがる、と思った。人は、完全のたのもしさに接
すると、まず、だらしなくげらげら笑ふものらしい。全身のネジが、他愛なくゆるんで、これはおかしな言いかたであるが、
帯紐といて笑ふといったような感じである。諸君が、もし恋人と逢って、逢ったとたんに、恋人がげらげら笑い出したら、慶
祝である。必ず、恋人の非礼をとがめてはならぬ。恋人は、君に逢って、君の完全のたのもしさを、全身に浴びているのだ。
東京の、アパートの窓から見る富士は、くるしい。冬には、はっきり、よく見える。小さい、真白い三角が、地平線にちょ
こんと出ていて、それが富士だ。なんのことはない、クリスマスの飾り菓子である。しかも左のほうに、肩が傾いて心細く、
船尾のほうからだんだん沈没しかけてゆく軍艦の姿に似ている。三年まえの冬、私は或る人から、意外の事実を打ち明けられ、
途方に暮れた。その夜、アパートの一室で、ひとりで、がぶがぶ酒のんだ。一睡もせず、酒のんだ。あかつき、小用に立って、
アパートの便所の金網張られた四角い窓から、富士が見えた。小さく、
ない。窓の下のアスファルト路を、さかなやの自転車が疾駆し、おう、
っぽう寒いや、など眩きのこして、私は、暗い便所の中に立ちつくし、
二度と繰りかえしたくない。
昭和十三年の初秋、思いをあらたにする覚悟で、私は、かばんひとつさげて旅に出た。
甲州。ここの山々の特徴は、山々の起伏の線の、へんに虚しい、なだらかさに在る。小島烏水という人の日本山水論にも、
「山の拗ね者は多く、此土に仙遊するが如し」と在った。甲州の山々は、あるいは山の、げてものなのかも知れない。私は甲
府市からバスにゆられて一時間。御坂峠へたどりつく。
真白で、左のはうにちよっと傾いて、あの富士を忘れ
けさは、やけに富士がはっきり見えるじゃねえか、め
窓の金網撫でながら、じめじめ泣いて、あんな思いは、
御坂峠、海抜千三百米。この峯の頂上に、天下茶屋という、小さい茶店があって、井伏鱒二氏が初夏のころから、ここの
©
©
二階に、こもって仕事をして居られる。私は、それを知ってここへ来た。井伏氏のお仕事の邪魔にならないようなら、隣室で
も借りて、私も、しばらくそこで仙遊しようと思っていた。
井伏氏は、仕事をして居られた。私は、井伏氏のゆるしを得て、当分その茶屋に落ちつくことになって、それから、毎日、
いやでも富士と真正面から、向き合っていなければならなくなった。この峠は、甲府から東海道に出る鎌倉往還の衝に当っ
ていて、北面富士の代表観望台であると言われ、ここから見た富士は、むかしから富士三景の一つにかぞえられているのだそ
うであるが、私は、あまり好かなかった。好かないばかりか、軽蔑さえした。あまりに、おあつらえむきの富士である。まん
なかに富士があって、その下に河口湖が白く寒々とひろがり、近景の山々がその両袖にひっそり蹲って湖を抱きかかるよう
にしている。私は、ひとめ見て、狼狽し、顔を赤らめた。これは、まるで、風呂屋のペンキ画だ。芝居の書割だ。どうにも註
文どおりの景色で、私は、恥ずかしくてならなかった。
私が、その峠の茶屋へ来て二、三日経って、井伏氏の仕事も一段落ついて、或る晴れた午後、私たちは三ツ峠へのぼった。
三ツ峠、海抜千七百米。御坂峠より、少し高い。急坂を這うようにしてよじ登り、一時間ほどにして三ツ峠頂上に達する。蔦
かずら搔きわけて、細い山路、這うようにしてよじ登る私の姿は、決して見よいものではなか•った。井伏氏はちゃんと登山服
着て居られて、軽快の姿であったが、私には登山服の持ち合せがなく、ドテラ姿であった。茶屋のドテラは短く、私の毛嚅は、
一尺以上も露出して、しかもそれに茶屋の老爺から借りたゴム底の地下足袋をはいたので、われながらむさ苦しく、少し工夫
して、角帯をしめ、茶屋の壁にかかっていた古い麦藁帽をかぶってみたのであるが、いよいよ変で、井伏氏は、人のなりふり
を決して軽蔑しない人であるが、このときだけは流石に少し、気の毒そうな顔をして、男は、しかし、身なりなんか気にしな
いほうがいい、と小声で眩いて私をいたわってくれたのを、私は忘れない。とかくして頂上についたのであるが、急に濃い霧
が吹き流れて来て、頂上のパノラマ台という、断崖の縁に立ってみてもいっこうに眺望がきかない。何も見えない。井伏氏
は、濃い霧の底、一岩に腰をおろし、ゆっくり煙草を吸いながら、放屁なされた。いかにも、つまらなそうであった。パノラマ
台には、茶店が三軒ならんで立っている。そのうちの一軒、老爺と老婆と二人きりで経営しているじみな一軒を選んで、そこ
で熱い茶を呑んだ。茶店の老婆は気の毒がり、ほんたうに生憎の霧で、もう少し経ったら霧もはれると思いますが、富士は、
ほんのすぐそこに、くっきり見えます、と言い茶店の奥から富士の大きい写真を持ち出し、崖の端に立ってその写真を両手で
高く掲示して、ちょうどこの辺に、このとおりに、こんなに大きく、こんなにはっきり、このとおりに見えます、と懸命に註
釈するのである。私たちは、番茶をすすりながら、その富士を眺めて、笑った。いい富士を見た。霧の深いのを、残念にも思
わなかった。
その翌々日であったろうか、井伏氏は、御坂峠を引きあげることになって、私も甲府までおともした。甲府で私は、或る娘
さんと見合いすることになっていた。井伏氏に連れられて甲府のまちはずれの、その娘さんのお家へお伺いした。井伏氏は無
雑作な登山服姿である。私は、角帯に、夏羽織を着ていた。娘さんのお家のお庭には、薔薇がたくさん植えられていた。母堂
に迎えられて客間に通され、挨拶して、そのうちに娘さんも出て来て、私は、娘さんの顔を見なかった。井伏氏と母堂とは、
おとな同士の、よもやまの話をして、ふと、井伏氏が、
「おや、富士」と眩いて、私の背後の長押を見あげた。私も、からだを捻じ曲げて、うしろの長押を見上げた。富士山頂大噴
火口の鳥瞰写真が、額縁にいれられて、かけられていた。まっしろい睡蓮の花に似ていた。私は、それを見とどけ、またゆ
っくりからだを捻じ戻すとき、娘さんを、ちらと見た。きめた。多少の困難があっても、このひとと結婚したいものだと思っ
た。あの富士は、ありがたかった。
井伏氏は、その日に帰京なされ、私は、ふたたび御坂にひきかえした。それから九月、十月、十一月の十五日まで、御坂の
茶屋の二階で、少しずつ、少しずつ、仕事をすすめ、あまり好かないこの「富士三景の一つ」と、へたばるほど対談した。
いちど、大笑いしたことがあった。大学の講師か何かやっている浪漫派の一友人が、ハイキングの途中、私の宿に立ち寄っ
てそのときに、ふたり二階の廊下に出て、富士を見ながら、
「どうも俗だねえ。お富士さん、という感じじゃないか」
「見ているほうで、かえって、てれるね」
などと生意気なこと言って、煙草をふかし、そのうちに、友人は、ふと、
「おや、あの僧形のものは、なんだね?」と顎でしゃくった。
墨染の破れたころもを身にまとい、長い杖を引きずり、富士を振り仰ぎ振り仰ぎ、峠をのぼって来る五十歳くらいの小男が
ある。
「富士見西行、といったところだね。かたちが、できてる」私は、その僧をなつかしく思った。
「いずれ、名のある聖僧かも知れないね」
「ばか言うなよ、乞食だよ」友人は、冷淡だった。
「いや、いや。脱俗しているところがあるよ。歩きかたなんか、なかなか、できてるじゃないか。むかし、能因法師が、この
峠で富士をほめた歌を作ったそうだが、——」
私が言っているうちに友人は、笑い出した。
「おい、見給え。できてないよ」
能因法師は、茶店のハチという飼犬に吠えられて、周章狼狽であった。その有様は、いやになるほど、みっともなかった。
「だめだねえ。やっぱり」
私は、がっかりした。
乞食の狼狽は、むしろ、
退散した。実に、それは、
しい。
あさましいほどに右往左往、ついには杖をかなぐり捨て、取り乱し、取り乱し、いまはかなわずと
できてなかった。富士も俗なら、法師も俗だ、ということになって、いま思い出しても、ばかばか
新田というーー十五歳の温厚な青年が、峠を降りきった岳麓の吉田という細長い町の、郵便局につとめていて、そのひとが、
郵便物に依って、私がここに来ていることを知った、と言って、峠の茶屋をたずねて来た。二階の私の部屋で、しばらく話を
して、ようやく馴れて来たころ、新田は笑いながら、実は、もう二、三人、僕の仲間がありまして、皆で一緒にお邪魔にあが
るつもりだったのですが、いざとなると、どうも皆、しりごみしまして、太宰さんは、ひどいデカダンで、それに、性格破産
者だ、と佐藤春夫先生の小説に書いてございましたし、まさか、こんなまじめな、ちゃんとしたお方だとは、思いませんでし
たから、僕も、無理に皆を連れて来るわけには、いきませんでした。こんどは、皆を連れて来ます。かまいませんでしょうか。
「それは、かまいませんけれど」私は、苦笑していた。「それでは、君は、必死の勇をふるって、君の仲間を代表して僕を偵
察に来たわけですね」
「決死隊でした」新田は、率直だった。「ゆうべも、佐藤先生のあの小説を、もういちど繰りかえして読んじろいろ覚悟をき
めて来ました」
私は、部屋の硝子戸越しに、富士を見ていた。富士は、のっそり黙って立っていた。偉いなあ、と思った。
「いいねえ。富士は、やっぱり、いいとこあるねえ。よくやってるなあ」富士には、かなわないと思った。念々と動く自分の
©
愛憎が恥ずかしく、富士は、やっぱり偉い、と思った。よくやってる、と思った。
「よくやっていますか」新田には、私の言葉がおかしかったらしく、聡明に笑っていた。
新田は、それから、いろいろな青年を連れて来た。皆、静かなひとである。皆は、私を、先生、と呼んだ。私はまじめにそ
その青年たちに' 先生、
れを受けた。私には、誇るべき何もない。学問もない。才能もない。肉体よごれて、心もまずしい。けれども、苦悩だけは、
と言われて、だまってそれを受けていいくらいの、苦悩は、経て来た。たったそれだけ。藁一すじの
自負である。けれども、
来た私の、裏の苦悩を、
私は、この自負だけは、はっきり持っていたいと思っている。わがままな駄々つ子のように言われて
ーたい幾人知っていたろう。新田と、それから田辺という短歌の上手な青年と、二人は、井伏氏の読
者であって、その安心もあって、私は、この二人と一ばん仲良くなった。いちど吉田に連れていってもらった。おそろしく細
長い町であった。岳麓の感じがあった。富士に、日も、風もさえぎられて、ひょろひょろに伸びた茎のようで、暗く、
うすら
寒い感じの町であった。道路に沿って清水が流れている。これは岳麓の町の特徴らしく、三島でも、こんな工合いに、
町じゅ
うを清水が、どんどん流れている。富士の雪が溶けて流れて来るのだ、とその地方の人たちが、まじめに信じている。
吉田の
水は、三島の水に較べると、水量も不足だし、汚い。水を眺めながら、私は、話した。
「モウパスサンの小説に、どこかの令嬢が、貴公子のところへ毎晩、河を泳いで逢いにいったと書いて在ったが、着物は、ど
うしたのだろうね。まさか、裸ではなかろう」
「そうですね」青年たちも、考えた。「海水着じゃないでしょうか」
「頭の上に着物を載せて、むすびつけて、そうして泳いでいったのかな?」
青年たちは、笑った。
「それとも、着物のままはいって、ずぶ濡れの姿で貴公子と逢って、ふたりでストオヴでかわかしたのかな? そうすると、
かえるときには、どうするだろう。せっかく、かわかした着物を、またずぶ濡れにして、泳がなければいけない。心配だね。
貴公子のほうで泳いで来ればいいのに。男なら、猿股一つで泳いでも、そんなにみっともなくないからね。貴公子、鉄鎚だっ
たのかな?」
「いや、令嬢のほうで、たくさん悔れていたからだと思います」新田は、まじめだった。
「そうかも知れないね。外国の物語の令嬢は、勇敢で、可愛いね。好きだとなったら、河を泳いでまで逢いに行くんだからな。
日本では、そうはいかない。なんとかいう芝居があるじゃないか。まんなかに川が流れて、両方の岸で男と姫君とが、愁嘆し
ている芝居が。あんなとき、何も姫君、愁嘆する必要がない。泳いでゆけば、どんなものだろう。芝居で見ると、とても狭い
川なんだ。じゃぶじゃぶ渡っていったら、どんなもんだろう。あんな愁嘆なんて、意味ないね。同情しないよ。朝顔の大井川
は、あれは大水で、それに朝顔は、めくらの身なんだし、あれには多少、同情するが、けれども、あれだって、泳いで泳けな
いことはない。大井川の棒杭にしがみついて、天道さまを、うらんでいたんじゃ、意味ないよ。あ、ひとり在るよ。日本にも、
勇敢なやつが、ひとり在ったぞ。あいつは、すごい。知ってるかい?」
「ありますか」青年たちも、眼を輝かせた。
「清姫。安珍を追いかけて、日高川を泳いだ。泳ぎまくった。あいつは、すごい。ものの本によると、清姫は、あのとき十四
だったんだってね」
路を歩きながら、ばかな話をして、まちはずれの田辺の知合いらしい、ひっそり古い宿屋に着いた。
そこで飲んで、その夜の富士がよかった。夜の十時ごろ、青年たちは、私ひとりを宿に残して、おのおの家へ帰っていった。
私は、眠れず、どてら姿で、外へ出てみた。おそろしく、明るい月夜だった。富士が、よかった。月光を受けて、青く透きと
おるようで、私は、狐に化かされているような気がした。富士が、したたるように青いのだ。燐が燃えているような感じだっ
た。鬼火。狐火。ほたる。すすき。葛の葉。私は、足のないような気持で、夜道を、まつつすぐに歩いた。下駄の音だけが、
自分のものでないように、他の生きもののように、からんころんからんころん、とても澄んで響く。そっと、振りむくと'富
士がある。青く燃えて空に浮んでいる。私は溜息をつく。維新の志士。鞍馬天狗。私は、自分を、それだと思った。ちよっと
気取って、ふところ手して歩いた。ずいぶん自分が、いい男のように思われた。ずいぶん歩いた。財布を落した。五十銭銀貨
が二十枚くらいはいっていたので、重すぎて、それで懐からするっと脱け落ちたのだろう。私は、不思議に平気だった。金が
なかったら、御坂まで歩いてかえればいい。そのまま歩いた。ふと、いま来た路を、そのとおりに、もういちど歩けば、財布
は在る、ということに気がついた。懐手のまま、ぶらぶら引きかした。富士。月夜。維新の志士。財布を落した。興あるロマ
ンスだと思った。財布は路のまんなかに光っていた。在るにきまっている。私は、それを拾って、宿へ帰って、寝た。
富士に、化かされたのである。私は、あの夜、阿呆であった。完全に、無意志であった。あの夜のことを、いま思い出して
も、へんに、だるい。
吉田に一泊して、あくる日' 御坂へ帰って来たら、茶店のおかみさんは、にやにや笑って、十五の娘さんは、つんとしてい
た。私は、不潔なことをして来たのではないということを、それとなく知らせたく、きのう一日の行動を、聞かれもしないの
に、ひとりでこまかに言いたてた。泊った宿屋の名前、吉田のお酒の味、月夜富士、財布を落したこと、みんな言った。娘さ
んも、機嫌が直った。
「お客さん!起きて見よ!」かん高い声で或る朝、茶店の外で、娘さんが絶叫したので、私は、しぶしぶ起きて、廊下へ出
て見た。
娘さんは、興奮して頰をまつかにしていた。だまって空を指さした。見ると、雪。はっと思った。富士に雪が降ったのだ。
山頂が、まっしろに、光りかがやいていた。御坂の富士も、ばかにできないぞと思った。
「いいね」
とほめてやると、娘さんは得意そうに、
「すばらしいでしょう?」といい言葉使って、「御坂の富士は、これでも、だめ?」としゃがんで言った。私が、かねがね、
こんな富士は俗でだめだ、と教えていたので、娘さんは、内心しょげていたのかも知れない。
「やはり、富士は、雪が降らなければ、だめなものだ」もっともらしい顔をして、私は、そう教えなおした。
私は、どてら着て山を歩きまわって、月見草の種を両の手のひらに一ぱいとって来て、それを茶店の背戸に播いてやって、
「いいかい、これは僕の月見草だからね、来年また来て見るのだからね、ここへお洗濯の水なんか捨てちゃいけないよ」娘さ
んは、うなずいた。
ことさらに、月見草を選んだわけは、富士には月見草がよく似合うと、思い込んだ事情があったからである。御坂峠のその
茶店は、謂わば山中の一軒家であるから、郵便物は、配達されない。峠の頂上から、バスで三十分程ゆられて峠の麓、河口
湖畔の、河口村という文字通りの寒村にたどり着くのであるが、その河口村の郵便局に、私宛の郵便物が留め置かれて、私は
三日に一度くらいの割で、その郵便物を受け取りに出かけなければならない。天気の良い日を選んで行く。ここのバスの女車
掌は、遊覧客のために、格別風景の説明をして呉れない。それでもときどき、思い出したように、甚だ散文的な口調で、あ
れが三ツ峠、向うが河口湖、わかさぎという魚がいます、など、物憂そうな、眩きに似た説明をして聞かせることもある。
©
©
河口局から郵便物を受け取り、またバスにゆられて峠の茶屋に引つ返す途中、私のすぐとなりに、濃い茶色の被布を着た青
白い端正の顔の、六十歳くらい、私の母とよく似た老婆がしゃんと坐っていて、女車掌が、思い出したように、みなさん、き
ようは富士がよく見えますね、と説明ともつかず、また自分ひとりの咏嘆ともつかぬ言葉を、突然言いだして、リユックサッ
クしょった若いサラリイマンや、大きい日本髪ゆって、口もとを大事にハンケチでおおいかくし、絹物まとった芸者風の女な
ど、からだをねじ曲げ、一せいに車窓から首を出して、いまさらのごとく、その変哲もない三角の山を眺めては、やあ、とか、
まあ、とか間抜けた嘆声を発して、車内はひとしきり、ざわめいた。けれども、私のとなりの御隠居は、胸に深い憂悶でもあ
るのか' 他の遊覽客とちがって、富士には一瞥も与ず、かえって富士と反対側の、山路に沿った断崖をじっと見つめて、私に
はその様が、からだがしびれるほど快く感ぜられ、私もまた、富士なんか、あんな俗な山見度くもないという、高尚な虚無の
心を、その老婆に見せてやりたく思って、あなたのお苦しみ、わびしさ、みなよくわかる、と頼まれもせぬのに、共鳴の素振
りを見せてあげたく、老婆に甘えかかるように、そっとすり寄って、老婆とおなじ姿勢で、ぼんやり崖の方を、眺めてやった。
老婆も何かしら、私に安心していたところがあったのだろう、ぼんやりひとこと、
「おや、月見草」
そう言って、細い指でもって、路傍の一箇所をゆびさした。さっと、バスは過ぎてゆき、私の目には、いま、ちらとひとめ
見た黄金色の月見草の花ひとつ、花弁もあざやかに消えず残った。
三七七八米の富士の山と、立派に相対峙し、みじんもゆるがず、なんと言うのか、金剛力草とでも言いたいくらい、けなげ
にすっくと立っていたあの月見草は、よかった。富士には、月見草がよく似合う。
十月のなかば過ぎても、私の仕事は遅々として進まぬ。人が恋しい。夕焼け赤き雁の腹雲、二階の廊下で、ひとり煙草を吸
いながら、わざと富士には目もくれず、それこそ血の滴るような真赤な山の紅葉を、凝視していた。茶店のまの落葉を掃き
あつめている茶店のおかみさんに、声をかけた。
「おばさん!あしたは、天気がいいね」
自分でも、びっくりするほど、うわずって、歓声にも似た声であった。おばさんは箒の手をやすめ、顔をあげて、不審げ
に眉をひそめ、
「あした、何かおありなさるの?」
そう聞かれて、私は窮した。
「なにもない」
おかみさんは笑い出した。
「おさびしいのでしょう。山へ でもおのぼりになったら?」
「山は、のぼっても、すぐまた降りなければいけないのだから、つまらない。どの山へのぼっても、おなじ富士山が見えるだ
けで、それを思うと、気が重くなります」
私の言葉が変だったのだろう。おばさんはただ曖昧にうなずいただけで、また枯葉を掃いた。
ねるまえに、部屋のカーテンをそっとあけて硝子窓越しに富士を見る。月の在る夜は富士が青白く、水の精みたいな姿で立
っている。私は溜息をつく。ああ、富士が見える。星が大きい。あしたは、お天気だな、とそれだけが、幽かに生きている喜
びで、そうしてまた、そっとカーテンをしめて、そのまま寝るのであるが、あした、天気だからとて、別段この身には、なん
ということもないのに、と思えば、おかしく、ひとりで蒲団の中で苦笑するのだ。くるしいのである。仕事が、——純粋に運
©
筆することの、その苦しさよりも、いや、運筆はかえって私の楽しみでさえあるのだが、そのことではなく、私の世界観、芸
術というもの、あすの文学というもの、謂わば、新しさというもの、私はそれらに就いて、未だ愚図愚図、思い悩み、誇張で
はなしに、身悶えしていた。
素朴な、自然のもの、従って簡潔な鮮明なもの、そいつをさっと一挙動で掴まえて、そのままに紙にうつしとること、それ
より他には無いと思い、そう思うときには、眼前の富士の姿も、別な意味をもって目にうつる。この姿は、この表現は、結局、
私の考えている「単一表現」の美しさなのかも知れない、と少し富士に妥協しかけて、けれどもやはりどこかこの富士の、あ
まりにも棒状の素朴には閉口しているところもあり、これがいいなら、ほていさまの置物だっていい筈だ'ほていさまの置物
は、どうにも我慢できない、あんなもの、とても、いい表現とは思えない、この富士の姿も、やはりどこか間違っている、こ
れは違う、と再び思いまどうのである。
朝に、タに、富士を見ながら、陰欝な日を送っていた。十月の末に、麓の吉田のまちの、遊女の一団体が、御坂峠へ、お
そらくは年に一度くらいの開放の日なのであろう、自動車五台に分乗してやって来た。私は二階から、その様を見ていた。自
動車からおろされて、色さまざまの遊女たちは、バスケットからぶちまけられた一群の伝書鳩のように、はじめは歩く方向を
知らず、ただかたまってうろうろして、沈黙のまま押し合い、へし合いしていたが、やがてそろそろ、その異様の緊張がほど
けて、てんでにぶらぶら歩きはじめた。茶店の店頭に並べられて在る絵葉書を、おとなしく選んでいるもの、佇んで富士を
眺めているもの、暗く、わびしく、見ちゃ居れない風景であった。二階のひとりの男の、いのち惜しまぬ共感も、これら遊女
の幸福に関しては、なんの加えるところがない。私は、ただ、見ていなければならぬのだ。苦しむものは苦しめ。落ちるもの
は落ちよ。私に関係したことではない。それが世の中だ。そう無理につめたく装い、かれらを見下ろしているのだが、私は、
かなり苦しかった。
富士にたのもう。突然それを思いついた。おい、こいつらを、よろしく頼むぜ、そんな気持で振り仰げば、寒空のなか、の
っそり突つ立っている富士山、そのときの富士はまるで、どてら姿に、ふところ手して傲然とかまている大親分のようにさえ
見えたのであるが、私は、そう富士に頼んで、大いに安心し、気軽くなって茶店の六歳の男の子と、ハチというむく犬を連れ、
その遊女の一団を見捨てて、峠のちかくのトンネルの方へ遊びに出掛けた。トンネルの入口のところで、三十歳くらいの瘦せ
た遊女が、ひとり、何かしらつまらぬ草花を、だまって摘み集めていた。私たちが傍を通っても、ふりむきもせず熱心に草花
をつんでいる。この女のひとのことも、ついでに頼みます、とまた振り仰いで富士にお願いして置いて、私は子供の手をひき、
とっとと、トンネルの中にはいって行った。トンネルの冷たい地下水を、頰に、首筋に、滴々と受けながら、おれの知ったこ
とじゃない、とわざと大股に歩いてみた。
そのころ、私の結婚の話も、一頓挫のかたちであった。私のふるさとからは、全然、助力が来ないということが、はっきり
判ってきたので、私は困って了った。せめて百円くらいは、助力してもらるだろうと、虫のいい、ひとりぎめをして、それで
もって、ささやかでも、厳粛な結婚式を举げ、あとの、世帯を持つに当っての費用は、私の仕事でかせいで、しようと思って
いた。けれども、ーー、三の手紙の往復に依り、うちから助力は、全く無いということが明らかになって、私は、途方にくれて
いたのである。このうえは、縁談ことわられても仕方がない、と覚悟をきめ、とにかく先方へ、事の次第を洗いざらい言って
見よう、と私は単身、峠を下り、甲府の娘さんのお家へお伺いした。さいわい娘さんも家にいた。私は客間に通され、娘さん
と、母堂と二人を前にして、悉皆の事情を告白した。ときどき演説口調になって、閉口した。けれども、割に素直に語りつく
したように思われた。娘さんは、.落ちついて、
「それで、おうちでは、反対なのでございましょうか」と、首をかしげて私にたずねた。
「いいえ、反対というのではなく」私は右の手のひらを、そっと卓の上に押し当て、「おまえひとりで、やれ、という工合い
らしく思われます」
「結構でございます」母堂は、品よく笑いながら、「私たちも、ごらんのとおりお金持ではございませぬし、ことごとしい式
などは、かつて当惑するようなもので、ただ、あなたおひとり、愛情と、職業に対する熱意さえ、お持ちならば、それで私た
ち、結構でございます」
私は、お辞儀するのも忘れて、しばらく呆然と庭を眺めていた。眼の熱いのを意識した。この母に、孝行しようと思った。
かえりに、娘さんは、バスの発着所まで送って来て呉れた。歩きながら、
「どうです。もう少し交際してみますか?」
きざなことを言ったものである。
「いいえ。もう、たくさん」娘さんは、笑っていた。
「なにか、質問ありませんか?」いよいよ、ばかである。
「ございます」
私は何を聞かれても、ありのまま答えようと思っていた。
「富士山には、もう雪が降ったでしょうか」
私は、その質問に拍子抜けがした。
「降りました。いただきのほうに、——」と言いかけて、ふと前方を見ると、富士が見える。へんな気がした。
「なあんだ。甲府からでも、富士が見えるじゃないか。ばかにしていやがる」やくざな口調になってしまって、「いまのは、
愚問です。ばかにしていやがる」
娘さんは、うつむいて、くすくす笑って、
「だって、御坂峠にいらっしゃるのですし、富士のことでもお聞きしなければ、わるいと思って」
おかしな娘さんだと思った。
甲府から帰って来ると、やはり、呼吸ができないくらいにひどく肩が凝っているのを覚えた。
「いいねえ、おばさん。やっぱり御坂は、いいよ。自分のうちに帰って来たような気さえするのだ」
夕食後、おかみさんと、娘さんと、交る交る、私の肩をたたいてくれる。おかみさんの拳は固く、鋭い。娘さんのこぶし
は柔かく、あまり効きめがない。もっと強く、もっと強くと私に言われて、娘さんは薪を持ち出し、それでもって私の肩をと
んとん叩いた。それ程にしてもらわなければ、肩の凝がとれないほど、私は甲府で緊張し、一心に努めたのである。
甲府行って来て、二、三日、流石に私はぼんやりして、仕事する気も起らず、机のまえに坐って、とりとめのない楽書をし
ながら、バットを七箱もハ箱も吸い、また寝ころんで、金剛石も磨かずば、という唱歌を、繰り返し繰り返し歌ってみたりし
ているばかりで、小説は、一枚も書きすすめることができなかった。
「お客さん。甲府へ行ったら、わるくなったわね」
朝、私が机に頰杖つき、目をつぶって、さまざまのことを考ていたら、•私の背後で、床の間ふきながら、十五の娘さんは、
しんからいまいましそうに、多少、とげとげしい口調で、そう言った。私は、振りむきもせず、
「そうかね。わるくなったかね」
迪
娘さんは、拭き掃除の手を休めず、
「ああ、わるくなった。この二、三日、ちっとも勉強すすまないじゃないの。あたしは毎朝、お客さんの書き散らした原稿用
紙、番号順にそろえるのが、とっても、たのしい。たくさんお書きになって居れば、うれしい。ゆうべもあたし、二階そっと
様子を見に来たの、知ってる? お客さん、ふとん頭からかぶって、寝てたじゃないか」
私は、ありがたい事だと思った。大袈裟な言いかたをすれば、これは人間の生き抜く努力に対しての、純粋な声援である。
なんの報酬も考えていない。私は娘さんを、美しいと思った。
十月末になると、山の紅葉も黒ずんで、汚くなり、とたんに一夜あらしがあって、みるみる山は、真黒い冬木立に化してし
まった。遊覽の客も、いまはほとんど、数えるほどしかない。茶店もさびれて、ときたま、おかみさんが、六つになる男の子
を連れて、峠のふもとの船津、吉田に買物をしに出かけて行って、あとには娘さんひとり、遊覧の客もなし、一日中、私と娘
さんと、ふたり切り、峠の上で、ひっそり暮すことがある。私が二階で退屈して、外をぶらぶら歩きまわり、茶店の脊戸で、
お洗濯している娘さんの傍へ近寄り、
「退屈だね」
と大声で言って、ふと笑いかけたら、娘さんはうつむき、私はその顔を覗いてみて、はっと思った。泣きべそかいているの
だ。あきらかに恐怖の情である。そうか、と苦が苦がしく私は、くるりと廻れ右して、落葉しきつめた細い山路を、まったく
いやな気持で、どんどん荒く歩きまわった。
それからは、気をつけた。娘さんひとりきりのときには、なるべく二階の室から出ないようにつとめた。茶店にお客でも来
たときには、私がその娘さんを守る意味もあり、のしのし二階から降りていって、茶店の一隅に腰をおろしゆっくりお茶を飲
むのである。いつか花嫁姿のお客が、紋附を着た爺さんふたりに附き添われて、自動車に乗ってやって来て、この峠の茶屋で
ひと休みしたことがある。そのときも、娘さんひとりしか茶店にいなかった。私は、やはり二階から降りていって、隅の椅子
に腰をおろし、煙草をふかした。花嫁は裾模様の長い着物を着て、金禰の帯を背負い、角隠しつけて、堂々正式の礼装であっ
た。全く異様のお客様だったので、娘さんもどうあしらいしていいのかわからず、花嫁さんと、二人の老人にお茶をついでや
っただけで、私の背後にひっそり隠れるように立つたまま、だまって花嫁のさまを見ていた。一生にいちどの晴の日に、——
峠の向う側から、反対側の船津か、吉田のまちへ嫁入りするのであろうが、その途中、この峠の頂上で一休みして、富士を眺
めるということは、はたで見ていても、くすぐったい程、ロマンチックで、そのうちに花嫁は、そっと茶店から出て、茶店の
まえの崖のふちに立ち、ゆっくり富士を眺めた。脚をX形に組んで立っていて、大胆なポオズであった。余裕のあるひとだな、
となおも花嫁を、富士と花嫁を、私は観賞していたのであるが、間もなく花嫁は、富士に向って、大きな欠伸ををした。
「あら!」
と背後で、小さい叫びを挙げた。娘さんも、素早くその欠伸を見つけたらしいのである。やがて花嫁の一行は、待たせて置
いた自動車に乗り、峠を降りていったが、あとで花嫁さんは、さんざんだった。
「馴れていやがる。あいつは、きっと二度目、いや、三度目くらいだよ。おむこさんが、峠の下で待っているだろうに、自動
車から降りて、富士を眺めるなんて、はじめてのお嫁だったら、そんな太いこと、できるわけがない」
「欠伸したのよ」娘さんも、カこめて賛意を表した。「あんな大きい□あけて欠伸して、図々しいのね。お客さん、あんなお
嫁さんもらっちゃ、いけない」
私は年甲斐もなく、顔を赤くした。私の結婚の話も、だんだん好転していって、或る先輩に、すべてお世話になってしまっ
た。結婚式も、ほんの身内の二、三のひとにだけ立ち合ってもらって、まずしくとも厳粛に、その先輩の宅で、していただけ
るようになって、私は人の情に、少年の如く感奮していた。
十一月にはいると、もはや御坂の寒気、堪えがたくなった。茶店では、ストオヴを備えた。
「お客さん、二階はお寒いでしょう。お仕事のときは、ストオヴの傍でなさったら」と、おかみさんは言うのであるが、私は、
人の見ているまでは、仕事のできないたちなので、それは断った。おかみさんは心配して、峠の麓の吉田へ行き、炬燧をひと
つ買って来た。私は二階の部屋でそれにもぐって、この茶店の人たちの親切には、心からお礼を言いたく思って、けれども、
もはやその全容の三分の二ほど、雪をかぶった富士の姿を眺め、また近くの山々の、蕭条たる冬木立に接しては、これ以上、
この峠で、皮膚を刺す寒気に辛抱していることも無意味に思われ、山を下ることに決意した。山を下る、その前日、私は、ど
てらを二枚かさねて着て、茶店の椅子に腰かけて、熱い番茶を啜っていたら、冬の外套着た、タイピストでもあろうか、若い
知的の娘さんがふたり、トンネルの方から、何かきやっきやつ笑いながら歩いて来て、ふと眼前に真白い富士を見つけ、打た
れたように立ち止り、それから、ひそひそ相談の様子で、そのうちのひとり、眼鏡かけた、色の白い子が、にこにこ笑いなが
ら、私のほうへやって来た。
「相すみません。シャッタア切って下さいな」
私は、へどもどした。私は機械のことには、あまり明るくないのだし、写真の趣味は皆無であり、しかも、どてらをーー枚も
かさねて着ていて、茶店の人たちさへ、山賊みたいだ、といって笑っているような、そんなむさくるしい姿でもあり、多分は
東京の、そんな華やかな娘さんから、はいからの用事を頼まれて、内心ひどく狼狽したのである。けれども、また思い直し、
こんな姿はしていても、やはり、見る人が見れば、どこかしら、きやしゃな 佛もあり、写真のシャッタアくらい器用に手さ
ばき出来るほどの男に見えるのかも知れない、などと少し浮き浮きした気持も手伝い、私は平静を装い、娘さんの差し出す力
メラを受け取り、何気なさそうな口調で、シャッタアの切りかたを鳥渡たずねてみてから、わななきわななき、レンズをのぞ
いた。まんなかに大きい富士、その下に小さい、罂粟の花ふたつ。ふたり揃いの赤い外套を着ているのである。ふたりは、ひ
しと抱き合うように寄り添い、屹っとまじめな顔になった。私は、おかしくてならない。カメラ持つ手がふるえて、どうにも
ならぬ。笑いをこらえて、レンズをのぞけば、S粟の花、いよいよ澄まして、固くなっている。どうにも狙いがつけにくく、
私は、ふたりの姿をレンズから追放して、ただ富士山だけを、レンズーぱいにキヤッチして、富士山、さようなら、お世話に
なりました。パチリ。
「はい、うつりました」
「ありがとう」
ふたり声をそろえてお礼を言う。うちへ帰って現像してみた時には驚くだろう。富士山だけが大きく大きく写っていて、ふ
たりの姿はどこにも見えない。
その翌る日に、山を下りた。まず、甲府.」安宿に一泊して、そのあくる朝、安宿の廊下の汚い欄干によりかかり、富士を見
ると、甲府の富士は、山々のうしろから、三分の一ほど顔を出している。酸漿に似ていた。
「神います」
夕暮になると、山際に一つの星が瓦斯燈のやうに輝いて、彼を驚かせた。こんな大きい目近の星を、彼はほかの土地で見た
ことがない。その光に射られて寒さを感じ、白い小石の道を狐のやうに飛んで歸った。落葉一つ動かずに靜かだった。
湯殿に走りこんで温泉に飛び込み、温かい濡手拭を顔にあてると、初めて冷たい星が頰から落ちた。
「お寒くなりました。たうとうお正月もこちらでなさいますか。」
見ると、宿へ來るので顔馴染の鳥屋だった。
「いいえ、南へ山を越えようかと思つてゐます。」
「南は結構ですな。私共も三四年前まで山南にゐたので、冬になると南へ歸りたくなりましてな。」と言ひながらも、鳥屋
は彼の方を見向かうとしなかった。彼は鳥屋の不思議な動作をじっと盗み見してゐた。鳥屋は湯の中に膝を突いて伸び上りな
がら、湯槽の縁に腰を掛けた妻の胸を洗ってやってゐるのだった。
若い妻は胸を夫にあてがうやうに突き出して、夫の顔を見てゐた。小さい胸には小さい乳房が白い盃のやうに貧しく膨らん
でゐて、病氣のためにいつまでも少女の體でゐるらしい彼女の幼い淸らかさのしるしであった。この柔かい草の莖のやうな體
は、その上に支へた美しい顔を一層花のやうに感じさせてゐた。
「お客様、山南においでになるのは初めてですか。」
「いいえ、五六年前に行ったことがあります。」
「さやうですか。」
鳥屋は片手で妻の方を抱きながら、石鹼の泡を胸から流してやってゐた。
「峠の茶店に中風の爺さんがゐましたね。今でもゐますかしら。」
彼は惡いことを言ったと思った。鳥屋の妻も手足が不自由らしいのだ。
「茶店の爺さんとワ——誰のことだらう。」
鳥屋は彼の方を振り向いた。妻が何氣なく言った。
「あのお爺さんは、もう三四年前になくなりました。」
「へえ、さうでしたか。」と彼は初めて妻の顔をまともに見た。そして、はっと目を反らせると同時に手拭で顔を蔽うた。
(あの少女だ。)
彼は夕暮の湯氣の中に身を隱したかった。良心が裸を恥かしがった。五六年前の旅に山南で傷つけた少女なのだ。その少女
のために五六年の間良心が痛み續けてゐたのだ。しかし感情は遠い夢を見續けてゐたのだ。それにしても、湯の中で會はせる
のは餘りに殘酷な偶然ではないか。彼は息苦しくなって手拭を顔から離した。
鳥屋はもう彼なんかを相手にせずに、湯から上って妻のうしろへ廻った。
「さあ、ー。へん沈め。」
妻は尖った兩肘をこころもち開いた。鳥屋が脇の下から輕々と抱き上げた。彼女は賢い猫のやうに手足を縮めた。彼女の沈
む波が彼の頤をちろちろと舐めた。
そこへ鳥屋が飛び込んで、少し禿げ上った頭に騒がしく湯を浴び始めた。彼がそっとうかがってみると彼女は熱い湯が體に
沁みるのか、二つの眉を引き寄せながら固く眼をつぶってゐた。少女の時分にも彼を驚かせた豊かな髪が、重過ぎる装飾品の
やうに形を毀して傾いてゐた。
泳いで廻れる程の廣い湯槽なので、一隅に沈んでゐる彼が誰であるかを、彼女は氣がつかないでゐるらしかった。彼は祈る
やうに彼女の許しを求めてゐた。彼女が病氣になったのも、彼の罪かもしれないのである。白い悲しみのやうな彼女の體が、
彼のためにかうまで不幸になったと、眼の前で語ってゐるのである。
鳥屋が手足の不自由な若い妻をこの世になく愛撫してゐることは、この温泉の評判になってゐた。毎日四十男が妻を負ぶっ
て湯に通ってゐても、妻の病身ゆゑに一個の詩として誰も心よく眺めてゐるのだった。しかし、大抵は村の共同湯にはいって
宿の湯へは來ないので、その妻があの少女であるとは、彼は知るはずもなかったのだった。
湯槽に彼がゐることなぞを忘れてしまったかのやうに、間もなく鳥屋は自分が先きに湯を出て、妻の着物を湯殿の階段に擴
げてゐた。肌着から羽織まで袖を通して重ねてしまふと、湯の中から妻を抱き上げてやった。うしろ向きに抱かれて、彼女は
やはり賢い猫のやうに手足を縮めてゐた。圓い膝頭が指環の蛋白石のやうだった。階段の着物の上に腰掛けさせて、彼女の顎
を中指一本で持ち上げて喉を拭いてやったり、櫛でおくれ毛を搔き上げてやったりしてゐた。それから、裸の蕊を花瓣で包む
やうに、すっぽりと着物でくるんでやった。
帶を結んでしまふと、柔かく彼女を負ぶって、河原傳ひに歸って行った。河原はほの明るい月かげだった。不恰好な半圓を
畫いて妻を支へてゐる鳥屋の腕よりもへその下に白く搖れてゐる彼女の足の方が小さかった。
鳥屋の後姿を見送ると、彼は柔かい涙をぽたぽたと湯の上に落した。知らず知らずのうちに素直な心で眩いてゐた。
「神います。」
自分が彼女を不幸にしたと信じてゐたのは誤りであることが分つた。身の程を知らない考へであることが分った。人間は人
間を不幸になぞ出來ないことが分った。彼女に許しを求めたりしたのも誤りであることが分った。傷つけたが故に高い立場に
ゐる者が傷つけられたが故に低い立場にゐる者に許しを求めると言ふ心なぞは驕りだと分った。人間は人間を傷つけたり出來
ないのだと分った。
「神よ、余は御身に負けた。」
彼はさうさうと流れる谷川の音を、自分がその音の上に流れてゐるやうな氣持で聞いた。
二人の幸福」
拜啓。久しく御無沙汰いたしました。姉さまお變りは御座いませんか。紀伊の方もこの頃は大分寒くなったでせう。こちら
は毎日零下二十度以上も下りますので、家々の窓のガラスは皆スリガラスのやうです。僕は達者ですが、手にはヒビが出來、
足にはアカギレが出來て、歩くにも困難です。そのはずです。朝は毎日五時に起きて飯を炊いて、湯をわかしたり、おツケを
こしらへたりして、朝飯は六時頃になります。朝飯がすむと後かたづけをしますが、皆水です。學校の始まりは九時ですが、
毎日ハ時半までは家の仕事を務めてゐます。中でも一番つらいのは、家の内外から便所までの掃除です。これも勿論水を使ひ
ます。
學校の終へるのは、二時半の時と三時の時とですが、二時半の時は三時までに、三時の時は三時半までに歸らねば、晩飯の
時に叱られます。家に歸れば先ず家の内を掃除し、翌朝焚く薪を細かく割って置きます。或る時なぞは降った雪が風にあふら
れて、一寸先きも見えないやうなことがあります。手はこごえ、足は冷え切って痛みます。また、襟のところからは冷たい雪
が吹き込みます。手のヒビから生新しい血がにじみ出て來るのを見ると、いっしかホロリとします。それがすむと晩飯の支度
に取りかかり、五時頃晩飯をすませて後かたづけをし、其の後は三朗の寢るまで子守をしなければなりませんから、勉強をす
る暇は寸時もありません。
また、日曜日は自分のシャツ、ズボンなぞの洗濯をし、時には父母の足袋、手袋まで冷たい水で洗ひ、暇があればまた三郎
の子守をしなければなりません。このやうに毎日毎日っとめますが、日々の學用品を買ふお金は、二十。へん位叱られてやっと
貰ふ程で、色々と足りない物もありますので、先生にも叱られ、この頃では大分成績が下り、體も衰弱したやうな氣がします。
この正月なんかも.、毎日一日中家の仕事ばかりしてゐました。親達は好きな物を澤山食べますが、僕には正月三日の間に蜜
柑をたったの一つくれたきりですから、平常は言ふまでもないことであります。正月二日のことでした。御飯をこげつかせた
ばかりに、火ばしのまがる程頭を毆られました。そのお蔭で今でも時々頭がひどく痛みます。
思ひ出せば六つの時、御ぢい御ばあの膝もとから何も知らずに、鬼のやうな父に連れられて來た寒い満州に苦しい月日を十
箇年、僕はどうしてこんなに不幸な子供なのでせう。毎日毎日けだものでも毆るやうに棒で毆られ、煙管で毆られては居りま
すが、さほど惡いことをしたとは思へないのです。
皆お母さんの出まかせの告げ口なのです。だが僕ももう一箇月程で學校を卒業しますから、この恐ろしい家を後にして、大
阪へ行って、晝は會社の給仕なりとして、晩は夜學で勉強を一心不亂にしようと思ってゐます。
カアチン(勝子姉樣)もたっしゃで暮して下さい。熊野のおぢいおばあにもよろしくお傳へ下さい。さやうなら。
彼がこの手紙を勝子から無理に奪ひ取って讀んでゐる間、彼女はじつと坐ってゐた。
「男の子にもこんなことをさせてゐるのか。」
「まさか男にはこんなことはさせまいと思ってゐたんですけど……。」
「男にもこんなことをさせるのか。」と、彼は同じことを繰り返した。その言葉の中に總ての同情を押しこんでしまった。
「君も満州ではこんな風に暮してゐたのか。」
「私はもっとひどかったんです。」
©
彼は勝子が十三の時にたった一人で満州から紀州へ歸って來た気持が初めて分った。これまでは唯、この少女の大膽に驚い
てゐたのだった。
「それで君はどうしてやるつもりだ。」
「弟を學校へ入れてやります。私はどんなになっても、弟を學校へ入れてやります。」
「それぢや直ぐ旅費を送って呼び寄せたらいい。」
「今は駄目です。汽車に乘れても途中の停車場でつかまります。聯絡船に乘る時にはきっとつかまります。弟がこの春高等小
学校を出たら、お父さんは弟を賣るつもりなんです。私も毎日、賣ってしまふぞ、賣ってしまふぞと、おどかされてゐたんで
す。弟が賣られたところへお金を送って買ひ戻さうと思ってゐます。」
「それこそ尚駄目だ。満州なんかで賣られたら、どこへやられてどんなことになるか分るものか。」
「でも仕方がありません。途中でつかまって連れ戻されたりしたら殺されてしまふかも知れませんもの。」
そして勝子はうつむいてしまった。
勝子は病氣の彼に一年附添って世話をしてゐる娘だった。彼には勝子に別れられない氣持が出來てゐた。しかし、妻のある
彼が今以上に勝子を愛することは、彼女を不幸に陥れることであるのが、世の習はしであるけれども、彼女を不幸にしても仕
方がないとまで彼は決心してゐた。そこへ弟の手紙である。弟の手紙は彼の類を冷たくした。彼女の弟よりももっと不幸な幼
い日々の生活から遠い土地へ死物狂ひで逃れて來た勝子に、また不幸な未來を迎へさせることは出來ないではないか。そこで
彼の感情は立ち止まった。しかし彼は病み上りであった。
さうだ。自分が満州へ行って、繼母の手から弟を奪ひ取って來てやらう。そして學校へ通はせてやらう。
彼は嬉しかった。弟の世話をしてやってゐれば、勝子とも生活が觸れて行くことが出來る。それに自分の力で一人の少年を
幸福にしてやることが實に明らかなのだ。一生の間に一人の人間でも幸福にすることが出來れば自分の幸福なのだ。
1
「合掌」
波の音が高くなった。彼は窓掛を上げた。やっぱり沖に漁火があった。しかし、さっきより遠くに見えた。それに海へ霧が
下りて來るらしかった。
彼は寢臺を振り返って、ぎよっと胸を冷やした。一枚の眞白な布が平らに擴がってゐるだけなのだ。
花嫁のからだは、その下の柔かい蒲團に沈み込んでしまってゐるのか、寢床に少しも膨らみがないのだ。頭だけが廣い枕に
乘って盛り上ってゐた。
その寢姿をじっと眺めてゐると、なんとはなしに靜かな涙が出た。
白い寢床が、月の光の中に落ちた一枚の白紙のやうに感じられた。すると、窓掛を開いた窓が急に恐ろしくなった。彼は窓
掛を下ろした。そして寢臺に歩み寄った。
枕の上の飾りに肘を突いて、暫く花嫁の顔を覗き込んでゐたが、寢臺の脚を掌の間にするすると迂らせながら膝を突いた。
鐵の圓い脚に額を押しあてた。金屬の冷たさが頭に沁み通った。
靜かに合掌した。
「いやでございますわ。いやでございますわ。まるで死んだ人にするやうなことをなすって。」
彼はすっくと立ち上って顔を紅らめた。
「起きてゐるんですか。」
「ちっとも眠って居りませんわ。夢ばかり見て居りましたわ。」
胸を弓のやうに張って、花嫁が彼を見る拍子に、眞白い布が温かく膨らんで動いた。彼は布を輕く叩いた。
「海に霧が降ってゐますよ。」
「さっきの舟はもうみんな歸ったんでございませう。」
「それがまだ沖にゐるんですよ。」
「霧が降ってるんぢゃございませんの。」
「淺い霧だから大丈夫なんでせう。さあ、お休みなさい。」
彼は白い布の上に片手を投げて、脣を持って行った。
「いやでございますわ。起きてゐるとこんなことをなさいますし、眠って居りますと死んだ人のやうになさいますわ。」
合掌は彼の幼い頃からの習慣だった。
兩親に早く死に別れた彼は、祖父と二人きりで山の町に住んでゐたが、その祖父が盲目だった。祖父は幼い孫をよく佛壇の
前へ連れて行った。そして、孫の小さい手を探りあてて合掌させ、その上に自分の手をあてて二重に合掌した。何と冷たい手
だらうと、孫は思った。
©
孫はかたくなに育って行った。無理を言って祖父を泣かせた。その度に祖父は山寺の和尚を呼んで來た。和尚が來ると孫は
いつもぴたりと靜まった。それが何故だか祖父は知らないのだが、和尚は孫の前へ端坐して瞑目しながら嚴かに合掌して見せ
るのだ。この合掌を見ると、孫はからだに寒氣を感じた。そして、和尚が歸って行くと、彼は祖父に向って静かに合掌するの
だった。盲目の祖父にはそれが見えなかった。白い眼が空しく開いてゐた。しかし孫はその時、心が洗はれるのを感じた。
こんな風にして、彼は合掌の力を信じるやうになった。それと同時に、肉親のない彼は多くの人々の世話になり、多くの人
に罪を犯して育った。しかし、彼の性質に出來ないことが二つあった。面と向ってお禮を言ふことと、面と向って許しを乞ふ
ことだった。だから彼は、他人の家で自分の床に行く時間を待ち兼ねて、毎夜のやうに合掌した。それで自分の言葉に出さな
い氣持が誰にも通じると信じた。
靑桐の葉蔭に石榴の花が燈火のやうに咲いてゐた。
やがて、鳩が松林から書齋の軒に歸って來た。
またやがて、月光の足が梅雨晴れの夜風に搖れてゐた。
畫から夜まで、彼は窓にじっと坐りつづけてゐた。そして合掌してゐた。簡單な置手紙をして、昔の戀人のところへ逃げて
行った妻を呼び返さうと祈ってゐるのだった。
耳がだんだん澄んで來た。十町も離れた停車場で吹く助役の笛が聞えるやうになった。無數の人間の足音が遠くの雨のやう
「起きてゐるんですか。」
「ちっとも眠って居りませんわ。夢ばかり見て居りましたわ。」
胸を弓のやうに張って、花嫁が彼を見る拍子に、眞白い布が温かく膨らんで動いた。彼は布を輕く叩いた。
「海に霧が降ってゐますよ。」
「さっきの舟はもうみんな歸ったんでございませう。」
「それがまだ沖にゐるんですよ。」
「霧が降ってるんぢゃございませんの。」
「淺い霧だから大丈夫なんでせう。さあ、お休みなさい。」
彼は白い布の上に片手を投げて、脣を持って行った。
「いやでございますわ。起きてゐるとこんなことをなさいますし、眠って居りますと死んだ人のやうになさいますわ。」
合掌は彼の幼い頃からの習慣だった。
兩親に早く死に別れた彼は、祖父と二人きりで山の町に住んでゐたが、その祖父が盲目だった。祖父は幼い孫をよく佛壇の
前へ連れて行った。そして、孫の小さい手を探りあてて合掌させ、その上に自分の手をあてて二重に合掌した。何と冷たい手
だらうと、孫は思った。
「いいえ。」
「お前がもう一度家へ歸って來ようと思ったのは、ハ時半頃だらう。それだってちゃんと分ったんだよ。」
「もう澤山よ。——私は死んぢゃってるんですわね。思ひ出しますわ。お嫁に來た晚にはね、あなたが私を死んだ人にす
るやうに手を合はせて拜んでいらっしゃいましたわね。あの時に私は死んぢやったんですわね。」
「あの時?」
「もうどこへも行きませんわ。ごめんなさいね。」
しかし、彼はこの時、自分の力をためすために、世の中のあらゆる女と夫婦の交はりを結んで彼女等を合掌したい欲望を感
じた。
「屋上の金魚」
千代子の寢臺には、枕のところに大きい飾鏡がついてゐた。
彼女は毎晩髪を解いて白い枕に頰を埋めると、その鏡を靜かに眺めるのだった。すると、水甕に沈めた赤い造化のやう
に、獅子頭の金魚の姿が三四十鏡の中へ浮んで來るのだった。金魚と一緒に月が寫る夜もあった。
しかし、月が窓越しにその鏡を照らすのではなかった。屋上庭園の水槽に落ちる月影が、千代子に見えるのだった。鏡は幻
の銀幕であった。だから彼女の精神は鋭い視覺のために、蓄音機の針のやうに摩り減らされて行った。だから彼女はこの寢臺
を離れることが出來ず、この寢臺の上で陰氣臭くふけて行った。白い枕の上に解き擴げた黑髪だけが、いつまでも豊かな若々
しさを殘してゐた。
ある夜、鏡の縁のマホガニイを薄羽かげらふが微かに這ひ登って行った。彼女は飛び起きて、父の寢室の扉を激しく叩いた。
「おとうさん、おとうさん、おとうさん。ー
靑褪めた拳で父の袂を引っぱりながら、屋上庭園へ駆け上った。
獅子頭が一つ、奇怪なものを妊娠した腹を水槽に浮べて死んでゐた。
「おとうさん、ごめんなさいましね。許して下さる?え、許して下さらないの?私夜も寢ないで番をしてゐるんですけれど
父は默って、死人の寢棺のやうに並んだ六つの水槽を見て廻った。
父が屋上庭園に水槽を造って蘭蟲を飼ひ始めたのは、北京から歸ってからだ。
彼は長年北京で妾と住んでゐた。千代子はその妾の子だった。
日本へ歸ったのは、千代子が十六の時だった。冬だった。古びた日本間に、北京から來た椅子やテエブルが置き亂されてゐ
た。腹違ひの姉が椅子に腰を掛けてゐた。千代子はその前の疊に坐って、姉を見上げてゐた。
「私はもう直ぐよその家の人になるからいいけれど、千代ちゃんはお父さんのほんとの子ぢゃないのよ。この家へ來て、私の
お母さんの世話になる以上、そのことだけは忘れないで頂戴。」
千代子がぎくっとうつむくと、姉は兩足を彼女の肩にかけて、足の甲で彼女の頤を持ち上げながら仰向かせようとした。彼
女は姉の足を抱いて泣いた。抱いた拍子に、姉の足が彼女の懐に迂り込んだ。
「ああ、暖かいわ。足袋を脱がせて暖めて頂戴。」
彼女は泣きながら懐の中で姉の足袋のこはぜを外して、冷たい足を乳房の上に抱きしめた。
間もなく日本家屋が西洋館に改築された。父はその屋上庭園に水槽を六つ並べて金魚を飼ひ、朝から晩まで屋上に上りつき
りだった。全國から金魚の専門家を招いたり、百里もーー百里も遠方の大會へ金魚を持って旅行したりした。
その金魚の世話を、いつからか千代子がするやうになった。日々に憂鬱になって行きながら、金魚ばかり眺めてゐた。
彼女の母は日本へ歸って別居すると同時に、激しいヒステリイを起した。それが靜まると黑く默ってしまった。輪郭の美し
さは北京にゐた頃と少しも變らなかったが、皮膚の色が急に氣味惡く黑ずんでしまった。
父の家に出入りする靑年で、千代子の戀人になりたいと言ふ靑年が多かった。それらの靑年に彼女は言った。
「みぢんこを取って來て下さい。金魚に食べさせるのです。」
「どこにゐます」
「泥溝を探し廻って下さればいいわ。」
しかし彼女は、夜毎に鏡の中を見つめて陰氣臭くふけて行きながら、二十六になった。
父が死んで、遺言状の封が開かれた。——千代子は自分の子ではないと書いてあった。
彼女は自分の寢室へ泣きに行った。枕のところの鏡を見ると、きゃっと叫んで屋上庭園へ飛び上った。
いつの間にどこから來たのか、彼女の母が水槽の横に黑ずんだ顔で立ってゐた。獅子頭の金魚をロ ーぱいに頰ばってゐた。
大きい尾が舌のやうに口からべろりと下ってゐた。娘を見ても素知らん顔で、金魚をむしゃむしゃ食ってゐた。
「ああ、お父さん。」
と叫びながら、娘は母を打った。母は化粧煉瓦の上にひっくり返って、金魚を銜へたまま死んだ。
これで千代子は、父母の一切から解放された。美しい若さを取戻して、幸福な生涯へと旅立った。
「朝の爪」
貧しい娘が貧しい家の二階を借りて住んでゐた。そして戀人との結婚を待ってゐた。しかし毎晩ちがった男が娘のところへ
通って來た。朝日の指さない家だった。娘は磨り切れた男の下駄を履いて、裏口でよく洗濯をした。
夜、男達は誰もかれもきまって言った。
「何だ。蚊帳もないのか。」
「すみませんわね。私が夜通し起きてゐて蚊を追って差し上げますから、ごめんなさいね。」
娘はおどおどして靑い蚊取線香に火をつけた。電燈を消してから、娘はその線香の小さい火を一つ眺めながら、いつも子供
の頃を思ひ出した。そして、いつまでも男の體を團扇で煽いでゐた。團扇を動かしてゐる夢を見續けてゐた。
もう初秋だ。
珍しく老人が貧しい二階に上って來た。
「蚊帳を吊らないのか。」
「すみませんわね。私が夜通し起きてゐて蚊を追って差し上げますから、ごめんなさいね。」
「さうか。ちよっと待ってゐてくれ。」
さう言って立ち上った老人に、娘が追ひ縄った。
「朝まで蚊を追ってゐますから。私ちっとも寢やしませんから。」
「うん。直ぐ戻って來るんだよ。」
老人は梯子段を下りてしまった。電燈をつけたまま、娘は蚊取線香を焚いた。明るいところに一人では、子供の自分を思ひ
出すことも出來なかった。
一時間程して老人が戻って來た。娘は飛び起きた。
「ほう、感心に吊手だけはあるんだな。」
老人は眞新しい白蚊帳を貧しい部屋に吊ってやった。娘はその中にはいって裾を擴げて歩きながら、爽かな肌觸りに胸を躍
らせた。
「きっと戻って來て下さると思って、電燈を消さずにお待ちしてゐましたわ。明るいままもっと白い蚊帳を眺めてゐたいわ。」
しかし娘は幾月ぶりかの深い眠りに落ちた。朝老人が歸るのも知らなかった。
「おい、おい、おい、おい。」
戀人の聲で眼が覺めた。
「いよいよ明日結婚出來るぞ。——うん。いい蚊帳だな。見ただけでもせいせいする。」
言ふなり彼は蚊帳の吊手を皆外してしまった。そして娘を蚊帳の下から引っぱり出して、蚊帳の上へはふり上げた。
「この蚊帳の上へのっかれ。大きい白蓮華みたいだ。これでこの部屋もお前のやうに淸らかだ。」
娘は新しい麻の肌觸りから、白い花嫁を感じた。
「私足の爪を切るわ®」
部屋一ぱいの白蚊帳の上に坐って、彼女は忘れてゐた足の長い爪を無心に切りはじめた。
「雨傘」
濡れはしないが、なんとはなしに肌の濕る、霧のやうな春雨だった。表に№け出した少女は、少年の傘を見てはじめて、
「あら。雨なのね?」
少年は雨のためよりも、少女が坐ってゐる店先きを通る恥かしさを隱すために、開いた雨傘だった。
しかし、少年は默って少女の體に傘をさしかけてやった。少女は片一方の肩だけを傘に入れた。少年は濡れながらおはいり
と、少女に身を寄せることが出來なかった。少女は自分も片手を傘の柄に持ち添へたいと思ひながら、しかも傘のなかから逃
げ出しさうにばかりしてゐた。
二人は寫眞屋へ入った。少年の父の官吏が遠く轉任する。別れの寫眞だった。
「どうぞお二人でここへお並びになって。」と寫眞屋は長椅子を指したが、少年と少女は並んで坐ることが出來なかった。少
年は少女のうしろに立って、二人の體がどこかで結ばれてゐると思ひたいために、椅子を握った指を輕く少女の羽織に觸れさ
せた。少女の體に觸れた初めだった。その指に傳はるほのかな體温で、少年は少女を裸で抱きしめたやうな温かさを感じた。
一生この寫眞を見る度に、彼女の體温を思ひだすだらう。
「もう一枚いかがでせう。お二人でお並びになったところを、上半身を大きく。」
少年はただうなづいて、
「髪は?」と、少女に小聲で言った。少女はひょいと少年を見上げて頰を染めると、明るい喜びに目を輝かせて、子供のやう
に、素直に、ばたばたと化粧室へ走って行った。
少女は店先きを通る少年を見ると、髪を直す暇もなく飛び出して來たのだった。海水帽を脱いだばかりのやうに亂れた髪が、
少女は絶えず氣になってゐた。しかし、男の前では恥かしくて、後毛を搔き上げる化粧の眞似も出來ない少女だった。少年は
また髪を直せと言ふことは少女を辱めると思ってゐたのだった。
化粧室へ行く少女の明るさは、少年をも明るくした。その明るさの後で、二人はあたりまへのことのやうに、身を寄せて長
椅子に坐った。
寫眞屋を出ようとして、少年は雨傘を捜した。ふと見ると、先きに出た少女がその傘を持って、表に出て立ってゐた。少年
に見られてはじめて、少女は自分が少年の傘を持って出たことに氣がついた。そして少女は驚いた。なにごころないしぐさの
うちに、彼女が彼のものだと感じてゐることを現はしたではないか。
少年は傘を持たうと言へなかった。少女は傘を少年に手渡すことが出來なかった。けれども寫眞屋へ來る道とはちがって、
二人は急に大人になり、夫婦のやうな氣持で歸って行くのだった。傘についてただこれだけのことで——。
够
「死面」
彼が彼女の何人目の戀人であるかは分らなかった。しかしとにかく、最後の戀人であることだけは明らかだった。なぜなら、
彼女にはもう死が近づいてゐたから。
「こんなに早く死ぬのだったら、あの時殺されておけばよかったわ。」と、彼女は彼に抱かれながらも、多くの男達を思ひ出
してゐるかのやうな眼色で、花やかに微笑まうとした•
命の終りが來ても、彼女は彼女の美しさを忘れることが出來ない。數々の戀を忘れることが出來ない。今はもうそれが却っ
て彼女を痛ましく見せるとは知らないで。
「男はみんな私を殺したがってゐたのよ。口に出して言はなくっても、心のうちでは。」
彼女の心をとらへておくには、彼女を殺すより外に術はないと、思ひ惱んだ戀人達にくらべて、彼女自ら彼の腕の中で死ん
でゆかうとしてゐる今の彼は、彼女を失ふ不安がないだけに、或ひは幸福な戀人かもしれないのだが、彼はもう少し彼女を抱
き疲れてゐた。激しい戀を追ひつづけてゐた彼女は、病人になってからも、首や胸に男の腕を感じないと、安らかに眠れない
のだった。
けれども、いよいよいけなくなると、
「足を握って頂戴。足が寂しくてしゃうがないの。」
死が足から忍び寄って來るかのやうに、彼女はしきりと足を寂しがった。彼は寢臺の裾に坐って、彼女の足を固く握ってや
った。それは死のやうに冷たかった。しかし思ひがけなく、彼の掌は怪しく顫へた。掌のなかの小さい足から、彼はなまなま
しい女を感じたのだ。その冷たく小さい足が彼の掌に温かく汗ばんだ女の足の裏に觸れるのと同じゃうな喜びを傳へたのだ。
彼は彼女の死の神聖を流すやうな彼の感覺を恥ぢた。でも、「足を握って頂戴。」と言ふのは、彼女のこの世での最後の愛の
技巧ではなかったらうか。ともすれば、彼は彼女のあさましいばかりの女らしさが恐ろしくなった。
「私達の戀で、あなたにはもう嫉妬といふものの必要がないことを、あなたはもの足りなく思っていらしたわね。でも、私が
死ねば、あなたの嫉妬の相手は現はれて來てよ。きっとどこからか。」と言ひながら、彼女は息を引き取った。
その言葉の通りであった。
お通夜に來た一人の新劇俳優が、彼女の死顔に化粧をした。その男と戀をした頃の彼女の生き生きしい美しさを、もう一度
甦らせるといふ風に。
その後で、一人の美術家が彼女の顔にべったり石膏をかぶせた時には、その男は俳優への嫉妬の餘り、彼女を窒息させて殺
さうとしてゐるかのやうに見えた程、俳優の化粧は彼女の死顔を生かせた。この美術家もまた、彼女の死面をつくって、彼
女の面影を偲ばうとするのであらう。
彼女をめぐる戀の爭ひは、彼女の死と共に終りはしないのだと知ると、彼女を自分の腕のなかで死なせたことも、まことに
はかない勝利に過ぎなかったのだと、彼は美術家のところへ彼女の死面を奪ひに行った。
ところがその死面は、女のやうでもあり、男のやうでもあった。幼い女のやうにも見え、老女のやうにも見えた。彼はふと
胸の火が消えたやうな聲で、
「これは彼女ですが、また彼女ぢゃありません。第一、男だか女だかも分りやしません。」
©
「さうです。」と美術家も沈んだ顔で、
「一般に死面といふものは、これは誰のだと知らずに見ると、性の區別は分らないものです。例へば、ベ エトオヴェンのやう
に魁偉な顔の死面も、じっと見てゐると、女の顔にも見えて來ます。けれども、彼女のやうに女らしい女はなかったのですか
ら、死面も實に女らしからうと思ったのですが、やっぱりこの通り、死には勝てなかったんです。死と共に性の區別も終るん
ですよ。」
「彼女の一生は女であることの喜びの悲劇でした。死の間際まで餘りに女でした。その悲劇から彼女が今はもう全く逃れたの
なら。」と彼は惡夢が消えたやうな淸々しさで、手を差し出しながら、
「僕達も手を握り合っていいわけですね。この男とも女とも分らない死面の前で。」
三島由紀夫
「橋づくし」
元はと問へば分別のあのいたいけな貝殻に一杯もなき覘橋、短かき物はわれわれが此の世の住居秋の日よ。
——『天の網島』名ごりの橋づくし——
陰曆ハ月十五日の夜、十一時半にお座敷が引けると、小弓とかな子は、銀座板甚道の分桂家へかえって、いそいで浴衣に着
かえた。ほんとうは風呂に行きたいのだが、今夜はその時間がない。
小弓は四十一 一歳で、五尺そこそこの小肥りした体に、巻きつけるように、白地の黒の秋草のちぢみの浴衣を着た。かな子は
二十二歳で踊りの筋もいいのに、旦那運がなくて、春秋の恒例の踊りにもいい役がつかない。これは白地に藍の観世水を染め
たちぢみの浴衣を着た。
「満佐子さんは、今夜はどんな柄かしら」
「萩に決ってるよ。早く子供がほしいんだとさ」
「だって、もうそこまで行ってるの?」
「行ってやしないよ。それから先の話なんだよ。岡惚れだけで子供が生れたら、とんだマリヤ様だわ」
©
と小弓が言った。花柳界では一般に、夏は萩、冬は遠山の衣裳を着ると、妊娠するという迷信がある。
いよいよ出ようというときに、又小弓は腹が空いた。毎度のことであるのに、空腹はまるで事故のように、突然天外から降
ってくる心地がする。それまではそんなに空いていない。又便利なことに、お座敷のあいだはどんなに退屈な席でも、腹が空
いて困ったことはない。お座敷の前と後とに限って、それまで腹工合のことなんか忘れているのに、突然発作に襲われたよう
に腹が空くのである。小弓はそれに備えて、程のいい時に、適度に喰べておくということができない。たとえばタ刻髪結へ行
くと、同じ土地の妓が順を待つあいだを、岡半の焼肉丼なんぞを眺えて、旨そうに喰べているのを見ることがある。それ
を見ても小弓は何とも思わない。旨そうだとも思わない。それだというのに、ものの一時間もすると、突如として空腹がはじ
まり、唾液が忽ち小さな丈夫な歯の附根から、温泉のように湧いた。
小弓やかな子は、分桂家へ看板料と食費を毎月納めている。小弓の食費は格別多いのである。それは小弓が大食の上に、口
が奢っているからであったが、考えてみると、お座敷の前後に腹の空く奇癖がはじまってから、食費がだんだんに減り、今で
は、かな子を下廻るようになっている。奇癖がはじまったのは、いつごろからとも知れない。呼ばれた家の台所で、お座敷へ
出る前に、小弓が足許に火がついたように、「ちょいと何か喰べるものないこと」と要求するようになったのは、いつごろか
らとも知れない。今日では、はじめに呼ばれた家の台所で夕食を喰べ、最後に呼ばれた家の台所で、お座敷の引けたあと、夜
食を喰べるのが習慣になった•そこで、腹もこの習慣に調子を合せ、分桂家へ納める食費も減るようになったのである。
すでに寝静まった銀座を、小弓とかな子が浴衣がけで新橋の米井へ歩いてゆくとき、かな子は窓々に鎧扉を下ろした銀行の
はずれの空を指して、
「晴れてよかったね。本当に兎のいそうな月よ」
と言ったが、小弓は自分の腹工合のことばかり考えていた。今夜のお座敷は、最初が米井である。最後が文迺家である。文
迺家で夜食をして来ればよかったが、時間がないのでまっすぐ着換えにかえって、又行先が米井では、夕食をした台所で、ー
晩のうちに又夜食を催促しなければならない。それを考えると大そう気が重い。
……が、米井の勝手口を入ったとき、小弓の煩悶は忽ち治った。すでに予想通り萩のちりめん浴衣を着て、厨口に立って
待っていた米井の箱入り娘満佐子が、小弓の姿を見るなり、
「まあ早かったわね。まだ急ぐことないわ。上ってお夜食でも喰べていらっしゃいよ。」
と気を利かせて言ったからである。
広い台所はまだ後片付で混雑している。明りの下に、夥しい皿小鉢がまばゆく光っている。満佐子は厨□の柱に片手を支
えているので、その体は灯を遮り、その顔は暗い。言われた小弓の顔にも灯影は届かず、小弓は安心した咄嗟の顔つきを見ら
れなかったのを喜んだ。
小弓が夜食を喰べているあいだ'満佐子はかな子を自分の部屋へ伴なった。家へ数多く来る芸者の中でも満佐子はかな子と
一等気が合った。同い年だということもある。小学校が一緒だということもある。どちらも器量が頃合だということもある。
そういう諸々の理由を越えて、何だか虫が好くのである。
かな子はそれに大人しくて、風にも耐えぬように見えるが積むべき経験を積んでいるので、何の気なしに言う一言が満佐子
の助けになることもあって頼もしい。それに比べて勝気な満佐子は、色事については臆病で子供っぽい。満佐子の子供っぽさ
は評判のたねで、母親もタカを括っていて、娘が萩の浴衣なんぞを謎えても気にもとめないのである。
満佐子は早大芸術科に通っている。前から好きだった映画俳優のRが、一度米井へ来てからは熱を上げて、部屋にはその写
真を一杯飾っている。そのときRとお座敷で一緒に撮った写真を、ボ1ン•チャイナの白地の花瓶に焼付けさせたのが、花を
盛って、机の上に飾ってある。
「きょう役の発表があったのよ」
と坐るなり、かな子は貧しい口もとを歪ませて言った。
「そう?」満佐子は気の毒に思って知らぬ振りをした。
「又唐子の一役きりだわ。いつもでたってもワンサで悲観しちまう。レビュ—だったら、万年ライダンスなのね、私って」
「来年はきっといい役がつくわよ」
「そのうち年をとって小弓さんみたいになるのが落ちだわ」
「ばかね。まだ二十年も先の話じゃないの」
こういう会話を交わしながら、今夜の願事はお互いに言ってはならないのであるが、満佐子もかな子も、相手の願事が何で
あるかがもう分っている。満佐子はRと一緒になりたいし、かな子は好い旦那が欲しいのである。そしてこの二人にはよくわ
かつているが、小弓はお金が欲しいのである。
この三人の願いは、傍から見ても、それぞれ筋が通っている。公明正大な望みというべきである。月が望みを叶えてくれな
かったら、それは月のほうがまちがっている。三人の願いは簡明で、正直に顔に出ていて、実に人間らしい願望だから、月下
の道を歩く三人を見れば、月はいやでもそれを見抜いて、叶えてやろうという気になるにちがいない。
満佐子がこう言った。
「今夜はもう一人ふえたのよ」
「まあ、誰」
「ート月ほど前に東北から来た家の女中。みなっていうのよ。私、要らないつていうのに、お母様がどうしてもお供を一人っ
けなければ心配だっていうんですもの」
「どんな子」
「まあ見てごらんなさい。そりゃあ発育がいいんだから」
そのとき葭障子をあけて、当のみなが立ったまま顔を出した。
「障子をあけるときは、坐ってあけなさいって言ったでしょう」
と満佐子が権高な声を出した。
「はい」
答は胴間声で、こちらの感情がまるっきり反映していないような声である。姿を見ると、かな子は思わず笑いを抑えた。妙
なありあわせの浴衣地で捋えたワンピースを着て、引っかきまわしたようなパーマネントの髪をして、袖口からあらわれたそ
の腕の太さと云ったらない。顔も真黒なら、腕も真黒である。その顔は思いきり厚手に仕立てられていて、ふくらみ返った頰
の肉に押しひしがれて、目はまるで糸のようである。口をどんな形にふさいでみても、乱杭歯のどの一本かがはみ出してしま
う。この顔から何かの感情を掘り当てることはむつかしい。
「一寸大した用心棒だわね」
とかな子は満佐子の耳もとで言った。
満佐子は力めて厳粛な表情を作っていた。
「いいこと?さつきもいったけど、もう一度言うわよ。家を出てから、七つの橋を渡りきるまで、絶対に口をきいちゃだめよ。
願い事がだめになってしまうんだから。……それから知ってる人から話しかけられてもだめなんだけれど、これはあんたは心
配が要らないわね。
それから同じ道を二度歩いちゃいけないんだけど、これは、小弓さんが先達だから、あとについて
行けばまちがいないわ」
満佐子は大学では、ブルウストの小説についてレポ—トを出したりしているのに、こういうことになると、学校でうけた近
代教育などは、見事にどこかへ吹き飛んでしまった。「はい」とみなは答えたが、本当にわかっているのかいないのか不明で
ある。
「どうせあんたもついて来るんだから、何か願い事をしなさいよ。何か考えといた?」
「はい」
とみなはもそもそした笑い方をした。
「あら、いっぱしだわね」
と横からかな子が言った。
するとそこへ 博多帯を平手で叩きながら、
「さあ、これで安心して出かけられるわ」
と小弓が顔を出した。
「小弓さん、いい橋を選っといてくれた?」
「三吉橋からはじめるのよ。あそこなら、一度にーーつ渡れる勘定でしょう。それだけ楽じゃないの。どう?この頭のいいこと」
これから口を利けなくなるので、三人は一せいに姦しく喋り留めをした。喋り留めは厨口までそのままつづいた。厨口
の三和土に満佐子の下駄が揃えてある。伊勢由の黒塗りの下駄である。そこへさし出した満佐子の足の爪先が紅くマニキュア
されていて、暗がりの中でもほのかな光沢を放って映えるのに、小弓ははじめて気づいた。
「まあ、お嬢さん、粋ねえ。黒塗りの下駄に爪紅なんて、お月さまでもほだされる」
「爪紅だって!小弓さんって時代ねえ」
「知ってるわよ。マネキンとか云うんでしょう、それ」
満佐子とかな子は顔を見合せて吹き出した。
小弓が先達になって' 都合四人は月下の昭和通りへ出た。自動車屋の駐車場に、今日一日の用が済んだ多くのハイヤーが、
黒塗りの車体に月光を流している。それらの車体の下から虫の音がきこえている。
昭和通りにはまだ車の往来が多い。しかし街がもう寝静まったので、オート三輪のけたたましい響きなどが、街の騒音とま
じらない、遊離した、孤独な躁音というふうにきこえる。
月の下には雲が幾片か浮んでおり、それが地平を包む雲の堆積に接している。月はあきらかである。車のゆききがしばらく
亟
途絶えると、四人の下駄の音が、月の硬い青ずんだ空のおもてへ、じかに弾けて響くように思われる。
小弓は先に立って歩きながら、自分の前には人通りのない歩道だけのあることに満足している。誰にも頼らずに生きてきた
ことが小弓の矜りなのである。そしてお腹のいっぱいなことにも満足している。こうして歩いていると' 何をその上、お金を
欲しがったりしているのかわからない。小弓は自分の願望が、目の前の舗道の月かげの中へ柔らかく無意味に融け入ってしま
うような気持がしている。硝子のかけらが、舗道の石のあいだに光っている。月の中では硝子だってこんなに光るので、日頃
の願望も、この硝子のようなものではないかと思われて来る。
小弓の引いている影を踏んで、満佐子とかな子は、小指をからみ合わせて歩いている。夜気は涼しく、ハツロから入る微風
が、出しなの昂奮で汗ばんだ乳房を、しずかに冷やして引締めているのを、二人ながら感じている。お互いの小指から、お互
いの願望が伝わってくる。無言なので、一そう鮮明に伝わってくるのである。
満佐子はRの甘い声や切れ長の目や長い揉上げを心に描いている。そこらのファンとちがって、新橋の一流の料亭の娘がこ
うと思い込んだことが、叶えられないわけはないと思う。Rがものを言ったとき、自分の耳にかかったその息が、少しも酒く
さくはなくて、香わしかったのを憶えている。夏草のいきれのように、若い旺んな息だったと憶えている。一人でいるときに
それを思い出すと、膝から腿へかけて、肌を 漣が渡るような気がする。今もこの世界のどこかにRの体の存在しているとい
うことが、自分の再現する記憶と同じほど確実でもあり、不確かでもあって、その不安が心をしじゅう苛んだ。
かな子は、肥った金持ちの中年か初老の男を夢みている。肥っていないと金持ちのような気がしない。その男の庇護がひた
すら惜しげなく注がれてくるのを、ただ目をつぶって浴びていればよいのだと思う。かな子は目をつぶることには馴れている。
ただ今までは、さて目をあいてみると、当の相手がもういなくなっていたのである。
……二人は申し合わせたように、うしろを振向いた。みなが黙ってついて来ていた。頰に両手をあてて、ワンピースの裾
を蹴立てて、赤い鼻緒の下駄をだらしなく転がすようにしてついて来る。その目はあらぬ方を見ていて、一向真剣味がない。
満佐子もかな子も、みなのその姿を、自分たちの願望に対する侮辱のように感じた。
四人は東銀座の一丁目と二丁目の堺のところで、昭和通りを右に曲った。ビル街に、街灯のあかりだけが、規則正しく水
を撒いたように降っている。月光はその細い通りでは、ビルの影に覆われている。
程なく四人の渡るべき最初の橋、三吉橋がゆくてに高まって見えた。それは三叉の川筋に架せられた珍しい三叉の橋で、向
う岸の角には中央区役所の陰気なビルがうずくまり、時計台の時計の文字板がしらじらと冴えて、とんちんかんな時刻をさし
示している。橋の欄干は低く、その三叉の中央の三角形を形づくる三つの角に、おのおの古雅な鈴蘭灯が立っている。鈴蘭灯
のひとつひとつが、四つの灯火を吊しているのに、その凡てが灯っているわけではない。月に照らされて灯っていない灯の丸
い磨硝子の覆いが、まつ白に見える。そして灯のまわりには、あまたの羽虫が音もなく群がっている。
川水は月のために擾されている。
先達の小弓に従って、一同はまずこちら岸の橋の袂で、手をあわせて祈願をこめた。
近くの小ビルの一つの窓の煙った灯が消えて、一人きりの残業を終って帰るらしい男が、ビルを出しなに、鍵をかけようと
して、この奇異な光景を見て立ちすくんだ。
女たちはそろそろと橋を渡りだした。下駄を鳴らして歩く同じ舗道のつづきであるのに、いざ第一の橋を渡るとなると、足
取は俄かに重々しく、檜の置舞台の上を歩くような心地になる。三叉の橋の中央へ来るまではわずかな間である。わずかな
画
間であるのに、そこまで歩いただけで、何か大事を仕遂げたような、ほっとした気持になった。
小弓は鈴蘭灯の下で、ふりむいて、又手をあわせ、三人がこれに習った。
小弓の計算では、三叉のニ辺を渡ることで、橋を二つ渡ったことになるが、渡るあとさきに祈念を凝らすので、三吉橋で四
度手をあわさねばならない。
たまたま通りすぎたタクシーの窓に、びっくりした人の顔が貼りついて、こちらを見ているのに満佐子は気づいたが、小弓
はそんなことに頓着していなかった。
区役所の前まで来て、区役所へお尻をむけて、四度目に手を合わせたとき、かな子も満佐子も、第一と第二の橋を無事に渡
ったという安堵と一緒に、今までさほどに思っていなかった願事が、この世でかけがえのないほど大切なものに思われだした。
満佐子はRと添えなければ死んでしまえというほどの気持になっている。橋を二つ渡っただけで、願望の強さが数倍になっ
たのである。かな子はいい旦那がつかなければ生きていても仕様がないと思う迄になっている。手を合わすときに、胸は迫っ
て、満佐子は忽ち目頭が熱くなった。
ふと横を見る。みなが殊勝に、目をとじて手を合わせている。私と比べて、どうせろくな望みを抱いていないと思うと、みな
の心の裡の何もない無感覚な空洞が、軽蔑に値するようにも、又羨ましいようにも思われた。
川ぞいに南下して、四人は築地から桜橋へゆく都電の通りへ出た。もちろん終電はとうの昔に去って、昼のあいだはまだ初
秋の日光に灼ける線路が、白く涼しげな二条を伸ばしていた。
ここへ出る前から、かな子は妙に下腹が痛んできた。何が中ったのか、食中りに相違ない。はじめは絞るような痛みが少し
兆して、二、三歩ゆくうちに忘れてしまったのが、今度は忘れているという安心がしじゅう意識にのぼり、この意識の無理に
亀裂が入って、忘れていると思うそばから又痛みが兆してくるのである。
第三の橋は築地橋である。ここへ来て気づいたのだが、都心の殺風景なこういう橋にも、袂には忠実に柳が植えてある。ふ
だん車で通っていては気のつかないこうした孤独な柳が、コンクリートのあいだのわずかな地面から生い立って、忠実に川風
をうけてその葉を揺らしている。深夜になると、まわりの騒がしい建物が死んで、柳だけが生きていた。
築地橋を渡るにつけて、小弓がまず柳の下かげで、桜橋の方向へ手を合わせた。先達という役目に気負っているのか、小弓
はいつになく、その小肥りの背筋をまっすぐに立てている。事実小弓は、自分の願事をいっしか没却して、大過なく七つの橋
を渡ることのほうが、目前の大事のように思っているのである。どうしても渡らなければならぬと思うと、そのこと自体が自
分の願事であるかのような気がしてきた。それはずいぶん変な心境であるけれど、あの突然襲ってくる空腹同様、自分はいつ
でもこのようにして人生を渡ってきたという思いが、月下をゆくうちにふしぎな確信に凝り固まり、その背筋はますます正し
く、顔は正面を切って歩いている。
築地橋は風情のない橋である。橋詰の四本の石柱も風情のない形をしている。しかしここを渡るとき、はじめて汐の匂いに
似たものが嗅がれ、汐風に似た風が吹き、南の川下に見える生命保険会社の赤いネオンも、おいおい近づく海の予告の標識の
ように眺められた。
これを渡って、手を合わせたとき、かな子は、痛みがいよいよ切迫して、腹を突き上げてくるのを感じた。電車通りを渡っ
て、S興行の古い黄いろのビルと川との間の道をゆくとき、かな子の足はだんだんと遅くなり、満佐子も気づかって歩みを緩
めるが、生憎口をきいて安否をたずねることができない。かな子が両手で下腹を押え、眉をしかめて見せたので、満佐子にも
ようやく納得が行った。
しかし一種の陶酔状態にいる先達の小弓は、何も気づかずに昂然と同じ歩度でゆくので、あとの三人との距離はひろがった。
いい旦那がすぐ目の前にいて、手をのばせばつかまろうというときに、その手がどうしても届きそうにない心地がかな子は
している。かな子の顔色は事実血の気を失って、額から油汗が滲み出ている。人の心はよくしたもので、下腹の痛みが募るに
つれ、かな子は先程まであれほど熱心に願い、それに従って現実性も色増すように思われたあの願事が、何だか不意に現実性
を喪って、いかにもはじめから非現実的な、夢のような、子供じみた願望であった気がしてきた。そして難儀な歩みを運び、
待ったなしで迫ってくる痛みに抗していると、そんな他愛もない望みを捨てさえすれば、痛みはたちどころに治るような気が
した。
いよいよ四番目の橋が目の前まで来たとき、かな子は満佐子の肩にちよっと手をかけ、その手の指で踊りのフリのように自
分の腹をさして、後ろ毛が汗で頰に貼りついた顔をもうだめだというこなしで振り、忽ち身をひるがえして、電車通りのほ
うへ駆け戻った。
満佐子はその後を追おうとしたが、道を戻っては自分の願が徒になるのを思って、下駄の爪先で踏み止まって、ただ振向い
た。
四番目の橋畔では、はじめて気づいた小弓も振向いていた。
月かげの下を、観世水を藍に流した白地の浴衣の女が、恥も外聞もない格好で馳け出してゆき、その下駄の音があたりのビ
ルに反響して散らばると思うと、一台のタクシーが折りよく角のところにひっそりと停るのが眺められた。
第四の橋は入船橋である。それを、さつき築地橋を渡ったのと逆の方向へ渡るのである。
橋詰に三人が集まる。同じように拝む。満佐子はかな子を気の毒にも思うが、その気の毒さが、ふだんのように素直に流れ
出ない。落伍した者は、これから先自分とはちがう道を辿るしかほかはないという、冷酷な感懐が浮ぶだけである。願い事は
自分一人の問題であって、こんな場合になっても、人の分まで背負うわけには行かない。山登りの重い荷物を扶けるのとはち
がい、そもそも人を扶けようのないことをしているのである。
入船橋の名は、橋詰の低い石柱の、綠か黒か夜目にわからぬ横長の鉄板に白字で読まれた。橋が明るく浮き上がってみえる
のは、向う岸のカルテックスのガソリン•スタンドが、抑揚のない明るい灯火をひろいコンクリートいっぱいにぶちまけてい
る反映のためであるらしい。
川の中には、橋の影の及ぶところに小さな灯も見える。桟橋の上に古い錯雑した小屋を建て、植木鉢を置き、
あ
つ
な
屋
み
り
わ
形
船
船
船
船
という看板を揚げて住む人が、まだ起きている灯火であるらしい。
ここあたりから、ビルのひしめきは徐々に低くなって、夜空がひろがるのが感じられる。気がつくと、あれほどあきらか
だった月が雲に隠れて、半透明になっている。総体に雲の嵩が増している。
三人は無事に入船橋を渡った。
川は入船橋の先でほとんど直角に右折している。第五の橋までは大分道のりがある。広いがらんとした川ぞいの道を、暁橋
まで歩かなければならない。
右側は多く料亭である。左側は川端に、何か工事用の石だの、砂利だの、砂だのが、そこかしこに積んであって、その暗い
堆積が、ところによっては道の半ばまでも侵している。やがて左方に、川むこうの聖路加病院の壮大な建築が見えてくる。
それは半透明の月かげに照らされて、鬱然と見えた。頂きの巨きな金の十字架があかあかと照らし出され、これに侍するよ
点々と屋上と空とを劃して明滅しているのである。病院の背後の会堂は、灯を消しているが、ゴ
うに、航空標識の赤い灯が、
シック風の薔薇窓の輪郭が、高く明瞭に見える。病院の窓々は、あちこちにまだ暗い灯火をかかげている。
"らまど
三人は黙って歩いている。
体が汗ばむほどに早くなった。はじめは気のせいかと思われたが、まだ月の4^如がわかる空が怪しくなって、満佐子のこめか
みに、最初の雨滴が感じられたからである。が、幸いにして、雨はそれ以上激しくなる気配はない。
第五の暁橋の、毒々しいほど白い柱がゆくてに見えた。奇抜な形にコンクリートで築いた柱に、白い塗料が塗ってあるので
ある。その袂で手を合わせるときに、満佐子は橋の上だけ裸かになって渡してある鉄管の、道から露わに抜き出た個所にっ
まづいて危くころびそうになった。橋を渡れば、聖路加病院の車廻しの前である。
その橋は長くない。あまつさえ三人とも足が早くなっている。すぐ渡り切ってしまうところを、小弓の身に不運が起った。
というのは、むこうから、だらしなく浴衣の衿をはだけて、金盥ををかかえた洗い髪の女が、いそぎ足で三人の前に来た
一心に、気が急いて歩いているあいだは、満佐子もあまり物を思わない。三人の足取はそのうち、
のである。ちらと見た満佐子は、洗い髪の顔がいやに白々と見えたのでぞっとした。
「ちょいと小弓さん、小弓さんじゃないの。まあしばらくね。知らん顔はひどいでしょう。ねえ、小弓さん」
橋の上で立ちどまった女は、異様なふうに首を横へ のばしてから、小弓の前に立ちふさがった。小弓は目を伏せて答えない。
女の声は甲高いのに、風が隙間から抜けてゆくように、力の支点の定まらない声である。そして呼びかけが、同じ抑揚のま
まつづき、小弓を呼んでいるにもかかわらず、そこにはいない人を呼ぶかのようである。
「小田原町のお風呂屋のかえりなのよ。それにしてもひさしぶりねえ。めずらしいところで会ったわね、小弓さん」
小弓は肩に手をかけられて、ようやく目をあげた。そのとき小弓の感じたことがある。いくら返事を渋っていても、一度知
り人から話しかけられたら、願はすでに破れたのである。
満佐子は女の顔を見て、一瞬のうちに考えて、小弓を置いてどんどん先へ立った。女の顔には満佐子にも見おぼえがある。
戦後わずかのあいだ新橋に出ていて頭がおかしくなって妓籍を退いた確か小えんと云った老妓である。お座敷に出ている時分
から、異様な若造りで気味わるがられたが、その後このあたりの遠縁の家で養生をしていて、大分よくなったという話をきい
たことがある。
小えんが親しかった小弓をおぼえていたのは当然だが、満佐子の顔を忘れていたことは僥倖である。
第六の橋はすぐ前にある。綠に塗った鉄板を張っただけの小さな堺橋である。満佐子は橋詰でする礼式もそこそこに、ほ
とんど驗けるようにして、堺橋を渡ってほっとした。そして気がつくと、もう小弓の姿は見えず、自分のすぐうしろに、みな
のむっつりした顔が附き従っていた。
先達がいなくなった今では、第七の、最後の橋を満佐子は知らない。しかしこの道をまっすぐ行けば、いずれ暁橋に平行し
た橋のあることがわかっている。それを渡っていよいよ願が叶うのである。
まばらな雨滴が、再び満佐子の頰を搏った。道は小田原町の外れの問屋の倉庫が並んでいるところで、工事場のバラックが
川の眺めを遮っている。大そう暗い。遠い街灯のあかりが鮮明に望まれるので、そこまでの闇が一そう深く思われる。
いざとなると勝気な満佐子は、深夜の道をこうして行くことが、願掛けという目的もあって、それほど怖ろしいわけではな
い。しかし自分のうしろに接してくるみなの下駄の音が、行くにつれて、心に重くかぶさって来るのである。その音は気楽に
乱れてきこえるが、満佐子の小刻みな足取に比べて、いかにも悠揚せまらぬ足音が、嘲けるように自分をつけてくるという心
地がする。
かな子が落伍した頃まで、みなの存在は、満佐子の心にほとんど軽侮に似たものを呼び起すだけだったが、それから何かし
ら気がかりになって、二人きりになった今では、この山出しの少女が一体どんな願い事を心に蔵しているのか、気にしまいと
思っても気にせずにはいられない。何か見当のつかない願事を抱いた岩乗な女が、自分のうしろに迫って来るのは、満佐子
には気持ちが悪い。気持が悪いというよりも、その不安はだんだん強くなって、恐怖に近くなるまで高じた。
満佐子は他人の願望というものが、これほど気持のわるいものだとは知らなかった。いわば黒い塊りがうしろをついて来る
かのようで、かな子や小弓の内に見透かされたあの透明な願望とはちがっている。
……こう思うと、満佐子は必死になって、自分の願事を搔き立てたり、大切に守ったりする気になった。Rの顔を思う。声
を思う。若々しい息を思う。しかし忽ちイメージは四散して、以前のように纏った像を結ぼうとしない。
少しも早く第七の橋を渡ってしまわなければならない。それまで何も思わないで急がなければならない。
するうちに、遠くに見える見える街灯は橋詰の灯らしく思われ、広い道にまじわるところが見えて、橋の近づく気配がした。
橋詰の小公園の砂場を、点々と黒く雨滴の穿っているのを、さきほどから遠く望んでいた街灯のあかりが直下に照らしてい
る。果して橋である。
三味線の箱みたいな形のコンクリートの柱に、備前橋と誌され、その柱の頂きに乏しい灯がついている。見ると、川向うの
左側は築地本願寺で、青い円屋根が夜空に聳えている。同じ道を戻らぬためには、この最後の橋を渡ってから、築地へ出て、
東劇から演舞場の前を通って、家へかえればよいのである。
満佐子はほっとして、橋の袂で手を合わせ、今までいそいだ埋め合せに、懇切丁寧に祈念を凝らした。しかし横目でうかが
うと、みながあいかわらず猿真似をして、分厚い掌を殊勝に合わせているのが忌々しい。祈願はいつしかあらぬ方へ外れて、
満佐子の心のなかでは、しきりにこんな言葉が泡立った。
『連れて来なきゃよかったんだわ。本当に忌々しい。連れて来るんじゃなかった。』
このとき、満佐子は男の声に呼びかけられて、身の凍る思いがした。パトロールの警官が立っている。若い警官で、頰
が緊張して、声が上ずっている。
「何をしているんです。今時分、こんなところで」
満佐子は今口をきいてはおしまいだと思うので、答えることができない。しかし警官の矢継早の質問の調子と、上ずった声
音で、咄嗟に満佐子の納得の行ったことは、深夜の橋畔で拝んでいる若い女を、投身自殺とまちがえたらしいのである。
満佐子は答えることができない。そしてこの場合、みなが満佐子に代って答えるべきだということを、みなに知らせてやら
なければならない。気の利かないにも程がある。満佐子はみなのワンピースの裾を引張って、しきりに注意を喚起した。
みながいかに気が利かなくても、それに気のつかぬ筈はないのであるが、みなも頑なに口をつぐみつづけているのを見た
満佐子は、最初の言いつけを守るつもりなのか、それとも自分の願い事を守るつもりなのか、みなが口をきかない決意を固め
ているのを覚って呆然とした。
「返事をしろ。返事を」
警官の言葉は荒くなった。
ともあれ橋を大いそぎで渡ってから釈明しようと決めた満佐子は、その手をふり払って、いきなりкけ出した。綠いろの欄
干に守られた備前橋は抛物線をなして、軽い勾配の太鼓橋になっている。кけ出したとき満佐子の気づいたのは、みなも同時
に橋の上へ騷け出したことである。
橋の中ほどで、満佐子は追いついた警官に腕をつかまれた。
「逃げる気か」
「逃げるなんてひどいわよ。そんなに腕を握っちゃ痛い!」
満佐子は思わずそう叫んだ。そして自分の願い事の破れたのを知って、橋のむこうを痛恨の目つきで見やると、すでに事な
く渡りきったみなが、十四回目の最終の祈念を凝らしている姿が見えた。
家へかえった満佐子が泣いて訴えたので、母親はわけもわからずにみなを叱った。
「一体おまえは何を願ったのだい」
そうきいても、みなはにやにや笑うばかりで答えない。
二三日して、いいことがあって、機嫌を直した満佐子が、又何度目かの質問をしてみなをからかった。
「一体何を願ったのよ。言いなさいよ。もういいじゃないの」
みなは不得要領に薄笑いをうかべるだけである。
「憎らしいわね。みなって本当に憎らしい」
笑いながら、満佐子は、マニキュアをした鋭い爪で、みなの丸い肩をつついた。その爪は弾力のある思い肉に弾かれ、指先
には鬱陶しい触感が残って、満佐子はその指のもってゆき場がないような気がした。
安部工房
「手」
おれが伝書鳩であったころ、おれは血統の正しいすぐれて美しい鳩で、利口でもあり、多くの手柄をたてて、足には通信管
のほかに、アルミ製の赤い「英雄勲章」をつけていた。しかしむろん、おれはそんなことを知らなかった。あれはただ青い空
と、仲間を追って空をかける翼の感覚のたのしさと、食事のときのあわただしさと、とぎれとぎれに拡大された時間の束が存
在するにすぎなかった。おれは単純で、唯一のおれだった。形容詞もなく、説明もつかないおれだった。今でこそこんな説明
もできるのだが、当時のおれはおれであることさえ意識しなかった。
ある日、突然、戦争が終って、おれとおれの仲間は持主のなくなった鳩舎におき去りにされた。笛を鳴らしておれたちに食
事を知らせる者も、鳩舎のわらを取りかえてくれる者も、毎朝水槽の水をかえてくれる者も、魔法にかかったように姿を消し
てしまい、わけの分らぬ無規律と混乱がおそいかかった。しかし、ほどなく、水と食物と配偶者をみつけることになれると、
その無秩序がそのまま秩序にかわり、再び青い空と、仲間を追って空をかける翼の感覚のたのしさと、食事のときのあわただ
しさと、とぎれとぎれに拡大された時間の束が存在するだけだった。
その間に、変わったことと言えば、手を入れる者もないままに、鳩舎のかこいのいたんだところから、野良猫の侵入がほし
いままになり、あるいはいたずら小僧の襲撃をうけたりして、仲間の数が へ っていったことだ。もっとも、餌をあさるに都合
0
のよい新しい巣をみつけて、飛去った仲間もいたのかもしれないが、何分、おれには漠然とした減少感を感じることができる
だけで、はっきりしたことは分らない。
何ヵ月かたったある日のこと、おれの責任者だった鳩班の兵隊がひょっこり現われた。そしてその日から、彼はおれの運命
の「手」になったのだった。「手」はやはり軍服を着ていたが、以前のように肩章もバンドもしておらず、折目はつぶれて
皺くちゃだった。帽子はかぶっておらず、油つ気のない髪がほこりっぽくのびていた。「手」はなつかしそうに、同時に幾分
やましそうに、おれを見た。突然習慣が、霧のようにおれをひたし、思わず「手」の肩にとまっておれは不安な郷愁を感じた。
「手」はしずかに翼の後ろからおれをつかんだ。おれはされるままになっている習慣を想出していた。「手」はおれを昔のよ
うに箱に入れ、そして何処かにつれ去った。
それは見世物小屋だった。そこでおれはシルクハットの底に閉じこめられ、ひっぱり出されたとき、勝手に飛出して鳩舎に
帰ってくればよかった。帰ってくると、「手」が先に来て待っていて、一合ほどの豆を、食べさせてくれた。これは決して割
の悪い仕事ではなかった。その日から、これがおれの日課になった。おれは「手」の生計の道具になり、むろんおれは自覚せ
ず、新しい習慣にとけこんで行った。
この期間は随分とながかったように思う。この見世物小屋の期間が終ったのは、あるのどかな春の午後だった。陽を全身に
受けて、うとうとしていたとき、見知らぬ男が近づいて来た。おれは警戒して、飛立つ姿勢で身構えたが、あと一歩近づけば
というところで立止り、小脇にかかえていた紙入をもちなおして、時折ちらっと流目をくれながら、しきりに鉛筆を動かしは
じめた。別に危険はなさそうなので、おれはじっとしていた。そこに「手」がやってきた。「手」と男は二言三言、小声であ
いさつを交わした。「手」は男の手許に見入りながら、言った。「たいそうな出来ばえですなあ。立派な鳩でしょう。こいつ
©
は私の自慢でね、戦時中、英雄勲章をもらったやつですよ。」男はびっくりしたように手を休めた。「じゃ、何か、こいつ、
伝書鳩だったんだね。」 「ええ、今じゃ、見世物小屋の手品の鳩をやっておりますがね、おちぶれたもんですよ。」「はつは、
そいつは皮肉だ。」男は笑って言った。「次に鳩の像のモデルというわけか。」
しばらくの間、二人は黙り、男は手を動かし、「手」は男の手許をのぞきこんだ。「ちえつ、動くなあ。」と男が言った。
「そりや、生物ですもの、仕方ありませんよ。」と「手」が言った。「君、商売だろ、なんとか、動かないようにできないも
のかね。」 「無理ですよ。」 「それじゃ'」と男は手を休め、急に真剣な語調で「つかまえることは出來るわけだね。」
「手」は素早くまたたきをくりかえし、その間に何やら計算したらしく、「ええ、」とうなずいた。
それから二人は小声で相談しはじめた。眉間に皺をよせ、指で輪や線を画き、首を四方に振って、ながいことかかって掛引
きした。男が両手を打ち合せ、「手」は小首をかしげたが、口をつぐみ、それで相談はまとまったらしかった。
「手」がおれをつかんだ。まだ何も仕事がすまないのに、ポケットから豆の袋を取出して、おれの餌箱を一杯にした。「さあ、
食えよ。」ひどくやさしい声で、そう言った。「淋しいかね。」と後ろから男が言った。「あたりまえですよ」と「手」が腹
立たしげに答えた。
おれはいつものように箱に入れられた。しかし、つれて行かれたのは見世物小屋でなかった。大きな、暗い建物の、薬品臭
い部屋だった。そこでおれは仰向けに寝かされ、胸の気をかき分けられ、鋭いメスで、切り開かれた。おれの中身はえぐり出
され、まるでシャツをぬぐように、皮だけにされた。おれの中身は、すぐ鍋に入れられ、煮て、食べられてしまった。そして、
皮のほうは、中に詰物をされ、針金の骨組で支えられて、はくせいになった。
それから' 再び箱におさめられ、次にはこばれたのは例の男のアトリエだった。男はおれをモデル台にのせ、翼の具合や首
の位置をなおした。もはや、おれはされるままだった。男はおれを見詰めては、粘土をこねたりけずったりした。
外見だけから言えば、今度の事件はおれにとってそう大したことではなかったように見えるかもしれない。だが、どうして、
大へんなちがいようだ。命がなくなったというような、当り前のことは別にしても、おれは一箇の完全な物体になり、それば
おれは観念に造型
かりでなく、おれは一個の観念そのものになった。いや、観念そのものになりつつあった。男の手の中で、
されつつあるのだ。これは大へんなちがいようではないか。感覚の積分値であるにすぎなかったおれから、
おれは意味の積分
値に変形したのだ。
その変形の完成は、ある夏の日、急いだために不完全だった防腐のために、おれの皮が内側から崩壊し、
じめたことによる。おれはかまどにほうりこまれ、燃されてしまい、そのかわりに、おれは男の手の下で、
蛆に食い破られは
「鳩の像」になっ
て仕上っていた。そして突然、おれは一切の意味を理解した。
おれは今、「平和の鳩」の像である。おれは明確な意味をもち、意味それ自体ではあるが、しかし、おれは単純におれ自身
であれであることは出来ないのだ。簡単に言えば、おれを支えてくれる者の行為によってのみ、おれは存在しうるのだ。そん
な事情で、おれは街の四つ辻に立たされた。それはまた、政治の力学の四つ辻でもあっただろう。
ところで、もとに戻ろう。「手」はおれの二本目の足をもう引きおわるようだ。しかし、その後のいきさつを一寸話してお
かないと、「手」の出現はあまり突然で、偶然すぎるように見えるかもしれない。「手」はおれの命を紙幣何枚かで売払って
しまったことに、ひどく後悔を感じたに相違いなかった。あの後毎日のように、四つ辻に現われては、タバコを一服吸いおわ
る間、じっとおれを見つめていたものだ。「手」の弱々しい眼差を見返すと、おれは様々なことを理解することができた。「手」
はますます暮しに追われていた。彼は日々の不幸が何かおれに対する罪のせいであるかのような妄想につかれはじめているら
しかった。むろんそれは単なる妄想にすぎなかった。しかし、彼にしてみれば、それは現実の意味に等しかった。彼はこの秘
密を自分独りで保っていることに耐えられなくなった。そして、会う人毎に、おれの運命について物語るのだった。おれを、
「平和の象徴」から、「手」の運命に引下ろすために。
ある日、その「手」の声が、反平和主義者の耳にとまったのだった。……だが、その話は後まわしにしよう。「手」はもう
おれの足を二本とも引切ってしまった。
さて、話は初めからのつづきである。「手」は倒れかかったおれを腕にうけ、腰にまいてあった□—プでくくると、静かに
おれを地面に下ろした。おれはすっぽり雪に埋まり、みるみる見えなくなってしまった。「手」はそのロープを台にくくりっ
け、すべり下りた。それから、おれを雪の中から掘出して、肩に背負い、息づまる吹雪の中を、風と反対の方角にころがるよ
うに甑出した。雪坊主が吠え、雪女が泣き、彼は十歩ごとにつまずいた。
町を二つほど越したある街角の、焼ビルの地下室の入口で、「手」は足を止め、中から四、五人の男が現われた。男の一人
がおれを受取り、別な一人が「手」に何か封筒を手渡し、ぽんと肩を打って笑った。それから、ぼんやり立ちつくす「手」を
後に残して、男たちは足早に立去った。
立去りながら、男の一人は言った。「うまく行ったね。気狂も使いようだ。奴は奴で金をもうけた上にやく払いしたつもり
だし、こちらはこちらでやく払いしたわけだからな。」別な男が言った。「現実が空想を利用したんだ。奴がこの像を盗みた
がっていたことを知っている者は多いし、奴が犯人だということは誰も疑わないよ。それに気狂と来てやがる。アリバイがお
れたちをかくまいに向うからやって来たようなものさ。」
この男たちは、政府のまわし者だったのだ。彼らはおれが目ざわりだった。おれを存在させているものたちが目ざわりだっ
た。そこで、狭い現実に盲目となり、狂気した「手」をそそのかしたというわけだ。だが、おれと「手」の関係は、これで
終ったわけではない。話はまだまだつづくのだ。
おれはすぐに秘密工場にはこばれ、溶解され、更に別な工場にはこばれて、他のおれと同成分の金属に混合され、おれは稀薄
な、膨大な塊になった。それから、おれは様々なものに加工され、おれの一部はピストルの弾になった。いや、一部ではあ
るが、すでに個体の条件を失ったおれにとっては、そのピストルの弾一つが、おれそのものでもあった。おれはあれでもあ
りこれでもあり、また一部でもあり全部でもあった。だから以後、おれというのはその一箇のピストルの弾のことである。
ピストルの弾といってもいろいろな運命がある。その中でおれは秘密の用途に割当てられた。おれが使用される目的は、す
でに定っていた。おれはピストルの中につめこまれ、背後には膨大な位置のエネルギーがおれが押出そうと身構えていた。お
れの頭は暗い小さなトンネルをのぞいていた。その先にはポケットのたもと屑がみえていた。
おれはポケットの中のピストルと一緒に、そんな状態で、二、三日も街々をさまよったであろうか。ある夜、突然、おれは
空中に引出された。トンネルの先には、
を見た。「手」であった。「平和の鳩」
物になったあわれな「手」の姿だった。
たのだ。しかも、おれをつかって!
引金が引かれ、喜劇のエネルギーが爆発して、おれは一直線にトンネルをすべり出た。それは唯一の必然の道だった。他の
道はなかった。それは「手」に向って真っすぐ走り、いくらかの肉と血をけずり取って、そのまま通りぬけ、街路樹の幹にっ
きささってつぶれた。おれの背後で、「手」がうめき、倒れる音がした。そしておれは最後の変形を完了した。
たもと屑ではなく、街の風景があった。ついで、街燈に照らし出された一人の男の姿
の盗人として、政府から、指名され、一月余り逃げまわって、ついに屈辱と疲労の腫
役人たちは、金をつかっておれを盗ませ、つぎにかれを亡きものにしようとくわだて
「プルートーのわな」
ある倉の二階に、オルフォイスとオイリディケというねずみの夫婦が住んでいました。オルフォイスはねずみの世界では絶
世の詩人として知れわたっていました。よく磨かれた宝石のようにするどく澄みわたったその叫びは、暗闇を引裂いて光をま
ねき、ねずみたちの心をよろこびに美しく輝かせたばかりでなく、ねこの爪を起すあの恐ろしい筋肉を麻痺させ、ねこいらず
の毒を中和させ、 ねずみとり機のバネを延ばしてしまい、小麦の袋は、自ら高い香りを発散させてそのありかを知らせ、油の
壺は重しをはねのけて蓋を開け、卵は自らコロコロところがってねずみたちの巣を訪れ、板や土の壁ばかりでなくコンクリー
卜や石の壁までがねずみたちの交通に便利なようにと、顔や胸のまん中に穴を開けて待っていたということです。
この評判は、考えてみると、オルフォイスが単なる詩人ではなく、現実のあらゆる隅々まで知りぬいた科学者であり哲学者
であったことを意味しているのだろうと思われます。
また例えばこんな噂も伝わっています。大飢饉の年でした。ササの実の国を目指して大移動をすることになったとき、ね
ずみたちが一番恐れたのはセレーネという山ねこの住む沼のそばを通らねばならないことでした。セレ!ネは不思議な歌をう
たってねずみを沼に誘い込むと伝えられていました。いよいよその沼に近づいた時、突然ねずみたちの間に激しい動揺がおこ
りました。
「セレーネが歌っている!」
苦しそうな囁きが波のようにひろがり、身もだえしながらその場にうずくまり、動けなくなるもの、さては理性を失って
すすり泣きながら沼のほうへよろめいて行こうとするものさえ現われました。オルフォイスは驚いて耳をすませました。しか
し彼の耳にはどんな歌も聞えないのでした。実際セレ—ネは歌ってなんかいなかったのです。オルフォイスはすぐにそれが沈
黙の歌であることを理解しました。そして沈黙の歌ほど恐ろしいものはないことを知りました。オルフォイスはねずみたちの
先頭に立って歌いはじめました。ながい闘いのあと、ついに彼の歌はセレーネにうちかち、ねずみたちは無事に目的地に辿り
っくことができました。
自然オルフォイスはねずみたちの教師であり指導者でした。ねずみたちは彼に、王様になってくれと嘆願しましたが、彼は
拒み、共和政治をしくことをすすめました。そこで彼はねずみ共和国の初代大統領にえらばれました。はじめにお話した倉が
大統領官邸に採用され、それ以来そこが彼の住居になったわけです。住居だったばかりでなく、その倉はねずみの社会の議事
堂であり、裁判所であり学校であり公民館でした。オルフォイスはそこで政治の事務をとり、壁争いやチーズの分け前につい
ての裁判をし、学生を集めて詩作法からねこいらずの解毒法にいたるまで教え、あるいは大音楽会を開いたりするのです。
そんなわけでしたから、自然ねずみたちの出入も多く始終ねこどもがうろうろと倉の周囲をうろついて、パリパリ壁を引っ
かいたり舌なめずりしたりしているのでした。しかしオルフォイスの知恵とねずみたちの共同したヵとは、倉を難攻不落の要
塞にしていました。
ある日のことです。不意に一人の人間がやってきて、倉の戸を開けたのです。ねずみたちはこんなことが起ろうとは、夢に
も考えなかったので、ひどく狼狽してしまいました。事実は単に春がきて、その倉の持ち主である農夫が耕作機の手入をしに
きたというにすぎなかったのですが、人間の一日がねずみにはひと月以上にもあたるのです。何十年来の、いやほとんどあり
うべからざる事件に思われたのも無理はなかったのです。
ねずみたちは狼狽しました。そして案じていたとおり、男は戸を半開きにしたまま帰って行ったのです。倉はもはや難攻不
落ではなくなりました。
老いぼれねこのプル—トーがやってきたのはその夜のことでした。老いぼれてはいましたが、残忍で名の聞えたプルートー
です。その名はねずみたちにとっては「死の王」という意味でした。
ねずみたちは一心に相談し意見をたたかわせました。「誰が鈴をつけに行くか?」というあの有名なイソップの寓話ができ
たのもこの時でした。オルフォイスはプル—卜—がいかに冷酷であり残忍であるかをこんこんと説き、どんな妥協もありえな
いことを強く主張しましたが、すっかりおびえたねずみたちは彼の気持を少しも理解しようとはしませんでした。もしねずみ
たち全部がその気になれば、いかにプルート!が恐ろしい爪をもっているにしても、必ず打ち破ることができたはずです。し
かしねずみたちはただおびえるだけで、まるで闘う気力を見せないのでした。そして馬鹿のようにいつまでも「誰が鈴をつけ
に行くか?」を繰返すのでした。
「困難が君達を強くするのを待つよりほかないのだろうか。」
オルフォイスは悲しそうに言って、一同の顔を見まわしました。しかし誰も返事をするものがないので、あきらめて言葉を
つづけました。「むろん交渉の余地がないわけじゃない。それが君たち全部の意見だというのなら、やってみよう。」
オルフォイスは壁ごしに、よく透る美しい声で呼びかけました。「プルートー君、相談だが……」
「なんだ?」プルート—の太いダミ声が意外に近くして、ねずみたちが気が遠くなるほどふるえ上りました。
オルフォイスは言いました。
「もし君がこの倉の出入にさいして私たちの生命を保証すると約束してくれるなら、私たちは一日ーポンドの肉と半ポンドの
油と、四匹のニシンを君にあげることを約束しよう。」
「なるほど、」とプルートーが言いました。「君は利口者だ。ニシンを六匹にしたらどうかね。」
「もし君がその約束を守るという証拠に、君の首に鈴をつけさしてくれればそうしよう。」オウフォイスは答えました。
さて、オルフォイスが鈴をもって下りて行こうとすると、我に返ったねずみたちはいっせいに騒ぎはじめました。万一のこ
とがあっては言うのです。そのくせ、では誰が行くかということになると、やはり尻込みして申し出るものは一人もないので
した。
そのとき、「私が参りましょう。」
そう言ったのはオイリディケでした。オイリディケは夫の手から鈴を受取り、恐ろしく静まりかえった中を、静かに下りて
行きました。チリチリと鈴の音が次第に遠のいて行き、やがて止りました。ねずみたちは息をこらして待っていました。
ところがいつまでたっても彼女は帰ってこないのです。
「行ってみよう。」そう言ったオルフォイスの声は不安げにふるえていました。だがオルフォイスは大胆にプルート!に近づ
いて行きました。
「妻を返してもらいたい。」
「ああ返すとも、」とプルートーはしきりに舌なめずりしながら言いました。
「どこにいるんだ。」
「いるところにいる。おれが知っている。」
「早く返してくれ。」
「返すよ。ただし、一つだけ条件を守ってもらいたいんだ。君の後をついて行かせるが、途中決して後を振向かないこと。振
向いたら、奥さんはむろん、君の命も保証できん。」
「なんのためにそんな約束が必要なんだ?」
「なんだっていいじゃないか。君に必要なのは結果であって理由じゃないだろう。」
オルフォイスは黙ってプルートーに背を向けました。プルートーが言いました。「さあ、美しいオイリディケさん、ダンナ
の後をついて行くがいい
オルフォイスはゆっくりみんなが待っている二階に歩を進めながら、本当にオイリディケがついてきているのかどうか不安
になりました。まるで臭いがしないのです。ふと足をとめ、オイリディケ、と小声で呼んでみました。やはり返事はありませ
ん。だまされた!そう気がついて思わず振向いたのと、プルートーの鋭い爪と牙が彼の全身を引裂いてしまったのとはほと
んど同時でした。
「おれが悪いんじゃない。約束を破ったオルフォイスが悪いのさ。」プルートーはよく光る冷たい目で二階を見上げ、思いき
り大きなアクビをすると、長い尻尾をぴんとつつ立てたまま、水を飲みに外に出て行きました。
大江健三郎
「他人の足」
僕らは、粘液質の厚い壁の中に、おとなしく暮していた。僕らの生活は、外部から完全に遮断されてい、不思議な監禁状態
にいたのに、決して僕らは、脱走を企てたり、外部の情報を聞きこむことに熱中したりしなかった。僕らには外部がなかった
のだといっていい。壁の中で、充実して、陽気に暮していた。
僕は、その厚い壁に触れてみたわけではない。しかし、壁はしっかり閉ざしてい、僕らを監禁していた。それは確かなこと
だ。僕らは、一種の強制収容所にいたのだが、決してその粘液質の透明な壁に、深い罅をいれて逃亡しようとはしなかった。
それは、海の近い高原に建てられた、脊椎カリエス患者の療養所の、未成年者病棟だった。十九歳の僕が最も年長で、次
は十五歳の唯一人の少女、残りの患者は五人とも十四歳だった。僕らの病棟は、個室とサンルームから成ってい、僕らは二人
ずつ個室へ配られて夜を過したが、昼の間は、大きいサンルームに寝椅子を並べて、日光浴した。僕らは、静かな子供たちだ
った。ひそひそ囁きあうとか、声を殺して笑うとかしながら、あるいは黙りこんで、僕らは褐色に皮膚の灼けた»をじっと
させていた。時々、大声で叫んで、看護婦に便器を運ばせるほかは、長く単調な時間を、僕らはじっとして生きている。
僕らは殆ど、歩き始める可能性を、将来に持っていなかった。院長は、おそらくその理由で、僕らを大人の病棟から広い
芝生を隔てて独立している一棟に集めて、特殊社会の雛型を作りあげる事を意図していたのだし、それは、かなり成功してい
た。その時も、十四歳の少年の一人が、複雑な方法で自殺未遂し、その後、サンルームの隅で黙りこんでいた他は、みんな快
楽的に生きていたのだ。
しかも僕らは、快楽に恵まれていた。それは、僕らの係の看護婦たちが、シーツや下着を汚されることをおそれて、あるい
は彼女たちの小さな好奇心から、そして殊に、今までの習慣から、僕らに手軽な快楽をあたえてくれたからだ。僕らの中には、
時どき昼の間も係の看護婦に、車つきの寝椅子を押させて個室へ帰り、二十分ほどたって、頰を紅潮させた看護婦を従えて、
得意げに戻って来る者がいた。僕らは彼を忍び笑いで迎えた。
僕らはゆったりし、時間について考えず、快楽にみちて暮していた。しかし、その男が来て、凡てが少しずつ、しかし執拗
に変り始め、外部が頭をもたげたのだ。
ある五月の朝、その男は両脚にかさばるギプスをつけて、サンルームに現われた。皆、彼を意識的に無視して低い声での会
話や忍び笑いを続けていたが、彼は気づまりな様子だった。暫く、ためらったあと、彼は寝椅子が隣りあわせていた僕に話
しかけた。
僕は大学の文学部にいましたけど、と彼は低く細い声でいった。両脚をだめにしちゃったんですよ。三週間たって、ギプス
を外してみて、どうなるか定まるんだけど、きっと、だめだろうと医者がいってました。
僕は冷淡にうなずいた。僕を含めて、この病棟の若い患者たちは、お互いの病状について話したり聞いたりすることに、飽
きあきしていたのだ。
君はどうなの?と学生は僕を覗きこむように肩をあげていった。ひどいカリエスなんですか。
自分の病気のことまで覚えていられないよ、と僕はいった。僕が覚えてなくても、一生病気は僕を見捨てないからね。
辛抱強くしなければだめよ、と僕の寝椅子の背に倚りかかっていた看護婦がいった。そんな投げやりな事いわないで、辛抱
強くなってよ。
僕は辛抱強くなくても、足は理想的に辛抱強いからね。
僕が君に話しかけた事、不愉快でしたか、と喉につまった声で学生がいった。
え?と驚いて僕はいった。
僕は慣れていないから。
あんたたち、仲良くしてね、と看護婦がいった。今夜から、あんたたち二人が一緒の部屋に寝てもらうわ。他の人は子供で
しょ。
手で動かすことのできる大きい車輪のついた寝椅子を近づけて来た少年の一人が学生にいった。
君、僕の血液検査表をみた?
いいえ、と当惑して学生はいった。
入口のドアに張ってあるよ、と少年は考えぶかそうにいった。僕は、六種類の検査を受けたんだけど、どれも陰性だったん
だ。部屋の中で、寝椅子に乗っかってるだけじゃ、性病にはならないね、と医者が、がっかりしていったよ。
その、たびたび繰返された冗談に、皆忍び笑い、看護婦は下品な声をあげて笑ったが、学生は頰を赤らめ脣を嚙みしめて
默从っていた。
車椅子を動かし、仲間の方へ帰って行きながら、少年は聞こえよがしにいった。
変な奴だよ、笑わねえんだ。
そして又、低く押し殺した笑いが起り、少年は、わざわざ膨れ面をしてみせていた。
僕は学生と同じ部屋で夜をすごすことを、億劫に感じた。その午後、学生は黙り込んで考えてい、夕食のあと、同じ病室へ
運びまれるまで、僕は平常と同じ暮し、ぼんやりして芝生の上の陽の翳りを見守っている暮しを続けたが、意識の深い隅で、
僕は学生を気にかけていた。
看護婦が、シーツをかけた毛布で僕を包んだ後、学生のベッドに近づいて行った。僕は、看護婦の赤茶けた頭髪の揺れ動く
向うの、学生の裸の腹部の白い膨らみを見守っていた。欠伸が、喉の奥で、小さい梨のように固まり、なかなか出て来ない。
よせ、と激しく学生がいった。よせ。
学生は羞恥で顔の皮膚を厚ぼったくし、喘いでいた。その下腹部から顔をあげ、濡れてぶよぶよしている脣を丸めて看護婦
が意外だという感じでいった。
私はあなたの解を、いつも清潔にしておきたいのよ、今済ましておいた方が、下着が汚れなくていいわ。
学生は、息を弾ませ、黙って、看護婦を睨みつけていた。
ほら、ごらんなさい。ほら、と看護婦は学生の下腹部を見おろしていった。あなたは正直じゃないわ。
シーツを掛けてくれ、と屈辱で®れた声で学生はいった。
そして、看護婦が金盥にタウルをいれて、部屋から出て行くと、彼は声をひそめて泣き始めた。僕は小さな虫のような笑
いが喉の奥からあふれ出てくるのを、注意深く押えていた。暫くたって、曖昧な声で学生が、いった。
ねえ。君、起きてるんだろう?
ああ、と僕は眼を開いていった。
僕は犬みたいな扱いを受ける、と学生がいった。僕は子供の時、犬を発情させて遊んだ事があるけど、今発情させられるの
は僕だ。
ひどく孤独な気持なのだろうな、と僕は思い、学生の方に向きなおっていった。
君は僕に羞ずかしがったるすることはないぜ。僕らは皆、看護婦にそうさせる習慣なんだ。
そんな事はいけない、と学生がいった。僕はそんな習慣には我慢できない。
そうかなあ、と僕はいった。
君たちも、あんな事を我慢してはいけないんだ。と学生は熱心にいった。明日、サンルームで皆にその事をいうよ。僕らは
生活を改良して行く意志を持つべきだ。僕はサンルームの雰囲気にも耐えられないものを感じていたんだ。
政党でも作ることだな、と僕はいった。
作るよ、と学生がいった。僕は皆と、この療養所の生活を検討したり、国際情勢を話しあったりする会を作る。そして、戦
争の脅威についても話しあうだろう。
戦争だって?と僕は驚いていった。僕らは、そんなものに関係ないぜ。
関係がないなんて、と学生も驚いた声を出した。僕と同じ世代の青年が、そんなことをいうなんて考えてもみなかった。
この男は外部から来たんだ、粘液質の厚い壁の外部から、と僕は思った。そして、穌の周りに外部の空気をしっかり纏いっ
かせている。
僕は、この姿勢のままで何十年か生きるんだ、そして死ぬ、と僕はいった。僕の掌に、銃を押しつける奴はいないさ。戦争
は、フットボールをできる青年たちの仕事だ。
そんな筈はない、と苛立って学生は僕を遮った。僕らにも発言権はあるんだ。僕らも平和のために立上らねばならない。
足が動かないのさ、と僕はいった。立上りたくてもね。僕らは、この一棟に漂流して来た遭難者なんだ。海の向うのことは
知らないよ。
そんな考えは無責任すぎる、と学生がいった。僕らこそ、手を繋ぎあって、一つの力になる必要がある。そして、病院の外
の運動と呼応するんだ。
僕は誰とも手を結ばない、と僕はいった。僕は立って歩ける男とは無関係だ。そして、僕と同じように歩けないで寝ている
連中、彼らは僕の同類で、執拗に琳をこすりつけてくるし、僕らは同じ表情、同じ厭らしさを持っている。僕は彼らと手を繋
ぐのも断わる。
同類だったら、なおさらじゃないか。僕らは結ばれているんだ。
賤民の団結だ、不具者の助けあいだ、と僕は怒りに喉を膨らませていった。僕はそういうみじめな事はやらないぞ。
学生は不服そうな顔をしながら、それでも僕の剣幕に押されて黙り込んだ。僕はベッドの金属枠を外し、看護婦に秘密にし
ている睡眠薬を取出して素早く飲むと、眼を閉じた。胸が激しく動機を打っていた。看護婦が入って来、いつもの鳩のような
ふくみ笑いをしながら、僕の下腹部に手を入れたが、夢うつつで僕はそれを拒んだ。あいつが自分の欲望に耐えている間、僕
も耐えてあいつを見張ってやる、と僕は考え、看護婦が消灯して出て行くと、柔かい粘土層へ穴をあけるように、自分の睡り
の中へもぐりこんでいった。
翌朝から、学生は彼の運動を始めた。彼は周りの寝椅子の少年たちに、熱心に話しかけ、軽い揶揄のまじった冷淡さであし
らわれながら、決して黙りこまなかった。彼は午前の間中、寝椅子の車輪を押して動きまわり、愛想よく話しかけていた。
そして、昼食のあと、看護婦の口から、学生が昨夜、断平として、あのありふれた日常的な小さい快楽を拒んだ話をひそひそ
打ちあけられると、少年たちは、皆一しきり低い声で笑ったあと、軽い興味を学生に、持ち始めた様子だった。そして、少し
ずつ彼の周囲に集まり始め、夕方には、円形に寝椅子を並べて少年たちは、学生と話してい、その中には、いつも花の栽培の
本だけ読んでいる少女のカリエス患者まで加わっていた。
しかし僕は学生を避けてサンルームの隅でじっと寝そべったまま、天井にある汚点が駱駝の頭部に似ているのを見つめたり
していた。僕は不思議な、孤独な感情をもてあましていたのだ。昨日までは、一日中黙っていて楽しく充実していたのに、今
日は喉がほてったり、むくむく動きそうだったりする。
僕は横で、やはり学生の周囲に近づかないで、黙りこみ、吸血鬼の本を読んでいる、自殺未遂少年に話しかけた。
吸血鬼、恐い?
少年は眼の周りにどす黒い隈のある痩せた顔をのろのろ傾け、僕を見つめてうなずいた。不断なら少年は僕の声が聞えなか
ったふりをして、本を読みつづける筈だった。僕は少年も、学生の周りで、おずおずした笑声をたてたり、熱心に話したりし
ている少年たちの集りを気にしているのだ、と思った。
あれは恐いなあ。吸われている時、自覚症状がないというのがやりきれないね。
吸血鬼伝説にも、いろいろあるから、と考えこんで、奇妙にかすれた声で少年は答えた。
吸血鬼が来るといいと思ってね、窓を開けて寝たことがある、と僕はいった。僕の萎びて赤ん坊の腕みたいな足をね、大き
い吸血鬼がせっせと吸うと思うと、おかしいし' 恐くて、黠がばらばらになりそうだった。
僕は低い声で笑ったが、少年は笑わなかった。振りむくと、少年は脣を固く嚙みしめていた。僕はぐったりして寝椅子の背
に頭を倒し、小さい音をたてた。学生と少年たちは、たびたび笑った。そしてその笑いは、いつものくすぐったい卑猥な笑い
とは微妙に異なっているのだ。あいつは、あいつは、うまくやっていやがる、と僕は苦い感情になって考えた。
政党の具合はどうだい?と僕は、その夜個室に帰ると学生に訊ねた。
僕の話を皆、よく聞いてくれるんだ、と学生が真面目にいった。皆の生活が変って行くよ、きっとそうなるんだ。
選举もやれよ、と僕はいった。スピ—カーを病院の事務所で借りるのさ。
僕は君にも、グループに入ってほしいと思っている、と学生は腹を立てないでいった。
僕はベッドの中で»を動かした。下腹と、腰の関節のすぐ下の皮膚がむずがゆく痛かった。腰や下腹をぽりぽり引搔きなが
ら、僕は学生の言葉を反芻した。しつこい奴だな、僕まで引込もうと思っている。
結局、ここで回復しなければならないのは、正常さの感覚なんだ、と学生がいった。僕らも正常な人間だという確信なんだ。
そうしたら、いろんな事に異常な反応をしなくなるよ。
僕らは正常でないじゃないか、と僕はいった。
正常だと考えるだけでいいんだ。
欺瞞だな。
僕はそう思わない。自分が正常だと考えたら、皆に日常の誇りが帰って来るよ。そして生活がきちんとしてくると思うんだ。
看護婦が二人、便器を提げて入って来た。僕は、髪を栗色に染めている大柄な看護婦に軽がると抱きあげられ、便器にまた
がった。自分の尿の臭いがむっと来る。背の低い看護婦は、学生の剥き出しの尻を短い掌で支え、注意深くその下を見守って
いた。
たいした日常の誇りだよ、と僕はいった。
便器にまたがったまま、紅潮した顔をむりに振りかえって学生がいった。
そうなんだ。誇りを回復する事が必要なんだ。
厭ねえ、零さないでよ、と学生の看護婦がいった。
僕は力をいれたため鼻孔をひくひく膨らませる看護婦にベッドへ戻されながら、小さい声で笑った。
翌日、自殺未遂の少年が、面会に来た両親に会うために、一般病棟へ運ばれて行ったので、僕は一人だけ部屋の隅に横たわ
り、学生の集りを見守っていた。学生は看護婦に、日刊紙を数種、買って来させ、それを彼の周りに集まったカリエスの少年
たちに解説しながら読んで聞かせた。新聞より小説が面白いし、猥雜な空想がもっと面白いという理由で、僕らは新聞を読ま
なかった。毎日、交通事故の死亡者数の載っている新聞'それが僕らにどんな関係があったろう。しかし、今、学生の周りで
少年たちは口をだらしなく開き、熱心に聞きほれている。ソヴィエトの大学制度について綿密に説明している学生の上気した
声が僕を苛立たせた。この病棟にいる唯一人の少女は、妹が優しい兄を見つめるような眼で、学生のよく動く脣を見つめ、学
生の寝椅子に片手をかけてい、それも僕を苛立たせた。
午睡のあと、あおむけに寝たまま僕は、浅い睡りの後の奇妙に黠中が熱くて、むずがゆい感覚を、暫く味わっていた。隣
に、少年が面会から帰って来てい、看護婦が平板な調子の言葉を、執拗に繰返していた。
ねえ、勇気を出すのよ。そして手術をなさい。お母様が泣いて頼んでらしたじゃないの。ねえ、勇気を出しなさい。男で
しょ?
僕は手術をしない、と少年は頑くなにいった。僕は歩きたくないよ。手術がうまくいって、歩いたり走ったりできるように
なっても、僕は一生チビのままなんだ。僕は手術なんか飽きあきしてるよ。
ねえ、勇気を出すのよ。病気は直さなければならないものよ。あなたは、歩かなきゃいけないのよ。人間は歩くようにでき
てるでしょ。ねえ、勇気を出すのよ。
僕は厭だ。手術しても直るかどうか分らないって医者がいってたじゃないか。
直ったら自転車にだって乗れるのよ。ねえ、勇気を出しなさいよ。
おい、と僕は首を挙げて、看護婦にいった。ほっといてやれよ。
看護婦は少年の寝椅子から琳を起し、疲れと敵意のこもった眼で僕を見た。少年は、僕の言葉をきかなかったように、熱心
に学生たちの集りを見守っていた。
その夜、満足した表情で学生がいった。
僕は今日、アジアの民主主義国家が、世界の動きに対して、どんな意味をもつかを中心に、説明したんだ。誰一人、毛沢東
を知らないんだからなあ。僕は、僕らの会をу世界を知る会チという名にしようと思うんだ。家から、いろいろ資料を取りよ
せるよ。
熱心なものだな、と僕は努めて冷淡にいった。社会主義国家における、身体不具者の更生という研究でも皆でやるといいや。
あ、と学生は眼を輝かせていった。僕はそんな特集を、何かの雑誌で読んだことがある。思い出して明日、話そう。
この男は、本当にこんなに単純なのだろうか、それとも僕を厭がらせるためにわざわざ単純さをよそおっているのだろうか、
と僕は考えた。しかし、どちらにしても学生は、無神経な感じにくさの甲冑で身をよろっていて、僕の言葉はそこから全部
はねかえって来る。僕は自分が、一日中緊張していた後のように、深い所で疲れきっているのを感じた。
学生を中心とする集りは非常にうまく成長している様子だった。少年たちが、あまりに柔順に学生の指導をうけていること
が、僕を無力感にみちた苛立ちにさそった。学生が来て一週間たっと、サンルームの空気は、以前のそれとすっかり変った。
そこには、ひそひそ話や、低く押し殺した卑猥な笑いは聞こえなくなった。サンルームは明るい笑顔で時どきいっぱいになっ
た。看護婦たちもたまには、学生たちの会に参加したし、院長がその雰囲気を喜んで学生たちのために定期刊行誌を数種、予
約してくれたりした。そして、重要な事は、皆が、かつて看護婦から得ていた衛生的な快楽、日常的な小さい快楽を棄てさっ
たことだった。僕は看護婦のもらす言葉の端はしから、それを確かめた。そして僕自身も、それについては、少年たちと同じ
生活の変化を被っていることを曖昧な苛立ちと一緒に気づくのだ。
その変化について、学生は、カリエス患者の少年たちが、すっかり自分たちの病棟を異常な小社会と考えることになれて
いたのが、学生の単純な行為を通じて、自分たちも決して異常な小社会に住んでいるのではないと知ったせいだといっていた。
そして学生は人の良さそうな小さい眼をぱちぱちやりながら附けたしたものだった。
誰にだって正常な生活は魅力があるし、誇りも回復するんですよ、ね?そうでなくちゃ、社会が成立しないと思うんだ。
君も僕らのグループに入ればいい。
しかし僕と自殺未遂の少年は彼の集りに入らないで、孤立を続けた。少年はサンルームの隅でいつも学生たちを見守ってい
るくせに、学生が呼びかけると急に冷たい、無表情な殻にとじこもって聞えないふりをした。そして、終日看護婦につきまと
われ、手術することをすすめられていた。看護婦も始めの熱心さは失って、惰性的な繰返しを少年の耳もとで囁くだけにす
ぎなかったが、根深い執拗さは彼女の声音にこもっていた。
©
あなただけよ、直る可能性のあるのは。ねえ、手術して歩きなさいよ。勇気を出すのよ、やってみなさいよ。損にはならな
いわよ。
そのうち僕は微熱が出始め、それを僕が最近、神経過敏になっているせいだと診断した院長は、昼の間も僕が個室に止まる
許可をあたえた。僕は昼の間ずっと、暗い個室で幾何の問題を解いて暇つぶしをした。しかし、サンルームからの笑声が聞え
るたびに、僕は証明の糸口を見失ってしまって、始めからやりなおさなければならないことに気づくのだ。
学生が病棟に来て三週間目の朝、学生は看護婦二人に別棟の診療室へ運ばれて行き、午後になってギプスをつけたまま個室
へ帰って来た。そして学生は、僕にも看護婦にも話しかけないで黙りこんだまま、ずっとベッドに寝ていたが、睡っていたわ
けではないらしく、時々、身じろぎしていた。僕は学生に、なにげなく話しかけたいのを、努力して我慢していた。
僕はだめらしいんだ、と夕食の後で学生が疲れきり眼のふちに隈のできた顔でいった。僕の両脚はやはりもういけないらし
いと、医者がいったんだ。
僕は黙ったまま、うなずいて窓のガラスの向う、木立の向うの、夜の空のぐったりした杳かな連なりを見た。それは豊かに
水をたたえた運河のようだった。僕はもう、一人で街を歩けない、と学生がやはり窓の向うの夜を見つめながらいった。フラ
ンス人に一生会えない。船に乗ることも泳ぐこともできない。
僕は初めて学生に対して、優しい感情が湧くのを感じていった。
思いつめることはないよ、僕らはきっと六十歳くらいまでおとなしく生きるんだ。
六十歳、と息がつまったような声で学生がいった。この不安定な、窮屈な姿勢のままで、あと四十年生きるんだ。寝椅子に
寝そべったままで僕は三十歳になり、四十歳になる。
嚙みしめた歯の間で学生は呻いた。
僕も四十歳になるだろう、と僕は考えた。四十歳の僕は分別くさい顔をして、いつもいつも穏かに微笑しているだろう。そ
して看護婦に抱えられて便器にまたがるのだ。僕の萎びた腿の皮膚はかさかさして脂がなく、汚点がいっぱいできているだ
ろう。まったく、辛抱強くなければならないかな。
空が運河みたいだろう?と僕はいった。大きい船がゆっくり航行しているようだな、暗い航跡を曳いて。
僕には自由なんて、もうなくなった、と考え込んでいた学生がいった。
良い色をした、豊かな自由が船のように、空の運河を溯る、と僕は思った。
翌朝、僕らはお互いにぎこちなかった。学生は僕に弱音を吐いたことを、非常に恥じている様子だった。そして、学生はそ
の日から、彼のグループの活動にもっと熱中し始めた。彼は僕に、そのグル—プへ加わることを、もう勧めなかった。僕は相
かわらず個室にじっとしていたので、学生たちの動静は分らなかったが、看護婦にそれとなく訊ねたところによると、学生た
ちは新しい運動を始め、それは、原水爆禁止のための声明文を新聞に送りつける事らしかった。夜、個室へ戻ってからも、学
生は僕に話しかけようとしないで、鉛筆を細く尖らせ、せっせと短い文章を書いていたが僕は全く興味のないふりをしていた。
ある朝、サンルームが度はずれて騒がしく、感動した叫び声や、快活な笑いが聞えて来た。僕は自分を抑制するための空し
い努力をした後、看護婦を呼んで、何週間ぶりに、サンルームへ寝椅子ごと運んでもらった。
学生の周りに集った脊椎カリエスの少年たちが、一枚の拡げられた新聞を覗きこんでは、陽気にざわめいていた。僕は、部
屋の隅で相かわらず孤立している少年の横に、寝椅子を留めさせ、できるだけ平静を装って、彼らの騒ぎを見守った。数人の
看護婦が、彼らの背後から、感嘆の声をあげては、その新聞を見下ろしていた。学生が興奮した声で繰返し読みあげていたが、
©
©
僕には聞こえなかった。僕の横で少年は苛立ちながら耳をすましていた。
僕をサンル—ムに運んで来た看護婦が、学生たちの集りの中から戻って来て、僕にせきこみながらいった。
新聞にここの事が載っかってるのよ。あの子たちの送った手紙が長く載っていてね、皆の名前まであるわ。活字で、きちん
とよー
そして看護婦は、左翼新聞の名前を、印象的に強く発音していった。
あれによ、あんな有名な新聞に、十センチも書いてあるのよ。原水爆に抗議する'脊椎カリエスの子供たち、ですって。凄
いわね。
学生グル—プの中から、誰かが大声で少年に呼びかけた。
おい、君も来いよ。君の名前も載つかってるんだ。来いったら。
少年はびくっと»を震わせ、努力して上半身を起した。その寝椅子を、騷けよって来た看護婦が引っぱって行った。少年の
細い肩を学生が優しく叩き、皆が一斉に笑う声が部屋をみたした。僕は眼をそむけた。
午後になって、自殺未遂の少年は、学生たちの快活な励ましに送られて、サンルームを運び出されて行った。手術する勇気
が出たのだろう、と僕は考えた。あいったちの馬鹿さわぎも、すっかりむだな訳ではないな。
しかし、その夜、学生が控え目な声で話しかけると、すぐに僕は頑くなになるのだ。それは自分で制御できない。
皆で文集を作ってね、と学生がいった。新聞や外国大使館に送りつけるつもりだ。原水爆反対というテーマに統一してね。
とにかく、僕らも外の社会と結びつけるということが、皆に分ってもらえて嬉しい。
新聞が君たちのことを取上げて報道するのは、と僕はできるだけ冷淡な口調でいった。それは、君たちが脊椎カリエスだか
らさ。数知れない人たちが、君たちの弱よわしいかたわの微笑を憐れみながら、あれを読むんだ。ごらんよ、かたわもこんな
事を考えるとさ、とかいいながらね。
君が皆の前でそんなことをいったら、承知しないぞ、怒りに声を震わせて、学生がいった。
しかし、自分の言葉に、最も激しく切望的に腹を立てていたのは僕自身なのだ。だから僕は、その夜消灯を終ったあと、看
護婦が、隣室の少女を寝椅子のまま、僕らの部屋に運んで来、学生のベッドに並べて出て行った時も、睡ったふりをして黙っ
ていた。
嬉しくて、睡れないのよ、と少女は低い声で学生に弁解した。今夜中、誰かと話していたいわ。私たちにも、力があるのね。
学生たちは長い間、ひそひそ話していたが、僕はできるだけ意識をそこから逸らした。しかも僕には、睡眠薬を取出すため
に腕を動かすこともできないので、苛立ちながらじっとしていた。夜明けがた、ギプスの音を鈍く響かせ、学生が上半身を起
して少女に接吻した。脣の触れあう、濡れた柔かい音がしていた。僕は優しい感情に充たされていったが、その奥に、押し
あげて来る怒りの感情もあるのだ。僕は朝まで睡れなかった。
翌日、朝食のあとで学生は診療室へ運ばれて行った。僕は昼近くまで浅い睡りをねむり、それから、頭の皮膚の下で虫が這
い続けているような、寝不足の感情のまま、サンルームに出た。学生は戻ってきていなくて、屈託ない良い表情をした少女を
かこんで、少年たちが低く合唱していた。
あおむけに寝椅子に横たわった脊椎カリエスの少年たちの歌は、高い天窓のあたりへ上って行き、ふりそそいで来た。僕は
それを聞きながら、うつらうつらしていた。そして、急に歌がやみ、静けさが充満した。僕は限りなく思い腰をずらし、上半
身を起して広い窓ガラスの向うを見た。
診療室の開かれたドアの前の青く光る芝生の上を、臆病な動物の仔のように、学生がゆっくり歩いていた。僕は胸をしめ
っけられた。学生は注意深く、しっかり芝生を見つめながら三 米ほど歩き、引返した。看護婦と医師が、職業的な冷淡さで
それを見守っていた。学生は額をあげ、歩幅をひろげて歩いた。彼の胸をはった娜に陽の光、五月の陽の光があふれていた。
拍手が起った。僕は少女を含めて、カリエスの子供たちが皆、幸福そうに拍手しているのを見た。拍手の音はガラス窓を透
し、響いて行ったが、学生は決して僕らの病棟を見返らなかった。あの男ははにかんでいる、と僕は思った。感動が喉にこみ
あげ底 あの男は、僕らの周りの、厚い粘液質の壁に罅を入れ、外への希望をはっきり回復したのだ、と僕は喉を燥かせて考
えた。僕の心の中で、小さいが形の良い、希望の芽が育ち始めた。
学生が、看護婦に軽く支えられて診療室に入って行き、ドアが陽ざしの中で音をたてて閉じられると、サンルームには、溜
息をもらすように深く呼吸する音がみち、それから、皆騒がしくしゃべり始めた。その少年も、夢中になって高い声をたて、
発作のように激しく笑った。少女は誇りにみちた固い表情をして、しきりにうなずいていた。僕は、やはり彼らから離れて孤
立していたが、彼らと肩を叩きあい、声高に話しあいたい気持でいっぱいだったのだ。
僕らは待っていた。しかし学生は、なかなか帰って来なかった。看護婦が昼食を知らせに来たが、僕らの誰一人それに答え
なかった。僕らは辛抱強く待ち続けた。午後二時近くになり、空腹が僕を息苦しくしたが、僕は待っていた、少年たちも話し
疲れ、ぐったりした表情で寝椅子に倒れ、しかし熱心に待ち続けていた。何年の間、この待ちくだびれる辛い感情を忘れてい
たことだろう、と僕は思った。僕はずっと時間について無関心だったのに、今は時計を見あげることばかりしている。
そしてサンルームのドアが開き、柔かい空色のズボンをはいた学生が戻って来た。ドアの把手に手をかけたまま、立ってい
る学生に、期待にみちた数かずの視線が集った。学生は曖昧な、固い表情をしていた。なにか、うまく行かない、しこりのよ
うなものがあるのだ。こんな筈はない、と僕はせきたてられるように考えた。これはどうしたのだろう。あの男はよそよそし
い。自分の足の上で立っている人間は、なぜ非人間的に見えるのだろう。こんな筈ではなかった。
学生は自分のためらいを押しきるように胸をつき出し、こわばった微笑を浮かべて、少年たちに近づいて行った。
少年の一人が、寝椅子から腕を差しのべ、おずおずした声でいった。
ね、君の足に触らせてくれないか。
初めて、安心した笑いが部屋にみちた。学生は意識した快活さで少年に琳をよせた。少年は、最初指で学生の腿にふれ、そ
れから静かに両掌でそれを支え、こすりつけた。少年は執拗にその動作を繰返し、やりなおした。僕は少年が口を半ば開き、
眼を瞑って熱っぽい息を吐いているのを見た。
急に琳を引き、邪慳な声で学生がいった。
よしてくれよ' よせったら。
学生と少年たちの間の不思議な均衡が破れ、粉ごなに砕けた。脊椎カリエスの少年たちと健康な青年との間の、意地悪い冷
却がその後を埋めた。学生は狼狽して顔を赤らめ、少年たちと共通の表情を取戻そうとつとめているようだったが、横たわっ
ている少年たちは既にそれを受けつけなかった。学生は皆から拒まれ、自分の下肢に支えられて胸をはっていた。
タカシさん、とサンルームの入口に立った中年の女が、横柄に僕らを見まわして呼びかけた、タカシさん、早くいらっしゃ
い、タカシさん。
僕はその女が学生とそっくりの、強靭で下品な顎を持っているのを見た。学生は振返り脣を歪めて、そのままドアへ歩い
て行った。ドアを閉ざす時、学生が僕に訴えかけるような弱よわしい視線をむけたが、僕は冷淡に顔をそむけた。
ドアが閉じられ、厚い粘液質の壁の罅は、癒合した。皆、あっけにとられたように、ぼんやりして黙っていた。看護婦がひ
どく遅れた昼食を運んで来、僕らは全く食欲のない人たちのやり方で、陰気な音をたてながら、それを食べた。少女は、食後、
個室に引籠った。午後は長かった。僕らはぐったりしていた。よく育った芝生の上を建物の影が縮んで行き、空気がさむざむ
としてきた。
おい、と僕は看護婦を呼んだ。おい、僕を個室へ帰してくれよ。
寝椅子に横たわったまま運ばれて、僕が廊下へ出る時、サンルームの中にあの聞きなれた、卑猥な忍び笑いが起った。それ
は、何週間かの間、すっかり消え去っていた押し殺した笑いなのだ。僕の寝椅子を押している看護婦が、僕の耳に熱い息を吹
きかけていった。
おしっこしたいの?怖い顔してるのね。
結局、僕はあいつを見張っていた。そして、あいつは贋ものだったのだ、と僕は考えた、勝利の感情が湧きおこりかけて、
急に消えた。そして暗い拡がりが静かに娜を寄せて来た。脣を固くひきしめ、個室のドアを閉まる音を背後に聞いてから僕は
いった。
僕を清潔にしておきたいんだろう?
え?と看護婦がいった。
下着を汚されたくないんだろう?
看護婦は当惑して僕を見つめてい、それから猥雑さと優しさの交った表情に変った。
わかったわ、と少し息を弾ませて看護婦はいった。わかったわ。近頃、皆少し変だったじゃない?私そう思っていたのよ。
初めに、乾いて冷たい掌が、荒あらしく触れた。看護婦は満足そうに繰返していた。
なんだか変だったわよ、近頃ずっと。